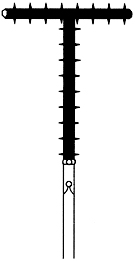複数辞典一括検索+![]()
![]()
つくば‐もんどう【筑波問答】‥ダフ🔗⭐🔉
つくば‐もんどう【筑波問答】‥ダフ
連歌書。二条良基著。1巻。1357年(延文2)以後72年(応安5)以前に成立。良基と老翁との問答体で、連歌の沿革・作法などを17項に分けて述べた書。まとまった連歌論書の最初。
⇒つくば【筑波】
つくば・る【蹲る】🔗⭐🔉
つくば・る【蹲る】
〔自五〕
しゃがみこむ。うずくまる。つくばう。
つく‐ひ【月日】🔗⭐🔉
つく‐ひ【月日】
(上代東国方言)つきひ。光陰。万葉集20「―やは過ぐは行けども母父あもししが玉の姿は忘れ為せなふも」
つぐ‐ひ【次ぐ日】🔗⭐🔉
つぐ‐ひ【次ぐ日】
明くる日。翌日。幸若舞曲、高館「―の御合戦に侍九人」
つく・ぶ【噤ぶ】🔗⭐🔉
つく・ぶ【噤ぶ】
〔他四〕
(ツクフとも)ふさぐ。閉じる。つぐむ。天武紀上「儵忽にわかに口―・ひて言ものいふこと能はず」
つく‐ぼう【突棒】‥バウ🔗⭐🔉
つく‐ほ・る🔗⭐🔉
つく‐ほ・る
〔自四〕
語義未詳。衰える意か。万葉集5「漸漸やくやくにかたち―・り」
つくま【筑摩】🔗⭐🔉
つくま【筑摩】
(チクマとも)古来、琵琶湖東端の地名。今、滋賀県米原市朝妻筑摩ちくま。筑摩神社がある。
⇒つくま‐まつり【筑摩祭】
⇒つくま‐みくりや【筑摩御厨】
つく‐まい【突舞・柱舞】‥マヒ🔗⭐🔉
つく‐まい【突舞・柱舞】‥マヒ
雑芸ぞうげい。庭先に船形を造り、柱を立て、舞人は雨蛙の面をかぶり、裁着たっつけをはき、竹弓を持って、柱の頂上で舞う。
つくま‐まつり【筑摩祭】🔗⭐🔉
つくま‐まつり【筑摩祭】
筑摩に鎮座する筑摩神社の祭事。古くは4月1日などに行われ、神輿に従う女性が、関係を結んだ男の数だけの鍋をかぶったというが、今は5月3日に、少女が緑の狩衣、緋の袴をつけ、張子はりこの鍋をかぶって供奉ぐぶする。鍋祭。鍋かぶり。鍋冠祭。〈[季]夏〉
⇒つくま【筑摩】
広辞苑 ページ 13121。