複数辞典一括検索+![]()
![]()
なか‐がさ【中蓋】🔗⭐🔉
なか‐がさ【中蓋】
①中椀のふた。ちゅうがさ。
②中形の盃。
なが‐がたな【長刀】🔗⭐🔉
なが‐がたな【長刀】
刀身の長い刀。
なが‐ガッパ【長合羽】🔗⭐🔉
なが‐ガッパ【長合羽】
丈が長く、衣服の下部までおおう合羽。
長合羽
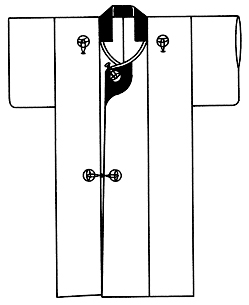
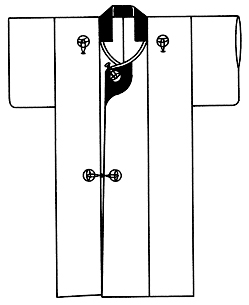
なか‐がみ【天一神】🔗⭐🔉
なか‐がみ【天一神】
暦神の名。十二神将の主将、あるいは地星の霊という。己酉の日に天から下って東北の隅に居ること6日、転じて正東に居ること5日というように順次に南・西・北を巡り、四隅に居ることそれぞれ6日、四方に居ることそれぞれ5日、計44日で、癸巳の日に正北から天に上り、天上に居ること16日、己酉の日に再び地上に下る。この神の天に在る間を天一天上という。下って地上に居る方角を「ふたがり」といって、この方角に向かって事をすることを忌み、その日他出するときは方違かたたがえをする。源氏物語帚木「こよひ―、内裏うちよりはふたがりて侍りけりと聞ゆ」
なかがみ【中上】🔗⭐🔉
なかがみ【中上】
姓氏の一つ。
⇒なかがみ‐けんじ【中上健次】
なかがみ‐けんじ【中上健次】🔗⭐🔉
なかがみ‐けんじ【中上健次】
小説家。和歌山県生れ。故郷熊野の土着思想を原点として近代の差別観と闘う。小説「岬」「枯木灘」「地の果て 至上の時」、紀行「紀州 木の国・根の物語」など。(1946〜1992)
⇒なかがみ【中上】
なが‐がみしも【長上下】🔗⭐🔉
なが‐がみしも【長上下】
江戸時代の武家の式服。肩衣かたぎぬと、それと同じ色文様の長袴とを着る。諸大名・高家および旗本の出仕の通常礼装。↔半上下
長上下


なが‐かもじ【長髢】🔗⭐🔉
なが‐かもじ【長髢】
毛が多く長い髢。江戸時代、奥女中などが用いた。
なかがわ【中川】‥ガハ🔗⭐🔉
なかがわ【中河】‥ガハ🔗⭐🔉
なかがわ【中河】‥ガハ
姓氏の一つ。
⇒なかがわ‐よいち【中河与一】
なか‐がわ【那珂川】‥ガハ🔗⭐🔉
なか‐がわ【那珂川】‥ガハ
関東地方北東部の川。栃木県北部の茶臼岳に発し、水戸平野を貫流して、茨城県ひたちなか市で太平洋に注ぐ。長さ150キロメートル。
那珂川
撮影:関戸 勇


広辞苑 ページ 14525。