複数辞典一括検索+![]()
![]()
荷鉦鼓】ニナヒシヤウ‥🔗⭐🔉
荷鉦鼓】ニナヒシヤウ‥
雅楽の鉦鼓。道楽みちがくの際、棒で荷って歩きながら打つもの。→鉦鼓2。
⇒にない【担い・荷い】
にない‐だいこ【
荷太鼓】ニナヒ‥🔗⭐🔉
荷太鼓】ニナヒ‥
雅楽の太鼓。道楽みちがくの際、棒で荷って歩きながら打つ小型の大太鼓だだいこ。
荷太鼓
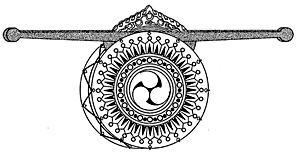 ⇒にない【担い・荷い】
にない‐ぢゃや【
⇒にない【担い・荷い】
にない‐ぢゃや【
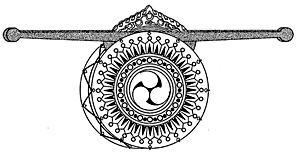 ⇒にない【担い・荷い】
にない‐ぢゃや【
⇒にない【担い・荷い】
にない‐ぢゃや【担い茶屋】ニナヒ‥🔗⭐🔉
担い茶屋】ニナヒ‥
茶釜や茶道具をにない歩き、客のために茶をたてて売ること。また、その商人。狂言、煎じ物「―を、橋がかりへもつてのく」
⇒にない【担い・荷い】
にない‐つじ【
担い旋毛】ニナヒ‥🔗⭐🔉
担い旋毛】ニナヒ‥
(→)「にないつむじ」に同じ。
⇒にない【担い・荷い】
にない‐つむじ【
担い旋毛】ニナヒ‥🔗⭐🔉
担い旋毛】ニナヒ‥
二つ並んである頭髪のつむじ。にないつじ。
⇒にない【担い・荷い】
にない‐て【
担い手】ニナヒ‥🔗⭐🔉
担い手】ニナヒ‥
①物をかつぐ人。
②中心となって物事をすすめる人。ささえ手。「生計の―」「新生国家の―」
⇒にない【担い・荷い】
にない‐ばね【
担い発条】ニナヒ‥🔗⭐🔉
担い発条】ニナヒ‥
鉄道車両・自動車などにおいて、車体を支えるために用いるばね。
⇒にない【担い・荷い】
にない‐ぶみ【
荷文】ニナヒ‥🔗⭐🔉
荷文】ニナヒ‥
狂言。(→)「文荷ふみにない」に同じ。
⇒にない【担い・荷い】
にない‐ぶろ【
担い風呂】ニナヒ‥🔗⭐🔉
担い風呂】ニナヒ‥
元禄(1688〜1704)の頃、方々へにない歩き、料金を取って入浴させた風呂。
⇒にない【担い・荷い】
にない‐ぼう【
担い棒】ニナヒバウ🔗⭐🔉
担い棒】ニナヒバウ
物をになう棒。てんびんぼう。
⇒にない【担い・荷い】
にない‐もの【
荷い物】ニナヒ‥🔗⭐🔉
荷い物】ニナヒ‥
祭礼で、二人でかついで見せ歩く物。
⇒にない【担い・荷い】
にな‐いろ【
蜷色】🔗⭐🔉
蜷色】
①襲かさねの色目。表は黄、裏は青。
②青黒い染色。
に‐な・う【
広辞苑 ページ 15005。