複数辞典一括検索+![]()
![]()
うみ‐あけ【海明け】🔗⭐🔉
うみ‐あけ【海明け】
接岸していた流氷が沖に去り、出漁が可能になること。
うみ‐あつ・む【生み集む・産み集む】🔗⭐🔉
うみ‐あつ・む【生み集む・産み集む】
〔他下二〕
子を多く生む。宇津保物語国譲中「よくも―・め給ひつるみ子たちかな」
うみ‐いし【海石】🔗⭐🔉
うみ‐いし【海石】
海にある岩石。また、海から取ってきた庭石。狂言、萩大名「あの石は―か山石か」
うみ‐いだ・す【生み出す・産み出す】🔗⭐🔉
うみ‐いだ・す【生み出す・産み出す】
〔他四〕
生んでこの世に出す。うむ。
うみ‐う【海鵜】🔗⭐🔉
うみ‐う【海鵜】
ウの一種。鵜飼に用いる。
うみ‐うさぎ【海兎】🔗⭐🔉
うみ‐うさぎ【海兎】
①ウミウサギガイのこと。
②アメフラシの別称。
⇒うみうさぎ‐がい【海兎貝】
うみうさぎ‐がい【海兎貝】‥ガヒ🔗⭐🔉
うみうさぎ‐がい【海兎貝】‥ガヒ
ウミウサギガイ科の巻貝。形はタカラガイに似て、表面は磁白色。長さ約7センチメートル。生きている時は、黒地に白斑のある外套膜に包まれる。紀伊半島以南の太平洋・インド洋のサンゴ礁にすむ。ウミウサギ。
⇒うみ‐うさぎ【海兎】
うみ‐うし【海牛】🔗⭐🔉
うみ‐うし【海牛】
主にウミウシ目の後鰓こうさい類の総称。巻貝の仲間であるが、殻は退化。体色は、種により赤・青・黄・橙・黒・白などさまざまで、美しい。浅海の岩礁上や砂泥底にすむ。体は細長いもの、楕円形のものがあり、頭部にその名の由来となる2本の触角を具える。後方の肛門のまわりを鰓が取り囲むものが多い。シロウミウシ・アオウミウシなど日本に約200種。
うみうし
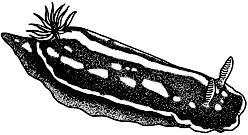 ウミウシ
提供:東京動物園協会
ウミウシ
提供:東京動物園協会

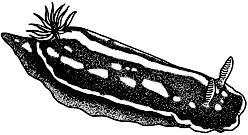 ウミウシ
提供:東京動物園協会
ウミウシ
提供:東京動物園協会

広辞苑 ページ 1945。