複数辞典一括検索+![]()
![]()
○馬を牛に乗り換えるうまをうしにのりかえる🔗⭐🔉
○馬を牛に乗り換えるうまをうしにのりかえる
速い馬をおそい牛に乗り換える意。よいものを捨てて悪いものにかえるのにいう。
⇒うま【馬】
○馬を鹿に通すうまをしかにとおす🔗⭐🔉
○馬を鹿に通すうまをしかにとおす
「鹿を指して馬となす」に同じ。→鹿(成句)
⇒うま【馬】
うみ【生み・産み】
うむこと。うんだこと。また、新しく作り出すこと。万葉集20「―の子のいやつぎつぎに」。「―の親」「―の苦しみ」
うみ【海】
①地球上の陸地以外の部分で、塩水をたたえた所。地球表面積の約7割を占め、その面積3億6000万平方キロメートル。平均深度3800メートル。允恭紀「いさな取り―の浜藻の寄る時時を」。「―の幸」↔陸りく。
②湖など広々と水をたたえた所。新古今和歌集秋「にほの―や月の光のうつろへば」
③あたり一面にひろがったもの、また、無数に多く集まっているさまにたとえていう。「火の―」「言葉の―」
④硯のほりくぼめて水を貯える所。↔陸おか
⇒海が涌く
⇒海波を揚げず
⇒海に千年河に千年
⇒海に千年山に千年
⇒海の事は漁師に問え
⇒海の物とも山の物ともつかない
⇒海も見えぬに船用意
⇒海を山にする
⇒海を渡る
うみ【膿】
腫物・傷などの化膿によって生じる組織の崩壊物質や白血球・腐敗物質・細菌を含む帯黄白色の不透明の粘液。一種の臭気がある。のう。また比喩的に、取り除かなければすっきりせず害になるもの。神代紀上「―沸き虫うじ流たる」。「政界の―を出す」
うみ‐あけ【海明け】
接岸していた流氷が沖に去り、出漁が可能になること。
うみ‐あつ・む【生み集む・産み集む】
〔他下二〕
子を多く生む。宇津保物語国譲中「よくも―・め給ひつるみ子たちかな」
うみ‐いし【海石】
海にある岩石。また、海から取ってきた庭石。狂言、萩大名「あの石は―か山石か」
うみ‐いだ・す【生み出す・産み出す】
〔他四〕
生んでこの世に出す。うむ。
うみ‐う【海鵜】
ウの一種。鵜飼に用いる。
うみ‐うさぎ【海兎】
①ウミウサギガイのこと。
②アメフラシの別称。
⇒うみうさぎ‐がい【海兎貝】
うみうさぎ‐がい【海兎貝】‥ガヒ
ウミウサギガイ科の巻貝。形はタカラガイに似て、表面は磁白色。長さ約7センチメートル。生きている時は、黒地に白斑のある外套膜に包まれる。紀伊半島以南の太平洋・インド洋のサンゴ礁にすむ。ウミウサギ。
⇒うみ‐うさぎ【海兎】
うみ‐うし【海牛】
主にウミウシ目の後鰓こうさい類の総称。巻貝の仲間であるが、殻は退化。体色は、種により赤・青・黄・橙・黒・白などさまざまで、美しい。浅海の岩礁上や砂泥底にすむ。体は細長いもの、楕円形のものがあり、頭部にその名の由来となる2本の触角を具える。後方の肛門のまわりを鰓が取り囲むものが多い。シロウミウシ・アオウミウシなど日本に約200種。
うみうし
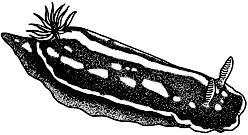 ウミウシ
提供:東京動物園協会
ウミウシ
提供:東京動物園協会
 うみ‐うそ【海獺】
アシカの異称。
うみ‐うちわ【海団扇】‥ウチハ
海産の褐藻。潮間帯の潮溜りや潮下帯の岩に生育。下部は短い茎状をなして岩などに付着、上部は縁辺が巻いた扇状体。大きなものは高さ20センチメートルに達し、放射状に裂ける。生時淡黄色で、乾けば暗褐色。
うみ‐うなぎ【海鰻】
マアナゴの別称。
うみ‐うま【海馬】
タツノオトシゴの別称。(物類称呼)
うみ‐うめ【熟梅】
熟した梅の実。金葉和歌集雑「葉がくれてつはると見えしほどもなくこは―となりにけるかな」
うみ‐うり【熟瓜】
熟した瓜の果実。存心要訓「―が熟柿を笑ふ」
うみ‐えら【海鰓】
八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミエラ科の花虫類。魚の鰓状を呈する群体を作り、ポリプは軸部の両側に突出して並ぶひだの上に配列する。群体の長さは約20センチメートルで、黄白または淡桃色。日本沿岸の浅海底に生息。なお、広くはトゲウミエラ科・フサウミエラ科などウミエラ類の総称。
うみ‐お【績苧・績麻】‥ヲ
つむいだ麻糸。うみそ。万葉集6「をとめらが―懸くとふ鹿背かせの山」
⇒うみお‐なす【績苧なす】
うみ‐おそ【海獺】‥ヲソ
アシカの異称。
うみ‐おと・す【生み落とす・産み落とす】
〔他五〕
子や卵を生む。分娩する。竹取物語「つばくらめ…七度巡りてなむ―・すめる」
うみ‐おなご【海女子】‥ヲナゴ
(→)磯姫いそひめに同じ。
うみお‐なす【績苧なす】‥ヲ‥
〔枕〕
「なが(長)」にかかる。万葉集6「―長柄ながらの宮に」
⇒うみ‐お【績苧・績麻】
うみ‐が【海処】
(カは所の意)海のほとり。古事記中「―行けば腰なづむ」↔陸くぬが
うみ‐がき【熟柿】
熟した柿の実。古今著聞集12「かたて矢はげて立ちたる上より、―の落ちけるが」
うみ‐かぜ【海風】
海から吹いてくる風。海の風。
うみ‐がた【海形】
海上の景色を模型に作ったもの。宇津保物語国譲中「左大将殿おほいなる―をして」
うみ‐が‐つき【産みが月】
うみづき。臨月。うむがつき。神代紀下「盈月うみがつき已に満ちて」
うみ‐かぶろ【海禿】
アシカの異称。
うみ‐がめ【海亀】
海産のカメ類の総称。アオウミガメ・アカウミガメ・タイマイ・オサガメなどの種類がある。いずれも形大きく、四肢はオール状またはひれ状。→青海亀(図)
アオウミガメ
提供:東京動物園協会
うみ‐うそ【海獺】
アシカの異称。
うみ‐うちわ【海団扇】‥ウチハ
海産の褐藻。潮間帯の潮溜りや潮下帯の岩に生育。下部は短い茎状をなして岩などに付着、上部は縁辺が巻いた扇状体。大きなものは高さ20センチメートルに達し、放射状に裂ける。生時淡黄色で、乾けば暗褐色。
うみ‐うなぎ【海鰻】
マアナゴの別称。
うみ‐うま【海馬】
タツノオトシゴの別称。(物類称呼)
うみ‐うめ【熟梅】
熟した梅の実。金葉和歌集雑「葉がくれてつはると見えしほどもなくこは―となりにけるかな」
うみ‐うり【熟瓜】
熟した瓜の果実。存心要訓「―が熟柿を笑ふ」
うみ‐えら【海鰓】
八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミエラ科の花虫類。魚の鰓状を呈する群体を作り、ポリプは軸部の両側に突出して並ぶひだの上に配列する。群体の長さは約20センチメートルで、黄白または淡桃色。日本沿岸の浅海底に生息。なお、広くはトゲウミエラ科・フサウミエラ科などウミエラ類の総称。
うみ‐お【績苧・績麻】‥ヲ
つむいだ麻糸。うみそ。万葉集6「をとめらが―懸くとふ鹿背かせの山」
⇒うみお‐なす【績苧なす】
うみ‐おそ【海獺】‥ヲソ
アシカの異称。
うみ‐おと・す【生み落とす・産み落とす】
〔他五〕
子や卵を生む。分娩する。竹取物語「つばくらめ…七度巡りてなむ―・すめる」
うみ‐おなご【海女子】‥ヲナゴ
(→)磯姫いそひめに同じ。
うみお‐なす【績苧なす】‥ヲ‥
〔枕〕
「なが(長)」にかかる。万葉集6「―長柄ながらの宮に」
⇒うみ‐お【績苧・績麻】
うみ‐が【海処】
(カは所の意)海のほとり。古事記中「―行けば腰なづむ」↔陸くぬが
うみ‐がき【熟柿】
熟した柿の実。古今著聞集12「かたて矢はげて立ちたる上より、―の落ちけるが」
うみ‐かぜ【海風】
海から吹いてくる風。海の風。
うみ‐がた【海形】
海上の景色を模型に作ったもの。宇津保物語国譲中「左大将殿おほいなる―をして」
うみ‐が‐つき【産みが月】
うみづき。臨月。うむがつき。神代紀下「盈月うみがつき已に満ちて」
うみ‐かぶろ【海禿】
アシカの異称。
うみ‐がめ【海亀】
海産のカメ類の総称。アオウミガメ・アカウミガメ・タイマイ・オサガメなどの種類がある。いずれも形大きく、四肢はオール状またはひれ状。→青海亀(図)
アオウミガメ
提供:東京動物園協会
 クロウミガメ
撮影:小宮輝之
クロウミガメ
撮影:小宮輝之
 タイマイ
提供:東京動物園協会
タイマイ
提供:東京動物園協会
 ヒメウミガメ
撮影:小宮輝之
ヒメウミガメ
撮影:小宮輝之
 うみ‐がも【海鴨】
主として海にすみ、潜水して採餌するカモ類。
うみ‐がらす【海烏】
チドリ目ウミスズメ科の海鳥。体はハトよりやや大きく、上面は灰黒色、下面は白色。大群をなして絶壁に産卵、潜水して巧みに魚を捕る。北方の海に分布し、サハリンのロッペン島(海豹島)はその繁殖地として有名。卵の色は変化が多い。ロッペンガモ。
うみがらす(夏羽)
うみ‐がも【海鴨】
主として海にすみ、潜水して採餌するカモ類。
うみ‐がらす【海烏】
チドリ目ウミスズメ科の海鳥。体はハトよりやや大きく、上面は灰黒色、下面は白色。大群をなして絶壁に産卵、潜水して巧みに魚を捕る。北方の海に分布し、サハリンのロッペン島(海豹島)はその繁殖地として有名。卵の色は変化が多い。ロッペンガモ。
うみがらす(夏羽)
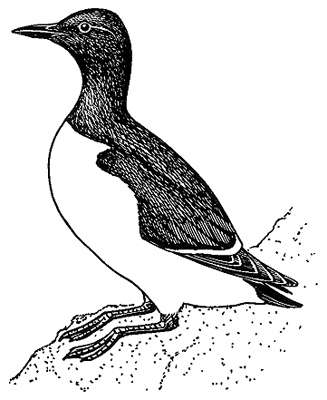 ウミガラス
撮影:小宮輝之
ウミガラス
撮影:小宮輝之
 →鳴声
提供:NHKサービスセンター
うみ‐からまつ【海唐松】
六放サンゴ亜綱ツノサンゴ目の花虫類。群体は一平面内で羽状に分岐して高さ2〜3メートルに達する。角質の骨格にとげがあり、白色または淡紅色の肉質部がその上をおおう。日本中部以南の浅海底に生育。骨格は黒珊瑚と称して印材・パイプその他の細工物とする。魔除まよけ珊瑚・角珊瑚ともいう。海松。
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
うみ‐からまつ【海唐松】
六放サンゴ亜綱ツノサンゴ目の花虫類。群体は一平面内で羽状に分岐して高さ2〜3メートルに達する。角質の骨格にとげがあり、白色または淡紅色の肉質部がその上をおおう。日本中部以南の浅海底に生育。骨格は黒珊瑚と称して印材・パイプその他の細工物とする。魔除まよけ珊瑚・角珊瑚ともいう。海松。
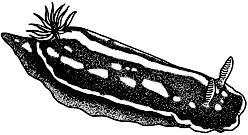 ウミウシ
提供:東京動物園協会
ウミウシ
提供:東京動物園協会
 うみ‐うそ【海獺】
アシカの異称。
うみ‐うちわ【海団扇】‥ウチハ
海産の褐藻。潮間帯の潮溜りや潮下帯の岩に生育。下部は短い茎状をなして岩などに付着、上部は縁辺が巻いた扇状体。大きなものは高さ20センチメートルに達し、放射状に裂ける。生時淡黄色で、乾けば暗褐色。
うみ‐うなぎ【海鰻】
マアナゴの別称。
うみ‐うま【海馬】
タツノオトシゴの別称。(物類称呼)
うみ‐うめ【熟梅】
熟した梅の実。金葉和歌集雑「葉がくれてつはると見えしほどもなくこは―となりにけるかな」
うみ‐うり【熟瓜】
熟した瓜の果実。存心要訓「―が熟柿を笑ふ」
うみ‐えら【海鰓】
八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミエラ科の花虫類。魚の鰓状を呈する群体を作り、ポリプは軸部の両側に突出して並ぶひだの上に配列する。群体の長さは約20センチメートルで、黄白または淡桃色。日本沿岸の浅海底に生息。なお、広くはトゲウミエラ科・フサウミエラ科などウミエラ類の総称。
うみ‐お【績苧・績麻】‥ヲ
つむいだ麻糸。うみそ。万葉集6「をとめらが―懸くとふ鹿背かせの山」
⇒うみお‐なす【績苧なす】
うみ‐おそ【海獺】‥ヲソ
アシカの異称。
うみ‐おと・す【生み落とす・産み落とす】
〔他五〕
子や卵を生む。分娩する。竹取物語「つばくらめ…七度巡りてなむ―・すめる」
うみ‐おなご【海女子】‥ヲナゴ
(→)磯姫いそひめに同じ。
うみお‐なす【績苧なす】‥ヲ‥
〔枕〕
「なが(長)」にかかる。万葉集6「―長柄ながらの宮に」
⇒うみ‐お【績苧・績麻】
うみ‐が【海処】
(カは所の意)海のほとり。古事記中「―行けば腰なづむ」↔陸くぬが
うみ‐がき【熟柿】
熟した柿の実。古今著聞集12「かたて矢はげて立ちたる上より、―の落ちけるが」
うみ‐かぜ【海風】
海から吹いてくる風。海の風。
うみ‐がた【海形】
海上の景色を模型に作ったもの。宇津保物語国譲中「左大将殿おほいなる―をして」
うみ‐が‐つき【産みが月】
うみづき。臨月。うむがつき。神代紀下「盈月うみがつき已に満ちて」
うみ‐かぶろ【海禿】
アシカの異称。
うみ‐がめ【海亀】
海産のカメ類の総称。アオウミガメ・アカウミガメ・タイマイ・オサガメなどの種類がある。いずれも形大きく、四肢はオール状またはひれ状。→青海亀(図)
アオウミガメ
提供:東京動物園協会
うみ‐うそ【海獺】
アシカの異称。
うみ‐うちわ【海団扇】‥ウチハ
海産の褐藻。潮間帯の潮溜りや潮下帯の岩に生育。下部は短い茎状をなして岩などに付着、上部は縁辺が巻いた扇状体。大きなものは高さ20センチメートルに達し、放射状に裂ける。生時淡黄色で、乾けば暗褐色。
うみ‐うなぎ【海鰻】
マアナゴの別称。
うみ‐うま【海馬】
タツノオトシゴの別称。(物類称呼)
うみ‐うめ【熟梅】
熟した梅の実。金葉和歌集雑「葉がくれてつはると見えしほどもなくこは―となりにけるかな」
うみ‐うり【熟瓜】
熟した瓜の果実。存心要訓「―が熟柿を笑ふ」
うみ‐えら【海鰓】
八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミエラ科の花虫類。魚の鰓状を呈する群体を作り、ポリプは軸部の両側に突出して並ぶひだの上に配列する。群体の長さは約20センチメートルで、黄白または淡桃色。日本沿岸の浅海底に生息。なお、広くはトゲウミエラ科・フサウミエラ科などウミエラ類の総称。
うみ‐お【績苧・績麻】‥ヲ
つむいだ麻糸。うみそ。万葉集6「をとめらが―懸くとふ鹿背かせの山」
⇒うみお‐なす【績苧なす】
うみ‐おそ【海獺】‥ヲソ
アシカの異称。
うみ‐おと・す【生み落とす・産み落とす】
〔他五〕
子や卵を生む。分娩する。竹取物語「つばくらめ…七度巡りてなむ―・すめる」
うみ‐おなご【海女子】‥ヲナゴ
(→)磯姫いそひめに同じ。
うみお‐なす【績苧なす】‥ヲ‥
〔枕〕
「なが(長)」にかかる。万葉集6「―長柄ながらの宮に」
⇒うみ‐お【績苧・績麻】
うみ‐が【海処】
(カは所の意)海のほとり。古事記中「―行けば腰なづむ」↔陸くぬが
うみ‐がき【熟柿】
熟した柿の実。古今著聞集12「かたて矢はげて立ちたる上より、―の落ちけるが」
うみ‐かぜ【海風】
海から吹いてくる風。海の風。
うみ‐がた【海形】
海上の景色を模型に作ったもの。宇津保物語国譲中「左大将殿おほいなる―をして」
うみ‐が‐つき【産みが月】
うみづき。臨月。うむがつき。神代紀下「盈月うみがつき已に満ちて」
うみ‐かぶろ【海禿】
アシカの異称。
うみ‐がめ【海亀】
海産のカメ類の総称。アオウミガメ・アカウミガメ・タイマイ・オサガメなどの種類がある。いずれも形大きく、四肢はオール状またはひれ状。→青海亀(図)
アオウミガメ
提供:東京動物園協会
 クロウミガメ
撮影:小宮輝之
クロウミガメ
撮影:小宮輝之
 タイマイ
提供:東京動物園協会
タイマイ
提供:東京動物園協会
 ヒメウミガメ
撮影:小宮輝之
ヒメウミガメ
撮影:小宮輝之
 うみ‐がも【海鴨】
主として海にすみ、潜水して採餌するカモ類。
うみ‐がらす【海烏】
チドリ目ウミスズメ科の海鳥。体はハトよりやや大きく、上面は灰黒色、下面は白色。大群をなして絶壁に産卵、潜水して巧みに魚を捕る。北方の海に分布し、サハリンのロッペン島(海豹島)はその繁殖地として有名。卵の色は変化が多い。ロッペンガモ。
うみがらす(夏羽)
うみ‐がも【海鴨】
主として海にすみ、潜水して採餌するカモ類。
うみ‐がらす【海烏】
チドリ目ウミスズメ科の海鳥。体はハトよりやや大きく、上面は灰黒色、下面は白色。大群をなして絶壁に産卵、潜水して巧みに魚を捕る。北方の海に分布し、サハリンのロッペン島(海豹島)はその繁殖地として有名。卵の色は変化が多い。ロッペンガモ。
うみがらす(夏羽)
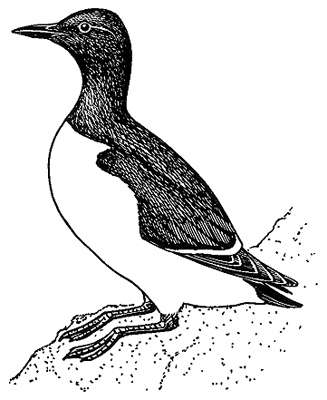 ウミガラス
撮影:小宮輝之
ウミガラス
撮影:小宮輝之
 →鳴声
提供:NHKサービスセンター
うみ‐からまつ【海唐松】
六放サンゴ亜綱ツノサンゴ目の花虫類。群体は一平面内で羽状に分岐して高さ2〜3メートルに達する。角質の骨格にとげがあり、白色または淡紅色の肉質部がその上をおおう。日本中部以南の浅海底に生育。骨格は黒珊瑚と称して印材・パイプその他の細工物とする。魔除まよけ珊瑚・角珊瑚ともいう。海松。
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
うみ‐からまつ【海唐松】
六放サンゴ亜綱ツノサンゴ目の花虫類。群体は一平面内で羽状に分岐して高さ2〜3メートルに達する。角質の骨格にとげがあり、白色または淡紅色の肉質部がその上をおおう。日本中部以南の浅海底に生育。骨格は黒珊瑚と称して印材・パイプその他の細工物とする。魔除まよけ珊瑚・角珊瑚ともいう。海松。
広辞苑 ページ 1944。