複数辞典一括検索+![]()
![]()
かい‐けいし【蓋擎子】🔗⭐🔉
かい‐けいし【蓋擎子】
(「蓋」はふた、「擎子」は台)蓋をした青磁の茶碗をのせる台。宮中で、正月歯固めなど供膳の時に用いた。
蓋擎子
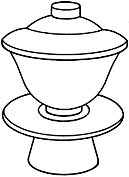
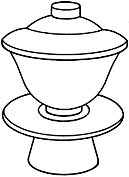
かいけいし‐ほ【会計士補】クワイ‥🔗⭐🔉
かいけいし‐ほ【会計士補】クワイ‥
公認会計士の補助を行う者。一定期間の実務補習などを経て、所定の試験に合格すると、公認会計士になる資格を得る。2006年廃止。
⇒かい‐けい【会計】
かいけい‐ねんど【会計年度】クワイ‥🔗⭐🔉
かいけい‐ねんど【会計年度】クワイ‥
収益・費用または収入・支出を区分整理し、その顛末を明らかにするために設けられた期間。また、その制度。日本の官公庁の制度では4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。企業では任意に設定される。事業年度。→営業年度。
⇒かい‐けい【会計】
かいけい‐の‐はじ【会稽の恥】クワイ‥ハヂ🔗⭐🔉
かいけい‐の‐はじ【会稽の恥】クワイ‥ハヂ
[史記越王勾践世家](春秋時代、越王勾践が、会稽山で呉王夫差に降伏したが、多年辛苦の後に夫差を破ってその恥をすすいだ故事から)以前に受けたひどい恥辱。「―をすすぐ」→石痳せきりんの味をなめて会稽の恥をすすぐ
⇒かいけい【会稽】
がいけい‐ひょうじゅん‐かぜい【外形標準課税】グワイ‥ヘウ‥クワ‥🔗⭐🔉
がいけい‐ひょうじゅん‐かぜい【外形標準課税】グワイ‥ヘウ‥クワ‥
事業所の資本金・従業員数など外面から明らかなものを課税標準とする課税。
⇒がい‐けい【外形】
かいけい‐ほう【会計法】クワイ‥ハフ🔗⭐🔉
かいけい‐ほう【会計法】クワイ‥ハフ
国の収入・支出・契約等に関する手続を定めた法律。1947年制定。明治憲法下の会計法は国の予算および会計に関する基本法であったが、そのうち予算・決算の手続に関しては、現在財政法が規定している。
⇒かい‐けい【会計】
かいけ‐おんせん【皆生温泉】‥ヲン‥🔗⭐🔉
かいけ‐おんせん【皆生温泉】‥ヲン‥
鳥取県西部、米子市北部美保湾に面する温泉地。1900年(明治33)発見。泉質は塩化物泉。
かい‐けつ【怪傑】クワイ‥🔗⭐🔉
かい‐けつ【怪傑】クワイ‥
ふしぎな力を持つ人物。
広辞苑 ページ 3221。