複数辞典一括検索+![]()
![]()
かたとき‐へんじ【片時片時】🔗⭐🔉
かたとき‐へんじ【片時片時】
「かたとき」を強めていう語。暫時。
⇒かた‐とき【片時】
かた‐どまり【片泊り】🔗⭐🔉
かた‐どまり【片泊り】
(→)「かたはたご」に同じ。
かた‐どり【肩取】🔗⭐🔉
かた‐どり【肩取】
肩取縅おどしの略。
⇒かたどり‐おどし【肩取縅】
かたどり‐おどし【肩取縅】‥ヲドシ🔗⭐🔉
かたどり‐おどし【肩取縅】‥ヲドシ
鎧よろいの袖の肩に当たる一の板・二の板、胴の前後の立挙たてあげの部分を、それ以外の部分と別の色でおどした様式の称。黒革縅で肩だけを赤縅にした黒革肩赤縅の類。
⇒かた‐どり【肩取】
かた‐ど・る【象る・模る】🔗⭐🔉
かた‐ど・る【象る・模る】
〔自五〕
(「形取る」の意)
①物の形を写しとる。まねる。似せる。紫式部日記「裳は海浦かいぶを織りて、大海のすりめに―・れり」。「数字を―・ったビスケット」
②形のないものをなにかの形にうつしかえる。象徴する。浮世物語「黒白三十の石を三十日に―・れり」
かた‐ど・る【方取る】🔗⭐🔉
かた‐ど・る【方取る】
〔自四〕
その方にばかり心が向く。栄華物語疑「学問に―・れるをば」
かた‐な【刀】🔗⭐🔉
かた‐な【刀】
(ナは刃の古語。片方の刃の意)
①刀身が短い片刃の刃物。垂仁紀「いましが袍ころもの中の―は何する―ぞ」↔剣。
②太刀の小さいもの。こしがたな。佩刀。平家物語9「腰の―を抜き、鎧の草摺ひきあげて、柄もこぶしも通れ通れと」
③小さい刃物。きれもの。
④脇差に添えておびる大刀。大小の大の方。
刀
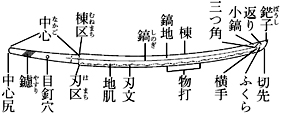 ⇒かたな‐かけ【刀掛け】
⇒かたな‐かじ【刀鍛冶】
⇒かたな‐がり【刀狩】
⇒かたな‐きず【刀疵】
⇒かたな‐さし【刀差し】
⇒かたな‐ざんまい【刀三昧】
⇒かたな‐だま【刀玉】
⇒かたな‐と【刀砥】
⇒かたな‐とぎ【刀磨ぎ】
⇒かたな‐の‐はわたり【刀の刃渡り】
⇒かたな‐ばや【刀早】
⇒かたな‐びき【刀引き】
⇒かたな‐め【刀目】
⇒かたな‐めい【刀銘】
⇒かたな‐めきき【刀目利き】
⇒かたな‐もち【刀持ち】
⇒かたな‐よごし【刀汚し】
⇒刀折れ矢尽きる
⇒刀にかけて
⇒かたな‐かけ【刀掛け】
⇒かたな‐かじ【刀鍛冶】
⇒かたな‐がり【刀狩】
⇒かたな‐きず【刀疵】
⇒かたな‐さし【刀差し】
⇒かたな‐ざんまい【刀三昧】
⇒かたな‐だま【刀玉】
⇒かたな‐と【刀砥】
⇒かたな‐とぎ【刀磨ぎ】
⇒かたな‐の‐はわたり【刀の刃渡り】
⇒かたな‐ばや【刀早】
⇒かたな‐びき【刀引き】
⇒かたな‐め【刀目】
⇒かたな‐めい【刀銘】
⇒かたな‐めきき【刀目利き】
⇒かたな‐もち【刀持ち】
⇒かたな‐よごし【刀汚し】
⇒刀折れ矢尽きる
⇒刀にかけて
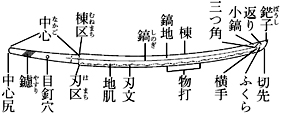 ⇒かたな‐かけ【刀掛け】
⇒かたな‐かじ【刀鍛冶】
⇒かたな‐がり【刀狩】
⇒かたな‐きず【刀疵】
⇒かたな‐さし【刀差し】
⇒かたな‐ざんまい【刀三昧】
⇒かたな‐だま【刀玉】
⇒かたな‐と【刀砥】
⇒かたな‐とぎ【刀磨ぎ】
⇒かたな‐の‐はわたり【刀の刃渡り】
⇒かたな‐ばや【刀早】
⇒かたな‐びき【刀引き】
⇒かたな‐め【刀目】
⇒かたな‐めい【刀銘】
⇒かたな‐めきき【刀目利き】
⇒かたな‐もち【刀持ち】
⇒かたな‐よごし【刀汚し】
⇒刀折れ矢尽きる
⇒刀にかけて
⇒かたな‐かけ【刀掛け】
⇒かたな‐かじ【刀鍛冶】
⇒かたな‐がり【刀狩】
⇒かたな‐きず【刀疵】
⇒かたな‐さし【刀差し】
⇒かたな‐ざんまい【刀三昧】
⇒かたな‐だま【刀玉】
⇒かたな‐と【刀砥】
⇒かたな‐とぎ【刀磨ぎ】
⇒かたな‐の‐はわたり【刀の刃渡り】
⇒かたな‐ばや【刀早】
⇒かたな‐びき【刀引き】
⇒かたな‐め【刀目】
⇒かたな‐めい【刀銘】
⇒かたな‐めきき【刀目利き】
⇒かたな‐もち【刀持ち】
⇒かたな‐よごし【刀汚し】
⇒刀折れ矢尽きる
⇒刀にかけて
広辞苑 ページ 3825。