複数辞典一括検索+![]()
![]()
きみ‐がり【君許】🔗⭐🔉
きみ‐けいせい【君傾城】🔗⭐🔉
きみ‐けいせい【君傾城】
(君と傾城と同義の語を重ねたもの)遊女。
きみ‐ざね【君ざね】🔗⭐🔉
きみ‐ざね【君ざね】
(ザネは接尾語)本妻。大和物語「我が―と頼むいかにぞ」
きみ‐さま【君様】🔗⭐🔉
きみ‐さま【君様】
①相手を敬っていう語。あなたさま。竹斎「―は当世はやる藪医師、人を殺しやる」
②男女が互いにその恋人を親しんでいう語。かのさま。かたさま。松の葉1「まだ夜は夜中よ、しげれとんと―」
③遊女を敬っていう語。好色一代男3「今や今やと待つほどに―の足音して」
きみさわ‐がた【君沢形】‥サハ‥🔗⭐🔉
きみさわ‐がた【君沢形】‥サハ‥
幕末、ロシア使節プチャーチンが伊豆国君沢郡戸田へだ村でスクーナー型帆船を建造して帰国した後、幕府が同地の船大工に造らせた同型帆船。1857年(安政4)に竣工。
き‐みじか【気短】🔗⭐🔉
き‐みじか【気短】
気の短いこと。せっかちで、ゆっくり待てないこと。「―な人」↔気長
きみ‐しぐれ【黄身時雨】🔗⭐🔉
きみ‐しぐれ【黄身時雨】
白餡しろあんに卵黄と砂糖とを加えてねり、微塵粉みじんこをまぜ、蒸した菓子。
黄身時雨
撮影:関戸 勇
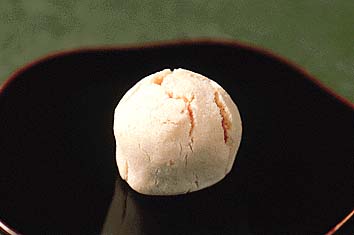
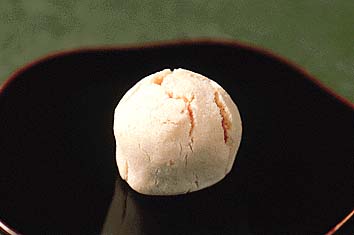
広辞苑 ページ 4952。