複数辞典一括検索+![]()
![]()
ごう‐ちょう【郷長】ガウチヤウ🔗⭐🔉
ごう‐ちょう【郷長】ガウチヤウ
律令時代、郡司の下にあって、1郷の戸口の監督、農業の奨励、非違の禁察、賦役の催促などをつかさどった地方官。717年(養老1)の郷里制施行前の里長に相当。さとおさ。
ごう‐ちょう【郷帳】ガウチヤウ🔗⭐🔉
ごう‐ちょう【郷帳】ガウチヤウ
①(→)取箇郷帳とりかごうちょうに同じ。
②江戸幕府が国郡ごとに村名・村高を記した帳簿。「天保―」→御前帳ごぜんちょう
こうちょう‐えき【高張液】カウチヤウ‥🔗⭐🔉
こうちょう‐えき【高張液】カウチヤウ‥
特に生体組織や細胞内液にとって高張である液体。この液に浸すと内部の水を奪われるため、動物細胞は収縮、植物細胞は原形質分離をおこす。
⇒こう‐ちょう【高張】
こうちょう‐かい【公聴会】‥チヤウクワイ🔗⭐🔉
こうちょう‐かい【公聴会】‥チヤウクワイ
国または地方公共団体の機関において、一般的関心および目的を有する重要な議案について利害関係者・学識経験者などから意見を聴く制度。
こうちょう‐し【貢調使】‥テウ‥🔗⭐🔉
こうちょう‐し【貢調使】‥テウ‥
四度使しどのつかいの一つ。古代、諸国の調・庸などの額を記した調帳を調・庸とともに京に運んで納入する使い。調使。調庸使。調帳使。
⇒こう‐ちょう【貢調】
こう‐ちょうし【皇長子】クワウチヤウ‥🔗⭐🔉
こう‐ちょうし【皇長子】クワウチヤウ‥
天皇の長子。
こうちょう‐じゅうにせん【皇朝十二銭】クワウテウジフ‥🔗⭐🔉
こうちょう‐じゅうにせん【皇朝十二銭】クワウテウジフ‥
奈良時代から平安時代にかけて日本で鋳造した12種の銭貨。円形・方孔の銅銭。和同開珎には銀銭もある。本朝十二銭。
皇朝十二銭(表)
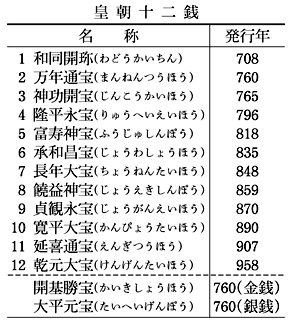 ⇒こう‐ちょう【皇朝】
⇒こう‐ちょう【皇朝】
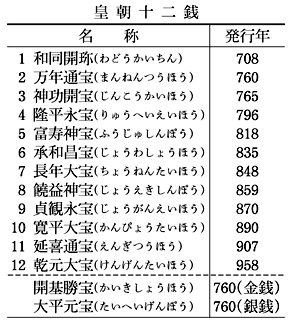 ⇒こう‐ちょう【皇朝】
⇒こう‐ちょう【皇朝】
こうちょうしりゃく【皇朝史略】クワウテウ‥🔗⭐🔉
こうちょうしりゃく【皇朝史略】クワウテウ‥
神武天皇から後小松天皇までの漢文体の史書。青山延于のぶゆき著。正編12巻、続編5巻。正編は1823年(文政6)成稿、26年刊。「大日本史」を簡略にしたもの。
広辞苑 ページ 6725。