複数辞典一括検索+![]()
![]()
コギト‐エルゴ‐スム【cogito, ergo sum ラテン】🔗⭐🔉
コギト‐エルゴ‐スム【cogito, ergo sum ラテン】
〔哲〕デカルトが「方法序説」でのべた言葉。「私は考える、ゆえに私はある」の意で、彼はあらゆることを懐疑したあげく、意識の内容は疑いえても、意識する私の存在は疑いえないという結論に到達し、これを第一原理とし、確実な認識の出発点とした。
ご‐きない【五畿内】🔗⭐🔉
ご‐きない【五畿内】
「畿内」参照。
こ‐ぎぬ【小衣】🔗⭐🔉
こ‐ぎぬ【小衣】
半袖または袖無しの短い仕事着。
こぎ‐ぬ・ける【漕ぎ抜ける】🔗⭐🔉
こぎ‐ぬ・ける【漕ぎ抜ける】
〔自下一〕
困難などを、通り抜ける。切り抜ける。
こぎ‐の‐こ【胡鬼の子】🔗⭐🔉
こぎ‐の‐こ【胡鬼の子】
①羽子。羽根。胡鬼。「黙れ子供羽を抜いてやらうに、―にせいやれ」(狂言歌謡)
②ツクバネの木。また、その実。〈[季]秋〉
ごき‐の‐み【御器の実】🔗⭐🔉
ごき‐の‐み【御器の実】
(御器の中に入れる実の意)飯。また、飯のたね。生活の手段。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「海道筋の―をぶちあげ」
こきば‐く【幾許く】🔗⭐🔉
こきば‐く【幾許く】
〔副〕
甚だしく。たいそう。万葉集20「―もゆたけきかも」
こき‐ばし【扱き箸】🔗⭐🔉
こき‐ばし【扱き箸】
50センチメートル前後の丸竹2本または割り竹の一端を括って、2本の間に稲の穂を挟んで扱く具。稲扱箸いねこばし。こいばし。→千歯せんば
こぎ‐は・つ【漕ぎ泊つ】🔗⭐🔉
こぎ‐は・つ【漕ぎ泊つ】
〔自下二〕
漕ぎ着いて碇泊する。万葉集3「わが船は比良の湊に―・てむ」
こ‐きび【小気味】🔗⭐🔉
こ‐きび【小気味】
コキミの訛。
ごき‐ひき【御器挽き】🔗⭐🔉
ごき‐ひき【御器挽き】
木地屋の別名。御器師ごきしとも。
こ‐きぶつ【古器物】🔗⭐🔉
こ‐きぶつ【古器物】
ふるい器物。古器。
ごきぶり【蜚蠊】🔗⭐🔉
ごきぶり【蜚蠊】
(御器ごき噛かぶりの転)ゴキブリ目ゴキブリ科の昆虫の総称。体は甚だしく扁平で幅が広く楕円形。多くは褐色や黒褐色で、油に浸ったような光沢がある。家住性のものは人間や荷物などの移動に伴って広く伝播し、台所などで食品を害するほか、伝染病を媒介する。ワモンゴキブリ、チャバネゴキブリなど。アブラムシ。古名、あくたむし・つのむし。〈[季]夏〉
クロゴキブリ
撮影:海野和男
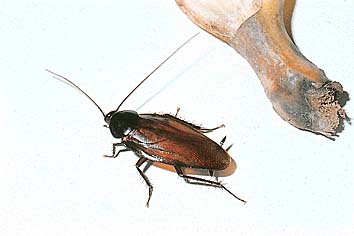 チャバネゴキブリ
撮影:海野和男
チャバネゴキブリ
撮影:海野和男
 ヤマトゴキブリ
撮影:海野和男
ヤマトゴキブリ
撮影:海野和男
 ワモンゴキブリ
撮影:海野和男
ワモンゴキブリ
撮影:海野和男

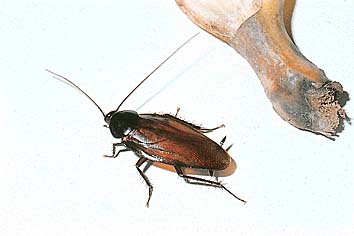 チャバネゴキブリ
撮影:海野和男
チャバネゴキブリ
撮影:海野和男
 ヤマトゴキブリ
撮影:海野和男
ヤマトゴキブリ
撮影:海野和男
 ワモンゴキブリ
撮影:海野和男
ワモンゴキブリ
撮影:海野和男

広辞苑 ページ 6919。