複数辞典一括検索+![]()
![]()
うちわ【団扇】ウチハ🔗⭐🔉
うちわ【団扇】ウチハ
(打羽の意)
①細い竹を骨とし、紙または絹を張って柄をつけた、あおいで風を起こす道具。多くは円形。〈[季]夏〉。「―であおぐ」
②軍配団扇ぐんばいうちわの略。
③1をかたどった紋所の名。一つ団扇・三つ団扇・団扇梅鉢などがある。
⇒うちわ‐えび【団扇海老】
⇒うちわ‐サボテン【団扇サボテン】
⇒うちわ・す【団扇す】
⇒うちわ‐だいこ【団扇太鼓】
うち‐わ【内輪・内曲】🔗⭐🔉
うち‐わ【内輪・内曲】
①他人(外部の者)をまじえないこと。家内。一家親族。「―の者だけの集まり」
②他人に示さないこと。内密。「―話」
③ひかえめにすること。出過ぎないこと。「―に見積もる」
④爪先が内方へ向いていること。
⇒うちわ‐げんか【内輪喧嘩】
⇒うちわ‐もめ【内輪揉め】
⇒うちわ‐われ【内輪割れ】
うちわ‐えび【団扇海老】ウチハ‥🔗⭐🔉
うちわ‐えび【団扇海老】ウチハ‥
セミエビ科のエビ。体は扁平で横に広く、一見、団扇状。全体が濃い紫褐色。体長15センチメートル。深さ約100メートルまでの泥底に生息、房総半島から南太平洋に分布。食用。近縁種に甲の側縁の歯が大きいオオバ‐ウチワエビがいる。
うちわえび
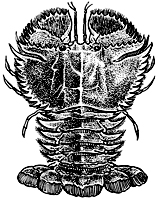 ウチワエビ
提供:東京動物園協会
ウチワエビ
提供:東京動物園協会
 ⇒うちわ【団扇】
⇒うちわ【団扇】
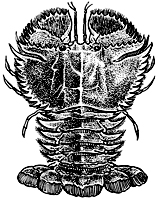 ウチワエビ
提供:東京動物園協会
ウチワエビ
提供:東京動物園協会
 ⇒うちわ【団扇】
⇒うちわ【団扇】
うち‐わく【内枠】🔗⭐🔉
うち‐わく【内枠】
①内側の枠。特に、競馬の枠順にいう。↔外枠。
②割り当てられた範囲内。
うち‐わけ【内分け】🔗⭐🔉
うち‐わけ【内分け】
近世、本家が所持する石高の一部を跡取り以外の子弟に与えながら、領主へは本家が所持するものとして、年貢・諸役のすべてを負担すること。
うち‐わけ【内訳】🔗⭐🔉
うち‐わけ【内訳】
金銭・物品の総高に対し、その内容を小分けにして品名・数量などを示すこと。「支出の―」
うち‐わけ【打分け】🔗⭐🔉
うち‐わけ【打分け】
囲碁で、勝敗が同数で優劣が決まらないこと。
うちわ‐げんか【内輪喧嘩】‥クワ🔗⭐🔉
うちわ‐げんか【内輪喧嘩】‥クワ
(→)「うちわもめ」に同じ。
⇒うち‐わ【内輪・内曲】
うちわ・す【団扇す】ウチハ‥🔗⭐🔉
うちわ・す【団扇す】ウチハ‥
〔他サ変〕
うちわをつかう。うちわであおぐ。能因本枕草子前の木立高う庭広き家の「うしろにゐて―・するもあり」
⇒うちわ【団扇】
うち‐わた【打綿】🔗⭐🔉
うち‐わた【打綿】
綿弓で打った綿。特に、古綿を打ちかえしたもの。
うちわ‐だいこ【団扇太鼓】ウチハ‥🔗⭐🔉
うちわ‐だいこ【団扇太鼓】ウチハ‥
一枚革を円く張り、柄をつけた太鼓。日蓮宗で用いる。
⇒うちわ【団扇】
うち‐わたし【内渡し】🔗⭐🔉
うち‐わたし【内渡し】
支払うべき金額の一部分を払い渡すこと。また、その金。
うち‐わたし【打ち渡し】🔗⭐🔉
うち‐わたし【打ち渡し】
⇒うちわたす3
うちわたし‐じょう【打渡状】‥ジヤウ🔗⭐🔉
うちわたし‐じょう【打渡状】‥ジヤウ
中世、土地の処分に関して、幕府の遵行状じゅんぎょうじょう・施行状せぎょうじょうを受けた守護代・代官などの遵行使が現地(下地したじ)を権利者に引き渡す時に出す文書。
うち‐わた・す【打ち渡す】🔗⭐🔉
うち‐わた・す【打ち渡す】
〔他四〕
①「渡す」を強めていう語。万葉集4「佐保の川門かわとの清き瀬を馬―・しいつか通はむ」
②見渡す。万葉集4「―・す竹田の原に鳴く鶴たずの」
③(連用形を副詞的に用いて)おしなべて。総じて。源氏物語宿木「―・し世にゆるしなき関川を」
うち‐わたり【内辺】🔗⭐🔉
うち‐わたり【内辺】
内裏だいり。宮中。大内。源氏物語賢木「年もかはりぬれば、―花やかに」
うちわ‐もめ【内輪揉め】🔗⭐🔉
うちわ‐もめ【内輪揉め】
家内の争い。味方同士の紛争。内輪喧嘩。
⇒うち‐わ【内輪・内曲】
うち‐わり【内割】🔗⭐🔉
うち‐わり【内割】
①内べりによって減じた分量。
②歩合高の元高に対する比。↔外割
うち‐わりびき【内割引】🔗⭐🔉
うち‐わりびき【内割引】
(→)銀行割引に同じ。
うち‐わ・る【打ち割る】🔗⭐🔉
うち‐わ・る【打ち割る】
〔他五〕
①たたき割る。
②打ち明ける。「―・って話せば」「腹を―・った話合い」
うちわ‐われ【内輪割れ】🔗⭐🔉
うちわ‐われ【内輪割れ】
内輪もめの結果、今までの仲がこわれること。仲間割れ。
⇒うち‐わ【内輪・内曲】
○家を空けるうちをあける
外出して家にいない。
⇒うち【内】
○内を外にするうちをそとにする
(遊蕩などで)出歩いていて、家にいることが少ないことにいう。
⇒うち【内】
○内を出違ううちをでちがう
訪れてくる人を避けるため、入れ違いに家を出る。
⇒うち【内】
広辞苑に「うちわ」で始まるの検索結果 1-23。