複数辞典一括検索+![]()
![]()
○叶わぬ時の神頼みかなわぬときのかみだのみ🔗⭐🔉
○叶わぬ時の神頼みかなわぬときのかみだのみ
平素は神を拝まない者が、困った時にだけ神の助けを頼みにすること。「苦しい時の神頼み」「困った時の神頼み」などとも。
⇒かな・う【適う・叶う】
かな‐わらび【鉄蕨】
オシダ科の常緑シダ数種の総称。葉は革質で硬い。葉柄には鱗片があり、ごわごわする。日本の関東以西から東南アジアに広く分布。
かな‐わん【金椀】
金属製の椀。かなまり。
か‐なん【火難】クワ‥
火による災難。火災。
かなん【河南】
(Henan)
①中国、華北地区南部の省。黄河中流以南を占め、黄河北方若干をも省域に含む。省都は鄭州。殷代以後しばしば洛陽・開封が首都となった。面積約17万平方キロメートル。別称、中州・豫よ。→中華人民共和国(図)。
②周代、洛陽の別称。
か‐なん【家難】
一家の災難。
か‐なん【華南】クワ‥
中国南部の称。今日の行政区分では、広東・海南両省と広西チワン族自治区を指す。福建・香港・マカオ・台湾を含めることもある。
か‐なん【禍難】クワ‥
災難。わざわい。
カナン【Canaan】
聖書におけるパレスチナの称。神がアブラハムとその子孫に与えると約束した地。前13世紀ごろ、イスラエルの民が定住。
かなんぷ【河南浦】
(カナンフとも)雅楽の唐楽、黄鐘調おうしきちょうの曲。舞人3人。料理の魚の骨をのどに刺して苦しむさまを表す。仁明天皇の大嘗会だいじょうえに尾張浜主が作ったという。楽・舞ともに廃絶。河南府。
かに【蟹】
①エビ目(十脚類)カニ亜目(短尾類)の甲殻類の総称。体は1枚の頭胸甲(甲あるいは甲羅と呼ばれる)で覆われた頭胸部と、7節に分かれた腹部をもつが、頭胸部は扁平で横に広くなり、腹部は小さくなって一般に頭胸部の下面に折り畳まれている。頭胸部の5対の歩脚のうち第1対は鋏脚(はさみ)となる。横向きに歩行するのが一般的であるが、前向きに歩く種も少なくない。雌は産んだ卵を腹肢に着け、孵化まで保護する。世界に約6000種、日本に約1200種。多くが海産であるが、約6000種の内500種あまりが淡水産である。食用として重要なガザミ・ケガニ・ズワイガニなどがある。〈[季]夏〉。古事記中「この―や何処いずくの―…横去らふ何処に到る」
②「かにくそ」の略。宇津保物語蔵開上「―といふもの、ゆめばかり付き給はぬこそなけれ」
⇒蟹の穴這入り
⇒蟹は甲羅に似せて穴を掘る
かに【可児】
岐阜県南部、木曾川左岸にある市。第二次大戦後、自動車部品工業が発展。人口9万8千。
がに【蟹】
①(全国的に広く用いられる方言)カニ。
②カニの呼吸器の部分。「かには食うとも―食うな」
がに
〔助詞〕
(接続助詞)
①(動詞・助動詞の終止形に付く。多く完了の助動詞「ぬ」に付き「ぬがに」の形をとる。一説に、疑問の助詞「か」と格助詞「に」との結合という)…しそうに。…するばかりに。…するかのように。万葉集8「生ふる橘玉に貫く五月を近み零あえぬ―花咲きにけり」。古今和歌集賀「桜花散りかひ曇れ…道紛ふ―」
②(動詞・助動詞の連体形に付く。願望・命令・禁止などを表す文と共に使われ、その理由・目的を表す。一説に「がね」の方言的転化という)…するだろうから。…するように。万葉集14「おもしろき野をばな焼きそ古草に新草にいくさまじり生ひは生ふる―」。古今和歌集哀傷「泣く涙雨と降らなむわたりがは水まさりなば帰り来る―」
か‐に‐あられ【窠に霰】クワ‥
織りの文様。霰文様(のちの石畳模様)の地に窠文かもんを散らしたもの。公卿若年の束帯の表袴うえのはかまなどに用いられた。
窠に霰
 かに‐いし【蟹石】
カニの化石。またはカニに似た形の貝の化石。
かに‐かくに
〔副〕
とやかくと。あれこれと。いろいろと。万葉集4「―人はいふとも」
か‐にく【果肉】クワ‥
液果実のうち、水分を多く含み多肉となる部分。
かにくい‐ざる【蟹食い猿】‥クヒ‥
オナガザル科のサル。体色はふつう黄褐色。ニホンザルに似るが、やや小形。頭胴長・尾長ともに50センチメートルほど。東南アジアに広く分布。20〜30頭の群れをつくる。森林に多いが、海岸にも出てくる。雑食性で、特にカニを好むわけではない。
かに‐くさ【蟹草】
カニクサ科の多年生シダ。地上部は長い蔓状をなすが、この全体が葉であって、蔓に当たる針金様の部分は葉柄である。地下には根茎が横走。葉は羽状複葉。胞子嚢・胞子を集めて「海金砂」と呼び丸薬の衣とする。ツルシノブ。シャミセンヅル。
かに‐くそ【蟹屎】
①赤子が生後初めてする大便。色黒く粘り気がある。かにばば。かに。胎便。
②湖水の葦あしなどにつく魚の卵。
かに‐ぐも【蟹蜘蛛】
カニグモ科のクモ類の総称。体長2〜20ミリメートル。歩脚が横に伸び、発達した前脚を広げて歩くさまが蟹を思わせる。徘徊性で網を張らず草木の上や地上で昆虫を待ち伏せし、脚で抱えるようにして捕らえる。世界中に分布し、日本には約60種。
かに‐こうせん【蟹工船】
北洋で蟹漁をして、船中で直ちに缶詰などに加工する設備をもった加工母船。
かにこうせん【蟹工船】
小説。小林多喜二作。1929年「戦旗」に発表。過酷な蟹工船の中で展開する弾圧と抗争、未組織労働者の覚醒を描いた、初期プロレタリア文学の代表的作品。
→文献資料[蟹工船]
かに‐こうもり【蟹蝙蝠】‥カウ‥
キク科の多年草。高さ0.5〜1メートル。葉は互生し、形がカニの甲に似る。夏、白色の管状花を数個集めた頭状花を茎頂につける。亜高山帯針葉樹林を中心に、本州・四国・九州に分布。
かにこうもり
かに‐いし【蟹石】
カニの化石。またはカニに似た形の貝の化石。
かに‐かくに
〔副〕
とやかくと。あれこれと。いろいろと。万葉集4「―人はいふとも」
か‐にく【果肉】クワ‥
液果実のうち、水分を多く含み多肉となる部分。
かにくい‐ざる【蟹食い猿】‥クヒ‥
オナガザル科のサル。体色はふつう黄褐色。ニホンザルに似るが、やや小形。頭胴長・尾長ともに50センチメートルほど。東南アジアに広く分布。20〜30頭の群れをつくる。森林に多いが、海岸にも出てくる。雑食性で、特にカニを好むわけではない。
かに‐くさ【蟹草】
カニクサ科の多年生シダ。地上部は長い蔓状をなすが、この全体が葉であって、蔓に当たる針金様の部分は葉柄である。地下には根茎が横走。葉は羽状複葉。胞子嚢・胞子を集めて「海金砂」と呼び丸薬の衣とする。ツルシノブ。シャミセンヅル。
かに‐くそ【蟹屎】
①赤子が生後初めてする大便。色黒く粘り気がある。かにばば。かに。胎便。
②湖水の葦あしなどにつく魚の卵。
かに‐ぐも【蟹蜘蛛】
カニグモ科のクモ類の総称。体長2〜20ミリメートル。歩脚が横に伸び、発達した前脚を広げて歩くさまが蟹を思わせる。徘徊性で網を張らず草木の上や地上で昆虫を待ち伏せし、脚で抱えるようにして捕らえる。世界中に分布し、日本には約60種。
かに‐こうせん【蟹工船】
北洋で蟹漁をして、船中で直ちに缶詰などに加工する設備をもった加工母船。
かにこうせん【蟹工船】
小説。小林多喜二作。1929年「戦旗」に発表。過酷な蟹工船の中で展開する弾圧と抗争、未組織労働者の覚醒を描いた、初期プロレタリア文学の代表的作品。
→文献資料[蟹工船]
かに‐こうもり【蟹蝙蝠】‥カウ‥
キク科の多年草。高さ0.5〜1メートル。葉は互生し、形がカニの甲に似る。夏、白色の管状花を数個集めた頭状花を茎頂につける。亜高山帯針葉樹林を中心に、本州・四国・九州に分布。
かにこうもり
 かに‐ざ【蟹座】
(Cancer ラテン)黄道上の第5星座。双子座ふたござの東、獅子座ししざの西にある。3月下旬の夕刻に南中。光輝は乏しい。
蟹座
かに‐ざ【蟹座】
(Cancer ラテン)黄道上の第5星座。双子座ふたござの東、獅子座ししざの西にある。3月下旬の夕刻に南中。光輝は乏しい。
蟹座
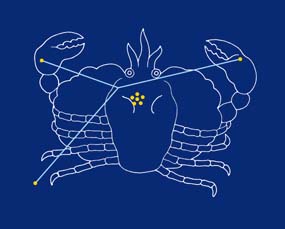 カニシカ【Kaniṣka 梵】
2世紀頃のクシャーナ朝の第3代国王。その領土は、南はインドのマトゥラー、東はパミールを越え于闐うてんに及び、クシャーナ朝の黄金期を現出。仏教を保護奨励し、特にガンダーラ地方は仏教の最も盛んな地となる。一説に、第4回仏典結集を行なったという。迦膩色迦。
かに‐せいうん【蟹星雲】
(Crab nebula)牡牛座にある星雲。強い電波源で、中心に中性子星のパルサーが見つかる。藤原定家の日記「明月記」と中国の記録とによって、1054年(天喜2)に木星ほどに明るく輝いた超新星の残骸であることがわかった。
かに‐たま【蟹玉】
中国料理。蟹の身と数種の野菜を入れて、芙蓉の花のようにふわっと仕上げた卵焼き。芙蓉蟹フーヨーハイ。
かに‐だまし【蟹瞞し】
カニダマシ科の甲殻類の総称。形はカニに似ているが、真のカニ類ではない。扁平な頭胸甲の腹面に腹部が折り曲げられており、第1歩脚は大きな鋏脚となる。小形で一般に甲長20ミリメートルまで。多くは潮間帯の転石の下や浅海の泥底などにすみ、後退りして歩く。本州中部以南の潮間帯に普通のイソカニダマシなど。
カニッツァーロ【Stanislao Cannizzaro】
イタリアの化学者。アボガドロの仮説を復活させ、原子量および分子量を推定する方法を確立。ベンズアルデヒドが水酸化カリウムの作用により安息香酸カリウムとベンジル‐アルコールを生成する反応を発見。(1826〜1910)→不均化
かに‐とり【蟹取】
貴人の生児の産衣うぶぎ。生絹すずしの練絹ねりぎぬを薄縹うすはなだに染め、蟹・鶴・宝尽たからづくしなどの小紋をつける。蟹取小袖こそで。
⇒かにとり‐こもん【蟹取小紋】
かにとり‐こもん【蟹取小紋】
蟹取の小紋。
⇒かに‐とり【蟹取】
カニシカ【Kaniṣka 梵】
2世紀頃のクシャーナ朝の第3代国王。その領土は、南はインドのマトゥラー、東はパミールを越え于闐うてんに及び、クシャーナ朝の黄金期を現出。仏教を保護奨励し、特にガンダーラ地方は仏教の最も盛んな地となる。一説に、第4回仏典結集を行なったという。迦膩色迦。
かに‐せいうん【蟹星雲】
(Crab nebula)牡牛座にある星雲。強い電波源で、中心に中性子星のパルサーが見つかる。藤原定家の日記「明月記」と中国の記録とによって、1054年(天喜2)に木星ほどに明るく輝いた超新星の残骸であることがわかった。
かに‐たま【蟹玉】
中国料理。蟹の身と数種の野菜を入れて、芙蓉の花のようにふわっと仕上げた卵焼き。芙蓉蟹フーヨーハイ。
かに‐だまし【蟹瞞し】
カニダマシ科の甲殻類の総称。形はカニに似ているが、真のカニ類ではない。扁平な頭胸甲の腹面に腹部が折り曲げられており、第1歩脚は大きな鋏脚となる。小形で一般に甲長20ミリメートルまで。多くは潮間帯の転石の下や浅海の泥底などにすみ、後退りして歩く。本州中部以南の潮間帯に普通のイソカニダマシなど。
カニッツァーロ【Stanislao Cannizzaro】
イタリアの化学者。アボガドロの仮説を復活させ、原子量および分子量を推定する方法を確立。ベンズアルデヒドが水酸化カリウムの作用により安息香酸カリウムとベンジル‐アルコールを生成する反応を発見。(1826〜1910)→不均化
かに‐とり【蟹取】
貴人の生児の産衣うぶぎ。生絹すずしの練絹ねりぎぬを薄縹うすはなだに染め、蟹・鶴・宝尽たからづくしなどの小紋をつける。蟹取小袖こそで。
⇒かにとり‐こもん【蟹取小紋】
かにとり‐こもん【蟹取小紋】
蟹取の小紋。
⇒かに‐とり【蟹取】
 かに‐いし【蟹石】
カニの化石。またはカニに似た形の貝の化石。
かに‐かくに
〔副〕
とやかくと。あれこれと。いろいろと。万葉集4「―人はいふとも」
か‐にく【果肉】クワ‥
液果実のうち、水分を多く含み多肉となる部分。
かにくい‐ざる【蟹食い猿】‥クヒ‥
オナガザル科のサル。体色はふつう黄褐色。ニホンザルに似るが、やや小形。頭胴長・尾長ともに50センチメートルほど。東南アジアに広く分布。20〜30頭の群れをつくる。森林に多いが、海岸にも出てくる。雑食性で、特にカニを好むわけではない。
かに‐くさ【蟹草】
カニクサ科の多年生シダ。地上部は長い蔓状をなすが、この全体が葉であって、蔓に当たる針金様の部分は葉柄である。地下には根茎が横走。葉は羽状複葉。胞子嚢・胞子を集めて「海金砂」と呼び丸薬の衣とする。ツルシノブ。シャミセンヅル。
かに‐くそ【蟹屎】
①赤子が生後初めてする大便。色黒く粘り気がある。かにばば。かに。胎便。
②湖水の葦あしなどにつく魚の卵。
かに‐ぐも【蟹蜘蛛】
カニグモ科のクモ類の総称。体長2〜20ミリメートル。歩脚が横に伸び、発達した前脚を広げて歩くさまが蟹を思わせる。徘徊性で網を張らず草木の上や地上で昆虫を待ち伏せし、脚で抱えるようにして捕らえる。世界中に分布し、日本には約60種。
かに‐こうせん【蟹工船】
北洋で蟹漁をして、船中で直ちに缶詰などに加工する設備をもった加工母船。
かにこうせん【蟹工船】
小説。小林多喜二作。1929年「戦旗」に発表。過酷な蟹工船の中で展開する弾圧と抗争、未組織労働者の覚醒を描いた、初期プロレタリア文学の代表的作品。
→文献資料[蟹工船]
かに‐こうもり【蟹蝙蝠】‥カウ‥
キク科の多年草。高さ0.5〜1メートル。葉は互生し、形がカニの甲に似る。夏、白色の管状花を数個集めた頭状花を茎頂につける。亜高山帯針葉樹林を中心に、本州・四国・九州に分布。
かにこうもり
かに‐いし【蟹石】
カニの化石。またはカニに似た形の貝の化石。
かに‐かくに
〔副〕
とやかくと。あれこれと。いろいろと。万葉集4「―人はいふとも」
か‐にく【果肉】クワ‥
液果実のうち、水分を多く含み多肉となる部分。
かにくい‐ざる【蟹食い猿】‥クヒ‥
オナガザル科のサル。体色はふつう黄褐色。ニホンザルに似るが、やや小形。頭胴長・尾長ともに50センチメートルほど。東南アジアに広く分布。20〜30頭の群れをつくる。森林に多いが、海岸にも出てくる。雑食性で、特にカニを好むわけではない。
かに‐くさ【蟹草】
カニクサ科の多年生シダ。地上部は長い蔓状をなすが、この全体が葉であって、蔓に当たる針金様の部分は葉柄である。地下には根茎が横走。葉は羽状複葉。胞子嚢・胞子を集めて「海金砂」と呼び丸薬の衣とする。ツルシノブ。シャミセンヅル。
かに‐くそ【蟹屎】
①赤子が生後初めてする大便。色黒く粘り気がある。かにばば。かに。胎便。
②湖水の葦あしなどにつく魚の卵。
かに‐ぐも【蟹蜘蛛】
カニグモ科のクモ類の総称。体長2〜20ミリメートル。歩脚が横に伸び、発達した前脚を広げて歩くさまが蟹を思わせる。徘徊性で網を張らず草木の上や地上で昆虫を待ち伏せし、脚で抱えるようにして捕らえる。世界中に分布し、日本には約60種。
かに‐こうせん【蟹工船】
北洋で蟹漁をして、船中で直ちに缶詰などに加工する設備をもった加工母船。
かにこうせん【蟹工船】
小説。小林多喜二作。1929年「戦旗」に発表。過酷な蟹工船の中で展開する弾圧と抗争、未組織労働者の覚醒を描いた、初期プロレタリア文学の代表的作品。
→文献資料[蟹工船]
かに‐こうもり【蟹蝙蝠】‥カウ‥
キク科の多年草。高さ0.5〜1メートル。葉は互生し、形がカニの甲に似る。夏、白色の管状花を数個集めた頭状花を茎頂につける。亜高山帯針葉樹林を中心に、本州・四国・九州に分布。
かにこうもり
 かに‐ざ【蟹座】
(Cancer ラテン)黄道上の第5星座。双子座ふたござの東、獅子座ししざの西にある。3月下旬の夕刻に南中。光輝は乏しい。
蟹座
かに‐ざ【蟹座】
(Cancer ラテン)黄道上の第5星座。双子座ふたござの東、獅子座ししざの西にある。3月下旬の夕刻に南中。光輝は乏しい。
蟹座
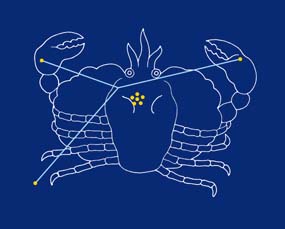 カニシカ【Kaniṣka 梵】
2世紀頃のクシャーナ朝の第3代国王。その領土は、南はインドのマトゥラー、東はパミールを越え于闐うてんに及び、クシャーナ朝の黄金期を現出。仏教を保護奨励し、特にガンダーラ地方は仏教の最も盛んな地となる。一説に、第4回仏典結集を行なったという。迦膩色迦。
かに‐せいうん【蟹星雲】
(Crab nebula)牡牛座にある星雲。強い電波源で、中心に中性子星のパルサーが見つかる。藤原定家の日記「明月記」と中国の記録とによって、1054年(天喜2)に木星ほどに明るく輝いた超新星の残骸であることがわかった。
かに‐たま【蟹玉】
中国料理。蟹の身と数種の野菜を入れて、芙蓉の花のようにふわっと仕上げた卵焼き。芙蓉蟹フーヨーハイ。
かに‐だまし【蟹瞞し】
カニダマシ科の甲殻類の総称。形はカニに似ているが、真のカニ類ではない。扁平な頭胸甲の腹面に腹部が折り曲げられており、第1歩脚は大きな鋏脚となる。小形で一般に甲長20ミリメートルまで。多くは潮間帯の転石の下や浅海の泥底などにすみ、後退りして歩く。本州中部以南の潮間帯に普通のイソカニダマシなど。
カニッツァーロ【Stanislao Cannizzaro】
イタリアの化学者。アボガドロの仮説を復活させ、原子量および分子量を推定する方法を確立。ベンズアルデヒドが水酸化カリウムの作用により安息香酸カリウムとベンジル‐アルコールを生成する反応を発見。(1826〜1910)→不均化
かに‐とり【蟹取】
貴人の生児の産衣うぶぎ。生絹すずしの練絹ねりぎぬを薄縹うすはなだに染め、蟹・鶴・宝尽たからづくしなどの小紋をつける。蟹取小袖こそで。
⇒かにとり‐こもん【蟹取小紋】
かにとり‐こもん【蟹取小紋】
蟹取の小紋。
⇒かに‐とり【蟹取】
カニシカ【Kaniṣka 梵】
2世紀頃のクシャーナ朝の第3代国王。その領土は、南はインドのマトゥラー、東はパミールを越え于闐うてんに及び、クシャーナ朝の黄金期を現出。仏教を保護奨励し、特にガンダーラ地方は仏教の最も盛んな地となる。一説に、第4回仏典結集を行なったという。迦膩色迦。
かに‐せいうん【蟹星雲】
(Crab nebula)牡牛座にある星雲。強い電波源で、中心に中性子星のパルサーが見つかる。藤原定家の日記「明月記」と中国の記録とによって、1054年(天喜2)に木星ほどに明るく輝いた超新星の残骸であることがわかった。
かに‐たま【蟹玉】
中国料理。蟹の身と数種の野菜を入れて、芙蓉の花のようにふわっと仕上げた卵焼き。芙蓉蟹フーヨーハイ。
かに‐だまし【蟹瞞し】
カニダマシ科の甲殻類の総称。形はカニに似ているが、真のカニ類ではない。扁平な頭胸甲の腹面に腹部が折り曲げられており、第1歩脚は大きな鋏脚となる。小形で一般に甲長20ミリメートルまで。多くは潮間帯の転石の下や浅海の泥底などにすみ、後退りして歩く。本州中部以南の潮間帯に普通のイソカニダマシなど。
カニッツァーロ【Stanislao Cannizzaro】
イタリアの化学者。アボガドロの仮説を復活させ、原子量および分子量を推定する方法を確立。ベンズアルデヒドが水酸化カリウムの作用により安息香酸カリウムとベンジル‐アルコールを生成する反応を発見。(1826〜1910)→不均化
かに‐とり【蟹取】
貴人の生児の産衣うぶぎ。生絹すずしの練絹ねりぎぬを薄縹うすはなだに染め、蟹・鶴・宝尽たからづくしなどの小紋をつける。蟹取小袖こそで。
⇒かにとり‐こもん【蟹取小紋】
かにとり‐こもん【蟹取小紋】
蟹取の小紋。
⇒かに‐とり【蟹取】
広辞苑に「叶わぬ時の神頼み」で始まるの検索結果 1-1。