複数辞典一括検索+![]()
![]()
さめ【白眼】🔗⭐🔉
さめ【白眼】
牛・馬の両眼縁が白いもの。一説に、毛の白いもの。太平記31「白葦毛・白瓦毛・白―・つき毛なる馬に乗つて」
しら‐め【白眼】🔗⭐🔉
しら‐め【白眼】
しろめ。竹取物語「御目は―にて伏し給へり」
○白い眼で見るしろいめでみる🔗⭐🔉
○白い眼で見るしろいめでみる
冷淡な、または憎しみのこもった目つきで見る。白眼視する。
⇒しろ・い【白い】
しろい‐もの【白い物】
①おしろい。枕草子184「裳・唐衣に―うつりて」
②雪や白髪をいう。
しろいろ‐しんこく【白色申告】
青色申告以外の、所得税・法人税の申告。白色の紙を用いる。
しろう【士朗】‥ラウ
⇒いのうえしろう(井上士朗)
し‐ろう【屍蝋】‥ラフ
蝋化した死体。死体が長時間、水中または湿地中にあった場合、脂肪が分解して脂肪酸となり、水中のカルシウムやマグネシウムと結合して石鹸様になったもの。屍脂。
し‐ろう【脂漏】
皮膚の皮脂腺分泌物の過度な状態。皮脂漏。
し‐ろう【資粮】‥ラウ
⇒しりょう(資糧)。今昔物語集1「車千に多くの―を積みて」
じ‐ろう【地牢】ヂラウ
地下の牢。
じ‐ろう【地蝋】ヂラフ
天然に産する鉱物性の蝋。黄・緑・褐色を呈し、純粋のものは白色。主成分は炭化水素。蝋燭ろうそく・艶つや出し・絶縁などに用いる。ポーランドなどの油田地帯に産出。ちろう。
じ‐ろう【次郎・二郎】‥ラウ
①第2番目の男子。次男。
②男女を問わず第2子、また次位にあるもの。
⇒じろう‐がき【次郎柿】
⇒じろう‐の‐ついたち【次郎の朔日】
じ‐ろう【耳漏】
外耳道から膿汁を出す病症。みみだれ。
じ‐ろう【耳聾】
耳がよく聞こえないこと。
じ‐ろう【侍郎】‥ラウ
中国の官名。秦・漢は郎中令の属官で宮門の守衛をつかさどる。唐では中書・門下両省の実質上の長官。また六部りくぶの次官。
じ‐ろう【痔瘻】ヂ‥
痔疾の一種。急性肛門周囲炎または結核性など慢性の肛門周囲炎が自潰して、肛門部または直腸部に瘻孔を生じ、絶えず膿汁を出すもの。あなじ。蓮痔はすじ。→痔
しろ‐うお【素魚】‥ウヲ
ハゼ科の海産の硬骨魚。全長約5センチメートル。体は細長く円筒状。透明で、鰾うきぶくろが透けて見え、目立つ。日本の所々の海岸に産し、春、産卵のため小石の多い川口をさかのぼる。美味。シラウオとは別目。シラス。ギャフ。イサザ。
じろう‐がき【次郎柿】‥ラウ‥
柿の一品種。静岡県原産。晩生の甘柿。果実は平たい。
⇒じ‐ろう【次郎・二郎】
しろ‐うさぎ【白兎】
①白毛の兎。
②冬、毛色が純白または白斑に変ずる兎。えちごうさぎ。
じろう‐しゅ【治聾酒】ヂ‥
春の社日しゃにちに飲む酒。この日に酒を飲むと聾が治るという。〈[季]春〉
しろ‐うすよう【白薄様】‥ヤウ
①白い薄手の鳥の子紙。
②五節ごせちの舞の宴で歌う歌謡の名。古今著聞集18「人々酔ひてのち、―うたひて」
しろ‐うと【素人】
(シロヒトの音便形。室町時代にはシラウト。「しろと」ともいう)
①ある物事に経験のない人。その事を職業としない人。専門でない人。しらひと。風姿花伝「―の老人が…舞ひ奏かなでんが如し」。「―らしからぬ技量」「ずぶの―」↔玄人くろうと。
②素人女の略。↔玄人くろうと。
③近世、京坂で私娼のこと。白人はくじん。浄瑠璃、女殺油地獄「かくとはいかで―の田舎の客に揚げられて」
⇒しろうと‐おんな【素人女】
⇒しろうと‐かんがえ【素人考え】
⇒しろうと‐きょうげん【素人狂言】
⇒しろうと‐くさ・い【素人臭い】
⇒しろうと‐げい【素人芸】
⇒しろうと‐げしゅく【素人下宿】
⇒しろうと‐しばい【素人芝居】
⇒しろうと‐すじ【素人筋】
⇒しろうと‐ばなれ【素人離れ】
⇒しろうと‐め【素人目】
⇒しろうと‐や【素人屋】
⇒しろうと‐やど【素人宿】
⇒しろうと‐わかり【素人分り】
しろうと‐おんな【素人女】‥ヲンナ
遊女や芸妓でない堅気の女。
⇒しろ‐うと【素人】
しろうと‐かんがえ【素人考え】‥カンガヘ
知識や経験のない人の浅はかな考え。
⇒しろ‐うと【素人】
しろうと‐きょうげん【素人狂言】‥キヤウ‥
(→)素人芝居に同じ。
⇒しろ‐うと【素人】
しろうと‐くさ・い【素人臭い】
〔形〕
素人のように感じられる。「―・い手つき」
⇒しろ‐うと【素人】
しろうと‐げい【素人芸】
本職でない、余技としての芸。つたない未熟な芸。
⇒しろ‐うと【素人】
しろうと‐げしゅく【素人下宿】
営業としてでなく、普通の家で人を下宿させること。また、その家。
⇒しろ‐うと【素人】
しろうと‐しばい【素人芝居】‥ヰ
本職の俳優でない者が演ずる芝居。素人狂言。
⇒しろ‐うと【素人】
しろうと‐すじ【素人筋】‥スヂ
(取引用語)相場の道に未熟な連中。
⇒しろ‐うと【素人】
しろうと‐ばなれ【素人離れ】
素人らしくないこと。専門家でないのに、まるで専門家のようであること。「―した芸」
⇒しろ‐うと【素人】
しろうと‐め【素人目】
専門家でない者の見る目。尾崎紅葉、冷熱「―には何を為るでも無く」。「―にも優劣は明らかだ」
⇒しろ‐うと【素人】
しろうと‐や【素人屋】
客商売をしない堅気の人の家。普通の人の家。
⇒しろ‐うと【素人】
しろうと‐やど【素人宿】
素人で、奉公人口入くちいれの周旋をする家。
⇒しろ‐うと【素人】
しろうと‐わかり【素人分り】
専門家でない人でも理解すること。「―のする話」
⇒しろ‐うと【素人】
じろう‐の‐ついたち【次郎の朔日】‥ラウ‥
(→)「太郎の朔日たろうのついたち」に同じ。
⇒じ‐ろう【次郎・二郎】
しろ‐うま【白馬】
①毛色の白い馬。あおうま。
②にごり酒。
しろうま‐だけ【白馬岳】
北アルプスの北部、長野・富山・新潟の3県にまたがる後立山うしろたてやま連峰の主峰。標高2932メートル。南の杓子岳・鑓ヶ岳とともに白馬三山と称し、お花畑・大雪渓などで有名。大蓮華岳。はくばさん。
白馬三山
提供:オフィス史朗
 白馬岳
提供:オフィス史朗
白馬岳
提供:オフィス史朗
 杓子岳(左)鑓ヶ岳(右)
提供:オフィス史朗
杓子岳(左)鑓ヶ岳(右)
提供:オフィス史朗
 しろ‐うり【白瓜】
ウリ科の一年生果菜。メロンの一変種。古くから中国で栽培。蔓性で、雌雄異花。果実は長楕円形で白緑色の表皮をもち、漬物として賞味。ツケウリ。アサウリ。漢名、越瓜。〈[季]夏〉
しろうり
撮影:関戸 勇
しろ‐うり【白瓜】
ウリ科の一年生果菜。メロンの一変種。古くから中国で栽培。蔓性で、雌雄異花。果実は長楕円形で白緑色の表皮をもち、漬物として賞味。ツケウリ。アサウリ。漢名、越瓜。〈[季]夏〉
しろうり
撮影:関戸 勇
 ⇒しろうり‐がい【白瓜貝】
しろうり‐がい【白瓜貝】‥ガヒ
オトヒメハマグリ科の二枚貝。殻は楕円形で殻長15センチメートル。地肌は白いが薄い殻皮を被る。相模湾などの水深700〜1000メートルぐらいの海底で、湧水のある付近など特異な環境に群生。
⇒しろ‐うり【白瓜】
しろ‐うるり【白うるり】
①語義不詳。一説に「うるり」は「うり(瓜)」の変化したもので、白瓜のことかという。徒然草「この僧都、ある法師を見て、―といふ名をつけたりけり。『とは、何物ぞ』と、人の問ひければ、『さる物を我も知らず。もしあらましかば、この僧の顔に似てん』とぞいひける」
②(徒然草の話をふまえて)江戸時代、正体の知れないもの、また、あやしげな者などのたとえ。大句数上「花はあつてない物見せう吉野山―とやきゆる白雪」
しろ‐うんも【白雲母】
⇒はくうんも
しろ‐えり【白襟】
衣服の白色のえり。
⇒しろえり‐もんつき【白襟紋付】
しろえり‐もんつき【白襟紋付】
白襟の襦袢ジバンなどの上に紋付を着用すること。和服の礼装で、吉凶ともに用いる。
⇒しろ‐えり【白襟】
しろ‐お【白魚】‥ヲ
シラウオの古名。〈倭名類聚鈔19〉
シローテ【G. B. Sidotti】
⇒シドッチ
しろ‐おとり【白御鳥】
(女房詞)雉きじ。
しろ‐おに【白鬼】
明治の初め頃、売春婦の異称。樋口一葉の「にごりえ」に所見。白首しろくび。
シローネ【Ignazio Silone】
イタリアの小説家・政治家。強い左翼的信条に裏打ちされたモラリストの立場を貫いた。地方農民の窮状を告発する小説「フォンタマーラ」「パンと葡萄酒」が代表作。(1900〜1978)
しろ‐おび【白帯】
①白色の帯。
②柔道・空手などで、段位の無い者が締める白色の帯。
しろ‐が・う【代替ふ】‥ガフ
〔他下二〕
(シロカウとも)売って金にかえる。しろなす。御伽草子、唐糸草子「小袖を町へいだし、―・へて」
しろ‐かが【白加賀】
白色の加賀絹。
しろ‐かき【代掻き】
水もれを防ぎ、苗の活着・発育をよくするなどのため、田植前の田に水を満たし、鍬や馬鍬まぐわ、ロータリーを装着したトラクターなどを用いて土塊を砕き田面を平らにする作業。荒代あらしろ・中代なかじろ・植代うえしろの三回行うのが普通。〈[季]夏〉
しろ‐がき【白柿】
干して白く粉をふいた柿。
しろ‐かげ【白鹿毛】
⇒しらかげ
しろ‐がさね【白重ね・白襲】
⇒しらがさね
しろ‐かしら【白頭】
能の仮髪の一つ。→頭➋2
しろ‐がすり【白絣・白飛白】
白地に紺または黒のかすり模様をあらわした布。夏の衣服に用いる。〈[季]夏〉
しろ‐がたな【白刀】
柄つかや鞘さやなどを銀の金具で飾った刀。
しろ‐がなもの【白金物】
甲冑・具足などにつける銀または鍍銀とぎんの金具。平家物語2「黒糸縅の腹巻の―うつたるむな板せめて」
しろ‐がね【銀】
(「白金」の意。古くは清音)
①銀ぎん。万葉集5「―も金くがねも玉も何せむに」
②銀泥ぎんでい。栄華物語衣珠「―の法華経一部」
③銀糸。紫式部日記「秋の草むら、蝶、鳥などを―してつくりかかやかしたり」
④「しろがねいろ」の略。
⑤銀貨。浄瑠璃、冥途飛脚「一歩小判や―に」
⇒しろがね‐いろ【銀色】
⇒しろがね‐し【銀師】
⇒しろがね‐づくり【銀作り】
しろがね‐いろ【銀色】
銀のように光る白色。ぎんいろ。
⇒しろ‐がね【銀】
しろがね‐し【銀師】
銀細工をする職人。
⇒しろ‐がね【銀】
しろがね‐づくり【銀作り】
銀で作り、または装飾したもの。ぎんごしらえ。
⇒しろ‐がね【銀】
しろ‐がまえ【城構え】‥ガマヘ
城郭を築くこと。また、その構え方。日葡辞書「シロガマエヲスル」
しろ‐かみ【白髪】
しらが。万葉集17「降る雪の―までに大君に仕へまつれば貴くもあるか」
しろ‐かみこ【白紙子】
柿渋を塗ってないかみこ。おもに律宗の僧または好事こうず者が着る。
しろ‐がや【白茅】
ヒドロ虫目(有鞘類)の刺胞しほう動物。群体は高さ10〜20センチメートル、白色の羽毛状の小枝を不規則に出す。触れると刺胞に刺され、痛みを感ずる。本州以南の浅海岩礁底に普通。
しろ‐がらす【白烏】
羽色の白い烏。すなわち、あり得ないことのたとえ。狂言、膏薬煉「海の底にすむ―」
しろ‐かわ【白皮】‥カハ
①白い皮。
②楮こうぞの靱皮じんぴの黒い表皮と甘皮層を取り除き、漂白して乾燥させたもの。和紙の原料に用いる。
しろ‐かわ【白革】‥カハ
白いなめしがわ。
⇒しろかわ‐や【白革屋】
しろかわ‐や【白革屋】‥カハ‥
生皮を精製して、なめしがわとする店または人。
⇒しろ‐かわ【白革】
しろ‐かわらげ【白川原毛】‥カハラ‥
⇒しらかわらげ
しろ‐き【白木】
①皮をむいた建築用材。
②材質の白い木材。杉・ヒノキなど。↔黒木
しろ‐き【白酒】
大嘗会だいじょうえなどに神前に供える酒。クサギの焼灰をまぜたものを黒酒くろきというのに対して、まぜないものをいう。万葉集19「天地と久しきまでに万代に仕へまつらむ黒酒―を」
⇒しろき‐でん【白酒殿】
しろ‐ぎく【白菊】
花の色の白い菊。しらぎく。
しろ‐きくらげ【白木耳】
「木耳」参照。
しろ‐ぎつね【白狐】
①年を経て毛色が白くなった狐。びゃっこ。
②北極狐の別称。
しろき‐でん【白酒殿】
大嘗会だいじょうえの時、白酒を醸造する殿舎。
⇒しろ‐き【白酒】
しろ‐きぬ【白衣】
①白色の着物。染めない衣。栄華物語初花「女房の―など」
②(墨染衣を着る僧に対していう)俗人。推古紀「俗しろきぬ七十五人」
しろ‐ぎぬ【白絹】
(シロキヌとも)
⇒しらぎぬ
しろき‐もの【白き物】
おしろい。「しろいもの」とも。紫式部日記「そらいたる櫛ども―いみじく」
しろきや【城木屋】
①浄瑠璃「恋娘昔八丈」の4段目。
②新内。初世鶴賀若狭掾作曲。歌詞は「恋娘昔八丈」から採ったお駒才三の物語。
しろ‐きわ【白際】‥キハ
①江戸時代の女官・御殿女中などに行われた化粧法。髪の生えぎわに墨で黒い筋を、その内側へ白粉で白い筋を描き、内側でぼかす。
②女官や奥女中が生えぎわから下額の中央にV字形を白粉で描き、その下に眉を描くこと。
し‐ろく【尸禄】
むなしく禄を食はむだけで、職責を果たさぬこと。その器にあらずして高禄を食むこと。ろくぬすびと。尸位素餐しいそさん。神皇正統記「臣のみだりにうくるを―とす」
し‐ろく【四六】
①4と6。また、6の4倍。
②四六判の略。
③四六文の略。
⇒しろくじ‐ちゅう【四六時中】
⇒しろく‐ばい‐ばん【四六倍判】
⇒しろく‐ばん【四六判】
⇒しろく‐ぶん【四六文】
⇒しろく‐べんれいぶん【四六駢儷文】
⇒しろく‐みせ【四六店】
し‐ろく【四緑】
九星の一つ。木星に配し、南東を本位とする。
しろ・ぐ
〔自五〕
(古くはシロク)(多く複合動詞の下位成分として)こまかに動く。「身じろぐ」「まじろぐ」「立ち―・ぐ」
しろ‐ぐくり【白括り】
白くくくった絞り染め。
しろくじ‐ちゅう【四六時中】
①二十四時間中。一日中。二六にろく時中。
②始終。つねに。日夜。
⇒し‐ろく【四六】
しろ‐くじゃく【白孔雀】
インドクジャクの白変種。→くじゃく
シロクジャク
撮影:小宮輝之
⇒しろうり‐がい【白瓜貝】
しろうり‐がい【白瓜貝】‥ガヒ
オトヒメハマグリ科の二枚貝。殻は楕円形で殻長15センチメートル。地肌は白いが薄い殻皮を被る。相模湾などの水深700〜1000メートルぐらいの海底で、湧水のある付近など特異な環境に群生。
⇒しろ‐うり【白瓜】
しろ‐うるり【白うるり】
①語義不詳。一説に「うるり」は「うり(瓜)」の変化したもので、白瓜のことかという。徒然草「この僧都、ある法師を見て、―といふ名をつけたりけり。『とは、何物ぞ』と、人の問ひければ、『さる物を我も知らず。もしあらましかば、この僧の顔に似てん』とぞいひける」
②(徒然草の話をふまえて)江戸時代、正体の知れないもの、また、あやしげな者などのたとえ。大句数上「花はあつてない物見せう吉野山―とやきゆる白雪」
しろ‐うんも【白雲母】
⇒はくうんも
しろ‐えり【白襟】
衣服の白色のえり。
⇒しろえり‐もんつき【白襟紋付】
しろえり‐もんつき【白襟紋付】
白襟の襦袢ジバンなどの上に紋付を着用すること。和服の礼装で、吉凶ともに用いる。
⇒しろ‐えり【白襟】
しろ‐お【白魚】‥ヲ
シラウオの古名。〈倭名類聚鈔19〉
シローテ【G. B. Sidotti】
⇒シドッチ
しろ‐おとり【白御鳥】
(女房詞)雉きじ。
しろ‐おに【白鬼】
明治の初め頃、売春婦の異称。樋口一葉の「にごりえ」に所見。白首しろくび。
シローネ【Ignazio Silone】
イタリアの小説家・政治家。強い左翼的信条に裏打ちされたモラリストの立場を貫いた。地方農民の窮状を告発する小説「フォンタマーラ」「パンと葡萄酒」が代表作。(1900〜1978)
しろ‐おび【白帯】
①白色の帯。
②柔道・空手などで、段位の無い者が締める白色の帯。
しろ‐が・う【代替ふ】‥ガフ
〔他下二〕
(シロカウとも)売って金にかえる。しろなす。御伽草子、唐糸草子「小袖を町へいだし、―・へて」
しろ‐かが【白加賀】
白色の加賀絹。
しろ‐かき【代掻き】
水もれを防ぎ、苗の活着・発育をよくするなどのため、田植前の田に水を満たし、鍬や馬鍬まぐわ、ロータリーを装着したトラクターなどを用いて土塊を砕き田面を平らにする作業。荒代あらしろ・中代なかじろ・植代うえしろの三回行うのが普通。〈[季]夏〉
しろ‐がき【白柿】
干して白く粉をふいた柿。
しろ‐かげ【白鹿毛】
⇒しらかげ
しろ‐がさね【白重ね・白襲】
⇒しらがさね
しろ‐かしら【白頭】
能の仮髪の一つ。→頭➋2
しろ‐がすり【白絣・白飛白】
白地に紺または黒のかすり模様をあらわした布。夏の衣服に用いる。〈[季]夏〉
しろ‐がたな【白刀】
柄つかや鞘さやなどを銀の金具で飾った刀。
しろ‐がなもの【白金物】
甲冑・具足などにつける銀または鍍銀とぎんの金具。平家物語2「黒糸縅の腹巻の―うつたるむな板せめて」
しろ‐がね【銀】
(「白金」の意。古くは清音)
①銀ぎん。万葉集5「―も金くがねも玉も何せむに」
②銀泥ぎんでい。栄華物語衣珠「―の法華経一部」
③銀糸。紫式部日記「秋の草むら、蝶、鳥などを―してつくりかかやかしたり」
④「しろがねいろ」の略。
⑤銀貨。浄瑠璃、冥途飛脚「一歩小判や―に」
⇒しろがね‐いろ【銀色】
⇒しろがね‐し【銀師】
⇒しろがね‐づくり【銀作り】
しろがね‐いろ【銀色】
銀のように光る白色。ぎんいろ。
⇒しろ‐がね【銀】
しろがね‐し【銀師】
銀細工をする職人。
⇒しろ‐がね【銀】
しろがね‐づくり【銀作り】
銀で作り、または装飾したもの。ぎんごしらえ。
⇒しろ‐がね【銀】
しろ‐がまえ【城構え】‥ガマヘ
城郭を築くこと。また、その構え方。日葡辞書「シロガマエヲスル」
しろ‐かみ【白髪】
しらが。万葉集17「降る雪の―までに大君に仕へまつれば貴くもあるか」
しろ‐かみこ【白紙子】
柿渋を塗ってないかみこ。おもに律宗の僧または好事こうず者が着る。
しろ‐がや【白茅】
ヒドロ虫目(有鞘類)の刺胞しほう動物。群体は高さ10〜20センチメートル、白色の羽毛状の小枝を不規則に出す。触れると刺胞に刺され、痛みを感ずる。本州以南の浅海岩礁底に普通。
しろ‐がらす【白烏】
羽色の白い烏。すなわち、あり得ないことのたとえ。狂言、膏薬煉「海の底にすむ―」
しろ‐かわ【白皮】‥カハ
①白い皮。
②楮こうぞの靱皮じんぴの黒い表皮と甘皮層を取り除き、漂白して乾燥させたもの。和紙の原料に用いる。
しろ‐かわ【白革】‥カハ
白いなめしがわ。
⇒しろかわ‐や【白革屋】
しろかわ‐や【白革屋】‥カハ‥
生皮を精製して、なめしがわとする店または人。
⇒しろ‐かわ【白革】
しろ‐かわらげ【白川原毛】‥カハラ‥
⇒しらかわらげ
しろ‐き【白木】
①皮をむいた建築用材。
②材質の白い木材。杉・ヒノキなど。↔黒木
しろ‐き【白酒】
大嘗会だいじょうえなどに神前に供える酒。クサギの焼灰をまぜたものを黒酒くろきというのに対して、まぜないものをいう。万葉集19「天地と久しきまでに万代に仕へまつらむ黒酒―を」
⇒しろき‐でん【白酒殿】
しろ‐ぎく【白菊】
花の色の白い菊。しらぎく。
しろ‐きくらげ【白木耳】
「木耳」参照。
しろ‐ぎつね【白狐】
①年を経て毛色が白くなった狐。びゃっこ。
②北極狐の別称。
しろき‐でん【白酒殿】
大嘗会だいじょうえの時、白酒を醸造する殿舎。
⇒しろ‐き【白酒】
しろ‐きぬ【白衣】
①白色の着物。染めない衣。栄華物語初花「女房の―など」
②(墨染衣を着る僧に対していう)俗人。推古紀「俗しろきぬ七十五人」
しろ‐ぎぬ【白絹】
(シロキヌとも)
⇒しらぎぬ
しろき‐もの【白き物】
おしろい。「しろいもの」とも。紫式部日記「そらいたる櫛ども―いみじく」
しろきや【城木屋】
①浄瑠璃「恋娘昔八丈」の4段目。
②新内。初世鶴賀若狭掾作曲。歌詞は「恋娘昔八丈」から採ったお駒才三の物語。
しろ‐きわ【白際】‥キハ
①江戸時代の女官・御殿女中などに行われた化粧法。髪の生えぎわに墨で黒い筋を、その内側へ白粉で白い筋を描き、内側でぼかす。
②女官や奥女中が生えぎわから下額の中央にV字形を白粉で描き、その下に眉を描くこと。
し‐ろく【尸禄】
むなしく禄を食はむだけで、職責を果たさぬこと。その器にあらずして高禄を食むこと。ろくぬすびと。尸位素餐しいそさん。神皇正統記「臣のみだりにうくるを―とす」
し‐ろく【四六】
①4と6。また、6の4倍。
②四六判の略。
③四六文の略。
⇒しろくじ‐ちゅう【四六時中】
⇒しろく‐ばい‐ばん【四六倍判】
⇒しろく‐ばん【四六判】
⇒しろく‐ぶん【四六文】
⇒しろく‐べんれいぶん【四六駢儷文】
⇒しろく‐みせ【四六店】
し‐ろく【四緑】
九星の一つ。木星に配し、南東を本位とする。
しろ・ぐ
〔自五〕
(古くはシロク)(多く複合動詞の下位成分として)こまかに動く。「身じろぐ」「まじろぐ」「立ち―・ぐ」
しろ‐ぐくり【白括り】
白くくくった絞り染め。
しろくじ‐ちゅう【四六時中】
①二十四時間中。一日中。二六にろく時中。
②始終。つねに。日夜。
⇒し‐ろく【四六】
しろ‐くじゃく【白孔雀】
インドクジャクの白変種。→くじゃく
シロクジャク
撮影:小宮輝之
 しろ‐くじら【白鯨】‥クヂラ
コククジラからとった鯨ひげ。色は白く美しい。籠目などに編んで汗衫かざみなどにする。
しろ‐ぐち【白ぐち】
ニベ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。体はスズキ型、灰色で銀色の光沢がある。鱗ははげやすい。南日本に多く、かまぼこの材料。イシモチ。
しろぐち
しろ‐くじら【白鯨】‥クヂラ
コククジラからとった鯨ひげ。色は白く美しい。籠目などに編んで汗衫かざみなどにする。
しろ‐ぐち【白ぐち】
ニベ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。体はスズキ型、灰色で銀色の光沢がある。鱗ははげやすい。南日本に多く、かまぼこの材料。イシモチ。
しろぐち
 シログチ
提供:東京動物園協会
シログチ
提供:東京動物園協会
 しろ‐ぐつ【白靴】
夏用の白いくつ。〈[季]夏〉
しろ‐ぐつわ【白轡】
白く光るように磨いた鉄製の轡。平家物語9「白葦毛なる老馬にかがみ鞍をき、―はげ」
しろく‐ばい‐ばん【四六倍判】
書籍の大きさ。四六判の2倍。
⇒し‐ろく【四六】
しろく‐ばん【四六判】
①紙の標準原紙寸法の一つ。788ミリメートル×1091ミリメートルで、B列本判よりやや大きい。四六全判。
②書籍寸法の一つ。四六全判32枚どり(64ページ分)を化粧裁ちした大きさ。127ミリメートル(4寸2分)×188ミリメートル(6寸2分)で、B6判よりやや大きい。
⇒し‐ろく【四六】
しろ‐くび【白首】
襟白粉えりおしろいを濃く塗りたて、客に媚こびを売る女。酌婦・娼妓など。しらくび。
しろく‐ぶん【四六文】
漢文の一体。古文と相対するもの。漢・魏に源を発し、六朝りくちょうから唐に流行。4字および6字の句を基本とし、対句ついくを多用し、平仄ひょうそくにも留意して声調を整え、文辞は華美で典故を繁用するのが特徴。奈良・平安時代の漢文は多くこの風により、「菅家文草」「和漢朗詠集」などに散見。四六駢儷べんれい文。駢儷文。駢文。
⇒し‐ろく【四六】
しろく‐べんれいぶん【四六駢儷文】
(→)四六文に同じ。
⇒し‐ろく【四六】
しろ‐くま【白熊】
ホッキョクグマの別称。
しろく‐みせ【四六店】
(夜は400文、昼は600文で遊興させたからいう)江戸後期、天明・寛政から天保の頃まで、江戸吉原の河岸見世かしみせや諸方の岡場所の下等の娼家の称。
⇒し‐ろく【四六】
しろ‐くら【白鞍】
①前輪まえわ・後輪しずわに銀を張った鞍。
②白木のままで漆を塗らない鞍。白鞍橋しろくらぼね。
しろ‐くりげ【白栗毛】
⇒しらくりげ
しろ‐ぐるま【代車】
代掻しろかきに用いる農具。牛馬にひかせるもの。
しろ‐くれない【白紅】‥クレナヰ
半ば白く、半ば紅に染めたみずひき。
しろ‐くろ【白黒】
①白と黒。「目を―させる」
②画面がカラーでなく、白と黒で表される写真・映画・テレビなど。「―写真」
③よしあし。是非。無罪か有罪か。こくびゃく。「―を決める」
しろ‐クローバー【白クローバー】
シロツメクサの別称。
しろ‐げ【白毛】
馬の毛色の名。白色のもの。
しろ‐こ【白子】
人間や動植物でメラニン・葉緑素などの色素を欠き、多くは白色となった個体。しらこ。アルビノ。
しろ‐ごし【白輿】
⇒しらごし
しろ‐こしょう【白胡椒】‥セウ
「胡椒2」参照。
しろ‐こそで【白小袖】
白無地の小袖。しろむく。↔色小袖
しろ‐ごま【白胡麻】
種子の白いゴマ。
しろ‐ごめ【白米】
搗ついてしらげた米。はくまい。↔玄米くろごめ
しろ‐ざ【白藜】
アカザの別称。本来はこのシロザのうちの、芽立ちが紅色になる変種をアカザと呼んだ。しろあかざ。
じろざえもん‐びな【次郎左衛門雛】‥ヱ‥
享保(1716〜1736)の頃、京都の人形師雛屋次郎左衛門が作り出した雛人形。顔は引目鉤鼻ひきめかぎはなに描き、典雅な気品を備える。1761年(宝暦11)江戸に進出し、30年間人気を独占。
しろ‐ざくら【白桜】
①襲かさねの色目。表は白、裏は白または紫。
②シラカバの異称。
③ミヤマザクラの異称。
しろ‐ざけ【白酒】
①粘りのある白濁した酒。蒸した糯米もちごめと米麹こめこうじとを味醂または清酒・焼酎に混和して発酵させ、後にすりつぶして造る。甘味豊かで一種特有の香気がある。多く雛祭に用いる。山川酒。〈[季]春〉
②濁酒どぶろくの別称。
しろ‐ざとう【白砂糖】‥タウ
精製した白色の砂糖。
しろ‐さま【白様】
(山形・新潟県で)蚕かいこ。おしらさま。
しろ‐さやまき【白鞘巻】
銀の金具で柄つか・鞘などを飾った鞘巻。義経記7「笈の中より―を取出して」
しろ‐さんご【白珊瑚】
本サンゴの一種で、アカサンゴに近縁。骨格が堅く、密で白い。装飾品に加工される。
しろ‐サントメ【白桟留】
純白色のサントメ革。
しろ・し【白し】
〔形ク〕
⇒しろい
しろ・し【著し】
〔形ク〕
きわだっている。あきらかである。しるし。平家物語9「褐かちに―・う黄なる糸をもつて、群千鳥むらちどり縫うたる直垂に」
しろ‐じ【白地】‥ヂ
布・紙などの、地質の白いもの。〈[季]夏〉。今昔物語集20「―の小瓶の有りけるが」→しらじ
しろし・い
〔形〕
(福岡県で)うっとうしい。しるしい。
しろ‐した【白下】
(白砂糖を製する下地の意)サトウキビの絞り汁のアクを抜き、煮詰めた黄褐色の半流動物。蔗糖結晶と糖蜜が混合した含蜜糖。白下糖。これを圧搾して繰り返し揉んで糖蜜を取り除いたものが和三盆。
しろした‐がれい【城下鰈】‥ガレヒ
大分県日出ひじ町の日出城下の別府湾で漁獲されるマコガレイの称。
しろ‐じたき【代下木】
(西日本で)水田に入れる緑肥。下木したき。刈敷かりしき。刈敷肥かっちきごえ。
しろ‐しっくい【白漆喰】‥クヒ
顔料を加えない、上塗り用の白色の漆喰。
しろ‐しぼり【白搾り・白絞り】
⇒しらしぼり
しろし‐め・す【知ろしめす】
〔他五〕
(「知る」の尊敬語「しろす」よりさらに敬意の強い言い方。上代には「しらしめす」とも)
①お知りになる。ご存知である。源氏物語花宴「くはしう―・し調へさせ給へるけなり」。天草本平家物語「鎌倉殿までもさる者のあるとは―・されつらう」
②領せられる。お治めになる。古今和歌集序「すべらぎの天の下―・すこと」。平家物語11「ただ世の乱れをしづめて、国を―・さんを君とせん」
③お世話なさる。源氏物語夢浮橋「更に―・すべきこととは、いかでか空に悟り侍らむ」
しろ‐しょいん【白書院】‥ヰン
書院の一形式。桧柾目ひのきまさめの素木しらきを主とした書院造。黒書院が奥向きで日常よく使われるのに対して、白書院は表向き正式の間。二条城のみ例外で、もとは御座間。しろじょいん。
しろ‐じょうえ【白浄衣】‥ジヤウ‥
純白の浄衣。
しろ‐しょうぞく【白装束】‥シヤウ‥
①公家装束の一種。下襲したがさね以下の下着の色目をすべて白一色にしたもの。
②白地の装束。昔は産室で着用し、後世は多く凶時に用いた。
しろ‐しょうゆ【白醤油】‥シヤウ‥
小麦を主原料に少量の炒った大豆を加えて作る醤油。発酵を抑制して作るので色が薄く、糖分が多い。愛知県の特産。
しろ‐じろ【白白】
めだって白いさま。
じろ‐じろ
好奇心や軽蔑の気持から無遠慮に見つめ続けるさま。「室内を―眺めまわす」
しろ・す【知ろす】
〔他四〕
「しる」の尊敬語。しらす。→しろしめす
しろ‐ず【白酢】
紫蘇しそを加えない梅酢。白梅酢。
しろ‐すぎ【白杉】
北山磨き丸太に用いる杉の品種。
しろ‐ずみ【白炭】
①木炭の一種。石窯いしがまでセ氏900度〜1400度の高熱で焼き、これを窯の外にかき出し、消粉と称する土・炭・炭粉をまぜたものをかぶせて火を消すので表面が灰白色を帯びる。質が密で堅い。原材は樫・栗など。備長びんちょうといって、ウバメガシを焼いたものが最良。かたずみ。↔黒炭くろずみ。
②茶の湯用の炭。→枝炭
シロ‐セット‐かこう【シロセット加工】
(「シロ」は、これを開発したオーストラリアの連邦科学産業研究機構の略称CSIRO)毛織物に耐久性のあるひだをつける加工法。
しろ‐ぜめ【城攻め】
城を攻めること。
しろ‐そこひ【白底翳】
白内障はくないしょうの俗称。
しろ‐た【代田】
田植え前の田。田植えの準備のととのった田。〈[季]夏〉
しろ‐た【白田】
①(「畠」の字を「白」と「田」とに分けていった語)はたけ。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「うろたへて―へ潜る畠垣」
②雪がつもって白くなっている冬の田。→青田→黒田。
⇒しろた‐ばいばい【白田売買】
しろ‐たえ【白妙・白
しろ‐ぐつ【白靴】
夏用の白いくつ。〈[季]夏〉
しろ‐ぐつわ【白轡】
白く光るように磨いた鉄製の轡。平家物語9「白葦毛なる老馬にかがみ鞍をき、―はげ」
しろく‐ばい‐ばん【四六倍判】
書籍の大きさ。四六判の2倍。
⇒し‐ろく【四六】
しろく‐ばん【四六判】
①紙の標準原紙寸法の一つ。788ミリメートル×1091ミリメートルで、B列本判よりやや大きい。四六全判。
②書籍寸法の一つ。四六全判32枚どり(64ページ分)を化粧裁ちした大きさ。127ミリメートル(4寸2分)×188ミリメートル(6寸2分)で、B6判よりやや大きい。
⇒し‐ろく【四六】
しろ‐くび【白首】
襟白粉えりおしろいを濃く塗りたて、客に媚こびを売る女。酌婦・娼妓など。しらくび。
しろく‐ぶん【四六文】
漢文の一体。古文と相対するもの。漢・魏に源を発し、六朝りくちょうから唐に流行。4字および6字の句を基本とし、対句ついくを多用し、平仄ひょうそくにも留意して声調を整え、文辞は華美で典故を繁用するのが特徴。奈良・平安時代の漢文は多くこの風により、「菅家文草」「和漢朗詠集」などに散見。四六駢儷べんれい文。駢儷文。駢文。
⇒し‐ろく【四六】
しろく‐べんれいぶん【四六駢儷文】
(→)四六文に同じ。
⇒し‐ろく【四六】
しろ‐くま【白熊】
ホッキョクグマの別称。
しろく‐みせ【四六店】
(夜は400文、昼は600文で遊興させたからいう)江戸後期、天明・寛政から天保の頃まで、江戸吉原の河岸見世かしみせや諸方の岡場所の下等の娼家の称。
⇒し‐ろく【四六】
しろ‐くら【白鞍】
①前輪まえわ・後輪しずわに銀を張った鞍。
②白木のままで漆を塗らない鞍。白鞍橋しろくらぼね。
しろ‐くりげ【白栗毛】
⇒しらくりげ
しろ‐ぐるま【代車】
代掻しろかきに用いる農具。牛馬にひかせるもの。
しろ‐くれない【白紅】‥クレナヰ
半ば白く、半ば紅に染めたみずひき。
しろ‐くろ【白黒】
①白と黒。「目を―させる」
②画面がカラーでなく、白と黒で表される写真・映画・テレビなど。「―写真」
③よしあし。是非。無罪か有罪か。こくびゃく。「―を決める」
しろ‐クローバー【白クローバー】
シロツメクサの別称。
しろ‐げ【白毛】
馬の毛色の名。白色のもの。
しろ‐こ【白子】
人間や動植物でメラニン・葉緑素などの色素を欠き、多くは白色となった個体。しらこ。アルビノ。
しろ‐ごし【白輿】
⇒しらごし
しろ‐こしょう【白胡椒】‥セウ
「胡椒2」参照。
しろ‐こそで【白小袖】
白無地の小袖。しろむく。↔色小袖
しろ‐ごま【白胡麻】
種子の白いゴマ。
しろ‐ごめ【白米】
搗ついてしらげた米。はくまい。↔玄米くろごめ
しろ‐ざ【白藜】
アカザの別称。本来はこのシロザのうちの、芽立ちが紅色になる変種をアカザと呼んだ。しろあかざ。
じろざえもん‐びな【次郎左衛門雛】‥ヱ‥
享保(1716〜1736)の頃、京都の人形師雛屋次郎左衛門が作り出した雛人形。顔は引目鉤鼻ひきめかぎはなに描き、典雅な気品を備える。1761年(宝暦11)江戸に進出し、30年間人気を独占。
しろ‐ざくら【白桜】
①襲かさねの色目。表は白、裏は白または紫。
②シラカバの異称。
③ミヤマザクラの異称。
しろ‐ざけ【白酒】
①粘りのある白濁した酒。蒸した糯米もちごめと米麹こめこうじとを味醂または清酒・焼酎に混和して発酵させ、後にすりつぶして造る。甘味豊かで一種特有の香気がある。多く雛祭に用いる。山川酒。〈[季]春〉
②濁酒どぶろくの別称。
しろ‐ざとう【白砂糖】‥タウ
精製した白色の砂糖。
しろ‐さま【白様】
(山形・新潟県で)蚕かいこ。おしらさま。
しろ‐さやまき【白鞘巻】
銀の金具で柄つか・鞘などを飾った鞘巻。義経記7「笈の中より―を取出して」
しろ‐さんご【白珊瑚】
本サンゴの一種で、アカサンゴに近縁。骨格が堅く、密で白い。装飾品に加工される。
しろ‐サントメ【白桟留】
純白色のサントメ革。
しろ・し【白し】
〔形ク〕
⇒しろい
しろ・し【著し】
〔形ク〕
きわだっている。あきらかである。しるし。平家物語9「褐かちに―・う黄なる糸をもつて、群千鳥むらちどり縫うたる直垂に」
しろ‐じ【白地】‥ヂ
布・紙などの、地質の白いもの。〈[季]夏〉。今昔物語集20「―の小瓶の有りけるが」→しらじ
しろし・い
〔形〕
(福岡県で)うっとうしい。しるしい。
しろ‐した【白下】
(白砂糖を製する下地の意)サトウキビの絞り汁のアクを抜き、煮詰めた黄褐色の半流動物。蔗糖結晶と糖蜜が混合した含蜜糖。白下糖。これを圧搾して繰り返し揉んで糖蜜を取り除いたものが和三盆。
しろした‐がれい【城下鰈】‥ガレヒ
大分県日出ひじ町の日出城下の別府湾で漁獲されるマコガレイの称。
しろ‐じたき【代下木】
(西日本で)水田に入れる緑肥。下木したき。刈敷かりしき。刈敷肥かっちきごえ。
しろ‐しっくい【白漆喰】‥クヒ
顔料を加えない、上塗り用の白色の漆喰。
しろ‐しぼり【白搾り・白絞り】
⇒しらしぼり
しろし‐め・す【知ろしめす】
〔他五〕
(「知る」の尊敬語「しろす」よりさらに敬意の強い言い方。上代には「しらしめす」とも)
①お知りになる。ご存知である。源氏物語花宴「くはしう―・し調へさせ給へるけなり」。天草本平家物語「鎌倉殿までもさる者のあるとは―・されつらう」
②領せられる。お治めになる。古今和歌集序「すべらぎの天の下―・すこと」。平家物語11「ただ世の乱れをしづめて、国を―・さんを君とせん」
③お世話なさる。源氏物語夢浮橋「更に―・すべきこととは、いかでか空に悟り侍らむ」
しろ‐しょいん【白書院】‥ヰン
書院の一形式。桧柾目ひのきまさめの素木しらきを主とした書院造。黒書院が奥向きで日常よく使われるのに対して、白書院は表向き正式の間。二条城のみ例外で、もとは御座間。しろじょいん。
しろ‐じょうえ【白浄衣】‥ジヤウ‥
純白の浄衣。
しろ‐しょうぞく【白装束】‥シヤウ‥
①公家装束の一種。下襲したがさね以下の下着の色目をすべて白一色にしたもの。
②白地の装束。昔は産室で着用し、後世は多く凶時に用いた。
しろ‐しょうゆ【白醤油】‥シヤウ‥
小麦を主原料に少量の炒った大豆を加えて作る醤油。発酵を抑制して作るので色が薄く、糖分が多い。愛知県の特産。
しろ‐じろ【白白】
めだって白いさま。
じろ‐じろ
好奇心や軽蔑の気持から無遠慮に見つめ続けるさま。「室内を―眺めまわす」
しろ・す【知ろす】
〔他四〕
「しる」の尊敬語。しらす。→しろしめす
しろ‐ず【白酢】
紫蘇しそを加えない梅酢。白梅酢。
しろ‐すぎ【白杉】
北山磨き丸太に用いる杉の品種。
しろ‐ずみ【白炭】
①木炭の一種。石窯いしがまでセ氏900度〜1400度の高熱で焼き、これを窯の外にかき出し、消粉と称する土・炭・炭粉をまぜたものをかぶせて火を消すので表面が灰白色を帯びる。質が密で堅い。原材は樫・栗など。備長びんちょうといって、ウバメガシを焼いたものが最良。かたずみ。↔黒炭くろずみ。
②茶の湯用の炭。→枝炭
シロ‐セット‐かこう【シロセット加工】
(「シロ」は、これを開発したオーストラリアの連邦科学産業研究機構の略称CSIRO)毛織物に耐久性のあるひだをつける加工法。
しろ‐ぜめ【城攻め】
城を攻めること。
しろ‐そこひ【白底翳】
白内障はくないしょうの俗称。
しろ‐た【代田】
田植え前の田。田植えの準備のととのった田。〈[季]夏〉
しろ‐た【白田】
①(「畠」の字を「白」と「田」とに分けていった語)はたけ。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「うろたへて―へ潜る畠垣」
②雪がつもって白くなっている冬の田。→青田→黒田。
⇒しろた‐ばいばい【白田売買】
しろ‐たえ【白妙・白 】‥タヘ
①(その色が白いからいう)穀かじの木の皮の繊維で織った布。万葉集3「―にころも取り着て」。万葉集10「―ごろも垢づくまでに」
②白い色。万葉集10「鶯のはね―にあわ雪そふる」
⇒しろたえ‐の【白妙の】
しろたえ‐の【白妙の】‥タヘ‥
〔枕〕
「ころも」「そで」「たもと」「ひも」「ひれ」「帯」「たすき」または「くも」「ゆき」にかかる。
⇒しろ‐たえ【白妙・白
】‥タヘ
①(その色が白いからいう)穀かじの木の皮の繊維で織った布。万葉集3「―にころも取り着て」。万葉集10「―ごろも垢づくまでに」
②白い色。万葉集10「鶯のはね―にあわ雪そふる」
⇒しろたえ‐の【白妙の】
しろたえ‐の【白妙の】‥タヘ‥
〔枕〕
「ころも」「そで」「たもと」「ひも」「ひれ」「帯」「たすき」または「くも」「ゆき」にかかる。
⇒しろ‐たえ【白妙・白 】
しろ‐タク【白タク】
営業許可を受けずに、自家用車の白ナンバーをつけてタクシー行為をしているものの通称。
しろ‐だすき【白襷】
白布のたすき。
しろ‐だち【白太刀】
銀作しろがねづくりの太刀。太平記34「四尺五尺の―に」
しろた‐ばいばい【白田売買】
まだ田に雪のある頃、その年に収穫を予想される産米の売買契約をすること。
⇒しろ‐た【白田】
しろ‐たぶ【白たぶ】
(→)「白だも」に同じ。
しろ‐だも【白だも】
クスノキ科の常緑高木。関東以南の山地に自生。葉は楕円形で裏面が白く、車輪状につく。木全体に精油を含み芳香がある。晩秋に黄褐色の小花を多数つけ、翌年の秋冬に赤色の球果が熟する。種子から採油し、蝋燭の材料とする。シロタブ。タマガヤ。
シロダモ
撮影:関戸 勇
】
しろ‐タク【白タク】
営業許可を受けずに、自家用車の白ナンバーをつけてタクシー行為をしているものの通称。
しろ‐だすき【白襷】
白布のたすき。
しろ‐だち【白太刀】
銀作しろがねづくりの太刀。太平記34「四尺五尺の―に」
しろた‐ばいばい【白田売買】
まだ田に雪のある頃、その年に収穫を予想される産米の売買契約をすること。
⇒しろ‐た【白田】
しろ‐たぶ【白たぶ】
(→)「白だも」に同じ。
しろ‐だも【白だも】
クスノキ科の常緑高木。関東以南の山地に自生。葉は楕円形で裏面が白く、車輪状につく。木全体に精油を含み芳香がある。晩秋に黄褐色の小花を多数つけ、翌年の秋冬に赤色の球果が熟する。種子から採油し、蝋燭の材料とする。シロタブ。タマガヤ。
シロダモ
撮影:関戸 勇
 しろ‐たれ【白垂】
能の仮髪の一つ。→垂たれ6
しろ‐ちょうがい【白蝶貝】‥テフガヒ
ウグイスガイ科の二枚貝。殻は円盤状で平たく、黄褐色。内面は白銀色で真珠光沢が強い。殻径30センチメートル内外。熱帯西太平洋に分布。貝ボタンその他工芸加工品の材料となる。稀に極めて高価な天然真珠を含む。
しろ‐ちょうちん【白提灯】‥チヤウ‥
白張しらはりの提灯。
しろ‐ちりめん【白縮緬】
染めない白地の縮緬。
しろ‐つか【白柄】
⇒しらつか
しろ‐づき【白搗き】
玄米を白くつきしらげること。また、ついて白くした米。日葡辞書「シロヅキノコメ」
しろ‐つきげ【白月毛】
⇒しらつきげ
シロッコ【scirocco イタリア】
サハラ砂漠から地中海方面に吹く熱風。
しろ‐つつじ【白躑躅】
①白色の花の咲くツツジの総称。〈本草和名〉
②襲かさねの色目。表は白、裏は紫。
じろっ‐と
〔副〕
険しい視線を向けるさま。「―にらむ」
シロップ【siroop オランダ】
①濃厚な砂糖溶液。単舎利別たんシャリベツ。シラップ。砂糖蜜。
②(→)果実シロップに同じ。
しろっ‐ぽ・い【白っぽい】
〔形〕
①白みがかっている。
②しろうとくさい。浮世風呂4「隈取といひなせえ、隈ゑどりだけ古風で―・い」
しろ‐づめ【城詰】
城中につめていること。また、その武士。
しろ‐つめくさ【白詰草】
マメ科の多年草。ヨーロッパ原産で日本各地に自生化。葉柄は長く、葉は倒卵形の3個の小葉から成る。夏に長軸を出し、白色の蝶形花を多数球状に集めてつける。緑肥・牧草用。クローバー。オランダゲンゲ。ツメクサ。→アカツメクサ
しろ‐で【白手】
白色の釉うわぐすりをかけた磁器。
しろ‐と【素人】
(→)「しろうと」に同じ。
⇒しろと‐すい【素人粋】
ジロドゥー【Jean Giraudoux】
フランスの劇作家・小説家・外交官。精妙な心理性、自在な幻想性、鋭い諷刺性が溶け合った戯曲でフランス現代劇を代表。代表作「トロイ戦争は起こらない」「エレクトル」のほか、小説「シュザンヌと太平洋」など。(1882〜1944)
しろと‐すい【素人粋】
素人しろうとでありながら、粋人ぶる者。半可通。好色一代女1「物に馴れたる客は各別、まだしき―は」
⇒しろ‐と【素人】
しろ‐とり【白鳥】
⇒しらとり
しろ‐どり【城取】
城郭を構え設けること。城構え。甲陽軍鑑3「―、陣取、一切の軍法をよく鍛錬いたす」
しろ‐ナイル【白ナイル】
(White Nile)ナイル川上流部の名称。狭義にはナイル川がスーダン南部のノー湖でガザル川を合わせる地点から、ハルツームで青ナイルと合流するまでをいう。広義にはノー湖から上流のスーダン南端のニムレに至るジェベル川を含める。
しろながす‐くじら【白長須鯨】‥クヂラ
鬚ひげクジラの一種。動物中最大で全長30メートル、体重100トン以上に達する。ナガスクジラに似るが、背鰭せびれが小さく体は青灰色。太平洋・大西洋の北部および南氷洋に分布し、オキアミなどを食う。かつては捕鯨の主目標とされた。
しろ‐なす【白茄子】
果実の色の白いナス。しろなすび。
しろ‐な・す【代為す】
〔他四〕
物品を売って金にかえる。売る。「うりしろなす」とも。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「侍の武具馬具を―・して」
しろ‐なでしこ【白撫子】
①白い花の咲くナデシコ。
②襲かさねの色目。表は白、裏は蘇芳すおう。夏に用いる。
しろ‐なまず【白癜】‥ナマヅ
色素の欠乏によって、白色の斑紋を生じる皮膚病。尋常性白斑。白斑。〈日葡辞書〉
しろ‐なまり【白鉛】
①錫すずの古名。〈倭名類聚鈔11〉
②白鑞しろめの別称。
しろ‐なめし【白鞣】
(「しろなめしがわ」の略)染色しないなめしがわ。
しろ‐なんてん【白南天】
白色の果実を結ぶナンテンの一品種。観賞用・薬用。シロミナンテン。
しろ‐ナンバー【白ナンバー】
(白地のナンバー‐プレートから)自家用自動車の俗称。→白タク
しろ‐ぬき【白抜き】
染色・印刷などで、その部分だけ地色を白く抜いて、模様・文字等を表すこと。また、そのもの。「黒地に―の文字」
しろ‐ぬの【白布】
白色の、さらし布。さらし。
しろ‐ぬめ【白絖】
白色の、つやのある絹布。世間胸算用1「―の足袋はくなど」
しろ‐ぬり【白塗り】
白く塗ること。白く塗ったもの。特に、俳優が顔を白く塗ること。→しらぬり
しろ‐ね【白根】
①シソ科の多年草。各地の湿地に自生。地下茎は多少肥厚して白色、先端は肥厚してチョロギに似る。この部分は食用にすることもある。茎は方形で高さ1メートル内外。夏、茎上・葉腋に白色の小唇形花をつける。
②(女房詞)ねぎ。
③野菜などの茎・根の地中にある白い部分。
⇒しろね‐ぐさ【白根草】
しろね【白根】
新潟県中部の地名。新潟市に属する。信濃川とその分流に囲まれ、低湿地の改良で越後平野の米作中心となる。
しろ‐ねぎ【白葱】
葱の軟化部が白色で長いもの。
しろね‐ぐさ【白根草】
セリの異称。
⇒しろ‐ね【白根】
しろ‐ねずみ【白鼠】
①毛色が白く、眼の赤いネズミの俗な総称。大黒天の使で、そのすむ家は繁昌すると伝え、大黒ねずみともいう。
②㋐ドブネズミの飼養変種。実験用に使われる。ラット。
㋑ハツカネズミの俗称。
③(1が大黒天に仕えたという伝えから)主家に忠実な番頭・雇人。好色一代女4「京の旦那の為に―といはれて」
④染色の名。薄いねずみ色。しろねず。うすねずみ。
しろ‐ねり【白練】
①白い練絹ねりぎぬ。
②白い練羊羹ねりようかん。
しろ‐ネル【白ネル】
白色のフランネル。毛織・綿織・綿毛交織の3種がある。下着類や寝衣に用いる。
しろ‐の【白箆】
⇒しらの
しろ‐のり【城乗り】
敵城に攻め入ること。
しろ‐バイ【白バイ】
(バイはオートバイの略)警察で使用する、白塗りのオートバイ。
しろ‐はえ【白南風】
⇒しらはえ
しろ‐ばえ【白映え】
梅雨つゆのとき、小雨が降りながら時々晴れそうになること。
しろはぜ‐らん【白罅卵】
色素が一方に偏在し、白濁した大きな斑点が見える蚕卵。冷蔵庫からの出し入れの際の温度の激変によって生ずるもので、孵化しない。
しろ‐はた【白旗】
⇒しらはた
しろ‐ば・む【白ばむ】
〔自五〕
白色を帯びる。白く色づく。
しろ‐はら【白腹】
スズメ目ツグミ科の鳥。大きさはツグミほどで、習性も似る。背面は褐色、翼と尾羽は黒褐色、胸以下の下面は白色。ウスリー・アムール・中国東北部で繁殖し、秋、日本に渡来。シナイ。
シロハラ
撮影:小宮輝之
しろ‐たれ【白垂】
能の仮髪の一つ。→垂たれ6
しろ‐ちょうがい【白蝶貝】‥テフガヒ
ウグイスガイ科の二枚貝。殻は円盤状で平たく、黄褐色。内面は白銀色で真珠光沢が強い。殻径30センチメートル内外。熱帯西太平洋に分布。貝ボタンその他工芸加工品の材料となる。稀に極めて高価な天然真珠を含む。
しろ‐ちょうちん【白提灯】‥チヤウ‥
白張しらはりの提灯。
しろ‐ちりめん【白縮緬】
染めない白地の縮緬。
しろ‐つか【白柄】
⇒しらつか
しろ‐づき【白搗き】
玄米を白くつきしらげること。また、ついて白くした米。日葡辞書「シロヅキノコメ」
しろ‐つきげ【白月毛】
⇒しらつきげ
シロッコ【scirocco イタリア】
サハラ砂漠から地中海方面に吹く熱風。
しろ‐つつじ【白躑躅】
①白色の花の咲くツツジの総称。〈本草和名〉
②襲かさねの色目。表は白、裏は紫。
じろっ‐と
〔副〕
険しい視線を向けるさま。「―にらむ」
シロップ【siroop オランダ】
①濃厚な砂糖溶液。単舎利別たんシャリベツ。シラップ。砂糖蜜。
②(→)果実シロップに同じ。
しろっ‐ぽ・い【白っぽい】
〔形〕
①白みがかっている。
②しろうとくさい。浮世風呂4「隈取といひなせえ、隈ゑどりだけ古風で―・い」
しろ‐づめ【城詰】
城中につめていること。また、その武士。
しろ‐つめくさ【白詰草】
マメ科の多年草。ヨーロッパ原産で日本各地に自生化。葉柄は長く、葉は倒卵形の3個の小葉から成る。夏に長軸を出し、白色の蝶形花を多数球状に集めてつける。緑肥・牧草用。クローバー。オランダゲンゲ。ツメクサ。→アカツメクサ
しろ‐で【白手】
白色の釉うわぐすりをかけた磁器。
しろ‐と【素人】
(→)「しろうと」に同じ。
⇒しろと‐すい【素人粋】
ジロドゥー【Jean Giraudoux】
フランスの劇作家・小説家・外交官。精妙な心理性、自在な幻想性、鋭い諷刺性が溶け合った戯曲でフランス現代劇を代表。代表作「トロイ戦争は起こらない」「エレクトル」のほか、小説「シュザンヌと太平洋」など。(1882〜1944)
しろと‐すい【素人粋】
素人しろうとでありながら、粋人ぶる者。半可通。好色一代女1「物に馴れたる客は各別、まだしき―は」
⇒しろ‐と【素人】
しろ‐とり【白鳥】
⇒しらとり
しろ‐どり【城取】
城郭を構え設けること。城構え。甲陽軍鑑3「―、陣取、一切の軍法をよく鍛錬いたす」
しろ‐ナイル【白ナイル】
(White Nile)ナイル川上流部の名称。狭義にはナイル川がスーダン南部のノー湖でガザル川を合わせる地点から、ハルツームで青ナイルと合流するまでをいう。広義にはノー湖から上流のスーダン南端のニムレに至るジェベル川を含める。
しろながす‐くじら【白長須鯨】‥クヂラ
鬚ひげクジラの一種。動物中最大で全長30メートル、体重100トン以上に達する。ナガスクジラに似るが、背鰭せびれが小さく体は青灰色。太平洋・大西洋の北部および南氷洋に分布し、オキアミなどを食う。かつては捕鯨の主目標とされた。
しろ‐なす【白茄子】
果実の色の白いナス。しろなすび。
しろ‐な・す【代為す】
〔他四〕
物品を売って金にかえる。売る。「うりしろなす」とも。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「侍の武具馬具を―・して」
しろ‐なでしこ【白撫子】
①白い花の咲くナデシコ。
②襲かさねの色目。表は白、裏は蘇芳すおう。夏に用いる。
しろ‐なまず【白癜】‥ナマヅ
色素の欠乏によって、白色の斑紋を生じる皮膚病。尋常性白斑。白斑。〈日葡辞書〉
しろ‐なまり【白鉛】
①錫すずの古名。〈倭名類聚鈔11〉
②白鑞しろめの別称。
しろ‐なめし【白鞣】
(「しろなめしがわ」の略)染色しないなめしがわ。
しろ‐なんてん【白南天】
白色の果実を結ぶナンテンの一品種。観賞用・薬用。シロミナンテン。
しろ‐ナンバー【白ナンバー】
(白地のナンバー‐プレートから)自家用自動車の俗称。→白タク
しろ‐ぬき【白抜き】
染色・印刷などで、その部分だけ地色を白く抜いて、模様・文字等を表すこと。また、そのもの。「黒地に―の文字」
しろ‐ぬの【白布】
白色の、さらし布。さらし。
しろ‐ぬめ【白絖】
白色の、つやのある絹布。世間胸算用1「―の足袋はくなど」
しろ‐ぬり【白塗り】
白く塗ること。白く塗ったもの。特に、俳優が顔を白く塗ること。→しらぬり
しろ‐ね【白根】
①シソ科の多年草。各地の湿地に自生。地下茎は多少肥厚して白色、先端は肥厚してチョロギに似る。この部分は食用にすることもある。茎は方形で高さ1メートル内外。夏、茎上・葉腋に白色の小唇形花をつける。
②(女房詞)ねぎ。
③野菜などの茎・根の地中にある白い部分。
⇒しろね‐ぐさ【白根草】
しろね【白根】
新潟県中部の地名。新潟市に属する。信濃川とその分流に囲まれ、低湿地の改良で越後平野の米作中心となる。
しろ‐ねぎ【白葱】
葱の軟化部が白色で長いもの。
しろね‐ぐさ【白根草】
セリの異称。
⇒しろ‐ね【白根】
しろ‐ねずみ【白鼠】
①毛色が白く、眼の赤いネズミの俗な総称。大黒天の使で、そのすむ家は繁昌すると伝え、大黒ねずみともいう。
②㋐ドブネズミの飼養変種。実験用に使われる。ラット。
㋑ハツカネズミの俗称。
③(1が大黒天に仕えたという伝えから)主家に忠実な番頭・雇人。好色一代女4「京の旦那の為に―といはれて」
④染色の名。薄いねずみ色。しろねず。うすねずみ。
しろ‐ねり【白練】
①白い練絹ねりぎぬ。
②白い練羊羹ねりようかん。
しろ‐ネル【白ネル】
白色のフランネル。毛織・綿織・綿毛交織の3種がある。下着類や寝衣に用いる。
しろ‐の【白箆】
⇒しらの
しろ‐のり【城乗り】
敵城に攻め入ること。
しろ‐バイ【白バイ】
(バイはオートバイの略)警察で使用する、白塗りのオートバイ。
しろ‐はえ【白南風】
⇒しらはえ
しろ‐ばえ【白映え】
梅雨つゆのとき、小雨が降りながら時々晴れそうになること。
しろはぜ‐らん【白罅卵】
色素が一方に偏在し、白濁した大きな斑点が見える蚕卵。冷蔵庫からの出し入れの際の温度の激変によって生ずるもので、孵化しない。
しろ‐はた【白旗】
⇒しらはた
しろ‐ば・む【白ばむ】
〔自五〕
白色を帯びる。白く色づく。
しろ‐はら【白腹】
スズメ目ツグミ科の鳥。大きさはツグミほどで、習性も似る。背面は褐色、翼と尾羽は黒褐色、胸以下の下面は白色。ウスリー・アムール・中国東北部で繁殖し、秋、日本に渡来。シナイ。
シロハラ
撮影:小宮輝之
 しろ‐びたい【白額】‥ビタヒ
馬の毛色の名。額の上に白色の小点があるもの。ほしづき。
しろ‐ひと【白人】
⇒しらひと
しろ‐ひとり【白灯蛾】
ヒトリガ科のガ。中形で、開張7〜8センチメートル。全体白色で、腹に赤い点がある。夜、灯火に飛来。幼虫はオオバコなどを食う。
シロヒトリ
撮影:海野和男
しろ‐びたい【白額】‥ビタヒ
馬の毛色の名。額の上に白色の小点があるもの。ほしづき。
しろ‐ひと【白人】
⇒しらひと
しろ‐ひとり【白灯蛾】
ヒトリガ科のガ。中形で、開張7〜8センチメートル。全体白色で、腹に赤い点がある。夜、灯火に飛来。幼虫はオオバコなどを食う。
シロヒトリ
撮影:海野和男
 シロフォン【xylophone】
(→)木琴もっきん。
しろ‐ぶくりん【白覆輪】
(→)銀覆輪ぎんぷくりんに同じ。
しろ‐ふくろう【白梟】‥フクロフ
フクロウ目フクロウ科の鳥。北極圏で繁殖。雄はほぼ全身が白く、雌には褐色の斑紋がある。
しろ‐ぶさ【白房・白総】
相撲で、土俵の屋根の南西隅に垂らす白色の房。秋と白虎びゃっこを表す。→赤房→青房→黒房
しろ‐ふじ【白藤】‥フヂ
白色の花の咲く藤。
しろ‐ぶち【白斑】
白色のぶち。白いまだら。
しろ‐ぶどうしゅ【白葡萄酒】‥ダウ‥
透明に近い淡黄色の葡萄酒。主に緑色葡萄を原料とし、圧搾して果皮および種子を除いた果汁を発酵させてつくる。白ワイン。→赤葡萄酒→ロゼ
しろ‐ぶな【白橅】
ブナの別称。
しろ‐ふね【白船】
中国のジャンク。または小舟。〈日葡辞書〉
しろべえ【四郎兵衛】‥ヱ
(総名主三浦屋が郭内取締りの会所を大門おおもん口に設け、その雇人四郎兵衛を定詰じょうづめとしたことから、その名を世襲)吉原の大門の番所に詰めた見張役の名。転じて、取締りの意。大門四郎兵衛。
しろ‐へび【白蛇】
アオダイショウの白化したもの。山口県岩国市に生息するものは天然記念物に指定。
しろ‐ほ【白保】
石灰などを加えて漉すいた、やや白色を帯びた浅草紙。
しろ‐ぼし【白星】
①中が白い星形または丸形のしるし。
②相撲で、勝を表すしるし。勝ち星。転じて、成功。手柄。「―をあげる」↔黒星
シロホン【xylophone】
(→)木琴もっきん。
しろ‐まい【城米】
城中に貯えた米。
しろ‐まく【白幕】
白地の幕。
しろ‐まだら【白斑】
①白地に斑のあるもの。
②ヘビの一種。全長約60センチメートル。やや褐色を帯びた白地に数十個の横帯がある。夜行性で、人目に触れることは少ない。トカゲ・ヘビを食う。日本の固有種で、本州・四国・九州および周辺の島にすむ。同属のアカマダラは対馬・朝鮮半島・中国に分布。
シロマダラ
提供:東京動物園協会
シロフォン【xylophone】
(→)木琴もっきん。
しろ‐ぶくりん【白覆輪】
(→)銀覆輪ぎんぷくりんに同じ。
しろ‐ふくろう【白梟】‥フクロフ
フクロウ目フクロウ科の鳥。北極圏で繁殖。雄はほぼ全身が白く、雌には褐色の斑紋がある。
しろ‐ぶさ【白房・白総】
相撲で、土俵の屋根の南西隅に垂らす白色の房。秋と白虎びゃっこを表す。→赤房→青房→黒房
しろ‐ふじ【白藤】‥フヂ
白色の花の咲く藤。
しろ‐ぶち【白斑】
白色のぶち。白いまだら。
しろ‐ぶどうしゅ【白葡萄酒】‥ダウ‥
透明に近い淡黄色の葡萄酒。主に緑色葡萄を原料とし、圧搾して果皮および種子を除いた果汁を発酵させてつくる。白ワイン。→赤葡萄酒→ロゼ
しろ‐ぶな【白橅】
ブナの別称。
しろ‐ふね【白船】
中国のジャンク。または小舟。〈日葡辞書〉
しろべえ【四郎兵衛】‥ヱ
(総名主三浦屋が郭内取締りの会所を大門おおもん口に設け、その雇人四郎兵衛を定詰じょうづめとしたことから、その名を世襲)吉原の大門の番所に詰めた見張役の名。転じて、取締りの意。大門四郎兵衛。
しろ‐へび【白蛇】
アオダイショウの白化したもの。山口県岩国市に生息するものは天然記念物に指定。
しろ‐ほ【白保】
石灰などを加えて漉すいた、やや白色を帯びた浅草紙。
しろ‐ぼし【白星】
①中が白い星形または丸形のしるし。
②相撲で、勝を表すしるし。勝ち星。転じて、成功。手柄。「―をあげる」↔黒星
シロホン【xylophone】
(→)木琴もっきん。
しろ‐まい【城米】
城中に貯えた米。
しろ‐まく【白幕】
白地の幕。
しろ‐まだら【白斑】
①白地に斑のあるもの。
②ヘビの一種。全長約60センチメートル。やや褐色を帯びた白地に数十個の横帯がある。夜行性で、人目に触れることは少ない。トカゲ・ヘビを食う。日本の固有種で、本州・四国・九州および周辺の島にすむ。同属のアカマダラは対馬・朝鮮半島・中国に分布。
シロマダラ
提供:東京動物園協会
 しろ‐まなこ【白眼】
白い目玉。しろめ。日葡辞書「シロマナコヲミイダス」
しろ‐み【白身】
①材木の白い部分。しらた。↔赤身。
②魚などの白い肉。「―の魚」↔赤身。
③鶏卵などの卵白らんぱく。↔黄身きみ
しろ‐み【白鑞】
(→)「しろめ」に同じ。日葡辞書「シロミノカガミ」
しろ‐みがき【白磨き】
磨いて白くすること。また、そのもの。
しろ‐みず【白水】‥ミヅ
米をといで白く濁った水。とぎじる。仁勢物語「―のあるところに滑りけり」
しろ‐みそ【白味噌】
黄白色の味噌。米麹こめこうじを多く用い、甘味に富む。京都産が有名。西京味噌など。
しろ‐みつ【白蜜】
砂糖蜜に対して、蜂蜜の称。
しろ‐みて【代満】
田植の終わったこと。田植の終わった祝日・休日。
しろ・む【白む】
[一]〔自四〕
(シラムとも)
①白色を帯びる。白くなる。枕草子51「牛はひたひはいとちひさく、―・みたるが」
②たじろぐ。ためらう。ひるむ。浄瑠璃、出世景清「双方―・みて控へたり」
③にぶくなる。なまる。日葡辞書「カタナノハガシロウダ」
[二]〔他下二〕
白くする。枕草子87「衣も―・めず」。日葡辞書「コメヲシロムル」
しろ・む【窄む】
〔他下二〕
しめる。しぼる。圧縮する。倭名類聚鈔12「擣押、俗語云、之路無」
しろ‐むく【白無垢】
①上着・下着ともに白1色の服装。浄瑠璃、曾根崎「初は―死出立しにでだち」。「―の花嫁衣装」
②白小袖。好色一代男4「下には水鹿子の―」
⇒しろむく‐てっか【白無垢鉄火】
しろむく‐てっか【白無垢鉄火】‥クワ
表面は上品で温厚に見えて、内実は無頼不良な者。羽織ごろつき。
⇒しろ‐むく【白無垢】
しろ‐め【白眼・白目】
眼球の、虹彩と瞳孔とを除いた白い部分。しろまなこ。しろめだま。
⇒白眼で見る
しろ‐め【白鑞・白目】
(ハクロウ・ビャクロウとも)
①鑞接ろうせつ剤の一種。銅と亜鉛との合金で、鉄・アンチモン・ヒ素などを含む。銅合金・ニッケル合金・鋳鉄・鋼製の継手の鑞接に適する。黄銅鑞。
②アンチモンを主成分としヒ素を含む鉱物。合金の中に混ぜて溶融しやすくするのに用い、また銅に混ぜれば灰黒色となり美麗。銅鉱中に含まれて産出し、産地によって伊予白目・堅白目・豊後白目などの名がある。
③錫を主成分とする鉛との合金。鉄・亜鉛・アンチモンなどを少量含む。古くから皿・花瓶・装飾品などに用いた。ピューター。
しろ‐まなこ【白眼】
白い目玉。しろめ。日葡辞書「シロマナコヲミイダス」
しろ‐み【白身】
①材木の白い部分。しらた。↔赤身。
②魚などの白い肉。「―の魚」↔赤身。
③鶏卵などの卵白らんぱく。↔黄身きみ
しろ‐み【白鑞】
(→)「しろめ」に同じ。日葡辞書「シロミノカガミ」
しろ‐みがき【白磨き】
磨いて白くすること。また、そのもの。
しろ‐みず【白水】‥ミヅ
米をといで白く濁った水。とぎじる。仁勢物語「―のあるところに滑りけり」
しろ‐みそ【白味噌】
黄白色の味噌。米麹こめこうじを多く用い、甘味に富む。京都産が有名。西京味噌など。
しろ‐みつ【白蜜】
砂糖蜜に対して、蜂蜜の称。
しろ‐みて【代満】
田植の終わったこと。田植の終わった祝日・休日。
しろ・む【白む】
[一]〔自四〕
(シラムとも)
①白色を帯びる。白くなる。枕草子51「牛はひたひはいとちひさく、―・みたるが」
②たじろぐ。ためらう。ひるむ。浄瑠璃、出世景清「双方―・みて控へたり」
③にぶくなる。なまる。日葡辞書「カタナノハガシロウダ」
[二]〔他下二〕
白くする。枕草子87「衣も―・めず」。日葡辞書「コメヲシロムル」
しろ・む【窄む】
〔他下二〕
しめる。しぼる。圧縮する。倭名類聚鈔12「擣押、俗語云、之路無」
しろ‐むく【白無垢】
①上着・下着ともに白1色の服装。浄瑠璃、曾根崎「初は―死出立しにでだち」。「―の花嫁衣装」
②白小袖。好色一代男4「下には水鹿子の―」
⇒しろむく‐てっか【白無垢鉄火】
しろむく‐てっか【白無垢鉄火】‥クワ
表面は上品で温厚に見えて、内実は無頼不良な者。羽織ごろつき。
⇒しろ‐むく【白無垢】
しろ‐め【白眼・白目】
眼球の、虹彩と瞳孔とを除いた白い部分。しろまなこ。しろめだま。
⇒白眼で見る
しろ‐め【白鑞・白目】
(ハクロウ・ビャクロウとも)
①鑞接ろうせつ剤の一種。銅と亜鉛との合金で、鉄・アンチモン・ヒ素などを含む。銅合金・ニッケル合金・鋳鉄・鋼製の継手の鑞接に適する。黄銅鑞。
②アンチモンを主成分としヒ素を含む鉱物。合金の中に混ぜて溶融しやすくするのに用い、また銅に混ぜれば灰黒色となり美麗。銅鉱中に含まれて産出し、産地によって伊予白目・堅白目・豊後白目などの名がある。
③錫を主成分とする鉛との合金。鉄・亜鉛・アンチモンなどを少量含む。古くから皿・花瓶・装飾品などに用いた。ピューター。
 白馬岳
提供:オフィス史朗
白馬岳
提供:オフィス史朗
 杓子岳(左)鑓ヶ岳(右)
提供:オフィス史朗
杓子岳(左)鑓ヶ岳(右)
提供:オフィス史朗
 しろ‐うり【白瓜】
ウリ科の一年生果菜。メロンの一変種。古くから中国で栽培。蔓性で、雌雄異花。果実は長楕円形で白緑色の表皮をもち、漬物として賞味。ツケウリ。アサウリ。漢名、越瓜。〈[季]夏〉
しろうり
撮影:関戸 勇
しろ‐うり【白瓜】
ウリ科の一年生果菜。メロンの一変種。古くから中国で栽培。蔓性で、雌雄異花。果実は長楕円形で白緑色の表皮をもち、漬物として賞味。ツケウリ。アサウリ。漢名、越瓜。〈[季]夏〉
しろうり
撮影:関戸 勇
 ⇒しろうり‐がい【白瓜貝】
しろうり‐がい【白瓜貝】‥ガヒ
オトヒメハマグリ科の二枚貝。殻は楕円形で殻長15センチメートル。地肌は白いが薄い殻皮を被る。相模湾などの水深700〜1000メートルぐらいの海底で、湧水のある付近など特異な環境に群生。
⇒しろ‐うり【白瓜】
しろ‐うるり【白うるり】
①語義不詳。一説に「うるり」は「うり(瓜)」の変化したもので、白瓜のことかという。徒然草「この僧都、ある法師を見て、―といふ名をつけたりけり。『とは、何物ぞ』と、人の問ひければ、『さる物を我も知らず。もしあらましかば、この僧の顔に似てん』とぞいひける」
②(徒然草の話をふまえて)江戸時代、正体の知れないもの、また、あやしげな者などのたとえ。大句数上「花はあつてない物見せう吉野山―とやきゆる白雪」
しろ‐うんも【白雲母】
⇒はくうんも
しろ‐えり【白襟】
衣服の白色のえり。
⇒しろえり‐もんつき【白襟紋付】
しろえり‐もんつき【白襟紋付】
白襟の襦袢ジバンなどの上に紋付を着用すること。和服の礼装で、吉凶ともに用いる。
⇒しろ‐えり【白襟】
しろ‐お【白魚】‥ヲ
シラウオの古名。〈倭名類聚鈔19〉
シローテ【G. B. Sidotti】
⇒シドッチ
しろ‐おとり【白御鳥】
(女房詞)雉きじ。
しろ‐おに【白鬼】
明治の初め頃、売春婦の異称。樋口一葉の「にごりえ」に所見。白首しろくび。
シローネ【Ignazio Silone】
イタリアの小説家・政治家。強い左翼的信条に裏打ちされたモラリストの立場を貫いた。地方農民の窮状を告発する小説「フォンタマーラ」「パンと葡萄酒」が代表作。(1900〜1978)
しろ‐おび【白帯】
①白色の帯。
②柔道・空手などで、段位の無い者が締める白色の帯。
しろ‐が・う【代替ふ】‥ガフ
〔他下二〕
(シロカウとも)売って金にかえる。しろなす。御伽草子、唐糸草子「小袖を町へいだし、―・へて」
しろ‐かが【白加賀】
白色の加賀絹。
しろ‐かき【代掻き】
水もれを防ぎ、苗の活着・発育をよくするなどのため、田植前の田に水を満たし、鍬や馬鍬まぐわ、ロータリーを装着したトラクターなどを用いて土塊を砕き田面を平らにする作業。荒代あらしろ・中代なかじろ・植代うえしろの三回行うのが普通。〈[季]夏〉
しろ‐がき【白柿】
干して白く粉をふいた柿。
しろ‐かげ【白鹿毛】
⇒しらかげ
しろ‐がさね【白重ね・白襲】
⇒しらがさね
しろ‐かしら【白頭】
能の仮髪の一つ。→頭➋2
しろ‐がすり【白絣・白飛白】
白地に紺または黒のかすり模様をあらわした布。夏の衣服に用いる。〈[季]夏〉
しろ‐がたな【白刀】
柄つかや鞘さやなどを銀の金具で飾った刀。
しろ‐がなもの【白金物】
甲冑・具足などにつける銀または鍍銀とぎんの金具。平家物語2「黒糸縅の腹巻の―うつたるむな板せめて」
しろ‐がね【銀】
(「白金」の意。古くは清音)
①銀ぎん。万葉集5「―も金くがねも玉も何せむに」
②銀泥ぎんでい。栄華物語衣珠「―の法華経一部」
③銀糸。紫式部日記「秋の草むら、蝶、鳥などを―してつくりかかやかしたり」
④「しろがねいろ」の略。
⑤銀貨。浄瑠璃、冥途飛脚「一歩小判や―に」
⇒しろがね‐いろ【銀色】
⇒しろがね‐し【銀師】
⇒しろがね‐づくり【銀作り】
しろがね‐いろ【銀色】
銀のように光る白色。ぎんいろ。
⇒しろ‐がね【銀】
しろがね‐し【銀師】
銀細工をする職人。
⇒しろ‐がね【銀】
しろがね‐づくり【銀作り】
銀で作り、または装飾したもの。ぎんごしらえ。
⇒しろ‐がね【銀】
しろ‐がまえ【城構え】‥ガマヘ
城郭を築くこと。また、その構え方。日葡辞書「シロガマエヲスル」
しろ‐かみ【白髪】
しらが。万葉集17「降る雪の―までに大君に仕へまつれば貴くもあるか」
しろ‐かみこ【白紙子】
柿渋を塗ってないかみこ。おもに律宗の僧または好事こうず者が着る。
しろ‐がや【白茅】
ヒドロ虫目(有鞘類)の刺胞しほう動物。群体は高さ10〜20センチメートル、白色の羽毛状の小枝を不規則に出す。触れると刺胞に刺され、痛みを感ずる。本州以南の浅海岩礁底に普通。
しろ‐がらす【白烏】
羽色の白い烏。すなわち、あり得ないことのたとえ。狂言、膏薬煉「海の底にすむ―」
しろ‐かわ【白皮】‥カハ
①白い皮。
②楮こうぞの靱皮じんぴの黒い表皮と甘皮層を取り除き、漂白して乾燥させたもの。和紙の原料に用いる。
しろ‐かわ【白革】‥カハ
白いなめしがわ。
⇒しろかわ‐や【白革屋】
しろかわ‐や【白革屋】‥カハ‥
生皮を精製して、なめしがわとする店または人。
⇒しろ‐かわ【白革】
しろ‐かわらげ【白川原毛】‥カハラ‥
⇒しらかわらげ
しろ‐き【白木】
①皮をむいた建築用材。
②材質の白い木材。杉・ヒノキなど。↔黒木
しろ‐き【白酒】
大嘗会だいじょうえなどに神前に供える酒。クサギの焼灰をまぜたものを黒酒くろきというのに対して、まぜないものをいう。万葉集19「天地と久しきまでに万代に仕へまつらむ黒酒―を」
⇒しろき‐でん【白酒殿】
しろ‐ぎく【白菊】
花の色の白い菊。しらぎく。
しろ‐きくらげ【白木耳】
「木耳」参照。
しろ‐ぎつね【白狐】
①年を経て毛色が白くなった狐。びゃっこ。
②北極狐の別称。
しろき‐でん【白酒殿】
大嘗会だいじょうえの時、白酒を醸造する殿舎。
⇒しろ‐き【白酒】
しろ‐きぬ【白衣】
①白色の着物。染めない衣。栄華物語初花「女房の―など」
②(墨染衣を着る僧に対していう)俗人。推古紀「俗しろきぬ七十五人」
しろ‐ぎぬ【白絹】
(シロキヌとも)
⇒しらぎぬ
しろき‐もの【白き物】
おしろい。「しろいもの」とも。紫式部日記「そらいたる櫛ども―いみじく」
しろきや【城木屋】
①浄瑠璃「恋娘昔八丈」の4段目。
②新内。初世鶴賀若狭掾作曲。歌詞は「恋娘昔八丈」から採ったお駒才三の物語。
しろ‐きわ【白際】‥キハ
①江戸時代の女官・御殿女中などに行われた化粧法。髪の生えぎわに墨で黒い筋を、その内側へ白粉で白い筋を描き、内側でぼかす。
②女官や奥女中が生えぎわから下額の中央にV字形を白粉で描き、その下に眉を描くこと。
し‐ろく【尸禄】
むなしく禄を食はむだけで、職責を果たさぬこと。その器にあらずして高禄を食むこと。ろくぬすびと。尸位素餐しいそさん。神皇正統記「臣のみだりにうくるを―とす」
し‐ろく【四六】
①4と6。また、6の4倍。
②四六判の略。
③四六文の略。
⇒しろくじ‐ちゅう【四六時中】
⇒しろく‐ばい‐ばん【四六倍判】
⇒しろく‐ばん【四六判】
⇒しろく‐ぶん【四六文】
⇒しろく‐べんれいぶん【四六駢儷文】
⇒しろく‐みせ【四六店】
し‐ろく【四緑】
九星の一つ。木星に配し、南東を本位とする。
しろ・ぐ
〔自五〕
(古くはシロク)(多く複合動詞の下位成分として)こまかに動く。「身じろぐ」「まじろぐ」「立ち―・ぐ」
しろ‐ぐくり【白括り】
白くくくった絞り染め。
しろくじ‐ちゅう【四六時中】
①二十四時間中。一日中。二六にろく時中。
②始終。つねに。日夜。
⇒し‐ろく【四六】
しろ‐くじゃく【白孔雀】
インドクジャクの白変種。→くじゃく
シロクジャク
撮影:小宮輝之
⇒しろうり‐がい【白瓜貝】
しろうり‐がい【白瓜貝】‥ガヒ
オトヒメハマグリ科の二枚貝。殻は楕円形で殻長15センチメートル。地肌は白いが薄い殻皮を被る。相模湾などの水深700〜1000メートルぐらいの海底で、湧水のある付近など特異な環境に群生。
⇒しろ‐うり【白瓜】
しろ‐うるり【白うるり】
①語義不詳。一説に「うるり」は「うり(瓜)」の変化したもので、白瓜のことかという。徒然草「この僧都、ある法師を見て、―といふ名をつけたりけり。『とは、何物ぞ』と、人の問ひければ、『さる物を我も知らず。もしあらましかば、この僧の顔に似てん』とぞいひける」
②(徒然草の話をふまえて)江戸時代、正体の知れないもの、また、あやしげな者などのたとえ。大句数上「花はあつてない物見せう吉野山―とやきゆる白雪」
しろ‐うんも【白雲母】
⇒はくうんも
しろ‐えり【白襟】
衣服の白色のえり。
⇒しろえり‐もんつき【白襟紋付】
しろえり‐もんつき【白襟紋付】
白襟の襦袢ジバンなどの上に紋付を着用すること。和服の礼装で、吉凶ともに用いる。
⇒しろ‐えり【白襟】
しろ‐お【白魚】‥ヲ
シラウオの古名。〈倭名類聚鈔19〉
シローテ【G. B. Sidotti】
⇒シドッチ
しろ‐おとり【白御鳥】
(女房詞)雉きじ。
しろ‐おに【白鬼】
明治の初め頃、売春婦の異称。樋口一葉の「にごりえ」に所見。白首しろくび。
シローネ【Ignazio Silone】
イタリアの小説家・政治家。強い左翼的信条に裏打ちされたモラリストの立場を貫いた。地方農民の窮状を告発する小説「フォンタマーラ」「パンと葡萄酒」が代表作。(1900〜1978)
しろ‐おび【白帯】
①白色の帯。
②柔道・空手などで、段位の無い者が締める白色の帯。
しろ‐が・う【代替ふ】‥ガフ
〔他下二〕
(シロカウとも)売って金にかえる。しろなす。御伽草子、唐糸草子「小袖を町へいだし、―・へて」
しろ‐かが【白加賀】
白色の加賀絹。
しろ‐かき【代掻き】
水もれを防ぎ、苗の活着・発育をよくするなどのため、田植前の田に水を満たし、鍬や馬鍬まぐわ、ロータリーを装着したトラクターなどを用いて土塊を砕き田面を平らにする作業。荒代あらしろ・中代なかじろ・植代うえしろの三回行うのが普通。〈[季]夏〉
しろ‐がき【白柿】
干して白く粉をふいた柿。
しろ‐かげ【白鹿毛】
⇒しらかげ
しろ‐がさね【白重ね・白襲】
⇒しらがさね
しろ‐かしら【白頭】
能の仮髪の一つ。→頭➋2
しろ‐がすり【白絣・白飛白】
白地に紺または黒のかすり模様をあらわした布。夏の衣服に用いる。〈[季]夏〉
しろ‐がたな【白刀】
柄つかや鞘さやなどを銀の金具で飾った刀。
しろ‐がなもの【白金物】
甲冑・具足などにつける銀または鍍銀とぎんの金具。平家物語2「黒糸縅の腹巻の―うつたるむな板せめて」
しろ‐がね【銀】
(「白金」の意。古くは清音)
①銀ぎん。万葉集5「―も金くがねも玉も何せむに」
②銀泥ぎんでい。栄華物語衣珠「―の法華経一部」
③銀糸。紫式部日記「秋の草むら、蝶、鳥などを―してつくりかかやかしたり」
④「しろがねいろ」の略。
⑤銀貨。浄瑠璃、冥途飛脚「一歩小判や―に」
⇒しろがね‐いろ【銀色】
⇒しろがね‐し【銀師】
⇒しろがね‐づくり【銀作り】
しろがね‐いろ【銀色】
銀のように光る白色。ぎんいろ。
⇒しろ‐がね【銀】
しろがね‐し【銀師】
銀細工をする職人。
⇒しろ‐がね【銀】
しろがね‐づくり【銀作り】
銀で作り、または装飾したもの。ぎんごしらえ。
⇒しろ‐がね【銀】
しろ‐がまえ【城構え】‥ガマヘ
城郭を築くこと。また、その構え方。日葡辞書「シロガマエヲスル」
しろ‐かみ【白髪】
しらが。万葉集17「降る雪の―までに大君に仕へまつれば貴くもあるか」
しろ‐かみこ【白紙子】
柿渋を塗ってないかみこ。おもに律宗の僧または好事こうず者が着る。
しろ‐がや【白茅】
ヒドロ虫目(有鞘類)の刺胞しほう動物。群体は高さ10〜20センチメートル、白色の羽毛状の小枝を不規則に出す。触れると刺胞に刺され、痛みを感ずる。本州以南の浅海岩礁底に普通。
しろ‐がらす【白烏】
羽色の白い烏。すなわち、あり得ないことのたとえ。狂言、膏薬煉「海の底にすむ―」
しろ‐かわ【白皮】‥カハ
①白い皮。
②楮こうぞの靱皮じんぴの黒い表皮と甘皮層を取り除き、漂白して乾燥させたもの。和紙の原料に用いる。
しろ‐かわ【白革】‥カハ
白いなめしがわ。
⇒しろかわ‐や【白革屋】
しろかわ‐や【白革屋】‥カハ‥
生皮を精製して、なめしがわとする店または人。
⇒しろ‐かわ【白革】
しろ‐かわらげ【白川原毛】‥カハラ‥
⇒しらかわらげ
しろ‐き【白木】
①皮をむいた建築用材。
②材質の白い木材。杉・ヒノキなど。↔黒木
しろ‐き【白酒】
大嘗会だいじょうえなどに神前に供える酒。クサギの焼灰をまぜたものを黒酒くろきというのに対して、まぜないものをいう。万葉集19「天地と久しきまでに万代に仕へまつらむ黒酒―を」
⇒しろき‐でん【白酒殿】
しろ‐ぎく【白菊】
花の色の白い菊。しらぎく。
しろ‐きくらげ【白木耳】
「木耳」参照。
しろ‐ぎつね【白狐】
①年を経て毛色が白くなった狐。びゃっこ。
②北極狐の別称。
しろき‐でん【白酒殿】
大嘗会だいじょうえの時、白酒を醸造する殿舎。
⇒しろ‐き【白酒】
しろ‐きぬ【白衣】
①白色の着物。染めない衣。栄華物語初花「女房の―など」
②(墨染衣を着る僧に対していう)俗人。推古紀「俗しろきぬ七十五人」
しろ‐ぎぬ【白絹】
(シロキヌとも)
⇒しらぎぬ
しろき‐もの【白き物】
おしろい。「しろいもの」とも。紫式部日記「そらいたる櫛ども―いみじく」
しろきや【城木屋】
①浄瑠璃「恋娘昔八丈」の4段目。
②新内。初世鶴賀若狭掾作曲。歌詞は「恋娘昔八丈」から採ったお駒才三の物語。
しろ‐きわ【白際】‥キハ
①江戸時代の女官・御殿女中などに行われた化粧法。髪の生えぎわに墨で黒い筋を、その内側へ白粉で白い筋を描き、内側でぼかす。
②女官や奥女中が生えぎわから下額の中央にV字形を白粉で描き、その下に眉を描くこと。
し‐ろく【尸禄】
むなしく禄を食はむだけで、職責を果たさぬこと。その器にあらずして高禄を食むこと。ろくぬすびと。尸位素餐しいそさん。神皇正統記「臣のみだりにうくるを―とす」
し‐ろく【四六】
①4と6。また、6の4倍。
②四六判の略。
③四六文の略。
⇒しろくじ‐ちゅう【四六時中】
⇒しろく‐ばい‐ばん【四六倍判】
⇒しろく‐ばん【四六判】
⇒しろく‐ぶん【四六文】
⇒しろく‐べんれいぶん【四六駢儷文】
⇒しろく‐みせ【四六店】
し‐ろく【四緑】
九星の一つ。木星に配し、南東を本位とする。
しろ・ぐ
〔自五〕
(古くはシロク)(多く複合動詞の下位成分として)こまかに動く。「身じろぐ」「まじろぐ」「立ち―・ぐ」
しろ‐ぐくり【白括り】
白くくくった絞り染め。
しろくじ‐ちゅう【四六時中】
①二十四時間中。一日中。二六にろく時中。
②始終。つねに。日夜。
⇒し‐ろく【四六】
しろ‐くじゃく【白孔雀】
インドクジャクの白変種。→くじゃく
シロクジャク
撮影:小宮輝之
 しろ‐くじら【白鯨】‥クヂラ
コククジラからとった鯨ひげ。色は白く美しい。籠目などに編んで汗衫かざみなどにする。
しろ‐ぐち【白ぐち】
ニベ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。体はスズキ型、灰色で銀色の光沢がある。鱗ははげやすい。南日本に多く、かまぼこの材料。イシモチ。
しろぐち
しろ‐くじら【白鯨】‥クヂラ
コククジラからとった鯨ひげ。色は白く美しい。籠目などに編んで汗衫かざみなどにする。
しろ‐ぐち【白ぐち】
ニベ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。体はスズキ型、灰色で銀色の光沢がある。鱗ははげやすい。南日本に多く、かまぼこの材料。イシモチ。
しろぐち
 シログチ
提供:東京動物園協会
シログチ
提供:東京動物園協会
 しろ‐ぐつ【白靴】
夏用の白いくつ。〈[季]夏〉
しろ‐ぐつわ【白轡】
白く光るように磨いた鉄製の轡。平家物語9「白葦毛なる老馬にかがみ鞍をき、―はげ」
しろく‐ばい‐ばん【四六倍判】
書籍の大きさ。四六判の2倍。
⇒し‐ろく【四六】
しろく‐ばん【四六判】
①紙の標準原紙寸法の一つ。788ミリメートル×1091ミリメートルで、B列本判よりやや大きい。四六全判。
②書籍寸法の一つ。四六全判32枚どり(64ページ分)を化粧裁ちした大きさ。127ミリメートル(4寸2分)×188ミリメートル(6寸2分)で、B6判よりやや大きい。
⇒し‐ろく【四六】
しろ‐くび【白首】
襟白粉えりおしろいを濃く塗りたて、客に媚こびを売る女。酌婦・娼妓など。しらくび。
しろく‐ぶん【四六文】
漢文の一体。古文と相対するもの。漢・魏に源を発し、六朝りくちょうから唐に流行。4字および6字の句を基本とし、対句ついくを多用し、平仄ひょうそくにも留意して声調を整え、文辞は華美で典故を繁用するのが特徴。奈良・平安時代の漢文は多くこの風により、「菅家文草」「和漢朗詠集」などに散見。四六駢儷べんれい文。駢儷文。駢文。
⇒し‐ろく【四六】
しろく‐べんれいぶん【四六駢儷文】
(→)四六文に同じ。
⇒し‐ろく【四六】
しろ‐くま【白熊】
ホッキョクグマの別称。
しろく‐みせ【四六店】
(夜は400文、昼は600文で遊興させたからいう)江戸後期、天明・寛政から天保の頃まで、江戸吉原の河岸見世かしみせや諸方の岡場所の下等の娼家の称。
⇒し‐ろく【四六】
しろ‐くら【白鞍】
①前輪まえわ・後輪しずわに銀を張った鞍。
②白木のままで漆を塗らない鞍。白鞍橋しろくらぼね。
しろ‐くりげ【白栗毛】
⇒しらくりげ
しろ‐ぐるま【代車】
代掻しろかきに用いる農具。牛馬にひかせるもの。
しろ‐くれない【白紅】‥クレナヰ
半ば白く、半ば紅に染めたみずひき。
しろ‐くろ【白黒】
①白と黒。「目を―させる」
②画面がカラーでなく、白と黒で表される写真・映画・テレビなど。「―写真」
③よしあし。是非。無罪か有罪か。こくびゃく。「―を決める」
しろ‐クローバー【白クローバー】
シロツメクサの別称。
しろ‐げ【白毛】
馬の毛色の名。白色のもの。
しろ‐こ【白子】
人間や動植物でメラニン・葉緑素などの色素を欠き、多くは白色となった個体。しらこ。アルビノ。
しろ‐ごし【白輿】
⇒しらごし
しろ‐こしょう【白胡椒】‥セウ
「胡椒2」参照。
しろ‐こそで【白小袖】
白無地の小袖。しろむく。↔色小袖
しろ‐ごま【白胡麻】
種子の白いゴマ。
しろ‐ごめ【白米】
搗ついてしらげた米。はくまい。↔玄米くろごめ
しろ‐ざ【白藜】
アカザの別称。本来はこのシロザのうちの、芽立ちが紅色になる変種をアカザと呼んだ。しろあかざ。
じろざえもん‐びな【次郎左衛門雛】‥ヱ‥
享保(1716〜1736)の頃、京都の人形師雛屋次郎左衛門が作り出した雛人形。顔は引目鉤鼻ひきめかぎはなに描き、典雅な気品を備える。1761年(宝暦11)江戸に進出し、30年間人気を独占。
しろ‐ざくら【白桜】
①襲かさねの色目。表は白、裏は白または紫。
②シラカバの異称。
③ミヤマザクラの異称。
しろ‐ざけ【白酒】
①粘りのある白濁した酒。蒸した糯米もちごめと米麹こめこうじとを味醂または清酒・焼酎に混和して発酵させ、後にすりつぶして造る。甘味豊かで一種特有の香気がある。多く雛祭に用いる。山川酒。〈[季]春〉
②濁酒どぶろくの別称。
しろ‐ざとう【白砂糖】‥タウ
精製した白色の砂糖。
しろ‐さま【白様】
(山形・新潟県で)蚕かいこ。おしらさま。
しろ‐さやまき【白鞘巻】
銀の金具で柄つか・鞘などを飾った鞘巻。義経記7「笈の中より―を取出して」
しろ‐さんご【白珊瑚】
本サンゴの一種で、アカサンゴに近縁。骨格が堅く、密で白い。装飾品に加工される。
しろ‐サントメ【白桟留】
純白色のサントメ革。
しろ・し【白し】
〔形ク〕
⇒しろい
しろ・し【著し】
〔形ク〕
きわだっている。あきらかである。しるし。平家物語9「褐かちに―・う黄なる糸をもつて、群千鳥むらちどり縫うたる直垂に」
しろ‐じ【白地】‥ヂ
布・紙などの、地質の白いもの。〈[季]夏〉。今昔物語集20「―の小瓶の有りけるが」→しらじ
しろし・い
〔形〕
(福岡県で)うっとうしい。しるしい。
しろ‐した【白下】
(白砂糖を製する下地の意)サトウキビの絞り汁のアクを抜き、煮詰めた黄褐色の半流動物。蔗糖結晶と糖蜜が混合した含蜜糖。白下糖。これを圧搾して繰り返し揉んで糖蜜を取り除いたものが和三盆。
しろした‐がれい【城下鰈】‥ガレヒ
大分県日出ひじ町の日出城下の別府湾で漁獲されるマコガレイの称。
しろ‐じたき【代下木】
(西日本で)水田に入れる緑肥。下木したき。刈敷かりしき。刈敷肥かっちきごえ。
しろ‐しっくい【白漆喰】‥クヒ
顔料を加えない、上塗り用の白色の漆喰。
しろ‐しぼり【白搾り・白絞り】
⇒しらしぼり
しろし‐め・す【知ろしめす】
〔他五〕
(「知る」の尊敬語「しろす」よりさらに敬意の強い言い方。上代には「しらしめす」とも)
①お知りになる。ご存知である。源氏物語花宴「くはしう―・し調へさせ給へるけなり」。天草本平家物語「鎌倉殿までもさる者のあるとは―・されつらう」
②領せられる。お治めになる。古今和歌集序「すべらぎの天の下―・すこと」。平家物語11「ただ世の乱れをしづめて、国を―・さんを君とせん」
③お世話なさる。源氏物語夢浮橋「更に―・すべきこととは、いかでか空に悟り侍らむ」
しろ‐しょいん【白書院】‥ヰン
書院の一形式。桧柾目ひのきまさめの素木しらきを主とした書院造。黒書院が奥向きで日常よく使われるのに対して、白書院は表向き正式の間。二条城のみ例外で、もとは御座間。しろじょいん。
しろ‐じょうえ【白浄衣】‥ジヤウ‥
純白の浄衣。
しろ‐しょうぞく【白装束】‥シヤウ‥
①公家装束の一種。下襲したがさね以下の下着の色目をすべて白一色にしたもの。
②白地の装束。昔は産室で着用し、後世は多く凶時に用いた。
しろ‐しょうゆ【白醤油】‥シヤウ‥
小麦を主原料に少量の炒った大豆を加えて作る醤油。発酵を抑制して作るので色が薄く、糖分が多い。愛知県の特産。
しろ‐じろ【白白】
めだって白いさま。
じろ‐じろ
好奇心や軽蔑の気持から無遠慮に見つめ続けるさま。「室内を―眺めまわす」
しろ・す【知ろす】
〔他四〕
「しる」の尊敬語。しらす。→しろしめす
しろ‐ず【白酢】
紫蘇しそを加えない梅酢。白梅酢。
しろ‐すぎ【白杉】
北山磨き丸太に用いる杉の品種。
しろ‐ずみ【白炭】
①木炭の一種。石窯いしがまでセ氏900度〜1400度の高熱で焼き、これを窯の外にかき出し、消粉と称する土・炭・炭粉をまぜたものをかぶせて火を消すので表面が灰白色を帯びる。質が密で堅い。原材は樫・栗など。備長びんちょうといって、ウバメガシを焼いたものが最良。かたずみ。↔黒炭くろずみ。
②茶の湯用の炭。→枝炭
シロ‐セット‐かこう【シロセット加工】
(「シロ」は、これを開発したオーストラリアの連邦科学産業研究機構の略称CSIRO)毛織物に耐久性のあるひだをつける加工法。
しろ‐ぜめ【城攻め】
城を攻めること。
しろ‐そこひ【白底翳】
白内障はくないしょうの俗称。
しろ‐た【代田】
田植え前の田。田植えの準備のととのった田。〈[季]夏〉
しろ‐た【白田】
①(「畠」の字を「白」と「田」とに分けていった語)はたけ。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「うろたへて―へ潜る畠垣」
②雪がつもって白くなっている冬の田。→青田→黒田。
⇒しろた‐ばいばい【白田売買】
しろ‐たえ【白妙・白
しろ‐ぐつ【白靴】
夏用の白いくつ。〈[季]夏〉
しろ‐ぐつわ【白轡】
白く光るように磨いた鉄製の轡。平家物語9「白葦毛なる老馬にかがみ鞍をき、―はげ」
しろく‐ばい‐ばん【四六倍判】
書籍の大きさ。四六判の2倍。
⇒し‐ろく【四六】
しろく‐ばん【四六判】
①紙の標準原紙寸法の一つ。788ミリメートル×1091ミリメートルで、B列本判よりやや大きい。四六全判。
②書籍寸法の一つ。四六全判32枚どり(64ページ分)を化粧裁ちした大きさ。127ミリメートル(4寸2分)×188ミリメートル(6寸2分)で、B6判よりやや大きい。
⇒し‐ろく【四六】
しろ‐くび【白首】
襟白粉えりおしろいを濃く塗りたて、客に媚こびを売る女。酌婦・娼妓など。しらくび。
しろく‐ぶん【四六文】
漢文の一体。古文と相対するもの。漢・魏に源を発し、六朝りくちょうから唐に流行。4字および6字の句を基本とし、対句ついくを多用し、平仄ひょうそくにも留意して声調を整え、文辞は華美で典故を繁用するのが特徴。奈良・平安時代の漢文は多くこの風により、「菅家文草」「和漢朗詠集」などに散見。四六駢儷べんれい文。駢儷文。駢文。
⇒し‐ろく【四六】
しろく‐べんれいぶん【四六駢儷文】
(→)四六文に同じ。
⇒し‐ろく【四六】
しろ‐くま【白熊】
ホッキョクグマの別称。
しろく‐みせ【四六店】
(夜は400文、昼は600文で遊興させたからいう)江戸後期、天明・寛政から天保の頃まで、江戸吉原の河岸見世かしみせや諸方の岡場所の下等の娼家の称。
⇒し‐ろく【四六】
しろ‐くら【白鞍】
①前輪まえわ・後輪しずわに銀を張った鞍。
②白木のままで漆を塗らない鞍。白鞍橋しろくらぼね。
しろ‐くりげ【白栗毛】
⇒しらくりげ
しろ‐ぐるま【代車】
代掻しろかきに用いる農具。牛馬にひかせるもの。
しろ‐くれない【白紅】‥クレナヰ
半ば白く、半ば紅に染めたみずひき。
しろ‐くろ【白黒】
①白と黒。「目を―させる」
②画面がカラーでなく、白と黒で表される写真・映画・テレビなど。「―写真」
③よしあし。是非。無罪か有罪か。こくびゃく。「―を決める」
しろ‐クローバー【白クローバー】
シロツメクサの別称。
しろ‐げ【白毛】
馬の毛色の名。白色のもの。
しろ‐こ【白子】
人間や動植物でメラニン・葉緑素などの色素を欠き、多くは白色となった個体。しらこ。アルビノ。
しろ‐ごし【白輿】
⇒しらごし
しろ‐こしょう【白胡椒】‥セウ
「胡椒2」参照。
しろ‐こそで【白小袖】
白無地の小袖。しろむく。↔色小袖
しろ‐ごま【白胡麻】
種子の白いゴマ。
しろ‐ごめ【白米】
搗ついてしらげた米。はくまい。↔玄米くろごめ
しろ‐ざ【白藜】
アカザの別称。本来はこのシロザのうちの、芽立ちが紅色になる変種をアカザと呼んだ。しろあかざ。
じろざえもん‐びな【次郎左衛門雛】‥ヱ‥
享保(1716〜1736)の頃、京都の人形師雛屋次郎左衛門が作り出した雛人形。顔は引目鉤鼻ひきめかぎはなに描き、典雅な気品を備える。1761年(宝暦11)江戸に進出し、30年間人気を独占。
しろ‐ざくら【白桜】
①襲かさねの色目。表は白、裏は白または紫。
②シラカバの異称。
③ミヤマザクラの異称。
しろ‐ざけ【白酒】
①粘りのある白濁した酒。蒸した糯米もちごめと米麹こめこうじとを味醂または清酒・焼酎に混和して発酵させ、後にすりつぶして造る。甘味豊かで一種特有の香気がある。多く雛祭に用いる。山川酒。〈[季]春〉
②濁酒どぶろくの別称。
しろ‐ざとう【白砂糖】‥タウ
精製した白色の砂糖。
しろ‐さま【白様】
(山形・新潟県で)蚕かいこ。おしらさま。
しろ‐さやまき【白鞘巻】
銀の金具で柄つか・鞘などを飾った鞘巻。義経記7「笈の中より―を取出して」
しろ‐さんご【白珊瑚】
本サンゴの一種で、アカサンゴに近縁。骨格が堅く、密で白い。装飾品に加工される。
しろ‐サントメ【白桟留】
純白色のサントメ革。
しろ・し【白し】
〔形ク〕
⇒しろい
しろ・し【著し】
〔形ク〕
きわだっている。あきらかである。しるし。平家物語9「褐かちに―・う黄なる糸をもつて、群千鳥むらちどり縫うたる直垂に」
しろ‐じ【白地】‥ヂ
布・紙などの、地質の白いもの。〈[季]夏〉。今昔物語集20「―の小瓶の有りけるが」→しらじ
しろし・い
〔形〕
(福岡県で)うっとうしい。しるしい。
しろ‐した【白下】
(白砂糖を製する下地の意)サトウキビの絞り汁のアクを抜き、煮詰めた黄褐色の半流動物。蔗糖結晶と糖蜜が混合した含蜜糖。白下糖。これを圧搾して繰り返し揉んで糖蜜を取り除いたものが和三盆。
しろした‐がれい【城下鰈】‥ガレヒ
大分県日出ひじ町の日出城下の別府湾で漁獲されるマコガレイの称。
しろ‐じたき【代下木】
(西日本で)水田に入れる緑肥。下木したき。刈敷かりしき。刈敷肥かっちきごえ。
しろ‐しっくい【白漆喰】‥クヒ
顔料を加えない、上塗り用の白色の漆喰。
しろ‐しぼり【白搾り・白絞り】
⇒しらしぼり
しろし‐め・す【知ろしめす】
〔他五〕
(「知る」の尊敬語「しろす」よりさらに敬意の強い言い方。上代には「しらしめす」とも)
①お知りになる。ご存知である。源氏物語花宴「くはしう―・し調へさせ給へるけなり」。天草本平家物語「鎌倉殿までもさる者のあるとは―・されつらう」
②領せられる。お治めになる。古今和歌集序「すべらぎの天の下―・すこと」。平家物語11「ただ世の乱れをしづめて、国を―・さんを君とせん」
③お世話なさる。源氏物語夢浮橋「更に―・すべきこととは、いかでか空に悟り侍らむ」
しろ‐しょいん【白書院】‥ヰン
書院の一形式。桧柾目ひのきまさめの素木しらきを主とした書院造。黒書院が奥向きで日常よく使われるのに対して、白書院は表向き正式の間。二条城のみ例外で、もとは御座間。しろじょいん。
しろ‐じょうえ【白浄衣】‥ジヤウ‥
純白の浄衣。
しろ‐しょうぞく【白装束】‥シヤウ‥
①公家装束の一種。下襲したがさね以下の下着の色目をすべて白一色にしたもの。
②白地の装束。昔は産室で着用し、後世は多く凶時に用いた。
しろ‐しょうゆ【白醤油】‥シヤウ‥
小麦を主原料に少量の炒った大豆を加えて作る醤油。発酵を抑制して作るので色が薄く、糖分が多い。愛知県の特産。
しろ‐じろ【白白】
めだって白いさま。
じろ‐じろ
好奇心や軽蔑の気持から無遠慮に見つめ続けるさま。「室内を―眺めまわす」
しろ・す【知ろす】
〔他四〕
「しる」の尊敬語。しらす。→しろしめす
しろ‐ず【白酢】
紫蘇しそを加えない梅酢。白梅酢。
しろ‐すぎ【白杉】
北山磨き丸太に用いる杉の品種。
しろ‐ずみ【白炭】
①木炭の一種。石窯いしがまでセ氏900度〜1400度の高熱で焼き、これを窯の外にかき出し、消粉と称する土・炭・炭粉をまぜたものをかぶせて火を消すので表面が灰白色を帯びる。質が密で堅い。原材は樫・栗など。備長びんちょうといって、ウバメガシを焼いたものが最良。かたずみ。↔黒炭くろずみ。
②茶の湯用の炭。→枝炭
シロ‐セット‐かこう【シロセット加工】
(「シロ」は、これを開発したオーストラリアの連邦科学産業研究機構の略称CSIRO)毛織物に耐久性のあるひだをつける加工法。
しろ‐ぜめ【城攻め】
城を攻めること。
しろ‐そこひ【白底翳】
白内障はくないしょうの俗称。
しろ‐た【代田】
田植え前の田。田植えの準備のととのった田。〈[季]夏〉
しろ‐た【白田】
①(「畠」の字を「白」と「田」とに分けていった語)はたけ。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「うろたへて―へ潜る畠垣」
②雪がつもって白くなっている冬の田。→青田→黒田。
⇒しろた‐ばいばい【白田売買】
しろ‐たえ【白妙・白 】‥タヘ
①(その色が白いからいう)穀かじの木の皮の繊維で織った布。万葉集3「―にころも取り着て」。万葉集10「―ごろも垢づくまでに」
②白い色。万葉集10「鶯のはね―にあわ雪そふる」
⇒しろたえ‐の【白妙の】
しろたえ‐の【白妙の】‥タヘ‥
〔枕〕
「ころも」「そで」「たもと」「ひも」「ひれ」「帯」「たすき」または「くも」「ゆき」にかかる。
⇒しろ‐たえ【白妙・白
】‥タヘ
①(その色が白いからいう)穀かじの木の皮の繊維で織った布。万葉集3「―にころも取り着て」。万葉集10「―ごろも垢づくまでに」
②白い色。万葉集10「鶯のはね―にあわ雪そふる」
⇒しろたえ‐の【白妙の】
しろたえ‐の【白妙の】‥タヘ‥
〔枕〕
「ころも」「そで」「たもと」「ひも」「ひれ」「帯」「たすき」または「くも」「ゆき」にかかる。
⇒しろ‐たえ【白妙・白 】
しろ‐タク【白タク】
営業許可を受けずに、自家用車の白ナンバーをつけてタクシー行為をしているものの通称。
しろ‐だすき【白襷】
白布のたすき。
しろ‐だち【白太刀】
銀作しろがねづくりの太刀。太平記34「四尺五尺の―に」
しろた‐ばいばい【白田売買】
まだ田に雪のある頃、その年に収穫を予想される産米の売買契約をすること。
⇒しろ‐た【白田】
しろ‐たぶ【白たぶ】
(→)「白だも」に同じ。
しろ‐だも【白だも】
クスノキ科の常緑高木。関東以南の山地に自生。葉は楕円形で裏面が白く、車輪状につく。木全体に精油を含み芳香がある。晩秋に黄褐色の小花を多数つけ、翌年の秋冬に赤色の球果が熟する。種子から採油し、蝋燭の材料とする。シロタブ。タマガヤ。
シロダモ
撮影:関戸 勇
】
しろ‐タク【白タク】
営業許可を受けずに、自家用車の白ナンバーをつけてタクシー行為をしているものの通称。
しろ‐だすき【白襷】
白布のたすき。
しろ‐だち【白太刀】
銀作しろがねづくりの太刀。太平記34「四尺五尺の―に」
しろた‐ばいばい【白田売買】
まだ田に雪のある頃、その年に収穫を予想される産米の売買契約をすること。
⇒しろ‐た【白田】
しろ‐たぶ【白たぶ】
(→)「白だも」に同じ。
しろ‐だも【白だも】
クスノキ科の常緑高木。関東以南の山地に自生。葉は楕円形で裏面が白く、車輪状につく。木全体に精油を含み芳香がある。晩秋に黄褐色の小花を多数つけ、翌年の秋冬に赤色の球果が熟する。種子から採油し、蝋燭の材料とする。シロタブ。タマガヤ。
シロダモ
撮影:関戸 勇
 しろ‐たれ【白垂】
能の仮髪の一つ。→垂たれ6
しろ‐ちょうがい【白蝶貝】‥テフガヒ
ウグイスガイ科の二枚貝。殻は円盤状で平たく、黄褐色。内面は白銀色で真珠光沢が強い。殻径30センチメートル内外。熱帯西太平洋に分布。貝ボタンその他工芸加工品の材料となる。稀に極めて高価な天然真珠を含む。
しろ‐ちょうちん【白提灯】‥チヤウ‥
白張しらはりの提灯。
しろ‐ちりめん【白縮緬】
染めない白地の縮緬。
しろ‐つか【白柄】
⇒しらつか
しろ‐づき【白搗き】
玄米を白くつきしらげること。また、ついて白くした米。日葡辞書「シロヅキノコメ」
しろ‐つきげ【白月毛】
⇒しらつきげ
シロッコ【scirocco イタリア】
サハラ砂漠から地中海方面に吹く熱風。
しろ‐つつじ【白躑躅】
①白色の花の咲くツツジの総称。〈本草和名〉
②襲かさねの色目。表は白、裏は紫。
じろっ‐と
〔副〕
険しい視線を向けるさま。「―にらむ」
シロップ【siroop オランダ】
①濃厚な砂糖溶液。単舎利別たんシャリベツ。シラップ。砂糖蜜。
②(→)果実シロップに同じ。
しろっ‐ぽ・い【白っぽい】
〔形〕
①白みがかっている。
②しろうとくさい。浮世風呂4「隈取といひなせえ、隈ゑどりだけ古風で―・い」
しろ‐づめ【城詰】
城中につめていること。また、その武士。
しろ‐つめくさ【白詰草】
マメ科の多年草。ヨーロッパ原産で日本各地に自生化。葉柄は長く、葉は倒卵形の3個の小葉から成る。夏に長軸を出し、白色の蝶形花を多数球状に集めてつける。緑肥・牧草用。クローバー。オランダゲンゲ。ツメクサ。→アカツメクサ
しろ‐で【白手】
白色の釉うわぐすりをかけた磁器。
しろ‐と【素人】
(→)「しろうと」に同じ。
⇒しろと‐すい【素人粋】
ジロドゥー【Jean Giraudoux】
フランスの劇作家・小説家・外交官。精妙な心理性、自在な幻想性、鋭い諷刺性が溶け合った戯曲でフランス現代劇を代表。代表作「トロイ戦争は起こらない」「エレクトル」のほか、小説「シュザンヌと太平洋」など。(1882〜1944)
しろと‐すい【素人粋】
素人しろうとでありながら、粋人ぶる者。半可通。好色一代女1「物に馴れたる客は各別、まだしき―は」
⇒しろ‐と【素人】
しろ‐とり【白鳥】
⇒しらとり
しろ‐どり【城取】
城郭を構え設けること。城構え。甲陽軍鑑3「―、陣取、一切の軍法をよく鍛錬いたす」
しろ‐ナイル【白ナイル】
(White Nile)ナイル川上流部の名称。狭義にはナイル川がスーダン南部のノー湖でガザル川を合わせる地点から、ハルツームで青ナイルと合流するまでをいう。広義にはノー湖から上流のスーダン南端のニムレに至るジェベル川を含める。
しろながす‐くじら【白長須鯨】‥クヂラ
鬚ひげクジラの一種。動物中最大で全長30メートル、体重100トン以上に達する。ナガスクジラに似るが、背鰭せびれが小さく体は青灰色。太平洋・大西洋の北部および南氷洋に分布し、オキアミなどを食う。かつては捕鯨の主目標とされた。
しろ‐なす【白茄子】
果実の色の白いナス。しろなすび。
しろ‐な・す【代為す】
〔他四〕
物品を売って金にかえる。売る。「うりしろなす」とも。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「侍の武具馬具を―・して」
しろ‐なでしこ【白撫子】
①白い花の咲くナデシコ。
②襲かさねの色目。表は白、裏は蘇芳すおう。夏に用いる。
しろ‐なまず【白癜】‥ナマヅ
色素の欠乏によって、白色の斑紋を生じる皮膚病。尋常性白斑。白斑。〈日葡辞書〉
しろ‐なまり【白鉛】
①錫すずの古名。〈倭名類聚鈔11〉
②白鑞しろめの別称。
しろ‐なめし【白鞣】
(「しろなめしがわ」の略)染色しないなめしがわ。
しろ‐なんてん【白南天】
白色の果実を結ぶナンテンの一品種。観賞用・薬用。シロミナンテン。
しろ‐ナンバー【白ナンバー】
(白地のナンバー‐プレートから)自家用自動車の俗称。→白タク
しろ‐ぬき【白抜き】
染色・印刷などで、その部分だけ地色を白く抜いて、模様・文字等を表すこと。また、そのもの。「黒地に―の文字」
しろ‐ぬの【白布】
白色の、さらし布。さらし。
しろ‐ぬめ【白絖】
白色の、つやのある絹布。世間胸算用1「―の足袋はくなど」
しろ‐ぬり【白塗り】
白く塗ること。白く塗ったもの。特に、俳優が顔を白く塗ること。→しらぬり
しろ‐ね【白根】
①シソ科の多年草。各地の湿地に自生。地下茎は多少肥厚して白色、先端は肥厚してチョロギに似る。この部分は食用にすることもある。茎は方形で高さ1メートル内外。夏、茎上・葉腋に白色の小唇形花をつける。
②(女房詞)ねぎ。
③野菜などの茎・根の地中にある白い部分。
⇒しろね‐ぐさ【白根草】
しろね【白根】
新潟県中部の地名。新潟市に属する。信濃川とその分流に囲まれ、低湿地の改良で越後平野の米作中心となる。
しろ‐ねぎ【白葱】
葱の軟化部が白色で長いもの。
しろね‐ぐさ【白根草】
セリの異称。
⇒しろ‐ね【白根】
しろ‐ねずみ【白鼠】
①毛色が白く、眼の赤いネズミの俗な総称。大黒天の使で、そのすむ家は繁昌すると伝え、大黒ねずみともいう。
②㋐ドブネズミの飼養変種。実験用に使われる。ラット。
㋑ハツカネズミの俗称。
③(1が大黒天に仕えたという伝えから)主家に忠実な番頭・雇人。好色一代女4「京の旦那の為に―といはれて」
④染色の名。薄いねずみ色。しろねず。うすねずみ。
しろ‐ねり【白練】
①白い練絹ねりぎぬ。
②白い練羊羹ねりようかん。
しろ‐ネル【白ネル】
白色のフランネル。毛織・綿織・綿毛交織の3種がある。下着類や寝衣に用いる。
しろ‐の【白箆】
⇒しらの
しろ‐のり【城乗り】
敵城に攻め入ること。
しろ‐バイ【白バイ】
(バイはオートバイの略)警察で使用する、白塗りのオートバイ。
しろ‐はえ【白南風】
⇒しらはえ
しろ‐ばえ【白映え】
梅雨つゆのとき、小雨が降りながら時々晴れそうになること。
しろはぜ‐らん【白罅卵】
色素が一方に偏在し、白濁した大きな斑点が見える蚕卵。冷蔵庫からの出し入れの際の温度の激変によって生ずるもので、孵化しない。
しろ‐はた【白旗】
⇒しらはた
しろ‐ば・む【白ばむ】
〔自五〕
白色を帯びる。白く色づく。
しろ‐はら【白腹】
スズメ目ツグミ科の鳥。大きさはツグミほどで、習性も似る。背面は褐色、翼と尾羽は黒褐色、胸以下の下面は白色。ウスリー・アムール・中国東北部で繁殖し、秋、日本に渡来。シナイ。
シロハラ
撮影:小宮輝之
しろ‐たれ【白垂】
能の仮髪の一つ。→垂たれ6
しろ‐ちょうがい【白蝶貝】‥テフガヒ
ウグイスガイ科の二枚貝。殻は円盤状で平たく、黄褐色。内面は白銀色で真珠光沢が強い。殻径30センチメートル内外。熱帯西太平洋に分布。貝ボタンその他工芸加工品の材料となる。稀に極めて高価な天然真珠を含む。
しろ‐ちょうちん【白提灯】‥チヤウ‥
白張しらはりの提灯。
しろ‐ちりめん【白縮緬】
染めない白地の縮緬。
しろ‐つか【白柄】
⇒しらつか
しろ‐づき【白搗き】
玄米を白くつきしらげること。また、ついて白くした米。日葡辞書「シロヅキノコメ」
しろ‐つきげ【白月毛】
⇒しらつきげ
シロッコ【scirocco イタリア】
サハラ砂漠から地中海方面に吹く熱風。
しろ‐つつじ【白躑躅】
①白色の花の咲くツツジの総称。〈本草和名〉
②襲かさねの色目。表は白、裏は紫。
じろっ‐と
〔副〕
険しい視線を向けるさま。「―にらむ」
シロップ【siroop オランダ】
①濃厚な砂糖溶液。単舎利別たんシャリベツ。シラップ。砂糖蜜。
②(→)果実シロップに同じ。
しろっ‐ぽ・い【白っぽい】
〔形〕
①白みがかっている。
②しろうとくさい。浮世風呂4「隈取といひなせえ、隈ゑどりだけ古風で―・い」
しろ‐づめ【城詰】
城中につめていること。また、その武士。
しろ‐つめくさ【白詰草】
マメ科の多年草。ヨーロッパ原産で日本各地に自生化。葉柄は長く、葉は倒卵形の3個の小葉から成る。夏に長軸を出し、白色の蝶形花を多数球状に集めてつける。緑肥・牧草用。クローバー。オランダゲンゲ。ツメクサ。→アカツメクサ
しろ‐で【白手】
白色の釉うわぐすりをかけた磁器。
しろ‐と【素人】
(→)「しろうと」に同じ。
⇒しろと‐すい【素人粋】
ジロドゥー【Jean Giraudoux】
フランスの劇作家・小説家・外交官。精妙な心理性、自在な幻想性、鋭い諷刺性が溶け合った戯曲でフランス現代劇を代表。代表作「トロイ戦争は起こらない」「エレクトル」のほか、小説「シュザンヌと太平洋」など。(1882〜1944)
しろと‐すい【素人粋】
素人しろうとでありながら、粋人ぶる者。半可通。好色一代女1「物に馴れたる客は各別、まだしき―は」
⇒しろ‐と【素人】
しろ‐とり【白鳥】
⇒しらとり
しろ‐どり【城取】
城郭を構え設けること。城構え。甲陽軍鑑3「―、陣取、一切の軍法をよく鍛錬いたす」
しろ‐ナイル【白ナイル】
(White Nile)ナイル川上流部の名称。狭義にはナイル川がスーダン南部のノー湖でガザル川を合わせる地点から、ハルツームで青ナイルと合流するまでをいう。広義にはノー湖から上流のスーダン南端のニムレに至るジェベル川を含める。
しろながす‐くじら【白長須鯨】‥クヂラ
鬚ひげクジラの一種。動物中最大で全長30メートル、体重100トン以上に達する。ナガスクジラに似るが、背鰭せびれが小さく体は青灰色。太平洋・大西洋の北部および南氷洋に分布し、オキアミなどを食う。かつては捕鯨の主目標とされた。
しろ‐なす【白茄子】
果実の色の白いナス。しろなすび。
しろ‐な・す【代為す】
〔他四〕
物品を売って金にかえる。売る。「うりしろなす」とも。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「侍の武具馬具を―・して」
しろ‐なでしこ【白撫子】
①白い花の咲くナデシコ。
②襲かさねの色目。表は白、裏は蘇芳すおう。夏に用いる。
しろ‐なまず【白癜】‥ナマヅ
色素の欠乏によって、白色の斑紋を生じる皮膚病。尋常性白斑。白斑。〈日葡辞書〉
しろ‐なまり【白鉛】
①錫すずの古名。〈倭名類聚鈔11〉
②白鑞しろめの別称。
しろ‐なめし【白鞣】
(「しろなめしがわ」の略)染色しないなめしがわ。
しろ‐なんてん【白南天】
白色の果実を結ぶナンテンの一品種。観賞用・薬用。シロミナンテン。
しろ‐ナンバー【白ナンバー】
(白地のナンバー‐プレートから)自家用自動車の俗称。→白タク
しろ‐ぬき【白抜き】
染色・印刷などで、その部分だけ地色を白く抜いて、模様・文字等を表すこと。また、そのもの。「黒地に―の文字」
しろ‐ぬの【白布】
白色の、さらし布。さらし。
しろ‐ぬめ【白絖】
白色の、つやのある絹布。世間胸算用1「―の足袋はくなど」
しろ‐ぬり【白塗り】
白く塗ること。白く塗ったもの。特に、俳優が顔を白く塗ること。→しらぬり
しろ‐ね【白根】
①シソ科の多年草。各地の湿地に自生。地下茎は多少肥厚して白色、先端は肥厚してチョロギに似る。この部分は食用にすることもある。茎は方形で高さ1メートル内外。夏、茎上・葉腋に白色の小唇形花をつける。
②(女房詞)ねぎ。
③野菜などの茎・根の地中にある白い部分。
⇒しろね‐ぐさ【白根草】
しろね【白根】
新潟県中部の地名。新潟市に属する。信濃川とその分流に囲まれ、低湿地の改良で越後平野の米作中心となる。
しろ‐ねぎ【白葱】
葱の軟化部が白色で長いもの。
しろね‐ぐさ【白根草】
セリの異称。
⇒しろ‐ね【白根】
しろ‐ねずみ【白鼠】
①毛色が白く、眼の赤いネズミの俗な総称。大黒天の使で、そのすむ家は繁昌すると伝え、大黒ねずみともいう。
②㋐ドブネズミの飼養変種。実験用に使われる。ラット。
㋑ハツカネズミの俗称。
③(1が大黒天に仕えたという伝えから)主家に忠実な番頭・雇人。好色一代女4「京の旦那の為に―といはれて」
④染色の名。薄いねずみ色。しろねず。うすねずみ。
しろ‐ねり【白練】
①白い練絹ねりぎぬ。
②白い練羊羹ねりようかん。
しろ‐ネル【白ネル】
白色のフランネル。毛織・綿織・綿毛交織の3種がある。下着類や寝衣に用いる。
しろ‐の【白箆】
⇒しらの
しろ‐のり【城乗り】
敵城に攻め入ること。
しろ‐バイ【白バイ】
(バイはオートバイの略)警察で使用する、白塗りのオートバイ。
しろ‐はえ【白南風】
⇒しらはえ
しろ‐ばえ【白映え】
梅雨つゆのとき、小雨が降りながら時々晴れそうになること。
しろはぜ‐らん【白罅卵】
色素が一方に偏在し、白濁した大きな斑点が見える蚕卵。冷蔵庫からの出し入れの際の温度の激変によって生ずるもので、孵化しない。
しろ‐はた【白旗】
⇒しらはた
しろ‐ば・む【白ばむ】
〔自五〕
白色を帯びる。白く色づく。
しろ‐はら【白腹】
スズメ目ツグミ科の鳥。大きさはツグミほどで、習性も似る。背面は褐色、翼と尾羽は黒褐色、胸以下の下面は白色。ウスリー・アムール・中国東北部で繁殖し、秋、日本に渡来。シナイ。
シロハラ
撮影:小宮輝之
 しろ‐びたい【白額】‥ビタヒ
馬の毛色の名。額の上に白色の小点があるもの。ほしづき。
しろ‐ひと【白人】
⇒しらひと
しろ‐ひとり【白灯蛾】
ヒトリガ科のガ。中形で、開張7〜8センチメートル。全体白色で、腹に赤い点がある。夜、灯火に飛来。幼虫はオオバコなどを食う。
シロヒトリ
撮影:海野和男
しろ‐びたい【白額】‥ビタヒ
馬の毛色の名。額の上に白色の小点があるもの。ほしづき。
しろ‐ひと【白人】
⇒しらひと
しろ‐ひとり【白灯蛾】
ヒトリガ科のガ。中形で、開張7〜8センチメートル。全体白色で、腹に赤い点がある。夜、灯火に飛来。幼虫はオオバコなどを食う。
シロヒトリ
撮影:海野和男
 シロフォン【xylophone】
(→)木琴もっきん。
しろ‐ぶくりん【白覆輪】
(→)銀覆輪ぎんぷくりんに同じ。
しろ‐ふくろう【白梟】‥フクロフ
フクロウ目フクロウ科の鳥。北極圏で繁殖。雄はほぼ全身が白く、雌には褐色の斑紋がある。
しろ‐ぶさ【白房・白総】
相撲で、土俵の屋根の南西隅に垂らす白色の房。秋と白虎びゃっこを表す。→赤房→青房→黒房
しろ‐ふじ【白藤】‥フヂ
白色の花の咲く藤。
しろ‐ぶち【白斑】
白色のぶち。白いまだら。
しろ‐ぶどうしゅ【白葡萄酒】‥ダウ‥
透明に近い淡黄色の葡萄酒。主に緑色葡萄を原料とし、圧搾して果皮および種子を除いた果汁を発酵させてつくる。白ワイン。→赤葡萄酒→ロゼ
しろ‐ぶな【白橅】
ブナの別称。
しろ‐ふね【白船】
中国のジャンク。または小舟。〈日葡辞書〉
しろべえ【四郎兵衛】‥ヱ
(総名主三浦屋が郭内取締りの会所を大門おおもん口に設け、その雇人四郎兵衛を定詰じょうづめとしたことから、その名を世襲)吉原の大門の番所に詰めた見張役の名。転じて、取締りの意。大門四郎兵衛。
しろ‐へび【白蛇】
アオダイショウの白化したもの。山口県岩国市に生息するものは天然記念物に指定。
しろ‐ほ【白保】
石灰などを加えて漉すいた、やや白色を帯びた浅草紙。
しろ‐ぼし【白星】
①中が白い星形または丸形のしるし。
②相撲で、勝を表すしるし。勝ち星。転じて、成功。手柄。「―をあげる」↔黒星
シロホン【xylophone】
(→)木琴もっきん。
しろ‐まい【城米】
城中に貯えた米。
しろ‐まく【白幕】
白地の幕。
しろ‐まだら【白斑】
①白地に斑のあるもの。
②ヘビの一種。全長約60センチメートル。やや褐色を帯びた白地に数十個の横帯がある。夜行性で、人目に触れることは少ない。トカゲ・ヘビを食う。日本の固有種で、本州・四国・九州および周辺の島にすむ。同属のアカマダラは対馬・朝鮮半島・中国に分布。
シロマダラ
提供:東京動物園協会
シロフォン【xylophone】
(→)木琴もっきん。
しろ‐ぶくりん【白覆輪】
(→)銀覆輪ぎんぷくりんに同じ。
しろ‐ふくろう【白梟】‥フクロフ
フクロウ目フクロウ科の鳥。北極圏で繁殖。雄はほぼ全身が白く、雌には褐色の斑紋がある。
しろ‐ぶさ【白房・白総】
相撲で、土俵の屋根の南西隅に垂らす白色の房。秋と白虎びゃっこを表す。→赤房→青房→黒房
しろ‐ふじ【白藤】‥フヂ
白色の花の咲く藤。
しろ‐ぶち【白斑】
白色のぶち。白いまだら。
しろ‐ぶどうしゅ【白葡萄酒】‥ダウ‥
透明に近い淡黄色の葡萄酒。主に緑色葡萄を原料とし、圧搾して果皮および種子を除いた果汁を発酵させてつくる。白ワイン。→赤葡萄酒→ロゼ
しろ‐ぶな【白橅】
ブナの別称。
しろ‐ふね【白船】
中国のジャンク。または小舟。〈日葡辞書〉
しろべえ【四郎兵衛】‥ヱ
(総名主三浦屋が郭内取締りの会所を大門おおもん口に設け、その雇人四郎兵衛を定詰じょうづめとしたことから、その名を世襲)吉原の大門の番所に詰めた見張役の名。転じて、取締りの意。大門四郎兵衛。
しろ‐へび【白蛇】
アオダイショウの白化したもの。山口県岩国市に生息するものは天然記念物に指定。
しろ‐ほ【白保】
石灰などを加えて漉すいた、やや白色を帯びた浅草紙。
しろ‐ぼし【白星】
①中が白い星形または丸形のしるし。
②相撲で、勝を表すしるし。勝ち星。転じて、成功。手柄。「―をあげる」↔黒星
シロホン【xylophone】
(→)木琴もっきん。
しろ‐まい【城米】
城中に貯えた米。
しろ‐まく【白幕】
白地の幕。
しろ‐まだら【白斑】
①白地に斑のあるもの。
②ヘビの一種。全長約60センチメートル。やや褐色を帯びた白地に数十個の横帯がある。夜行性で、人目に触れることは少ない。トカゲ・ヘビを食う。日本の固有種で、本州・四国・九州および周辺の島にすむ。同属のアカマダラは対馬・朝鮮半島・中国に分布。
シロマダラ
提供:東京動物園協会
 しろ‐まなこ【白眼】
白い目玉。しろめ。日葡辞書「シロマナコヲミイダス」
しろ‐み【白身】
①材木の白い部分。しらた。↔赤身。
②魚などの白い肉。「―の魚」↔赤身。
③鶏卵などの卵白らんぱく。↔黄身きみ
しろ‐み【白鑞】
(→)「しろめ」に同じ。日葡辞書「シロミノカガミ」
しろ‐みがき【白磨き】
磨いて白くすること。また、そのもの。
しろ‐みず【白水】‥ミヅ
米をといで白く濁った水。とぎじる。仁勢物語「―のあるところに滑りけり」
しろ‐みそ【白味噌】
黄白色の味噌。米麹こめこうじを多く用い、甘味に富む。京都産が有名。西京味噌など。
しろ‐みつ【白蜜】
砂糖蜜に対して、蜂蜜の称。
しろ‐みて【代満】
田植の終わったこと。田植の終わった祝日・休日。
しろ・む【白む】
[一]〔自四〕
(シラムとも)
①白色を帯びる。白くなる。枕草子51「牛はひたひはいとちひさく、―・みたるが」
②たじろぐ。ためらう。ひるむ。浄瑠璃、出世景清「双方―・みて控へたり」
③にぶくなる。なまる。日葡辞書「カタナノハガシロウダ」
[二]〔他下二〕
白くする。枕草子87「衣も―・めず」。日葡辞書「コメヲシロムル」
しろ・む【窄む】
〔他下二〕
しめる。しぼる。圧縮する。倭名類聚鈔12「擣押、俗語云、之路無」
しろ‐むく【白無垢】
①上着・下着ともに白1色の服装。浄瑠璃、曾根崎「初は―死出立しにでだち」。「―の花嫁衣装」
②白小袖。好色一代男4「下には水鹿子の―」
⇒しろむく‐てっか【白無垢鉄火】
しろむく‐てっか【白無垢鉄火】‥クワ
表面は上品で温厚に見えて、内実は無頼不良な者。羽織ごろつき。
⇒しろ‐むく【白無垢】
しろ‐め【白眼・白目】
眼球の、虹彩と瞳孔とを除いた白い部分。しろまなこ。しろめだま。
⇒白眼で見る
しろ‐め【白鑞・白目】
(ハクロウ・ビャクロウとも)
①鑞接ろうせつ剤の一種。銅と亜鉛との合金で、鉄・アンチモン・ヒ素などを含む。銅合金・ニッケル合金・鋳鉄・鋼製の継手の鑞接に適する。黄銅鑞。
②アンチモンを主成分としヒ素を含む鉱物。合金の中に混ぜて溶融しやすくするのに用い、また銅に混ぜれば灰黒色となり美麗。銅鉱中に含まれて産出し、産地によって伊予白目・堅白目・豊後白目などの名がある。
③錫を主成分とする鉛との合金。鉄・亜鉛・アンチモンなどを少量含む。古くから皿・花瓶・装飾品などに用いた。ピューター。
しろ‐まなこ【白眼】
白い目玉。しろめ。日葡辞書「シロマナコヲミイダス」
しろ‐み【白身】
①材木の白い部分。しらた。↔赤身。
②魚などの白い肉。「―の魚」↔赤身。
③鶏卵などの卵白らんぱく。↔黄身きみ
しろ‐み【白鑞】
(→)「しろめ」に同じ。日葡辞書「シロミノカガミ」
しろ‐みがき【白磨き】
磨いて白くすること。また、そのもの。
しろ‐みず【白水】‥ミヅ
米をといで白く濁った水。とぎじる。仁勢物語「―のあるところに滑りけり」
しろ‐みそ【白味噌】
黄白色の味噌。米麹こめこうじを多く用い、甘味に富む。京都産が有名。西京味噌など。
しろ‐みつ【白蜜】
砂糖蜜に対して、蜂蜜の称。
しろ‐みて【代満】
田植の終わったこと。田植の終わった祝日・休日。
しろ・む【白む】
[一]〔自四〕
(シラムとも)
①白色を帯びる。白くなる。枕草子51「牛はひたひはいとちひさく、―・みたるが」
②たじろぐ。ためらう。ひるむ。浄瑠璃、出世景清「双方―・みて控へたり」
③にぶくなる。なまる。日葡辞書「カタナノハガシロウダ」
[二]〔他下二〕
白くする。枕草子87「衣も―・めず」。日葡辞書「コメヲシロムル」
しろ・む【窄む】
〔他下二〕
しめる。しぼる。圧縮する。倭名類聚鈔12「擣押、俗語云、之路無」
しろ‐むく【白無垢】
①上着・下着ともに白1色の服装。浄瑠璃、曾根崎「初は―死出立しにでだち」。「―の花嫁衣装」
②白小袖。好色一代男4「下には水鹿子の―」
⇒しろむく‐てっか【白無垢鉄火】
しろむく‐てっか【白無垢鉄火】‥クワ
表面は上品で温厚に見えて、内実は無頼不良な者。羽織ごろつき。
⇒しろ‐むく【白無垢】
しろ‐め【白眼・白目】
眼球の、虹彩と瞳孔とを除いた白い部分。しろまなこ。しろめだま。
⇒白眼で見る
しろ‐め【白鑞・白目】
(ハクロウ・ビャクロウとも)
①鑞接ろうせつ剤の一種。銅と亜鉛との合金で、鉄・アンチモン・ヒ素などを含む。銅合金・ニッケル合金・鋳鉄・鋼製の継手の鑞接に適する。黄銅鑞。
②アンチモンを主成分としヒ素を含む鉱物。合金の中に混ぜて溶融しやすくするのに用い、また銅に混ぜれば灰黒色となり美麗。銅鉱中に含まれて産出し、産地によって伊予白目・堅白目・豊後白目などの名がある。
③錫を主成分とする鉛との合金。鉄・亜鉛・アンチモンなどを少量含む。古くから皿・花瓶・装飾品などに用いた。ピューター。
しろ‐まなこ【白眼】🔗⭐🔉
しろ‐まなこ【白眼】
白い目玉。しろめ。日葡辞書「シロマナコヲミイダス」
しろ‐め【白眼・白目】🔗⭐🔉
しろ‐め【白眼・白目】
眼球の、虹彩と瞳孔とを除いた白い部分。しろまなこ。しろめだま。
⇒白眼で見る
○白眼で見るしろめでみる🔗⭐🔉
○白眼で見るしろめでみる
冷やかに見る。
⇒しろ‐め【白眼・白目】
しろ‐もじ【白文字】
クスノキ科の落葉低木。木全体に芳香があり、高さ約3メートル。葉は浅く3裂、雌雄異株。新葉に先だって淡黄色の小花を開く。果実は球形。種子および葉から灯油(白文字油)を採る。
しろ‐もち【白餅】
①米以外のものをまぜないで搗ついた餅。また、餡あんなどをつけてない餅。
②紋所の名。白い円で、中に模様のないもの。
しろ‐もち【城持】
一城をかまえた大名。城持大名。
しろ‐もと【城本】
居城のある所。領国。浄瑠璃、薩摩歌「御―は但馬の国」
しろ‐もの【代物】
①売買する品物。商品。
②品物を売った代金。銭。
③原料。材料。たね。
④ある評価の対象となる人や物。多く、あなどっていう。洒落本、蕩子筌枉解「おろかさは余程の―とみへる」。「困った―だ」「大した―だ」
⑤容貌の美しい女。また、女郎。東海道中膝栗毛2「ここにやア―はなしかの」
⇒しろもの‐がえ【代物替】
しろ‐もの【白物】
(女房詞)
①白酒。
②塩。〈日葡辞書〉
③豆腐。
しろもの‐がえ【代物替】‥ガヘ
①品物と品物とを交換すること。
②江戸時代、長崎で行われた貿易方法の一種。17世紀末〜18世紀初め、幕府の認可のもとに、定額(定められた貿易額)の枠外に行われた、舶載品と銅・海産物などとの物物交換の形態をとる交易。
⇒しろ‐もの【代物】
しろ‐もめん【白木綿】
漂白した紡績糸。また、糸染めなどの加工をせず、すぐに織った木綿織物の総称。
しろ‐やしお【白八入】‥シホ
ツツジの一種。本州と四国の山地のやや高所に生える。高さ3〜6メートル。樹皮は滑らかで斑紋がある。葉は枝先に5枚、輪生。5月頃、枝先に白色漏斗状の花をつけ、直径3〜4センチメートル、花冠は5裂し、上面に緑色の斑点がある。日光の中禅寺湖畔の群落は有名。ごようつつじ。
シロヤシオ(花)
撮影:関戸 勇
 しろ‐やま【城山】
①城を築いた山・丘陵。
②鹿児島市にある丘陵。1877年(明治10)西南戦争の際、西郷隆盛が決戦し、自刃した地。島津氏の鶴丸城跡がある。
しろやま【城山】
姓氏の一つ。
⇒しろやま‐さぶろう【城山三郎】
しろやま‐さぶろう【城山三郎】‥ラウ
小説家。本名、杉浦英一。名古屋市生れ。組織と人間をテーマに多くの経済小説・伝記小説を残す。作「男子の本懐」「落日燃ゆ」「官僚たちの夏」など。(1927〜2007)
城山三郎(2002年)
提供:毎日新聞社
しろ‐やま【城山】
①城を築いた山・丘陵。
②鹿児島市にある丘陵。1877年(明治10)西南戦争の際、西郷隆盛が決戦し、自刃した地。島津氏の鶴丸城跡がある。
しろやま【城山】
姓氏の一つ。
⇒しろやま‐さぶろう【城山三郎】
しろやま‐さぶろう【城山三郎】‥ラウ
小説家。本名、杉浦英一。名古屋市生れ。組織と人間をテーマに多くの経済小説・伝記小説を残す。作「男子の本懐」「落日燃ゆ」「官僚たちの夏」など。(1927〜2007)
城山三郎(2002年)
提供:毎日新聞社
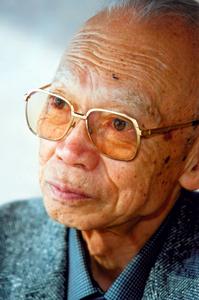 ⇒しろやま【城山】
しろ‐やまぶき【白山吹】
バラ科の小低木。観賞用に栽培。高さ約2メートル。葉は対生し、卵形、下面には絹毛を密生。初夏、枝端に白色のヤマブキに似た花をつけるが、花弁・萼片は各4枚でヤマブキとは別属。
しろ‐ゆもじ【白湯文字】
(上方語。遊女が赤湯文字をつけるのに対していう)素人の淫売婦。しろいもじ。
しろ‐よめな【白嫁菜】
ヤマシロギクの別称。
しろ‐よもぎ【白艾・白蒿】
キク科の多年草。日本北部からシベリアに分布。全株に白色の綿毛を密生し、葉は倒卵形またはへら形で羽状に裂け、花は鐘形で小さく、穂状につく。カワラヨモギ。
じろり
目玉を一回動かして険しい視線を向けるさま。狂言、居杭「こなたのお顔を一目―」。「―とにらむ」
しろ‐ワイン【白ワイン】
(→)白葡萄酒ぶどうしゅに同じ。
しろ‐わけ【代分け】
漁獲物の配当を勘定すること。また、その分配制度。共同で営む漁業では船代・網代・乗り代などに分けた。「―制度」
しろ‐わり【城割り】
城郭を破却すること。織豊期から江戸初期に、大名の居城と番城以外の在地領主の城郭を破却したこと。→一国一城
し‐ろん【史論】
歴史の理論。歴史に関する論説・評論。
し‐ろん【至論】
万人が納得するような、至極もっともな議論。
し‐ろん【私論】
個人的な議論。自分だけの意見。
し‐ろん【詩論】
①詩に関する理論・評論。
②(→)詩学に同じ。
し‐ろん【試論】
①(essayの訳語)自由な形式で書かれた文学的な小論。
②試みにする論。
じ‐ろん【持論】ヂ‥
その人が常に主張している意見・議論。持説。「―をくり返す」
じ‐ろん【時論】
①時事に関する議論。
②その時代・時期の世論。
じろん‐しゅう【地論宗】ヂ‥
6世紀初めに訳された、世親著と伝えられる「十地経論」を研究する中国の仏教学派。中国仏教十三宗の一つ。洛陽に向かう南北二道により北道派と南道派とに分かれ、共に摂論宗しょうろんしゅうに押されて消滅。
ジロンド【Gironde】
フランス西端の県。主都ボルドー。
⇒ジロンド‐とう【ジロンド党】
⇒ジロンド‐は【ジロンド派】
ジロンド‐とう【ジロンド党】‥タウ
(→)ジロンド派に同じ。
⇒ジロンド【Gironde】
ジロンド‐は【ジロンド派】
(Girondins フランス)フランス革命当時の商工業ブルジョアの穏健な共和派の政治団体。指導者のうち3人までがジロンド県の出身だったことからこう呼ぶ。ジャコバン派と対立し、一時は国民公会を支配したが1793年敗退。ジロンド党。
⇒ジロンド【Gironde】
しわ【皺・皴】
①皮膚・紙・布などの表面にこまかい筋目の縮みよったもの。万葉集5「紅の面おもての上にいづくゆか―が来りし」。「―が寄る」「―になる」「―だらけ」
②水面の波紋をたとえていう語。古今和歌集雑体「波の―にやおぼほれむ」
⇒皺伸ぶ
し‐わ【史話】
歴史上の事実・逸話などについての話。史談。
し‐わ【私和】
当事者双方が表沙汰とせず、示談で事をすますこと。和談。内済。
し‐わ【私話】
ひそひそ話。内証話。私語。
し‐わ【詞話】
①中唐頃から起こった長短句の歌曲(詞)についての評論書。
②元・明代の説唱芸術。1967年出土した明の成化(1465〜1487)年間の「説唱詞話十一種」など。
③明代の長編小説で文中に詩・詞を挟んだもの。「金瓶梅詞話」など。
し‐わ【詩話】
詩についての逸話または評論。
じわ
(劇場用語)最高潮の場面やすぐれた演技の際に客席にざわめきがおこること。じわじわ。「―がくる」
しわい【潮合】シハヒ
(シホアヒの約)
⇒しおあい
しわ・い【吝い】
〔形〕[文]しわ・し(ク)
けちである。しみったれだ。日本永代蔵2「生れ付て―・きにあらず」。「―・い奴だ」
じ‐わい【磁歪】
磁場内に置かれた強磁性体が磁場の作用でわずかに伸縮・変形する現象。電気振動と力学的振動との間の電気音響変換に利用する。磁気ひずみ。
しわ‐うで【皺腕】
年老いて皺のよった腕。
しわ‐かぶ【吝株】
けちな性質。また、けちな人。
しわ‐がみ【皺紙】
縮緬ちりめん状の皺をよせた紙。手芸・ナプキン用。ちりめんがみ。クレープ‐ペーパー。
しわ‐が・る【嗄る】シハガル
〔自下二〕
⇒しわがれる(下一)
じ‐わかれ【地分れ】ヂ‥
親類。縁者。
しわがれ‐ごえ【嗄れ声】シハガレゴヱ
しわがれたこえ。しゃがれごえ。塩辛声。
しわ‐が・れる【嗄れる】シハガレル
〔自下一〕[文]しはが・る(下二)
声がかすれたようになる。声がしぶってかれる。しゃがれる。平家物語6「大きなる声の―・れたるをもつて」
し‐わく【思惑】
〔仏〕世間の事物に対しておこす貪とん・瞋じん・痴などの迷い。三道のうち修道しゅどうにおいて断ぜられる。思想的な迷いである見惑に対し、より深い情的な迷いで、対治が困難。修惑。→おもわく
しわく‐しょとう【塩飽諸島】‥タウ
瀬戸内海中部の諸島。大部分は香川県、一部は岡山県に属する。古来瀬戸内水運の要地で、海運業従事者が多い。一部は瀬戸大橋の橋脚島。しあくしょとう。
塩飽諸島
撮影:山梨勝弘
⇒しろやま【城山】
しろ‐やまぶき【白山吹】
バラ科の小低木。観賞用に栽培。高さ約2メートル。葉は対生し、卵形、下面には絹毛を密生。初夏、枝端に白色のヤマブキに似た花をつけるが、花弁・萼片は各4枚でヤマブキとは別属。
しろ‐ゆもじ【白湯文字】
(上方語。遊女が赤湯文字をつけるのに対していう)素人の淫売婦。しろいもじ。
しろ‐よめな【白嫁菜】
ヤマシロギクの別称。
しろ‐よもぎ【白艾・白蒿】
キク科の多年草。日本北部からシベリアに分布。全株に白色の綿毛を密生し、葉は倒卵形またはへら形で羽状に裂け、花は鐘形で小さく、穂状につく。カワラヨモギ。
じろり
目玉を一回動かして険しい視線を向けるさま。狂言、居杭「こなたのお顔を一目―」。「―とにらむ」
しろ‐ワイン【白ワイン】
(→)白葡萄酒ぶどうしゅに同じ。
しろ‐わけ【代分け】
漁獲物の配当を勘定すること。また、その分配制度。共同で営む漁業では船代・網代・乗り代などに分けた。「―制度」
しろ‐わり【城割り】
城郭を破却すること。織豊期から江戸初期に、大名の居城と番城以外の在地領主の城郭を破却したこと。→一国一城
し‐ろん【史論】
歴史の理論。歴史に関する論説・評論。
し‐ろん【至論】
万人が納得するような、至極もっともな議論。
し‐ろん【私論】
個人的な議論。自分だけの意見。
し‐ろん【詩論】
①詩に関する理論・評論。
②(→)詩学に同じ。
し‐ろん【試論】
①(essayの訳語)自由な形式で書かれた文学的な小論。
②試みにする論。
じ‐ろん【持論】ヂ‥
その人が常に主張している意見・議論。持説。「―をくり返す」
じ‐ろん【時論】
①時事に関する議論。
②その時代・時期の世論。
じろん‐しゅう【地論宗】ヂ‥
6世紀初めに訳された、世親著と伝えられる「十地経論」を研究する中国の仏教学派。中国仏教十三宗の一つ。洛陽に向かう南北二道により北道派と南道派とに分かれ、共に摂論宗しょうろんしゅうに押されて消滅。
ジロンド【Gironde】
フランス西端の県。主都ボルドー。
⇒ジロンド‐とう【ジロンド党】
⇒ジロンド‐は【ジロンド派】
ジロンド‐とう【ジロンド党】‥タウ
(→)ジロンド派に同じ。
⇒ジロンド【Gironde】
ジロンド‐は【ジロンド派】
(Girondins フランス)フランス革命当時の商工業ブルジョアの穏健な共和派の政治団体。指導者のうち3人までがジロンド県の出身だったことからこう呼ぶ。ジャコバン派と対立し、一時は国民公会を支配したが1793年敗退。ジロンド党。
⇒ジロンド【Gironde】
しわ【皺・皴】
①皮膚・紙・布などの表面にこまかい筋目の縮みよったもの。万葉集5「紅の面おもての上にいづくゆか―が来りし」。「―が寄る」「―になる」「―だらけ」
②水面の波紋をたとえていう語。古今和歌集雑体「波の―にやおぼほれむ」
⇒皺伸ぶ
し‐わ【史話】
歴史上の事実・逸話などについての話。史談。
し‐わ【私和】
当事者双方が表沙汰とせず、示談で事をすますこと。和談。内済。
し‐わ【私話】
ひそひそ話。内証話。私語。
し‐わ【詞話】
①中唐頃から起こった長短句の歌曲(詞)についての評論書。
②元・明代の説唱芸術。1967年出土した明の成化(1465〜1487)年間の「説唱詞話十一種」など。
③明代の長編小説で文中に詩・詞を挟んだもの。「金瓶梅詞話」など。
し‐わ【詩話】
詩についての逸話または評論。
じわ
(劇場用語)最高潮の場面やすぐれた演技の際に客席にざわめきがおこること。じわじわ。「―がくる」
しわい【潮合】シハヒ
(シホアヒの約)
⇒しおあい
しわ・い【吝い】
〔形〕[文]しわ・し(ク)
けちである。しみったれだ。日本永代蔵2「生れ付て―・きにあらず」。「―・い奴だ」
じ‐わい【磁歪】
磁場内に置かれた強磁性体が磁場の作用でわずかに伸縮・変形する現象。電気振動と力学的振動との間の電気音響変換に利用する。磁気ひずみ。
しわ‐うで【皺腕】
年老いて皺のよった腕。
しわ‐かぶ【吝株】
けちな性質。また、けちな人。
しわ‐がみ【皺紙】
縮緬ちりめん状の皺をよせた紙。手芸・ナプキン用。ちりめんがみ。クレープ‐ペーパー。
しわ‐が・る【嗄る】シハガル
〔自下二〕
⇒しわがれる(下一)
じ‐わかれ【地分れ】ヂ‥
親類。縁者。
しわがれ‐ごえ【嗄れ声】シハガレゴヱ
しわがれたこえ。しゃがれごえ。塩辛声。
しわ‐が・れる【嗄れる】シハガレル
〔自下一〕[文]しはが・る(下二)
声がかすれたようになる。声がしぶってかれる。しゃがれる。平家物語6「大きなる声の―・れたるをもつて」
し‐わく【思惑】
〔仏〕世間の事物に対しておこす貪とん・瞋じん・痴などの迷い。三道のうち修道しゅどうにおいて断ぜられる。思想的な迷いである見惑に対し、より深い情的な迷いで、対治が困難。修惑。→おもわく
しわく‐しょとう【塩飽諸島】‥タウ
瀬戸内海中部の諸島。大部分は香川県、一部は岡山県に属する。古来瀬戸内水運の要地で、海運業従事者が多い。一部は瀬戸大橋の橋脚島。しあくしょとう。
塩飽諸島
撮影:山梨勝弘
 しわ‐くちゃ【皺くちゃ】
ひどくしわの寄っているさま。しわくた。「―なズボン」「紙が―になる」「顔中―にして笑う」
しわ‐ぐ・む【皺組む】
〔自四〕
しわがよる。しわむ。住吉物語「―・み憎さげなる顔して」
し‐わけ【仕分け・仕訳】
①区分すること。分類。類別。「郵便物を―する」
②複式簿記で、取引を借方要素と貸方要素とに分解し、各要素に付すべき勘定科目と金額とを決定し、その結果を仕訳帳などに記入すること。「―を切る」
③税関上屋うわや内などにおいて、貨物を荷主別・到着港別などに分割・類別すること。
⇒しわけ‐ちょう【仕訳帳】
⇒しわけ‐にっきちょう【仕訳日記帳】
じ‐わけ【字分け】
文字の見わけ。日葡辞書「ジワケガミエヌ」
しわけ‐ちょう【仕訳帳】‥チヤウ
複式簿記で、仕訳の結果を記入する帳簿。
⇒し‐わけ【仕分け・仕訳】
しわけ‐にっきちょう【仕訳日記帳】‥チヤウ
簿記で、仕訳帳と日記帳とを兼ねた帳簿。単に仕訳帳または日記帳と呼ばれるものは、これを指す。日記仕訳帳。
⇒し‐わけ【仕分け・仕訳】
し‐わ・ける【仕分ける】
〔他下一〕[文]しわ・く(下二)
それぞれに分ける。区分する。「材料を―・ける」
し‐わざ【為業・仕業】
(シはサ変動詞「す」の連用形)するわざ。また、したわざ。行為。所業。竹取物語「これは竜の―にこそありけれ」。「だれの―だ」
しわ‐し【私窩子】
⇒しかし
しわ‐じょう【志波城】シハジヤウ
蝦夷鎮定のため坂上田村麻呂により803年(延暦22)に築かれた城柵。遺跡は盛岡市の太田方八丁遺跡といわれる。のち徳丹城(岩手県紫波郡矢巾やはば町徳田)に移る。
しわ‐しわ【撓撓】
物のしなうさま。へなへな。浄瑠璃、当麻中将姫「さしもに細き反り橋の上は―たよたよと足の踏みども軽やかに」
しわ‐しわ【皺皺】
しわだらけであるさま。日葡辞書「シワシワト」
じわ‐じわ
①少しずつゆっくりと確実に物事が進行するさま。「―と追いつめる」
②液体が次第にしみ出るさま。「汗が―吹き出る」
③(→)「じわ」に同じ。洒落本、御膳手打翁曾我「いふほどの事が―〈とハ芝居通言、しろうとにて当りおちがくるといふ事〉で」
しわす【師走】シハス
陰暦12月の異称。また、太陽暦の12月にもいう。極月ごくげつ。〈[季]冬〉
⇒しわす‐あぶら【師走油】
⇒しわす‐ぎつね【師走狐】
⇒しわす‐びくに【師走比丘尼】
⇒しわす‐ぼうず【師走坊主】
⇒しわす‐まつり【師走祭】
⇒しわす‐ろうにん【師走浪人】
しわす‐あぶら【師走油】シハス‥
師走に油をこぼすこと。火にたたられるとして、こぼした人に水をあびせる習俗があった。
⇒しわす【師走】
しわす‐ぎつね【師走狐】シハス‥
師走に鳴く狐。その声は冴えて聞こえるという。狂言、末広がり「―のごとくこんこんといふほどはつてござる」
⇒しわす【師走】
しわす‐びくに【師走比丘尼】シハス‥
おちぶれて姿のみすぼらしい比丘尼。
⇒しわす【師走】
しわす‐ぼうず【師走坊主】シハスバウ‥
(盂蘭盆とは異なり、歳末には布施もないところから)おちぶれ、やつれている坊主。また、みすぼらしい者をたとえていう語。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「掴めば跡に―師走浪人」
⇒しわす【師走】
しわす‐まつり【師走祭】シハス‥
(→)「川浸かわびたりの朔日ついたち」に同じ。
⇒しわす【師走】
しわす‐ろうにん【師走浪人】シハスラウ‥
落ちぶれて姿のやつれている浪人。
⇒しわす【師走】
し‐わた・す【為渡す】
〔他四〕
垣などを、長々と作り構える。源氏物語若紫「同じ小柴なれど、うるはしう―・して」
しわ‐だ・つ【皺立つ】
[一]〔自五〕
皺が立つ。皺がよる。
[二]〔他下二〕
⇒しわだてる(下一)
しわ‐だ・てる【皺立てる】
〔他下一〕[文]しわだ・つ(下二)
しわをよせる。「額に―・てる」
しわたろう【吝太郎】‥ラウ
けちな人をののしっていう語。
じわっ‐と
〔副〕
ゆっくりと力が加わるさま。また、液体がにじみ出るさま。「心に―くる」「汗が―出る」
しわ‐のばし【皺伸ばし】
①しわをのばすこと。また、その器具。
②老人が気晴らしをすること。
しわ‐くちゃ【皺くちゃ】
ひどくしわの寄っているさま。しわくた。「―なズボン」「紙が―になる」「顔中―にして笑う」
しわ‐ぐ・む【皺組む】
〔自四〕
しわがよる。しわむ。住吉物語「―・み憎さげなる顔して」
し‐わけ【仕分け・仕訳】
①区分すること。分類。類別。「郵便物を―する」
②複式簿記で、取引を借方要素と貸方要素とに分解し、各要素に付すべき勘定科目と金額とを決定し、その結果を仕訳帳などに記入すること。「―を切る」
③税関上屋うわや内などにおいて、貨物を荷主別・到着港別などに分割・類別すること。
⇒しわけ‐ちょう【仕訳帳】
⇒しわけ‐にっきちょう【仕訳日記帳】
じ‐わけ【字分け】
文字の見わけ。日葡辞書「ジワケガミエヌ」
しわけ‐ちょう【仕訳帳】‥チヤウ
複式簿記で、仕訳の結果を記入する帳簿。
⇒し‐わけ【仕分け・仕訳】
しわけ‐にっきちょう【仕訳日記帳】‥チヤウ
簿記で、仕訳帳と日記帳とを兼ねた帳簿。単に仕訳帳または日記帳と呼ばれるものは、これを指す。日記仕訳帳。
⇒し‐わけ【仕分け・仕訳】
し‐わ・ける【仕分ける】
〔他下一〕[文]しわ・く(下二)
それぞれに分ける。区分する。「材料を―・ける」
し‐わざ【為業・仕業】
(シはサ変動詞「す」の連用形)するわざ。また、したわざ。行為。所業。竹取物語「これは竜の―にこそありけれ」。「だれの―だ」
しわ‐し【私窩子】
⇒しかし
しわ‐じょう【志波城】シハジヤウ
蝦夷鎮定のため坂上田村麻呂により803年(延暦22)に築かれた城柵。遺跡は盛岡市の太田方八丁遺跡といわれる。のち徳丹城(岩手県紫波郡矢巾やはば町徳田)に移る。
しわ‐しわ【撓撓】
物のしなうさま。へなへな。浄瑠璃、当麻中将姫「さしもに細き反り橋の上は―たよたよと足の踏みども軽やかに」
しわ‐しわ【皺皺】
しわだらけであるさま。日葡辞書「シワシワト」
じわ‐じわ
①少しずつゆっくりと確実に物事が進行するさま。「―と追いつめる」
②液体が次第にしみ出るさま。「汗が―吹き出る」
③(→)「じわ」に同じ。洒落本、御膳手打翁曾我「いふほどの事が―〈とハ芝居通言、しろうとにて当りおちがくるといふ事〉で」
しわす【師走】シハス
陰暦12月の異称。また、太陽暦の12月にもいう。極月ごくげつ。〈[季]冬〉
⇒しわす‐あぶら【師走油】
⇒しわす‐ぎつね【師走狐】
⇒しわす‐びくに【師走比丘尼】
⇒しわす‐ぼうず【師走坊主】
⇒しわす‐まつり【師走祭】
⇒しわす‐ろうにん【師走浪人】
しわす‐あぶら【師走油】シハス‥
師走に油をこぼすこと。火にたたられるとして、こぼした人に水をあびせる習俗があった。
⇒しわす【師走】
しわす‐ぎつね【師走狐】シハス‥
師走に鳴く狐。その声は冴えて聞こえるという。狂言、末広がり「―のごとくこんこんといふほどはつてござる」
⇒しわす【師走】
しわす‐びくに【師走比丘尼】シハス‥
おちぶれて姿のみすぼらしい比丘尼。
⇒しわす【師走】
しわす‐ぼうず【師走坊主】シハスバウ‥
(盂蘭盆とは異なり、歳末には布施もないところから)おちぶれ、やつれている坊主。また、みすぼらしい者をたとえていう語。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「掴めば跡に―師走浪人」
⇒しわす【師走】
しわす‐まつり【師走祭】シハス‥
(→)「川浸かわびたりの朔日ついたち」に同じ。
⇒しわす【師走】
しわす‐ろうにん【師走浪人】シハスラウ‥
落ちぶれて姿のやつれている浪人。
⇒しわす【師走】
し‐わた・す【為渡す】
〔他四〕
垣などを、長々と作り構える。源氏物語若紫「同じ小柴なれど、うるはしう―・して」
しわ‐だ・つ【皺立つ】
[一]〔自五〕
皺が立つ。皺がよる。
[二]〔他下二〕
⇒しわだてる(下一)
しわ‐だ・てる【皺立てる】
〔他下一〕[文]しわだ・つ(下二)
しわをよせる。「額に―・てる」
しわたろう【吝太郎】‥ラウ
けちな人をののしっていう語。
じわっ‐と
〔副〕
ゆっくりと力が加わるさま。また、液体がにじみ出るさま。「心に―くる」「汗が―出る」
しわ‐のばし【皺伸ばし】
①しわをのばすこと。また、その器具。
②老人が気晴らしをすること。
 しろ‐やま【城山】
①城を築いた山・丘陵。
②鹿児島市にある丘陵。1877年(明治10)西南戦争の際、西郷隆盛が決戦し、自刃した地。島津氏の鶴丸城跡がある。
しろやま【城山】
姓氏の一つ。
⇒しろやま‐さぶろう【城山三郎】
しろやま‐さぶろう【城山三郎】‥ラウ
小説家。本名、杉浦英一。名古屋市生れ。組織と人間をテーマに多くの経済小説・伝記小説を残す。作「男子の本懐」「落日燃ゆ」「官僚たちの夏」など。(1927〜2007)
城山三郎(2002年)
提供:毎日新聞社
しろ‐やま【城山】
①城を築いた山・丘陵。
②鹿児島市にある丘陵。1877年(明治10)西南戦争の際、西郷隆盛が決戦し、自刃した地。島津氏の鶴丸城跡がある。
しろやま【城山】
姓氏の一つ。
⇒しろやま‐さぶろう【城山三郎】
しろやま‐さぶろう【城山三郎】‥ラウ
小説家。本名、杉浦英一。名古屋市生れ。組織と人間をテーマに多くの経済小説・伝記小説を残す。作「男子の本懐」「落日燃ゆ」「官僚たちの夏」など。(1927〜2007)
城山三郎(2002年)
提供:毎日新聞社
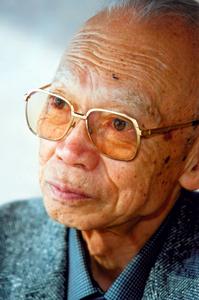 ⇒しろやま【城山】
しろ‐やまぶき【白山吹】
バラ科の小低木。観賞用に栽培。高さ約2メートル。葉は対生し、卵形、下面には絹毛を密生。初夏、枝端に白色のヤマブキに似た花をつけるが、花弁・萼片は各4枚でヤマブキとは別属。
しろ‐ゆもじ【白湯文字】
(上方語。遊女が赤湯文字をつけるのに対していう)素人の淫売婦。しろいもじ。
しろ‐よめな【白嫁菜】
ヤマシロギクの別称。
しろ‐よもぎ【白艾・白蒿】
キク科の多年草。日本北部からシベリアに分布。全株に白色の綿毛を密生し、葉は倒卵形またはへら形で羽状に裂け、花は鐘形で小さく、穂状につく。カワラヨモギ。
じろり
目玉を一回動かして険しい視線を向けるさま。狂言、居杭「こなたのお顔を一目―」。「―とにらむ」
しろ‐ワイン【白ワイン】
(→)白葡萄酒ぶどうしゅに同じ。
しろ‐わけ【代分け】
漁獲物の配当を勘定すること。また、その分配制度。共同で営む漁業では船代・網代・乗り代などに分けた。「―制度」
しろ‐わり【城割り】
城郭を破却すること。織豊期から江戸初期に、大名の居城と番城以外の在地領主の城郭を破却したこと。→一国一城
し‐ろん【史論】
歴史の理論。歴史に関する論説・評論。
し‐ろん【至論】
万人が納得するような、至極もっともな議論。
し‐ろん【私論】
個人的な議論。自分だけの意見。
し‐ろん【詩論】
①詩に関する理論・評論。
②(→)詩学に同じ。
し‐ろん【試論】
①(essayの訳語)自由な形式で書かれた文学的な小論。
②試みにする論。
じ‐ろん【持論】ヂ‥
その人が常に主張している意見・議論。持説。「―をくり返す」
じ‐ろん【時論】
①時事に関する議論。
②その時代・時期の世論。
じろん‐しゅう【地論宗】ヂ‥
6世紀初めに訳された、世親著と伝えられる「十地経論」を研究する中国の仏教学派。中国仏教十三宗の一つ。洛陽に向かう南北二道により北道派と南道派とに分かれ、共に摂論宗しょうろんしゅうに押されて消滅。
ジロンド【Gironde】
フランス西端の県。主都ボルドー。
⇒ジロンド‐とう【ジロンド党】
⇒ジロンド‐は【ジロンド派】
ジロンド‐とう【ジロンド党】‥タウ
(→)ジロンド派に同じ。
⇒ジロンド【Gironde】
ジロンド‐は【ジロンド派】
(Girondins フランス)フランス革命当時の商工業ブルジョアの穏健な共和派の政治団体。指導者のうち3人までがジロンド県の出身だったことからこう呼ぶ。ジャコバン派と対立し、一時は国民公会を支配したが1793年敗退。ジロンド党。
⇒ジロンド【Gironde】
しわ【皺・皴】
①皮膚・紙・布などの表面にこまかい筋目の縮みよったもの。万葉集5「紅の面おもての上にいづくゆか―が来りし」。「―が寄る」「―になる」「―だらけ」
②水面の波紋をたとえていう語。古今和歌集雑体「波の―にやおぼほれむ」
⇒皺伸ぶ
し‐わ【史話】
歴史上の事実・逸話などについての話。史談。
し‐わ【私和】
当事者双方が表沙汰とせず、示談で事をすますこと。和談。内済。
し‐わ【私話】
ひそひそ話。内証話。私語。
し‐わ【詞話】
①中唐頃から起こった長短句の歌曲(詞)についての評論書。
②元・明代の説唱芸術。1967年出土した明の成化(1465〜1487)年間の「説唱詞話十一種」など。
③明代の長編小説で文中に詩・詞を挟んだもの。「金瓶梅詞話」など。
し‐わ【詩話】
詩についての逸話または評論。
じわ
(劇場用語)最高潮の場面やすぐれた演技の際に客席にざわめきがおこること。じわじわ。「―がくる」
しわい【潮合】シハヒ
(シホアヒの約)
⇒しおあい
しわ・い【吝い】
〔形〕[文]しわ・し(ク)
けちである。しみったれだ。日本永代蔵2「生れ付て―・きにあらず」。「―・い奴だ」
じ‐わい【磁歪】
磁場内に置かれた強磁性体が磁場の作用でわずかに伸縮・変形する現象。電気振動と力学的振動との間の電気音響変換に利用する。磁気ひずみ。
しわ‐うで【皺腕】
年老いて皺のよった腕。
しわ‐かぶ【吝株】
けちな性質。また、けちな人。
しわ‐がみ【皺紙】
縮緬ちりめん状の皺をよせた紙。手芸・ナプキン用。ちりめんがみ。クレープ‐ペーパー。
しわ‐が・る【嗄る】シハガル
〔自下二〕
⇒しわがれる(下一)
じ‐わかれ【地分れ】ヂ‥
親類。縁者。
しわがれ‐ごえ【嗄れ声】シハガレゴヱ
しわがれたこえ。しゃがれごえ。塩辛声。
しわ‐が・れる【嗄れる】シハガレル
〔自下一〕[文]しはが・る(下二)
声がかすれたようになる。声がしぶってかれる。しゃがれる。平家物語6「大きなる声の―・れたるをもつて」
し‐わく【思惑】
〔仏〕世間の事物に対しておこす貪とん・瞋じん・痴などの迷い。三道のうち修道しゅどうにおいて断ぜられる。思想的な迷いである見惑に対し、より深い情的な迷いで、対治が困難。修惑。→おもわく
しわく‐しょとう【塩飽諸島】‥タウ
瀬戸内海中部の諸島。大部分は香川県、一部は岡山県に属する。古来瀬戸内水運の要地で、海運業従事者が多い。一部は瀬戸大橋の橋脚島。しあくしょとう。
塩飽諸島
撮影:山梨勝弘
⇒しろやま【城山】
しろ‐やまぶき【白山吹】
バラ科の小低木。観賞用に栽培。高さ約2メートル。葉は対生し、卵形、下面には絹毛を密生。初夏、枝端に白色のヤマブキに似た花をつけるが、花弁・萼片は各4枚でヤマブキとは別属。
しろ‐ゆもじ【白湯文字】
(上方語。遊女が赤湯文字をつけるのに対していう)素人の淫売婦。しろいもじ。
しろ‐よめな【白嫁菜】
ヤマシロギクの別称。
しろ‐よもぎ【白艾・白蒿】
キク科の多年草。日本北部からシベリアに分布。全株に白色の綿毛を密生し、葉は倒卵形またはへら形で羽状に裂け、花は鐘形で小さく、穂状につく。カワラヨモギ。
じろり
目玉を一回動かして険しい視線を向けるさま。狂言、居杭「こなたのお顔を一目―」。「―とにらむ」
しろ‐ワイン【白ワイン】
(→)白葡萄酒ぶどうしゅに同じ。
しろ‐わけ【代分け】
漁獲物の配当を勘定すること。また、その分配制度。共同で営む漁業では船代・網代・乗り代などに分けた。「―制度」
しろ‐わり【城割り】
城郭を破却すること。織豊期から江戸初期に、大名の居城と番城以外の在地領主の城郭を破却したこと。→一国一城
し‐ろん【史論】
歴史の理論。歴史に関する論説・評論。
し‐ろん【至論】
万人が納得するような、至極もっともな議論。
し‐ろん【私論】
個人的な議論。自分だけの意見。
し‐ろん【詩論】
①詩に関する理論・評論。
②(→)詩学に同じ。
し‐ろん【試論】
①(essayの訳語)自由な形式で書かれた文学的な小論。
②試みにする論。
じ‐ろん【持論】ヂ‥
その人が常に主張している意見・議論。持説。「―をくり返す」
じ‐ろん【時論】
①時事に関する議論。
②その時代・時期の世論。
じろん‐しゅう【地論宗】ヂ‥
6世紀初めに訳された、世親著と伝えられる「十地経論」を研究する中国の仏教学派。中国仏教十三宗の一つ。洛陽に向かう南北二道により北道派と南道派とに分かれ、共に摂論宗しょうろんしゅうに押されて消滅。
ジロンド【Gironde】
フランス西端の県。主都ボルドー。
⇒ジロンド‐とう【ジロンド党】
⇒ジロンド‐は【ジロンド派】
ジロンド‐とう【ジロンド党】‥タウ
(→)ジロンド派に同じ。
⇒ジロンド【Gironde】
ジロンド‐は【ジロンド派】
(Girondins フランス)フランス革命当時の商工業ブルジョアの穏健な共和派の政治団体。指導者のうち3人までがジロンド県の出身だったことからこう呼ぶ。ジャコバン派と対立し、一時は国民公会を支配したが1793年敗退。ジロンド党。
⇒ジロンド【Gironde】
しわ【皺・皴】
①皮膚・紙・布などの表面にこまかい筋目の縮みよったもの。万葉集5「紅の面おもての上にいづくゆか―が来りし」。「―が寄る」「―になる」「―だらけ」
②水面の波紋をたとえていう語。古今和歌集雑体「波の―にやおぼほれむ」
⇒皺伸ぶ
し‐わ【史話】
歴史上の事実・逸話などについての話。史談。
し‐わ【私和】
当事者双方が表沙汰とせず、示談で事をすますこと。和談。内済。
し‐わ【私話】
ひそひそ話。内証話。私語。
し‐わ【詞話】
①中唐頃から起こった長短句の歌曲(詞)についての評論書。
②元・明代の説唱芸術。1967年出土した明の成化(1465〜1487)年間の「説唱詞話十一種」など。
③明代の長編小説で文中に詩・詞を挟んだもの。「金瓶梅詞話」など。
し‐わ【詩話】
詩についての逸話または評論。
じわ
(劇場用語)最高潮の場面やすぐれた演技の際に客席にざわめきがおこること。じわじわ。「―がくる」
しわい【潮合】シハヒ
(シホアヒの約)
⇒しおあい
しわ・い【吝い】
〔形〕[文]しわ・し(ク)
けちである。しみったれだ。日本永代蔵2「生れ付て―・きにあらず」。「―・い奴だ」
じ‐わい【磁歪】
磁場内に置かれた強磁性体が磁場の作用でわずかに伸縮・変形する現象。電気振動と力学的振動との間の電気音響変換に利用する。磁気ひずみ。
しわ‐うで【皺腕】
年老いて皺のよった腕。
しわ‐かぶ【吝株】
けちな性質。また、けちな人。
しわ‐がみ【皺紙】
縮緬ちりめん状の皺をよせた紙。手芸・ナプキン用。ちりめんがみ。クレープ‐ペーパー。
しわ‐が・る【嗄る】シハガル
〔自下二〕
⇒しわがれる(下一)
じ‐わかれ【地分れ】ヂ‥
親類。縁者。
しわがれ‐ごえ【嗄れ声】シハガレゴヱ
しわがれたこえ。しゃがれごえ。塩辛声。
しわ‐が・れる【嗄れる】シハガレル
〔自下一〕[文]しはが・る(下二)
声がかすれたようになる。声がしぶってかれる。しゃがれる。平家物語6「大きなる声の―・れたるをもつて」
し‐わく【思惑】
〔仏〕世間の事物に対しておこす貪とん・瞋じん・痴などの迷い。三道のうち修道しゅどうにおいて断ぜられる。思想的な迷いである見惑に対し、より深い情的な迷いで、対治が困難。修惑。→おもわく
しわく‐しょとう【塩飽諸島】‥タウ
瀬戸内海中部の諸島。大部分は香川県、一部は岡山県に属する。古来瀬戸内水運の要地で、海運業従事者が多い。一部は瀬戸大橋の橋脚島。しあくしょとう。
塩飽諸島
撮影:山梨勝弘
 しわ‐くちゃ【皺くちゃ】
ひどくしわの寄っているさま。しわくた。「―なズボン」「紙が―になる」「顔中―にして笑う」
しわ‐ぐ・む【皺組む】
〔自四〕
しわがよる。しわむ。住吉物語「―・み憎さげなる顔して」
し‐わけ【仕分け・仕訳】
①区分すること。分類。類別。「郵便物を―する」
②複式簿記で、取引を借方要素と貸方要素とに分解し、各要素に付すべき勘定科目と金額とを決定し、その結果を仕訳帳などに記入すること。「―を切る」
③税関上屋うわや内などにおいて、貨物を荷主別・到着港別などに分割・類別すること。
⇒しわけ‐ちょう【仕訳帳】
⇒しわけ‐にっきちょう【仕訳日記帳】
じ‐わけ【字分け】
文字の見わけ。日葡辞書「ジワケガミエヌ」
しわけ‐ちょう【仕訳帳】‥チヤウ
複式簿記で、仕訳の結果を記入する帳簿。
⇒し‐わけ【仕分け・仕訳】
しわけ‐にっきちょう【仕訳日記帳】‥チヤウ
簿記で、仕訳帳と日記帳とを兼ねた帳簿。単に仕訳帳または日記帳と呼ばれるものは、これを指す。日記仕訳帳。
⇒し‐わけ【仕分け・仕訳】
し‐わ・ける【仕分ける】
〔他下一〕[文]しわ・く(下二)
それぞれに分ける。区分する。「材料を―・ける」
し‐わざ【為業・仕業】
(シはサ変動詞「す」の連用形)するわざ。また、したわざ。行為。所業。竹取物語「これは竜の―にこそありけれ」。「だれの―だ」
しわ‐し【私窩子】
⇒しかし
しわ‐じょう【志波城】シハジヤウ
蝦夷鎮定のため坂上田村麻呂により803年(延暦22)に築かれた城柵。遺跡は盛岡市の太田方八丁遺跡といわれる。のち徳丹城(岩手県紫波郡矢巾やはば町徳田)に移る。
しわ‐しわ【撓撓】
物のしなうさま。へなへな。浄瑠璃、当麻中将姫「さしもに細き反り橋の上は―たよたよと足の踏みども軽やかに」
しわ‐しわ【皺皺】
しわだらけであるさま。日葡辞書「シワシワト」
じわ‐じわ
①少しずつゆっくりと確実に物事が進行するさま。「―と追いつめる」
②液体が次第にしみ出るさま。「汗が―吹き出る」
③(→)「じわ」に同じ。洒落本、御膳手打翁曾我「いふほどの事が―〈とハ芝居通言、しろうとにて当りおちがくるといふ事〉で」
しわす【師走】シハス
陰暦12月の異称。また、太陽暦の12月にもいう。極月ごくげつ。〈[季]冬〉
⇒しわす‐あぶら【師走油】
⇒しわす‐ぎつね【師走狐】
⇒しわす‐びくに【師走比丘尼】
⇒しわす‐ぼうず【師走坊主】
⇒しわす‐まつり【師走祭】
⇒しわす‐ろうにん【師走浪人】
しわす‐あぶら【師走油】シハス‥
師走に油をこぼすこと。火にたたられるとして、こぼした人に水をあびせる習俗があった。
⇒しわす【師走】
しわす‐ぎつね【師走狐】シハス‥
師走に鳴く狐。その声は冴えて聞こえるという。狂言、末広がり「―のごとくこんこんといふほどはつてござる」
⇒しわす【師走】
しわす‐びくに【師走比丘尼】シハス‥
おちぶれて姿のみすぼらしい比丘尼。
⇒しわす【師走】
しわす‐ぼうず【師走坊主】シハスバウ‥
(盂蘭盆とは異なり、歳末には布施もないところから)おちぶれ、やつれている坊主。また、みすぼらしい者をたとえていう語。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「掴めば跡に―師走浪人」
⇒しわす【師走】
しわす‐まつり【師走祭】シハス‥
(→)「川浸かわびたりの朔日ついたち」に同じ。
⇒しわす【師走】
しわす‐ろうにん【師走浪人】シハスラウ‥
落ちぶれて姿のやつれている浪人。
⇒しわす【師走】
し‐わた・す【為渡す】
〔他四〕
垣などを、長々と作り構える。源氏物語若紫「同じ小柴なれど、うるはしう―・して」
しわ‐だ・つ【皺立つ】
[一]〔自五〕
皺が立つ。皺がよる。
[二]〔他下二〕
⇒しわだてる(下一)
しわ‐だ・てる【皺立てる】
〔他下一〕[文]しわだ・つ(下二)
しわをよせる。「額に―・てる」
しわたろう【吝太郎】‥ラウ
けちな人をののしっていう語。
じわっ‐と
〔副〕
ゆっくりと力が加わるさま。また、液体がにじみ出るさま。「心に―くる」「汗が―出る」
しわ‐のばし【皺伸ばし】
①しわをのばすこと。また、その器具。
②老人が気晴らしをすること。
しわ‐くちゃ【皺くちゃ】
ひどくしわの寄っているさま。しわくた。「―なズボン」「紙が―になる」「顔中―にして笑う」
しわ‐ぐ・む【皺組む】
〔自四〕
しわがよる。しわむ。住吉物語「―・み憎さげなる顔して」
し‐わけ【仕分け・仕訳】
①区分すること。分類。類別。「郵便物を―する」
②複式簿記で、取引を借方要素と貸方要素とに分解し、各要素に付すべき勘定科目と金額とを決定し、その結果を仕訳帳などに記入すること。「―を切る」
③税関上屋うわや内などにおいて、貨物を荷主別・到着港別などに分割・類別すること。
⇒しわけ‐ちょう【仕訳帳】
⇒しわけ‐にっきちょう【仕訳日記帳】
じ‐わけ【字分け】
文字の見わけ。日葡辞書「ジワケガミエヌ」
しわけ‐ちょう【仕訳帳】‥チヤウ
複式簿記で、仕訳の結果を記入する帳簿。
⇒し‐わけ【仕分け・仕訳】
しわけ‐にっきちょう【仕訳日記帳】‥チヤウ
簿記で、仕訳帳と日記帳とを兼ねた帳簿。単に仕訳帳または日記帳と呼ばれるものは、これを指す。日記仕訳帳。
⇒し‐わけ【仕分け・仕訳】
し‐わ・ける【仕分ける】
〔他下一〕[文]しわ・く(下二)
それぞれに分ける。区分する。「材料を―・ける」
し‐わざ【為業・仕業】
(シはサ変動詞「す」の連用形)するわざ。また、したわざ。行為。所業。竹取物語「これは竜の―にこそありけれ」。「だれの―だ」
しわ‐し【私窩子】
⇒しかし
しわ‐じょう【志波城】シハジヤウ
蝦夷鎮定のため坂上田村麻呂により803年(延暦22)に築かれた城柵。遺跡は盛岡市の太田方八丁遺跡といわれる。のち徳丹城(岩手県紫波郡矢巾やはば町徳田)に移る。
しわ‐しわ【撓撓】
物のしなうさま。へなへな。浄瑠璃、当麻中将姫「さしもに細き反り橋の上は―たよたよと足の踏みども軽やかに」
しわ‐しわ【皺皺】
しわだらけであるさま。日葡辞書「シワシワト」
じわ‐じわ
①少しずつゆっくりと確実に物事が進行するさま。「―と追いつめる」
②液体が次第にしみ出るさま。「汗が―吹き出る」
③(→)「じわ」に同じ。洒落本、御膳手打翁曾我「いふほどの事が―〈とハ芝居通言、しろうとにて当りおちがくるといふ事〉で」
しわす【師走】シハス
陰暦12月の異称。また、太陽暦の12月にもいう。極月ごくげつ。〈[季]冬〉
⇒しわす‐あぶら【師走油】
⇒しわす‐ぎつね【師走狐】
⇒しわす‐びくに【師走比丘尼】
⇒しわす‐ぼうず【師走坊主】
⇒しわす‐まつり【師走祭】
⇒しわす‐ろうにん【師走浪人】
しわす‐あぶら【師走油】シハス‥
師走に油をこぼすこと。火にたたられるとして、こぼした人に水をあびせる習俗があった。
⇒しわす【師走】
しわす‐ぎつね【師走狐】シハス‥
師走に鳴く狐。その声は冴えて聞こえるという。狂言、末広がり「―のごとくこんこんといふほどはつてござる」
⇒しわす【師走】
しわす‐びくに【師走比丘尼】シハス‥
おちぶれて姿のみすぼらしい比丘尼。
⇒しわす【師走】
しわす‐ぼうず【師走坊主】シハスバウ‥
(盂蘭盆とは異なり、歳末には布施もないところから)おちぶれ、やつれている坊主。また、みすぼらしい者をたとえていう語。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「掴めば跡に―師走浪人」
⇒しわす【師走】
しわす‐まつり【師走祭】シハス‥
(→)「川浸かわびたりの朔日ついたち」に同じ。
⇒しわす【師走】
しわす‐ろうにん【師走浪人】シハスラウ‥
落ちぶれて姿のやつれている浪人。
⇒しわす【師走】
し‐わた・す【為渡す】
〔他四〕
垣などを、長々と作り構える。源氏物語若紫「同じ小柴なれど、うるはしう―・して」
しわ‐だ・つ【皺立つ】
[一]〔自五〕
皺が立つ。皺がよる。
[二]〔他下二〕
⇒しわだてる(下一)
しわ‐だ・てる【皺立てる】
〔他下一〕[文]しわだ・つ(下二)
しわをよせる。「額に―・てる」
しわたろう【吝太郎】‥ラウ
けちな人をののしっていう語。
じわっ‐と
〔副〕
ゆっくりと力が加わるさま。また、液体がにじみ出るさま。「心に―くる」「汗が―出る」
しわ‐のばし【皺伸ばし】
①しわをのばすこと。また、その器具。
②老人が気晴らしをすること。
はく‐がん【白眼】🔗⭐🔉
はく‐がん【白眼】
①しろめ。
②[晋書阮籍伝](「青白眼」の故事から)しろめ勝ちに人をみる目つき。冷淡な目つき。↔青眼。→青白眼。
⇒はくがん‐し【白眼視】
はくがん‐し【白眼視】🔗⭐🔉
はくがん‐し【白眼視】
人を冷たい眼で見ること。冷淡に扱うこと。「周囲から―される」
⇒はく‐がん【白眼】
広辞苑に「白眼」で始まるの検索結果 1-8。