複数辞典一括検索+![]()
![]()
○車を懸くくるまをかく🔗⭐🔉
○車を懸くくるまをかく
[孝経「七十にして車を懸く」](漢の薛広徳せつこうとくが年老いて退官した時、天子から賜った老人用の車を懸けつるして、光栄の記念とした故事から)年老いて退官する。辞職する。懸車。夫木和歌抄33「数ふれば車を懸くるよはひにてなほこの世にぞめぐりきにける」
⇒くるま【車】
○車を摧くくるまをくだく🔗⭐🔉
○車を摧くくるまをくだく
[白居易、大行路]人心の頼み難いことを、険悪な行路で車の輪がくだけこわれることにたとえていう。夫木和歌抄33「人心憂しともいはじ昔より―道に譬へて」
⇒くるま【車】
○車を捨てるくるまをすてる🔗⭐🔉
○車を捨てるくるまをすてる
①車を降りる。
②(→)「車を懸く」に同じ。
⇒くるま【車】
グルマン【gourmand フランス】
食い道楽。大食家。
くるみ【包み】
①くるむこと。つつむこと。また、そのもの。
②(「くるみ蒲団」の略)幼児用の抱きぶとん。おくるみ。
⇒くるみ‐せいほん【包み製本】
⇒くるみ‐のりいれ【包み糊入れ】
⇒くるみ‐ばり【包み貼り】
⇒くるみ‐びょうし【包み表紙】
⇒くるみ‐ボタン【包みボタン】
くるみ【胡桃・山胡桃】
①クルミ科クルミ属の落葉高木の総称、またその食用果実。欧州産のテウチグルミ(カシグルミ)など北半球に15種ほどが分布。オニグルミは日本の山地に自生し、栽培もされる。幹は高さ20メートル以上、樹皮は褐色を帯びた紫黒色。葉は羽状複葉。雌雄同株で、雄花は緑色、雌花の花柱は帯赤色で6月頃咲く。花後、石果を結び、核は極めて堅い。材は種々の器材に用い、樹皮・果皮は染料、種子は薬用または食用、また、油を搾る。〈[季]秋〉。枕草子154「見るにことなることなきものの文字に書きてことごとしきもの。…―」
テウチグルミ
 ②紋所の名。割ったクルミの実を図案化したもの。
⇒くるみあし‐ぜん【胡桃足膳】
⇒くるみ‐あぶら【胡桃油】
⇒くるみ‐いろ【胡桃色】
⇒くるみ‐か【胡桃科】
⇒くるみ‐どうふ【胡桃豆腐】
⇒くるみ‐もち【胡桃餅】
⇒くるみ‐わり【胡桃割り】
ぐるみ【包み】
〔接尾〕
ある語の下に添えて、「ひっくるめて」「残らず」などの意を表す。ぐるめ。「家族―のつきあい」「身―」
くるみあし‐ぜん【胡桃足膳】
盆の裏の四隅にクルミを二つ割りにして付けて足とした膳。家族用・雇人用として使われた。
胡桃足膳
②紋所の名。割ったクルミの実を図案化したもの。
⇒くるみあし‐ぜん【胡桃足膳】
⇒くるみ‐あぶら【胡桃油】
⇒くるみ‐いろ【胡桃色】
⇒くるみ‐か【胡桃科】
⇒くるみ‐どうふ【胡桃豆腐】
⇒くるみ‐もち【胡桃餅】
⇒くるみ‐わり【胡桃割り】
ぐるみ【包み】
〔接尾〕
ある語の下に添えて、「ひっくるめて」「残らず」などの意を表す。ぐるめ。「家族―のつきあい」「身―」
くるみあし‐ぜん【胡桃足膳】
盆の裏の四隅にクルミを二つ割りにして付けて足とした膳。家族用・雇人用として使われた。
胡桃足膳
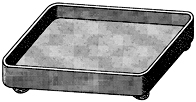 ⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐あぶら【胡桃油】
クルミの実をしぼって製した脂肪油。淡黄色で香味がある。食用・油絵具製造用など。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐いろ【胡桃色】
①クルミの核に似た色。淡い褐色。
Munsell color system: 5YR5.5/6.5
②襲かさねの色目。表は薄香、裏は白。または、表は香色、裏は青。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐か【胡桃科】‥クワ
双子葉植物の一科。北半球の温帯および熱帯アジアに産し、7属約50種、日本には3種がある。ほとんどが大木で複葉、褐色の毛におおわれた大形冬芽が特徴。雌雄同株、雄花は尾状花序をなす。オニグルミ・サワグルミ・カシグルミ、またペカン・ヒッコリーなど。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐せいほん【包み製本】
(→)「くるみ表紙」に同じ。
⇒くるみ【包み】
くるみ‐どうふ【胡桃豆腐】
クルミの実をすりつぶして葛粉と水をまぜ、火にかけて練ったものを箱に流し込み、凝固させて豆腐のように作ったもの。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐のりいれ【包み糊入れ】
書籍の装丁で、くるみ表紙の表と裏との内側に見返しの紙を入れて、その背の部分をくるみ表紙に糊づけすること。
⇒くるみ【包み】
くるみ‐ばり【包み貼り】
衝立ついたてなどを、縁をつけないでもよいように、くるむように貼ること。
⇒くるみ【包み】
くるみ‐びょうし【包み表紙】‥ベウ‥
製本様式の一つ。書籍の中身の表・背・裏を1枚の表紙でくるみ、上下(天地)と一方(小口こぐち)とを化粧裁ちして仕上げるもの。包背ほうはい装。おかしわ。
⇒くるみ【包み】
くるみ‐ボタン【包みボタン】
裏に糸通し穴のある金属製またはプラスチック製の型を芯にして、布・革・編み地などで包んで作ったボタン。
⇒くるみ【包み】
くるみ‐もち【胡桃餅】
①クルミの実をすりつぶし、砂糖・醤油で味をつけ、餅にまぶしたもの。
②クルミの実を糯米もちごめ粉・味噌・白砂糖などとまぜ合わせ、蒸して搗ついた餅。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐もち【くるみ餅】
枝豆をゆでて実をすりつぶし、砂糖で味をつけて餅にまぶしたもの。クルミのかわりに枝豆を用いるからとも、枝豆の餡あんでくるむからともいう。
くるみ‐わり【胡桃割り】
クルミを挟んで殻を割る器具。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみわりにんぎょう【胡桃割人形】‥ギヤウ
チャイコフスキー作曲のバレエ音楽。E.T.A.ホフマンのクリスマス童話「胡桃割人形と鼠の王様」による。1892年初演。後に組曲化。
くる・む【包む】
[一]〔他五〕
包み巻きこむ。つつむ。「足を毛布で―・む」
[二]〔他下二〕
⇒くるめる(下一)
クルム‐ホルン【Krummhorn ドイツ】
〔音〕木製のキャップをかぶせて演奏する2枚リードの管楽器。ルネサンスから初期バロック時代に流行。
くるめ【久留米】
①福岡県南西部、筑後川下流にある市。もと有馬氏21万石の城下町。紡織・ゴム工業で発展。久留米絣がすりの産地。人口30万6千。
②久留米絣・久留米縞じまの略。
⇒くるめ‐がすり【久留米絣】
⇒くるめ‐じま【久留米縞】
⇒くるめ‐つつじ【久留米躑躅】
グルメ【gourmet フランス】
食通。美食家。
ぐるめ【包め】
〔接尾〕
(→)「ぐるみ」に同じ。浄瑠璃、心中天の網島「武士―に小春殿貰うた」
くる‐めか・す【転めかす】
〔他四〕
くるめくようにする。くるくる回す。くるべかす。宇治拾遺物語13「と引きかう引き―・せば」
くるめ‐がすり【久留米絣】
久留米地方から産する木綿の堅牢な紺絣。寛政(1789〜1801)の頃、井上でんの創製。1839年(天保10)大塚太蔵によって絵絣の新技法が、また弘化(1844〜1848)の頃、国武村の牛島乃志によって小絣(国武絣)が考案され、久留米絣の名を高めた。久留米。
⇒くるめ【久留米】
くる‐め・く【眩く】
〔自五〕
(「転めく」とも書く)
①くるくる回る。回転する。くるべく。
②目が回る。めまいがする。徒然草「目―・き枝危きほど」
③せわしく動き回る。あわてさわぐ。古今著聞集20「女俄に病みいでて…―・くことおびただし」
くるめ‐じま【久留米縞】
久留米地方から産する絹糸またはガス糸の縞織物。久留米。
⇒くるめ【久留米】
くるめ‐つつじ【久留米躑躅】
観賞用に広く栽培される小型のツツジ。ミヤマキリシマの園芸品種とされる。品種は非常に多い。
⇒くるめ【久留米】
くる・める【包める】
〔他下一〕[文]くる・む(下二)
①巻き包む。包み巻く。
②一つにくくる。一つにまとめる。「荷物を―・める」
③巧みにあざむく。まるめこむ。「言い―・める」
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐あぶら【胡桃油】
クルミの実をしぼって製した脂肪油。淡黄色で香味がある。食用・油絵具製造用など。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐いろ【胡桃色】
①クルミの核に似た色。淡い褐色。
Munsell color system: 5YR5.5/6.5
②襲かさねの色目。表は薄香、裏は白。または、表は香色、裏は青。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐か【胡桃科】‥クワ
双子葉植物の一科。北半球の温帯および熱帯アジアに産し、7属約50種、日本には3種がある。ほとんどが大木で複葉、褐色の毛におおわれた大形冬芽が特徴。雌雄同株、雄花は尾状花序をなす。オニグルミ・サワグルミ・カシグルミ、またペカン・ヒッコリーなど。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐せいほん【包み製本】
(→)「くるみ表紙」に同じ。
⇒くるみ【包み】
くるみ‐どうふ【胡桃豆腐】
クルミの実をすりつぶして葛粉と水をまぜ、火にかけて練ったものを箱に流し込み、凝固させて豆腐のように作ったもの。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐のりいれ【包み糊入れ】
書籍の装丁で、くるみ表紙の表と裏との内側に見返しの紙を入れて、その背の部分をくるみ表紙に糊づけすること。
⇒くるみ【包み】
くるみ‐ばり【包み貼り】
衝立ついたてなどを、縁をつけないでもよいように、くるむように貼ること。
⇒くるみ【包み】
くるみ‐びょうし【包み表紙】‥ベウ‥
製本様式の一つ。書籍の中身の表・背・裏を1枚の表紙でくるみ、上下(天地)と一方(小口こぐち)とを化粧裁ちして仕上げるもの。包背ほうはい装。おかしわ。
⇒くるみ【包み】
くるみ‐ボタン【包みボタン】
裏に糸通し穴のある金属製またはプラスチック製の型を芯にして、布・革・編み地などで包んで作ったボタン。
⇒くるみ【包み】
くるみ‐もち【胡桃餅】
①クルミの実をすりつぶし、砂糖・醤油で味をつけ、餅にまぶしたもの。
②クルミの実を糯米もちごめ粉・味噌・白砂糖などとまぜ合わせ、蒸して搗ついた餅。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐もち【くるみ餅】
枝豆をゆでて実をすりつぶし、砂糖で味をつけて餅にまぶしたもの。クルミのかわりに枝豆を用いるからとも、枝豆の餡あんでくるむからともいう。
くるみ‐わり【胡桃割り】
クルミを挟んで殻を割る器具。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみわりにんぎょう【胡桃割人形】‥ギヤウ
チャイコフスキー作曲のバレエ音楽。E.T.A.ホフマンのクリスマス童話「胡桃割人形と鼠の王様」による。1892年初演。後に組曲化。
くる・む【包む】
[一]〔他五〕
包み巻きこむ。つつむ。「足を毛布で―・む」
[二]〔他下二〕
⇒くるめる(下一)
クルム‐ホルン【Krummhorn ドイツ】
〔音〕木製のキャップをかぶせて演奏する2枚リードの管楽器。ルネサンスから初期バロック時代に流行。
くるめ【久留米】
①福岡県南西部、筑後川下流にある市。もと有馬氏21万石の城下町。紡織・ゴム工業で発展。久留米絣がすりの産地。人口30万6千。
②久留米絣・久留米縞じまの略。
⇒くるめ‐がすり【久留米絣】
⇒くるめ‐じま【久留米縞】
⇒くるめ‐つつじ【久留米躑躅】
グルメ【gourmet フランス】
食通。美食家。
ぐるめ【包め】
〔接尾〕
(→)「ぐるみ」に同じ。浄瑠璃、心中天の網島「武士―に小春殿貰うた」
くる‐めか・す【転めかす】
〔他四〕
くるめくようにする。くるくる回す。くるべかす。宇治拾遺物語13「と引きかう引き―・せば」
くるめ‐がすり【久留米絣】
久留米地方から産する木綿の堅牢な紺絣。寛政(1789〜1801)の頃、井上でんの創製。1839年(天保10)大塚太蔵によって絵絣の新技法が、また弘化(1844〜1848)の頃、国武村の牛島乃志によって小絣(国武絣)が考案され、久留米絣の名を高めた。久留米。
⇒くるめ【久留米】
くる‐め・く【眩く】
〔自五〕
(「転めく」とも書く)
①くるくる回る。回転する。くるべく。
②目が回る。めまいがする。徒然草「目―・き枝危きほど」
③せわしく動き回る。あわてさわぐ。古今著聞集20「女俄に病みいでて…―・くことおびただし」
くるめ‐じま【久留米縞】
久留米地方から産する絹糸またはガス糸の縞織物。久留米。
⇒くるめ【久留米】
くるめ‐つつじ【久留米躑躅】
観賞用に広く栽培される小型のツツジ。ミヤマキリシマの園芸品種とされる。品種は非常に多い。
⇒くるめ【久留米】
くる・める【包める】
〔他下一〕[文]くる・む(下二)
①巻き包む。包み巻く。
②一つにくくる。一つにまとめる。「荷物を―・める」
③巧みにあざむく。まるめこむ。「言い―・める」
 ②紋所の名。割ったクルミの実を図案化したもの。
⇒くるみあし‐ぜん【胡桃足膳】
⇒くるみ‐あぶら【胡桃油】
⇒くるみ‐いろ【胡桃色】
⇒くるみ‐か【胡桃科】
⇒くるみ‐どうふ【胡桃豆腐】
⇒くるみ‐もち【胡桃餅】
⇒くるみ‐わり【胡桃割り】
ぐるみ【包み】
〔接尾〕
ある語の下に添えて、「ひっくるめて」「残らず」などの意を表す。ぐるめ。「家族―のつきあい」「身―」
くるみあし‐ぜん【胡桃足膳】
盆の裏の四隅にクルミを二つ割りにして付けて足とした膳。家族用・雇人用として使われた。
胡桃足膳
②紋所の名。割ったクルミの実を図案化したもの。
⇒くるみあし‐ぜん【胡桃足膳】
⇒くるみ‐あぶら【胡桃油】
⇒くるみ‐いろ【胡桃色】
⇒くるみ‐か【胡桃科】
⇒くるみ‐どうふ【胡桃豆腐】
⇒くるみ‐もち【胡桃餅】
⇒くるみ‐わり【胡桃割り】
ぐるみ【包み】
〔接尾〕
ある語の下に添えて、「ひっくるめて」「残らず」などの意を表す。ぐるめ。「家族―のつきあい」「身―」
くるみあし‐ぜん【胡桃足膳】
盆の裏の四隅にクルミを二つ割りにして付けて足とした膳。家族用・雇人用として使われた。
胡桃足膳
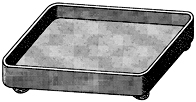 ⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐あぶら【胡桃油】
クルミの実をしぼって製した脂肪油。淡黄色で香味がある。食用・油絵具製造用など。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐いろ【胡桃色】
①クルミの核に似た色。淡い褐色。
Munsell color system: 5YR5.5/6.5
②襲かさねの色目。表は薄香、裏は白。または、表は香色、裏は青。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐か【胡桃科】‥クワ
双子葉植物の一科。北半球の温帯および熱帯アジアに産し、7属約50種、日本には3種がある。ほとんどが大木で複葉、褐色の毛におおわれた大形冬芽が特徴。雌雄同株、雄花は尾状花序をなす。オニグルミ・サワグルミ・カシグルミ、またペカン・ヒッコリーなど。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐せいほん【包み製本】
(→)「くるみ表紙」に同じ。
⇒くるみ【包み】
くるみ‐どうふ【胡桃豆腐】
クルミの実をすりつぶして葛粉と水をまぜ、火にかけて練ったものを箱に流し込み、凝固させて豆腐のように作ったもの。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐のりいれ【包み糊入れ】
書籍の装丁で、くるみ表紙の表と裏との内側に見返しの紙を入れて、その背の部分をくるみ表紙に糊づけすること。
⇒くるみ【包み】
くるみ‐ばり【包み貼り】
衝立ついたてなどを、縁をつけないでもよいように、くるむように貼ること。
⇒くるみ【包み】
くるみ‐びょうし【包み表紙】‥ベウ‥
製本様式の一つ。書籍の中身の表・背・裏を1枚の表紙でくるみ、上下(天地)と一方(小口こぐち)とを化粧裁ちして仕上げるもの。包背ほうはい装。おかしわ。
⇒くるみ【包み】
くるみ‐ボタン【包みボタン】
裏に糸通し穴のある金属製またはプラスチック製の型を芯にして、布・革・編み地などで包んで作ったボタン。
⇒くるみ【包み】
くるみ‐もち【胡桃餅】
①クルミの実をすりつぶし、砂糖・醤油で味をつけ、餅にまぶしたもの。
②クルミの実を糯米もちごめ粉・味噌・白砂糖などとまぜ合わせ、蒸して搗ついた餅。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐もち【くるみ餅】
枝豆をゆでて実をすりつぶし、砂糖で味をつけて餅にまぶしたもの。クルミのかわりに枝豆を用いるからとも、枝豆の餡あんでくるむからともいう。
くるみ‐わり【胡桃割り】
クルミを挟んで殻を割る器具。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみわりにんぎょう【胡桃割人形】‥ギヤウ
チャイコフスキー作曲のバレエ音楽。E.T.A.ホフマンのクリスマス童話「胡桃割人形と鼠の王様」による。1892年初演。後に組曲化。
くる・む【包む】
[一]〔他五〕
包み巻きこむ。つつむ。「足を毛布で―・む」
[二]〔他下二〕
⇒くるめる(下一)
クルム‐ホルン【Krummhorn ドイツ】
〔音〕木製のキャップをかぶせて演奏する2枚リードの管楽器。ルネサンスから初期バロック時代に流行。
くるめ【久留米】
①福岡県南西部、筑後川下流にある市。もと有馬氏21万石の城下町。紡織・ゴム工業で発展。久留米絣がすりの産地。人口30万6千。
②久留米絣・久留米縞じまの略。
⇒くるめ‐がすり【久留米絣】
⇒くるめ‐じま【久留米縞】
⇒くるめ‐つつじ【久留米躑躅】
グルメ【gourmet フランス】
食通。美食家。
ぐるめ【包め】
〔接尾〕
(→)「ぐるみ」に同じ。浄瑠璃、心中天の網島「武士―に小春殿貰うた」
くる‐めか・す【転めかす】
〔他四〕
くるめくようにする。くるくる回す。くるべかす。宇治拾遺物語13「と引きかう引き―・せば」
くるめ‐がすり【久留米絣】
久留米地方から産する木綿の堅牢な紺絣。寛政(1789〜1801)の頃、井上でんの創製。1839年(天保10)大塚太蔵によって絵絣の新技法が、また弘化(1844〜1848)の頃、国武村の牛島乃志によって小絣(国武絣)が考案され、久留米絣の名を高めた。久留米。
⇒くるめ【久留米】
くる‐め・く【眩く】
〔自五〕
(「転めく」とも書く)
①くるくる回る。回転する。くるべく。
②目が回る。めまいがする。徒然草「目―・き枝危きほど」
③せわしく動き回る。あわてさわぐ。古今著聞集20「女俄に病みいでて…―・くことおびただし」
くるめ‐じま【久留米縞】
久留米地方から産する絹糸またはガス糸の縞織物。久留米。
⇒くるめ【久留米】
くるめ‐つつじ【久留米躑躅】
観賞用に広く栽培される小型のツツジ。ミヤマキリシマの園芸品種とされる。品種は非常に多い。
⇒くるめ【久留米】
くる・める【包める】
〔他下一〕[文]くる・む(下二)
①巻き包む。包み巻く。
②一つにくくる。一つにまとめる。「荷物を―・める」
③巧みにあざむく。まるめこむ。「言い―・める」
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐あぶら【胡桃油】
クルミの実をしぼって製した脂肪油。淡黄色で香味がある。食用・油絵具製造用など。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐いろ【胡桃色】
①クルミの核に似た色。淡い褐色。
Munsell color system: 5YR5.5/6.5
②襲かさねの色目。表は薄香、裏は白。または、表は香色、裏は青。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐か【胡桃科】‥クワ
双子葉植物の一科。北半球の温帯および熱帯アジアに産し、7属約50種、日本には3種がある。ほとんどが大木で複葉、褐色の毛におおわれた大形冬芽が特徴。雌雄同株、雄花は尾状花序をなす。オニグルミ・サワグルミ・カシグルミ、またペカン・ヒッコリーなど。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐せいほん【包み製本】
(→)「くるみ表紙」に同じ。
⇒くるみ【包み】
くるみ‐どうふ【胡桃豆腐】
クルミの実をすりつぶして葛粉と水をまぜ、火にかけて練ったものを箱に流し込み、凝固させて豆腐のように作ったもの。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐のりいれ【包み糊入れ】
書籍の装丁で、くるみ表紙の表と裏との内側に見返しの紙を入れて、その背の部分をくるみ表紙に糊づけすること。
⇒くるみ【包み】
くるみ‐ばり【包み貼り】
衝立ついたてなどを、縁をつけないでもよいように、くるむように貼ること。
⇒くるみ【包み】
くるみ‐びょうし【包み表紙】‥ベウ‥
製本様式の一つ。書籍の中身の表・背・裏を1枚の表紙でくるみ、上下(天地)と一方(小口こぐち)とを化粧裁ちして仕上げるもの。包背ほうはい装。おかしわ。
⇒くるみ【包み】
くるみ‐ボタン【包みボタン】
裏に糸通し穴のある金属製またはプラスチック製の型を芯にして、布・革・編み地などで包んで作ったボタン。
⇒くるみ【包み】
くるみ‐もち【胡桃餅】
①クルミの実をすりつぶし、砂糖・醤油で味をつけ、餅にまぶしたもの。
②クルミの実を糯米もちごめ粉・味噌・白砂糖などとまぜ合わせ、蒸して搗ついた餅。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみ‐もち【くるみ餅】
枝豆をゆでて実をすりつぶし、砂糖で味をつけて餅にまぶしたもの。クルミのかわりに枝豆を用いるからとも、枝豆の餡あんでくるむからともいう。
くるみ‐わり【胡桃割り】
クルミを挟んで殻を割る器具。
⇒くるみ【胡桃・山胡桃】
くるみわりにんぎょう【胡桃割人形】‥ギヤウ
チャイコフスキー作曲のバレエ音楽。E.T.A.ホフマンのクリスマス童話「胡桃割人形と鼠の王様」による。1892年初演。後に組曲化。
くる・む【包む】
[一]〔他五〕
包み巻きこむ。つつむ。「足を毛布で―・む」
[二]〔他下二〕
⇒くるめる(下一)
クルム‐ホルン【Krummhorn ドイツ】
〔音〕木製のキャップをかぶせて演奏する2枚リードの管楽器。ルネサンスから初期バロック時代に流行。
くるめ【久留米】
①福岡県南西部、筑後川下流にある市。もと有馬氏21万石の城下町。紡織・ゴム工業で発展。久留米絣がすりの産地。人口30万6千。
②久留米絣・久留米縞じまの略。
⇒くるめ‐がすり【久留米絣】
⇒くるめ‐じま【久留米縞】
⇒くるめ‐つつじ【久留米躑躅】
グルメ【gourmet フランス】
食通。美食家。
ぐるめ【包め】
〔接尾〕
(→)「ぐるみ」に同じ。浄瑠璃、心中天の網島「武士―に小春殿貰うた」
くる‐めか・す【転めかす】
〔他四〕
くるめくようにする。くるくる回す。くるべかす。宇治拾遺物語13「と引きかう引き―・せば」
くるめ‐がすり【久留米絣】
久留米地方から産する木綿の堅牢な紺絣。寛政(1789〜1801)の頃、井上でんの創製。1839年(天保10)大塚太蔵によって絵絣の新技法が、また弘化(1844〜1848)の頃、国武村の牛島乃志によって小絣(国武絣)が考案され、久留米絣の名を高めた。久留米。
⇒くるめ【久留米】
くる‐め・く【眩く】
〔自五〕
(「転めく」とも書く)
①くるくる回る。回転する。くるべく。
②目が回る。めまいがする。徒然草「目―・き枝危きほど」
③せわしく動き回る。あわてさわぐ。古今著聞集20「女俄に病みいでて…―・くことおびただし」
くるめ‐じま【久留米縞】
久留米地方から産する絹糸またはガス糸の縞織物。久留米。
⇒くるめ【久留米】
くるめ‐つつじ【久留米躑躅】
観賞用に広く栽培される小型のツツジ。ミヤマキリシマの園芸品種とされる。品種は非常に多い。
⇒くるめ【久留米】
くる・める【包める】
〔他下一〕[文]くる・む(下二)
①巻き包む。包み巻く。
②一つにくくる。一つにまとめる。「荷物を―・める」
③巧みにあざむく。まるめこむ。「言い―・める」
広辞苑に「車を」で始まるの検索結果 1-3。