複数辞典一括検索+![]()
![]()
きび【黍・稷】🔗⭐🔉
きび【黍・稷】
(キミ(黍)の転)イネ科の一年生作物。インド原産とされ、中国では古くから主要な穀物で五穀の一つ。古く朝鮮を経て渡来したが、現在はほとんど栽培しない。果実は、食用・飼料、また餅菓子・酒などの原料。粳うるちと糯もちとがある。茎は黍稈きびがら細工の材料。〈[季]秋〉。〈類聚名義抄〉
きび


きびがら‐ざいく【黍稈細工】🔗⭐🔉
きびがら‐ざいく【黍稈細工】
色彩を施したキビ・トウモロコシの茎の芯と、細く割いたその皮を材料として、種々の形をつくる手細工。また、その細工品。
きびがら姉さま(鳥取)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 きびがら細工(栃木)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
きびがら細工(栃木)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 きびがら細工(沖縄石垣島)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
きびがら細工(沖縄石垣島)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
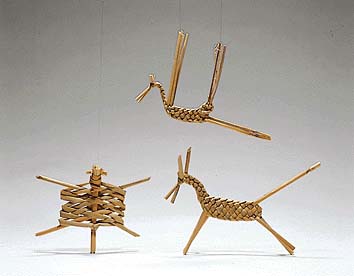 きびがら細工(香川)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
きびがら細工(香川)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)

 きびがら細工(栃木)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
きびがら細工(栃木)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 きびがら細工(沖縄石垣島)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
きびがら細工(沖縄石垣島)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
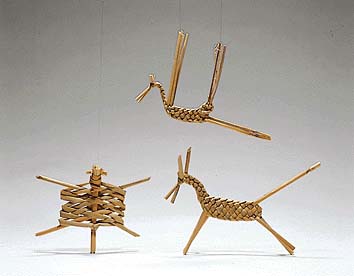 きびがら細工(香川)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
きびがら細工(香川)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きび‐だんご【黍団子】🔗⭐🔉
きび‐だんご【黍団子】
黍の実の粉で製した団子。〈日葡辞書〉
黍団子
撮影:関戸 勇


きび‐なご【黍魚子・吉備奈仔】🔗⭐🔉
きび‐なご【黍魚子・吉備奈仔】
ニシン科の海産硬骨魚。全長約10センチメートル。体は青褐色で、広い銀白色の縦帯がある。南日本産。4〜5月頃の産卵期に波打ちぎわに群集。食用また釣餌・撒餌用。きみなご。
きびなご
 ○驥尾に付すきびにふす
[史記伯夷伝、注]蠅はえが駿馬の尾について千里も遠い地に行くように、後進者がすぐれた先達につき従って、事を成しとげたり功を立てたりすることをいう。蒼蠅そうよう驥尾に付して千里を致す。
⇒き‐び【驥尾】
○驥尾に付すきびにふす
[史記伯夷伝、注]蠅はえが駿馬の尾について千里も遠い地に行くように、後進者がすぐれた先達につき従って、事を成しとげたり功を立てたりすることをいう。蒼蠅そうよう驥尾に付して千里を致す。
⇒き‐び【驥尾】
 ○驥尾に付すきびにふす
[史記伯夷伝、注]蠅はえが駿馬の尾について千里も遠い地に行くように、後進者がすぐれた先達につき従って、事を成しとげたり功を立てたりすることをいう。蒼蠅そうよう驥尾に付して千里を致す。
⇒き‐び【驥尾】
○驥尾に付すきびにふす
[史記伯夷伝、注]蠅はえが駿馬の尾について千里も遠い地に行くように、後進者がすぐれた先達につき従って、事を成しとげたり功を立てたりすることをいう。蒼蠅そうよう驥尾に付して千里を致す。
⇒き‐び【驥尾】
きび‐もち【黍餅】🔗⭐🔉
きび‐もち【黍餅】
黍の実を蒸してついた餅。また、黍の実を糯米もちごめに入れてついた餅。
しょ‐しょく【黍稷】🔗⭐🔉
しょ‐しょく【黍稷】
[書経盤庚上]もちきびとうるちきび。また、きびとあわ。転じて、五穀ごこく。
しょ‐り【黍離】🔗⭐🔉
しょ‐り【黍離】
[詩経王風、黍離]旧都や故郷が荒れはてて、黍きびなどが生い茂ったさびしい光景。世の移り変りを嘆く語。
[漢]黍🔗⭐🔉
黍 字形
 〔黍部0画/12画/2148・3550〕
〔音〕ショ(呉)(漢)
〔訓〕きび
[意味]
五穀の一つ。きび。「黍稷しょしょく・蜀黍しょくしょ・もろこし」
[解字]
会意。「禾」(=いね)+「氺」(=水)。水分を与えて育てる穀物の意。
[難読]
黍魚子きびなご
〔黍部0画/12画/2148・3550〕
〔音〕ショ(呉)(漢)
〔訓〕きび
[意味]
五穀の一つ。きび。「黍稷しょしょく・蜀黍しょくしょ・もろこし」
[解字]
会意。「禾」(=いね)+「氺」(=水)。水分を与えて育てる穀物の意。
[難読]
黍魚子きびなご
 〔黍部0画/12画/2148・3550〕
〔音〕ショ(呉)(漢)
〔訓〕きび
[意味]
五穀の一つ。きび。「黍稷しょしょく・蜀黍しょくしょ・もろこし」
[解字]
会意。「禾」(=いね)+「氺」(=水)。水分を与えて育てる穀物の意。
[難読]
黍魚子きびなご
〔黍部0画/12画/2148・3550〕
〔音〕ショ(呉)(漢)
〔訓〕きび
[意味]
五穀の一つ。きび。「黍稷しょしょく・蜀黍しょくしょ・もろこし」
[解字]
会意。「禾」(=いね)+「氺」(=水)。水分を与えて育てる穀物の意。
[難読]
黍魚子きびなご
広辞苑に「黍」で始まるの検索結果 1-9。