複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (2)
くさ‐ぎ【臭木】🔗⭐🔉
くさ‐ぎ【臭木】
クマツヅラ科の落葉小高木。山野に多く自生し、高さ約3メートル。葉は大きく、広卵形。茎・葉に悪臭がある。夏、赤色の萼がくと白色の花冠とを有する管状5裂の花を開く。果実は碧色、下部に星状に開いた紅紫色の宿存萼があり、古くから染料に使われた。若葉は食用。臭桐くさぎり。くさぎな。漢名、臭牡丹樹・海州常山。〈[季]秋〉。本草和名「恒山、和名久佐岐」
クサギ(花)
提供:ネイチャー・プロダクション
 クサギ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
クサギ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
 ⇒くさぎ‐の‐むし【臭木の虫】
⇒くさぎ‐の‐むし【臭木の虫】
 クサギ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
クサギ(実)
提供:ネイチャー・プロダクション
 ⇒くさぎ‐の‐むし【臭木の虫】
⇒くさぎ‐の‐むし【臭木の虫】
大辞林の検索結果 (3)
くさ-ぎ【臭木】🔗⭐🔉
くさ-ぎ [0] 【臭木】
クマツヅラ科の落葉小高木。山野に多い。高さ約3メートル。全体に臭気がある。葉は大きく広卵形。八月頃,枝頂に白花を多数つける。果実は球形で濃青色,果実の下に赤紫色の萼が星形に残る。果実を染料に,若葉を食用にする。クサギリ。
〔「臭木の花」「臭木の実」は [季]秋〕
臭木
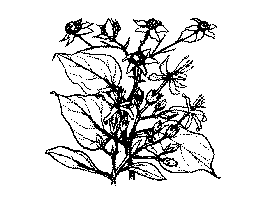 [図]
[図]
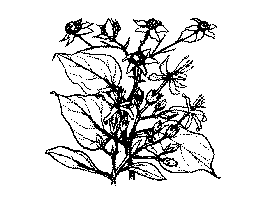 [図]
[図]
くさぎ-かめむし【臭木椿象】🔗⭐🔉
くさぎ-かめむし [5] 【臭木椿象】
カメムシの一種。体長約16ミリメートル。体は黒褐色の地に黄褐色の斑紋がある。サクラ・モモ・クサギなどについて果実から汁を吸う。不快な臭気を発する。九州以北の各地と東アジアに分布。
くさぎ-の-むし【臭木の虫】🔗⭐🔉
くさぎ-の-むし [0] 【臭木の虫】
クサギの幹につくカミキリムシなどの幼虫。子供の疳(カン)の薬とした。
広辞苑+大辞林に「臭木」で始まるの検索結果。