複数辞典一括検索+![]()
![]()
【精衛】🔗⭐🔉
【精衛】
セイエイ 鳥の名。▽海におぼれて死んだ炎帝の娘が、精衛という鳥に化して木や石をくちばしで運び、海を埋めてしまおうとしたという伝説がある。「精衛銜微木、将以填滄海=精衛ハ微サキ木ヲ銜ミテ、マサニモッテ滄海ヲ填メントス」〔→陶潜〕
【精整】🔗⭐🔉
【精整】
セイセイ きちんと整っている。
【精錬】🔗⭐🔉
【精錬】
セイレン  じゅうぶんにきたえてすぐれたものにする。
じゅうぶんにきたえてすぐれたものにする。 〔国〕鉱石などから含有金属をとり出し、混じり物をとり除いて良質の金属にする。
〔国〕鉱石などから含有金属をとり出し、混じり物をとり除いて良質の金属にする。
 じゅうぶんにきたえてすぐれたものにする。
じゅうぶんにきたえてすぐれたものにする。 〔国〕鉱石などから含有金属をとり出し、混じり物をとり除いて良質の金属にする。
〔国〕鉱石などから含有金属をとり出し、混じり物をとり除いて良質の金属にする。
【精鮮】🔗⭐🔉
【精鮮】
セイセン 模様・彩りがひじょうにあざやかで、くっきりとしている。
【精騎】🔗⭐🔉
【精騎】
セイキ えりぬきのすぐれた騎兵。
【精髄】🔗⭐🔉
【精髄】
セイズイ 物事の中心になる、最もすぐれた部分。〈類義語〉真髄・神髄。
【精鑑】🔗⭐🔉
【精鑑】
セイカン 細かく詳しく観察する。また、そのようなすぐれた観察。
【糊】🔗⭐🔉
【糊】
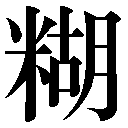 15画 米部
区点=2450 16進=3852 シフトJIS=8CD0
《音読み》 コ
15画 米部
区点=2450 16進=3852 シフトJIS=8CD0
《音読み》 コ /ゴ
/ゴ 〈h
〈h ・h
・h ・h
・h 〉
《訓読み》 のり/のりする(のりす)
《意味》
〉
《訓読み》 のり/のりする(のりす)
《意味》
 {名}書きまちがった所の上にぬりかぶせて、それを消す米の粉。「糊粉ゴフン(白い粉のえのぐ)」「糊塗コト」
{名}書きまちがった所の上にぬりかぶせて、それを消す米の粉。「糊粉ゴフン(白い粉のえのぐ)」「糊塗コト」
 {名}のり。米の粉をといてつくったのり。また、穀物を煮て、のり状になったかゆ。〈同義語〉→餬。〈類義語〉→粥シュク(かゆ)。
{名}のり。米の粉をといてつくったのり。また、穀物を煮て、のり状になったかゆ。〈同義語〉→餬。〈類義語〉→粥シュク(かゆ)。
 {動}のりする(ノリス)。かゆをすする。口すぎとする。〈同義語〉→餬。「糊口=口ヲ糊ス」
{動}のりする(ノリス)。かゆをすする。口すぎとする。〈同義語〉→餬。「糊口=口ヲ糊ス」
 「模糊モコ」とは、胡粉をこすりつけたように、物事の状態がぼんやりとしてあいまいなさま。
《解字》
会意兼形声。胡コは「肉+音符古」の形声文字で、牛の下あごの上にかぶさる垂れた肉。糊は「米+音符胡(かぶせる)」で、誤字の上にかぶせて消す白い粉。
《単語家族》
湖(地上にかぶさる大きなみずうみ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
「模糊モコ」とは、胡粉をこすりつけたように、物事の状態がぼんやりとしてあいまいなさま。
《解字》
会意兼形声。胡コは「肉+音符古」の形声文字で、牛の下あごの上にかぶさる垂れた肉。糊は「米+音符胡(かぶせる)」で、誤字の上にかぶせて消す白い粉。
《単語家族》
湖(地上にかぶさる大きなみずうみ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
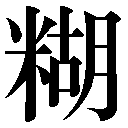 15画 米部
区点=2450 16進=3852 シフトJIS=8CD0
《音読み》 コ
15画 米部
区点=2450 16進=3852 シフトJIS=8CD0
《音読み》 コ /ゴ
/ゴ 〈h
〈h ・h
・h ・h
・h 〉
《訓読み》 のり/のりする(のりす)
《意味》
〉
《訓読み》 のり/のりする(のりす)
《意味》
 {名}書きまちがった所の上にぬりかぶせて、それを消す米の粉。「糊粉ゴフン(白い粉のえのぐ)」「糊塗コト」
{名}書きまちがった所の上にぬりかぶせて、それを消す米の粉。「糊粉ゴフン(白い粉のえのぐ)」「糊塗コト」
 {名}のり。米の粉をといてつくったのり。また、穀物を煮て、のり状になったかゆ。〈同義語〉→餬。〈類義語〉→粥シュク(かゆ)。
{名}のり。米の粉をといてつくったのり。また、穀物を煮て、のり状になったかゆ。〈同義語〉→餬。〈類義語〉→粥シュク(かゆ)。
 {動}のりする(ノリス)。かゆをすする。口すぎとする。〈同義語〉→餬。「糊口=口ヲ糊ス」
{動}のりする(ノリス)。かゆをすする。口すぎとする。〈同義語〉→餬。「糊口=口ヲ糊ス」
 「模糊モコ」とは、胡粉をこすりつけたように、物事の状態がぼんやりとしてあいまいなさま。
《解字》
会意兼形声。胡コは「肉+音符古」の形声文字で、牛の下あごの上にかぶさる垂れた肉。糊は「米+音符胡(かぶせる)」で、誤字の上にかぶせて消す白い粉。
《単語家族》
湖(地上にかぶさる大きなみずうみ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
「模糊モコ」とは、胡粉をこすりつけたように、物事の状態がぼんやりとしてあいまいなさま。
《解字》
会意兼形声。胡コは「肉+音符古」の形声文字で、牛の下あごの上にかぶさる垂れた肉。糊は「米+音符胡(かぶせる)」で、誤字の上にかぶせて消す白い粉。
《単語家族》
湖(地上にかぶさる大きなみずうみ)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
漢字源 ページ 3346。