複数辞典一括検索+![]()
![]()
【量移】🔗⭐🔉
【量移】
リョウイ 唐代、罪のために辺地に左遷された役人が、事情をみはからって近い任地に移されること。
【量検】🔗⭐🔉
【量検】
リョウケン はかって調べる。
【量概】🔗⭐🔉
【量概】
リョウガイ ますに盛った穀物を、ますの縁と平らにならす棒。とかき。ますかき。
【量器】🔗⭐🔉
【量器】
リョウキ  ますなど、物の分量をはかる器具。
ますなど、物の分量をはかる器具。 役にたつすぐれた才能や能力。器量。
役にたつすぐれた才能や能力。器量。
 ますなど、物の分量をはかる器具。
ますなど、物の分量をはかる器具。 役にたつすぐれた才能や能力。器量。
役にたつすぐれた才能や能力。器量。
【釐】🔗⭐🔉
【釐】
 18画 里部
区点=7858 16進=6E5A シフトJIS=E7D8
《音読み》 リ
18画 里部
区点=7858 16進=6E5A シフトJIS=E7D8
《音読み》 リ
 〈l
〈l 〉
《訓読み》 おさめる(をさむ)
《意味》
〉
《訓読み》 おさめる(をさむ)
《意味》
 {動}おさめる(ヲサム)。すじをとおしてきちんとととのえる。すじみちを正す。〈同義語〉→理。「釐改リカイ」「允釐百工=マコトニ百工ヲ釐ム」〔→書経〕
{動}おさめる(ヲサム)。すじをとおしてきちんとととのえる。すじみちを正す。〈同義語〉→理。「釐改リカイ」「允釐百工=マコトニ百工ヲ釐ム」〔→書経〕
 {名}祭りで神に供えたあと、下げた肉。転じて、神から授かる福。
{名}祭りで神に供えたあと、下げた肉。転じて、神から授かる福。
 {単位}割合・長さ・重さ・面積の単位。一釐は、一毫ゴウの十倍で、一分の十分の一。
{単位}割合・長さ・重さ・面積の単位。一釐は、一毫ゴウの十倍で、一分の十分の一。
 {名}やもめ。未亡人。「釐婦リフ」
《解字》
会意兼形声。「すきをもつさま+音符里(すじめをたてて整理した村ざとの畑)」。もと、すきで畑地にきちんとすじめを通すこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}やもめ。未亡人。「釐婦リフ」
《解字》
会意兼形声。「すきをもつさま+音符里(すじめをたてて整理した村ざとの畑)」。もと、すきで畑地にきちんとすじめを通すこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 18画 里部
区点=7858 16進=6E5A シフトJIS=E7D8
《音読み》 リ
18画 里部
区点=7858 16進=6E5A シフトJIS=E7D8
《音読み》 リ
 〈l
〈l 〉
《訓読み》 おさめる(をさむ)
《意味》
〉
《訓読み》 おさめる(をさむ)
《意味》
 {動}おさめる(ヲサム)。すじをとおしてきちんとととのえる。すじみちを正す。〈同義語〉→理。「釐改リカイ」「允釐百工=マコトニ百工ヲ釐ム」〔→書経〕
{動}おさめる(ヲサム)。すじをとおしてきちんとととのえる。すじみちを正す。〈同義語〉→理。「釐改リカイ」「允釐百工=マコトニ百工ヲ釐ム」〔→書経〕
 {名}祭りで神に供えたあと、下げた肉。転じて、神から授かる福。
{名}祭りで神に供えたあと、下げた肉。転じて、神から授かる福。
 {単位}割合・長さ・重さ・面積の単位。一釐は、一毫ゴウの十倍で、一分の十分の一。
{単位}割合・長さ・重さ・面積の単位。一釐は、一毫ゴウの十倍で、一分の十分の一。
 {名}やもめ。未亡人。「釐婦リフ」
《解字》
会意兼形声。「すきをもつさま+音符里(すじめをたてて整理した村ざとの畑)」。もと、すきで畑地にきちんとすじめを通すこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}やもめ。未亡人。「釐婦リフ」
《解字》
会意兼形声。「すきをもつさま+音符里(すじめをたてて整理した村ざとの畑)」。もと、すきで畑地にきちんとすじめを通すこと。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
【釐改】🔗⭐🔉
【釐改】
リカイ きちんとおさめ改める。制度などを改正すること。『釐革リカク』
【釐定】🔗⭐🔉
【釐定】
リテイ すじみちをたてて、制度・方針などを改定すること。
【釐降】🔗⭐🔉
【釐降】
リコウ 天子が、娘を臣下の嫁にやること。降嫁。▽衣装・道具などをおさめととのえて嫁にやるの意。一説に、女の心をおさめて承諾させるの意。
【金】🔗⭐🔉
【金】
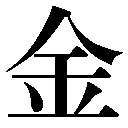 8画 金部 [一年]
区点=2266 16進=3662 シフトJIS=8BE0
《常用音訓》キン/コン/かな/かね
《音読み》 キン(キム)
8画 金部 [一年]
区点=2266 16進=3662 シフトJIS=8BE0
《常用音訓》キン/コン/かな/かね
《音読み》 キン(キム) /コン(コム)
/コン(コム) 〈j
〈j n〉
《訓読み》 かな/かね/こがね/きん
《名付け》 か・かな・かね
《意味》
n〉
《訓読み》 かな/かね/こがね/きん
《名付け》 か・かな・かね
《意味》
 {名}かね。金属の総称。▽殷イン・周代のころには、おもに青銅をいい、春秋時代以後には黄金をさす。「金石文(青銅器や石にほった古代文字)」「五金(金・銀・銅・鉄・錫)」「赤金(あかがね、銅)」「黒金(くろがね、鉄)」
{名}かね。金属の総称。▽殷イン・周代のころには、おもに青銅をいい、春秋時代以後には黄金をさす。「金石文(青銅器や石にほった古代文字)」「五金(金・銀・銅・鉄・錫)」「赤金(あかがね、銅)」「黒金(くろがね、鉄)」
 {名}こがね。黄金。かたいが、のびがよくてさびにくい。「金銀財宝」
{名}こがね。黄金。かたいが、のびがよくてさびにくい。「金銀財宝」
 {名・単位}かね。おかね。金銭。また、貨幣の単位をあらわす。▽漢代には、黄金一斤を、清シン代には、銀一両を一金という。「資金」「漢購我頭千金邑万戸=漢ハ我ガ頭ヲ千金邑万戸ニ購フ」〔→史記〕
{名・単位}かね。おかね。金銭。また、貨幣の単位をあらわす。▽漢代には、黄金一斤を、清シン代には、銀一両を一金という。「資金」「漢購我頭千金邑万戸=漢ハ我ガ頭ヲ千金邑万戸ニ購フ」〔→史記〕
 {名}金属でつくった楽器。鐘や鉦ショウなど。「金石糸竹(いろいろな楽器)」
{名}金属でつくった楽器。鐘や鉦ショウなど。「金石糸竹(いろいろな楽器)」
 {形}こがねいろの。黄いろい。「金波」
{形}こがねいろの。黄いろい。「金波」
 {形}こがねのようにたいせつな。「金言」「金科玉条」
{形}こがねのようにたいせつな。「金言」「金科玉条」
 {形}黄金のようにかたい。「金城鉄壁」
{形}黄金のようにかたい。「金城鉄壁」
 {形}こがねのように美しい。「金殿玉楼」
{形}こがねのように美しい。「金殿玉楼」
 {名}五行の一つ。方角では西、季節では秋、音階では商、星では太白星(金星)、十干ジッカンでは庚コウ・辛シンに当てる。
{名}五行の一つ。方角では西、季節では秋、音階では商、星では太白星(金星)、十干ジッカンでは庚コウ・辛シンに当てる。
 {名}金星のこと。
{名}金星のこと。
 {名}王朝名。女真族の完顔部の阿骨打がたてた。北宋ホクソウと遼リョウを滅ぼして北中国を支配した。十代、一二〇年間で元ゲンに滅ぼされた。一一一五〜一二三四
{名}王朝名。女真族の完顔部の阿骨打がたてた。北宋ホクソウと遼リョウを滅ぼして北中国を支配した。十代、一二〇年間で元ゲンに滅ぼされた。一一一五〜一二三四
 {単位}黄金を含む率を示す単位。「十八金」
〔国〕きん。将棋のこまの一つ。金将。
《解字》
{単位}黄金を含む率を示す単位。「十八金」
〔国〕きん。将棋のこまの一つ。金将。
《解字》
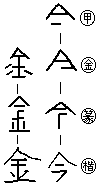 会意兼形声。今は「ふたでおさえるさま+―」から成る会意文字で、何かを含んでおさえたさまを示す。金は「点々のしるし+土+音符今」で、土の中に点々ととじこもって含まれた砂金をあらわす。
《単語家族》
禁キン(おさえてとじこめる)
会意兼形声。今は「ふたでおさえるさま+―」から成る会意文字で、何かを含んでおさえたさまを示す。金は「点々のしるし+土+音符今」で、土の中に点々ととじこもって含まれた砂金をあらわす。
《単語家族》
禁キン(おさえてとじこめる) 含ガン(ふくむ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
含ガン(ふくむ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
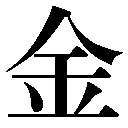 8画 金部 [一年]
区点=2266 16進=3662 シフトJIS=8BE0
《常用音訓》キン/コン/かな/かね
《音読み》 キン(キム)
8画 金部 [一年]
区点=2266 16進=3662 シフトJIS=8BE0
《常用音訓》キン/コン/かな/かね
《音読み》 キン(キム) /コン(コム)
/コン(コム) 〈j
〈j n〉
《訓読み》 かな/かね/こがね/きん
《名付け》 か・かな・かね
《意味》
n〉
《訓読み》 かな/かね/こがね/きん
《名付け》 か・かな・かね
《意味》
 {名}かね。金属の総称。▽殷イン・周代のころには、おもに青銅をいい、春秋時代以後には黄金をさす。「金石文(青銅器や石にほった古代文字)」「五金(金・銀・銅・鉄・錫)」「赤金(あかがね、銅)」「黒金(くろがね、鉄)」
{名}かね。金属の総称。▽殷イン・周代のころには、おもに青銅をいい、春秋時代以後には黄金をさす。「金石文(青銅器や石にほった古代文字)」「五金(金・銀・銅・鉄・錫)」「赤金(あかがね、銅)」「黒金(くろがね、鉄)」
 {名}こがね。黄金。かたいが、のびがよくてさびにくい。「金銀財宝」
{名}こがね。黄金。かたいが、のびがよくてさびにくい。「金銀財宝」
 {名・単位}かね。おかね。金銭。また、貨幣の単位をあらわす。▽漢代には、黄金一斤を、清シン代には、銀一両を一金という。「資金」「漢購我頭千金邑万戸=漢ハ我ガ頭ヲ千金邑万戸ニ購フ」〔→史記〕
{名・単位}かね。おかね。金銭。また、貨幣の単位をあらわす。▽漢代には、黄金一斤を、清シン代には、銀一両を一金という。「資金」「漢購我頭千金邑万戸=漢ハ我ガ頭ヲ千金邑万戸ニ購フ」〔→史記〕
 {名}金属でつくった楽器。鐘や鉦ショウなど。「金石糸竹(いろいろな楽器)」
{名}金属でつくった楽器。鐘や鉦ショウなど。「金石糸竹(いろいろな楽器)」
 {形}こがねいろの。黄いろい。「金波」
{形}こがねいろの。黄いろい。「金波」
 {形}こがねのようにたいせつな。「金言」「金科玉条」
{形}こがねのようにたいせつな。「金言」「金科玉条」
 {形}黄金のようにかたい。「金城鉄壁」
{形}黄金のようにかたい。「金城鉄壁」
 {形}こがねのように美しい。「金殿玉楼」
{形}こがねのように美しい。「金殿玉楼」
 {名}五行の一つ。方角では西、季節では秋、音階では商、星では太白星(金星)、十干ジッカンでは庚コウ・辛シンに当てる。
{名}五行の一つ。方角では西、季節では秋、音階では商、星では太白星(金星)、十干ジッカンでは庚コウ・辛シンに当てる。
 {名}金星のこと。
{名}金星のこと。
 {名}王朝名。女真族の完顔部の阿骨打がたてた。北宋ホクソウと遼リョウを滅ぼして北中国を支配した。十代、一二〇年間で元ゲンに滅ぼされた。一一一五〜一二三四
{名}王朝名。女真族の完顔部の阿骨打がたてた。北宋ホクソウと遼リョウを滅ぼして北中国を支配した。十代、一二〇年間で元ゲンに滅ぼされた。一一一五〜一二三四
 {単位}黄金を含む率を示す単位。「十八金」
〔国〕きん。将棋のこまの一つ。金将。
《解字》
{単位}黄金を含む率を示す単位。「十八金」
〔国〕きん。将棋のこまの一つ。金将。
《解字》
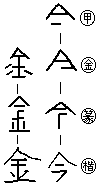 会意兼形声。今は「ふたでおさえるさま+―」から成る会意文字で、何かを含んでおさえたさまを示す。金は「点々のしるし+土+音符今」で、土の中に点々ととじこもって含まれた砂金をあらわす。
《単語家族》
禁キン(おさえてとじこめる)
会意兼形声。今は「ふたでおさえるさま+―」から成る会意文字で、何かを含んでおさえたさまを示す。金は「点々のしるし+土+音符今」で、土の中に点々ととじこもって含まれた砂金をあらわす。
《単語家族》
禁キン(おさえてとじこめる) 含ガン(ふくむ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
含ガン(ふくむ)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
漢字源 ページ 4578。