複数辞典一括検索+![]()
![]()
【鐸】🔗⭐🔉
【鐸】
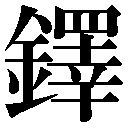 21画 金部
区点=3488 16進=4278 シフトJIS=91F6
【鈬】異体字異体字
21画 金部
区点=3488 16進=4278 シフトJIS=91F6
【鈬】異体字異体字
 12画 金部
区点=7869 16進=6E65 シフトJIS=E7E3
《音読み》 タク
12画 金部
区点=7869 16進=6E65 シフトJIS=E7E3
《音読み》 タク /ダク
/ダク 〈du
〈du 〉
《訓読み》 おおすず(おほすず)
《意味》
〉
《訓読み》 おおすず(おほすず)
《意味》

 {名}おおすず(オホスズ)。振って鳴らす大きなすず。すずの舌が木製のものを木鐸ボクタク、金属製のものを金鐸キンタクといい、昔、政令を発する時、文事には木鐸、武事には金鐸を用いた。
{名}おおすず(オホスズ)。振って鳴らす大きなすず。すずの舌が木製のものを木鐸ボクタク、金属製のものを金鐸キンタクといい、昔、政令を発する時、文事には木鐸、武事には金鐸を用いた。
 {名}軒につるして、その音を楽しむすず。風鈴。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音エキ・タク)は、一定の間をおいて連続する意を含む。鐸はそれを音符とし、金を加えた字で、一定の間をおいて、ちんちんと鳴る金属製のすず。
《熟語》
→下付・中付語
{名}軒につるして、その音を楽しむすず。風鈴。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音エキ・タク)は、一定の間をおいて連続する意を含む。鐸はそれを音符とし、金を加えた字で、一定の間をおいて、ちんちんと鳴る金属製のすず。
《熟語》
→下付・中付語
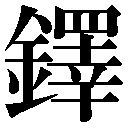 21画 金部
区点=3488 16進=4278 シフトJIS=91F6
【鈬】異体字異体字
21画 金部
区点=3488 16進=4278 シフトJIS=91F6
【鈬】異体字異体字
 12画 金部
区点=7869 16進=6E65 シフトJIS=E7E3
《音読み》 タク
12画 金部
区点=7869 16進=6E65 シフトJIS=E7E3
《音読み》 タク /ダク
/ダク 〈du
〈du 〉
《訓読み》 おおすず(おほすず)
《意味》
〉
《訓読み》 おおすず(おほすず)
《意味》

 {名}おおすず(オホスズ)。振って鳴らす大きなすず。すずの舌が木製のものを木鐸ボクタク、金属製のものを金鐸キンタクといい、昔、政令を発する時、文事には木鐸、武事には金鐸を用いた。
{名}おおすず(オホスズ)。振って鳴らす大きなすず。すずの舌が木製のものを木鐸ボクタク、金属製のものを金鐸キンタクといい、昔、政令を発する時、文事には木鐸、武事には金鐸を用いた。
 {名}軒につるして、その音を楽しむすず。風鈴。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音エキ・タク)は、一定の間をおいて連続する意を含む。鐸はそれを音符とし、金を加えた字で、一定の間をおいて、ちんちんと鳴る金属製のすず。
《熟語》
→下付・中付語
{名}軒につるして、その音を楽しむすず。風鈴。
《解字》
会意兼形声。右側の字(音エキ・タク)は、一定の間をおいて連続する意を含む。鐸はそれを音符とし、金を加えた字で、一定の間をおいて、ちんちんと鳴る金属製のすず。
《熟語》
→下付・中付語
【鐺】🔗⭐🔉
【鐺】
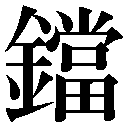 21画 金部
区点=7938 16進=6F46 シフトJIS=E865
《音読み》
21画 金部
区点=7938 16進=6F46 シフトJIS=E865
《音読み》  トウ(タウ)
トウ(タウ)
 〈d
〈d ng〉/
ng〉/ ソウ(サウ)
ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)
/ショウ(シャウ) 〈ch
〈ch ng〉
《訓読み》 こて/こじり
《意味》
ng〉
《訓読み》 こて/こじり
《意味》

 {名}こて。左官が泥をおしあてて壁を塗る道具。〈類義語〉→鏝マン。
{名}こて。左官が泥をおしあてて壁を塗る道具。〈類義語〉→鏝マン。
 {名}とんとんと鳴る鼓の音の形容。
{名}とんとんと鳴る鼓の音の形容。
 {名}火にあてて酒を温めるのに用いる三本あしのなべ。また、平底の浅いなべ。
〔国〕こじり。刀の鞘サヤの末端につける装飾の金具。
《解字》
会意兼形声。「金+音符當(あてる、おしあてる)」。
{名}火にあてて酒を温めるのに用いる三本あしのなべ。また、平底の浅いなべ。
〔国〕こじり。刀の鞘サヤの末端につける装飾の金具。
《解字》
会意兼形声。「金+音符當(あてる、おしあてる)」。
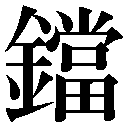 21画 金部
区点=7938 16進=6F46 シフトJIS=E865
《音読み》
21画 金部
区点=7938 16進=6F46 シフトJIS=E865
《音読み》  トウ(タウ)
トウ(タウ)
 〈d
〈d ng〉/
ng〉/ ソウ(サウ)
ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)
/ショウ(シャウ) 〈ch
〈ch ng〉
《訓読み》 こて/こじり
《意味》
ng〉
《訓読み》 こて/こじり
《意味》

 {名}こて。左官が泥をおしあてて壁を塗る道具。〈類義語〉→鏝マン。
{名}こて。左官が泥をおしあてて壁を塗る道具。〈類義語〉→鏝マン。
 {名}とんとんと鳴る鼓の音の形容。
{名}とんとんと鳴る鼓の音の形容。
 {名}火にあてて酒を温めるのに用いる三本あしのなべ。また、平底の浅いなべ。
〔国〕こじり。刀の鞘サヤの末端につける装飾の金具。
《解字》
会意兼形声。「金+音符當(あてる、おしあてる)」。
{名}火にあてて酒を温めるのに用いる三本あしのなべ。また、平底の浅いなべ。
〔国〕こじり。刀の鞘サヤの末端につける装飾の金具。
《解字》
会意兼形声。「金+音符當(あてる、おしあてる)」。
【鑓】🔗⭐🔉
【鑓】
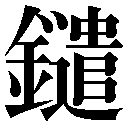 21画 金部 〔国〕
区点=4490 16進=4C7A シフトJIS=96F8
《訓読み》 やり
《意味》
やり。武器の名。長い柄に細長い刃をつけたもの。槍。
《解字》
「金+遣(やるの連用形やり)」からなる日本製の漢字。
21画 金部 〔国〕
区点=4490 16進=4C7A シフトJIS=96F8
《訓読み》 やり
《意味》
やり。武器の名。長い柄に細長い刃をつけたもの。槍。
《解字》
「金+遣(やるの連用形やり)」からなる日本製の漢字。
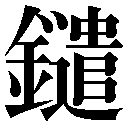 21画 金部 〔国〕
区点=4490 16進=4C7A シフトJIS=96F8
《訓読み》 やり
《意味》
やり。武器の名。長い柄に細長い刃をつけたもの。槍。
《解字》
「金+遣(やるの連用形やり)」からなる日本製の漢字。
21画 金部 〔国〕
区点=4490 16進=4C7A シフトJIS=96F8
《訓読み》 やり
《意味》
やり。武器の名。長い柄に細長い刃をつけたもの。槍。
《解字》
「金+遣(やるの連用形やり)」からなる日本製の漢字。
【鑑】🔗⭐🔉
【鑑】
 23画 金部 [常用漢字]
区点=2053 16進=3455 シフトJIS=8AD3
【鑒】異体字異体字
23画 金部 [常用漢字]
区点=2053 16進=3455 シフトJIS=8AD3
【鑒】異体字異体字
 23画 金部
区点=7940 16進=6F48 シフトJIS=E867
《常用音訓》カン
《音読み》 カン(カム)
23画 金部
区点=7940 16進=6F48 シフトJIS=E867
《常用音訓》カン
《音読み》 カン(カム) /ケン(ケム)
/ケン(ケム) 〈ji
〈ji n〉
《訓読み》 かがみ/かんがみる
《名付け》 あき・あきら・かた・かね・しげ・のり・み・みる
《意味》
n〉
《訓読み》 かがみ/かんがみる
《名付け》 あき・あきら・かた・かね・しげ・のり・み・みる
《意味》
 {名}かがみ。光の反射を利用して物の姿・形などをうつす道具。▽昔は水かがみを用い、盆に水を入れ、上からからだを伏せて顔をうつした。春秋時代からのちは、青銅の面を平らにみがいて姿をうつす。「漢鑑(漢代のかがみ)」「宝鑑(たいせつなかがみ)」
{名}かがみ。光の反射を利用して物の姿・形などをうつす道具。▽昔は水かがみを用い、盆に水を入れ、上からからだを伏せて顔をうつした。春秋時代からのちは、青銅の面を平らにみがいて姿をうつす。「漢鑑(漢代のかがみ)」「宝鑑(たいせつなかがみ)」
 {名}かがみ。姿をうつして見て、自分の戒めとする材料。戒めとなる手本や前例。「亀鑑キカン(物事の規準になる、占いやかがみ→手本)」「鑑戒」「商鑑不遠=商鑑遠カラズ」
{名}かがみ。姿をうつして見て、自分の戒めとする材料。戒めとなる手本や前例。「亀鑑キカン(物事の規準になる、占いやかがみ→手本)」「鑑戒」「商鑑不遠=商鑑遠カラズ」
 {名}かがみ。検討の資料や、手本となる文書。転じて、手形や、人に見せるしるし。
{名}かがみ。検討の資料や、手本となる文書。転じて、手形や、人に見せるしるし。
 {動}かんがみる。かがみにうつす。転じて、前例をみてよしあしを考える。また、よく見て品定めをする。検討する。「鑑別」「鑑定」
{動}かんがみる。かがみにうつす。転じて、前例をみてよしあしを考える。また、よく見て品定めをする。検討する。「鑑別」「鑑定」
 {名}大きな鉢ハチ。水かがみに使えるような盆のこと。
{名}大きな鉢ハチ。水かがみに使えるような盆のこと。
 {動}ごらんいただきたいとの意味をあらわす書簡用語。「台鑑」
《解字》
会意兼形声。監カンは「伏し目+人+皿サラに水を入れたさま」の会意文字で、水かがみの上にからだを伏せて、顔をうつすことをあらわす。のち青銅をみがいたかがみを用いるようになったので、金へんをそえ、鑑の字となった。鑑は「金+音符監」。→監
《単語家族》
監(よしあしを見定める)
{動}ごらんいただきたいとの意味をあらわす書簡用語。「台鑑」
《解字》
会意兼形声。監カンは「伏し目+人+皿サラに水を入れたさま」の会意文字で、水かがみの上にからだを伏せて、顔をうつすことをあらわす。のち青銅をみがいたかがみを用いるようになったので、金へんをそえ、鑑の字となった。鑑は「金+音符監」。→監
《単語家族》
監(よしあしを見定める) 覽ラン(=覧。伏し目で下の物を見る)と縁が近い。
《類義》
→鏡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
覽ラン(=覧。伏し目で下の物を見る)と縁が近い。
《類義》
→鏡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 23画 金部 [常用漢字]
区点=2053 16進=3455 シフトJIS=8AD3
【鑒】異体字異体字
23画 金部 [常用漢字]
区点=2053 16進=3455 シフトJIS=8AD3
【鑒】異体字異体字
 23画 金部
区点=7940 16進=6F48 シフトJIS=E867
《常用音訓》カン
《音読み》 カン(カム)
23画 金部
区点=7940 16進=6F48 シフトJIS=E867
《常用音訓》カン
《音読み》 カン(カム) /ケン(ケム)
/ケン(ケム) 〈ji
〈ji n〉
《訓読み》 かがみ/かんがみる
《名付け》 あき・あきら・かた・かね・しげ・のり・み・みる
《意味》
n〉
《訓読み》 かがみ/かんがみる
《名付け》 あき・あきら・かた・かね・しげ・のり・み・みる
《意味》
 {名}かがみ。光の反射を利用して物の姿・形などをうつす道具。▽昔は水かがみを用い、盆に水を入れ、上からからだを伏せて顔をうつした。春秋時代からのちは、青銅の面を平らにみがいて姿をうつす。「漢鑑(漢代のかがみ)」「宝鑑(たいせつなかがみ)」
{名}かがみ。光の反射を利用して物の姿・形などをうつす道具。▽昔は水かがみを用い、盆に水を入れ、上からからだを伏せて顔をうつした。春秋時代からのちは、青銅の面を平らにみがいて姿をうつす。「漢鑑(漢代のかがみ)」「宝鑑(たいせつなかがみ)」
 {名}かがみ。姿をうつして見て、自分の戒めとする材料。戒めとなる手本や前例。「亀鑑キカン(物事の規準になる、占いやかがみ→手本)」「鑑戒」「商鑑不遠=商鑑遠カラズ」
{名}かがみ。姿をうつして見て、自分の戒めとする材料。戒めとなる手本や前例。「亀鑑キカン(物事の規準になる、占いやかがみ→手本)」「鑑戒」「商鑑不遠=商鑑遠カラズ」
 {名}かがみ。検討の資料や、手本となる文書。転じて、手形や、人に見せるしるし。
{名}かがみ。検討の資料や、手本となる文書。転じて、手形や、人に見せるしるし。
 {動}かんがみる。かがみにうつす。転じて、前例をみてよしあしを考える。また、よく見て品定めをする。検討する。「鑑別」「鑑定」
{動}かんがみる。かがみにうつす。転じて、前例をみてよしあしを考える。また、よく見て品定めをする。検討する。「鑑別」「鑑定」
 {名}大きな鉢ハチ。水かがみに使えるような盆のこと。
{名}大きな鉢ハチ。水かがみに使えるような盆のこと。
 {動}ごらんいただきたいとの意味をあらわす書簡用語。「台鑑」
《解字》
会意兼形声。監カンは「伏し目+人+皿サラに水を入れたさま」の会意文字で、水かがみの上にからだを伏せて、顔をうつすことをあらわす。のち青銅をみがいたかがみを用いるようになったので、金へんをそえ、鑑の字となった。鑑は「金+音符監」。→監
《単語家族》
監(よしあしを見定める)
{動}ごらんいただきたいとの意味をあらわす書簡用語。「台鑑」
《解字》
会意兼形声。監カンは「伏し目+人+皿サラに水を入れたさま」の会意文字で、水かがみの上にからだを伏せて、顔をうつすことをあらわす。のち青銅をみがいたかがみを用いるようになったので、金へんをそえ、鑑の字となった。鑑は「金+音符監」。→監
《単語家族》
監(よしあしを見定める) 覽ラン(=覧。伏し目で下の物を見る)と縁が近い。
《類義》
→鏡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
覽ラン(=覧。伏し目で下の物を見る)と縁が近い。
《類義》
→鏡
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
漢字源 ページ 4662。