複数辞典一括検索+![]()
![]()
み🔗⭐🔉
み
(1)五十音図マ行第二段の仮名。両唇鼻音の有声子音と前舌の狭母音とから成る音節。
(2)平仮名「み」は「美」の草体。片仮名「ミ」は「三」の全画。
〔奈良時代までは,上代特殊仮名遣いで甲乙二類の別があり,発音上区別があったとされる〕
み【三】🔗⭐🔉
み [1] 【三】
みっつ。さん。物を数えるときなどに用いる。「ひ,ふ,―,よ」
み【巳】🔗⭐🔉
み [0] 【巳】
(1)十二支の第六。年・日・時刻・方位などに当てる。へび。
(2)時刻の名。今の午前一〇時頃。また,午前九時から午前一一時の間。または午前一〇時から午前一二時まで。
(3)方角の名。南から東へ三〇度。
み【水】🔗⭐🔉
み 【水】
みず。「汀(ミギワ)」「源(ミナモト)」「垂水(タルミ)」など他の語と複合した形でみられる。
み【曲・回】🔗⭐🔉
み 【曲・回】
〔動詞「みる(廻)」の連用形から〕
山・川・海岸線などの折れ曲がった所。他の語と複合して用いられる。「浦み」「里み」など。「石見(イワミ)の海角の浦―を/万葉 131」
み【見】🔗⭐🔉
み 【見】
(1)見ること。他の語と複合して用いる。「花―」「月―」
(2)ながめ。「山見れば―のともしく川見れば―のさやけく/万葉 4360」
み【身】🔗⭐🔉
み [0] 【身】
■一■ (名)
〔「み(実)」と同源〕
 生きている人のからだ,またその主体としての自分。
(1)身体。からだ。「―をよじって笑う」
(2)我が身。自分自身。「信仰に―をささげる」「危険が―に迫る」「―みづから煙草をつめて/当世書生気質(逍遥)」
生きている人のからだ,またその主体としての自分。
(1)身体。からだ。「―をよじって笑う」
(2)我が身。自分自身。「信仰に―をささげる」「危険が―に迫る」「―みづから煙草をつめて/当世書生気質(逍遥)」
 社会的存在としての自分のありようをいう語。
(1)地位。身分。分際。「流浪の―となる」「―のほどを知れ」
(2)立場。「私の―にもなって下さい」
(3)身持ち。「―が修まらない」
社会的存在としての自分のありようをいう語。
(1)地位。身分。分際。「流浪の―となる」「―のほどを知れ」
(2)立場。「私の―にもなって下さい」
(3)身持ち。「―が修まらない」
 あるものの本体部分。付属部分や表面部分に対していう。
(1)(皮・骨に対して)肉。「―だけ食べる」「白―の魚」
(2)ふたのある器物で物を入れる本体の部分。「―とふたとが合わない」
(3)(鞘(サヤ)や柄(エ)に対して)刀や鋸(ノコギリ)の,刃を持つ金属部分。「―が鞘に入らない」
(4)木の皮の下の,材の部分。
(5)衣服の袖・襟などを除いた,胴体をおおう部分。
■二■ (代)
(1)一人称。男子がやや優越感をもって自分をさしていう。中世・近世の語。「―が家は三条東洞院に有りしなり/正徹物語」
(2)(接頭語「お」「おん」を冠して,「おみ」「おんみ」の形で)二人称。相手をさしていう。
→おみ(代)
→おんみ(代)
あるものの本体部分。付属部分や表面部分に対していう。
(1)(皮・骨に対して)肉。「―だけ食べる」「白―の魚」
(2)ふたのある器物で物を入れる本体の部分。「―とふたとが合わない」
(3)(鞘(サヤ)や柄(エ)に対して)刀や鋸(ノコギリ)の,刃を持つ金属部分。「―が鞘に入らない」
(4)木の皮の下の,材の部分。
(5)衣服の袖・襟などを除いた,胴体をおおう部分。
■二■ (代)
(1)一人称。男子がやや優越感をもって自分をさしていう。中世・近世の語。「―が家は三条東洞院に有りしなり/正徹物語」
(2)(接頭語「お」「おん」を冠して,「おみ」「おんみ」の形で)二人称。相手をさしていう。
→おみ(代)
→おんみ(代)
 生きている人のからだ,またその主体としての自分。
(1)身体。からだ。「―をよじって笑う」
(2)我が身。自分自身。「信仰に―をささげる」「危険が―に迫る」「―みづから煙草をつめて/当世書生気質(逍遥)」
生きている人のからだ,またその主体としての自分。
(1)身体。からだ。「―をよじって笑う」
(2)我が身。自分自身。「信仰に―をささげる」「危険が―に迫る」「―みづから煙草をつめて/当世書生気質(逍遥)」
 社会的存在としての自分のありようをいう語。
(1)地位。身分。分際。「流浪の―となる」「―のほどを知れ」
(2)立場。「私の―にもなって下さい」
(3)身持ち。「―が修まらない」
社会的存在としての自分のありようをいう語。
(1)地位。身分。分際。「流浪の―となる」「―のほどを知れ」
(2)立場。「私の―にもなって下さい」
(3)身持ち。「―が修まらない」
 あるものの本体部分。付属部分や表面部分に対していう。
(1)(皮・骨に対して)肉。「―だけ食べる」「白―の魚」
(2)ふたのある器物で物を入れる本体の部分。「―とふたとが合わない」
(3)(鞘(サヤ)や柄(エ)に対して)刀や鋸(ノコギリ)の,刃を持つ金属部分。「―が鞘に入らない」
(4)木の皮の下の,材の部分。
(5)衣服の袖・襟などを除いた,胴体をおおう部分。
■二■ (代)
(1)一人称。男子がやや優越感をもって自分をさしていう。中世・近世の語。「―が家は三条東洞院に有りしなり/正徹物語」
(2)(接頭語「お」「おん」を冠して,「おみ」「おんみ」の形で)二人称。相手をさしていう。
→おみ(代)
→おんみ(代)
あるものの本体部分。付属部分や表面部分に対していう。
(1)(皮・骨に対して)肉。「―だけ食べる」「白―の魚」
(2)ふたのある器物で物を入れる本体の部分。「―とふたとが合わない」
(3)(鞘(サヤ)や柄(エ)に対して)刀や鋸(ノコギリ)の,刃を持つ金属部分。「―が鞘に入らない」
(4)木の皮の下の,材の部分。
(5)衣服の袖・襟などを除いた,胴体をおおう部分。
■二■ (代)
(1)一人称。男子がやや優越感をもって自分をさしていう。中世・近世の語。「―が家は三条東洞院に有りしなり/正徹物語」
(2)(接頭語「お」「おん」を冠して,「おみ」「おんみ」の形で)二人称。相手をさしていう。
→おみ(代)
→おんみ(代)
み【実・子】🔗⭐🔉
み [0] 【実・子】
〔「み(身)」と同源〕
(1)植物の果実。「―がなる」
(2)植物の種子。「草の―」
(3)汁の中に入れる野菜や肉など。「みそ汁の―」
(4)中身。内容。「―のある話」
み【海】🔗⭐🔉
み 【海】
〔「うみ」の「う」が脱落した形〕
うみ。「淡海(オウミ)の―瀬田のわたりに潜(カズ)く鳥/日本書紀(神功)」
み【神・霊】🔗⭐🔉
み 【神・霊】
霊的な力をもつものの意。「山祇(ヤマツミ)」「海神(ワタツミ)」など他の語と複合して用いられる。「やまつ―の奉る御調(ミツギ)と/万葉 38」
み【箕】🔗⭐🔉
み [1] 【箕】
穀類をあおってふるい,殻・ごみを除く農具。
箕
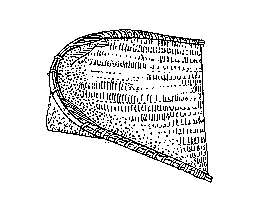 [図]
[図]
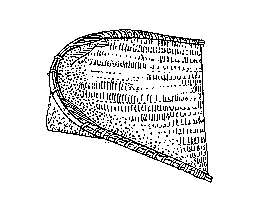 [図]
[図]
み【未】🔗⭐🔉
み 【未】
接頭語的に用いて,まだ…していない,まだ…でない意を添える。「―成年」「―開発」「―完成」「―処理」「―解決」「―確認」
み【味】🔗⭐🔉
み 【味】
■一■ (名)
あじ。味覚。
■二■ (接尾)
助数詞。飲食物や薬品などの種類を数えるのに用いる。「五―」
ミ (イタリア) mi
(イタリア) mi 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ミ [1]  (イタリア) mi
(イタリア) mi (1)洋楽の階名の一。長音階の第三度,短音階の第五度の音。
(2)ホ( E )音のイタリア音名。
(1)洋楽の階名の一。長音階の第三度,短音階の第五度の音。
(2)ホ( E )音のイタリア音名。
 (イタリア) mi
(イタリア) mi (1)洋楽の階名の一。長音階の第三度,短音階の第五度の音。
(2)ホ( E )音のイタリア音名。
(1)洋楽の階名の一。長音階の第三度,短音階の第五度の音。
(2)ホ( E )音のイタリア音名。
み【御】🔗⭐🔉
み 【御】 (接頭)
〔本来は神など霊威のあるものに対する畏敬の念を表した〕
(1)主として和語の名詞に付いて,それが神仏・天皇・貴人など,尊敬すべき人に属するものであることを示し,敬意を添える。お。「神の―心」「―子」「―姿」
(2)(多く「深」と書く)主として和語の名詞や地名に付けて,美しいとほめたたえたり,語調を整えたりするのに用いられる。「―山」「―雪」「―草」「―吉野」
み🔗⭐🔉
み (接尾)
形容詞・形容動詞の語幹に付いて名詞を作る。
(1)そういう性質・状態,またそういう感じを表す。「暖か―」「厚―」「おもしろ―」「新鮮―」
〔「味」を当てることがある。接続する語が「さ」より少なく,対象の性質・状態・程度を主観的・感覚的にとらえる〕
(2)そういう状態をしている場所をいう。「深―にはまる」「弱―」「茂―」
み🔗⭐🔉
み (接尾)
意味上対立する二つの動詞の連用形や,動詞とその動詞に「ず」の付いた形に接して,動作・状態が交互に現れる意を表す。…たり…たり。「照り―曇り―」「降り―降らず―」
み🔗⭐🔉
み (接尾)
〔上代語〕
形容詞および形容詞型助動詞の語幹に付く。
(1)原因や理由を表す。…が…なので。…が…から。「我妹子(ワギモコ)をいざみの山を高―かも大和の見えぬ国遠―かも/万葉 44」
(2)中止法として,叙述の並列に用いる。「山高―川とほしろし/万葉 324」
(3)「思ふ」や「す」を伴って,思考・感情の内容を示す。「我妹子を相知らしめし人をこそ恋のまされば恨めし―思へ/万葉 494」
〔中古以降は和歌だけに用いられた〕
み【身】(和英)🔗⭐🔉
み【身】
the body (身体);→英和
oneself (自分);→英和
a blade (刀身).→英和
〜にしみてdeeply;→英和
heartily.〜につまされる deeply sympathize;feel deeply.(技術を)〜につける acquire skill.〜に余る光栄 a great honor.〜の振り方を相談する ask a person's advice about one's future.〜を任せる give[submit]oneself.〜を固める (marry and) settle down.そう言っては〜も蓋もない That's too frank.
み【実】(和英)🔗⭐🔉
み【巳(年)】(和英)🔗⭐🔉
み【巳(年)】
(the year of) the Snake.
大辞林に「み」で完全一致するの検索結果 1-23。