複数辞典一括検索+![]()
![]()
あきのいろくさ 【秋の色種】🔗⭐🔉
あきのいろくさ 【秋の色種】
長唄の一。1845年初演。南部侯佐竹利済(トシナリ)作詞。一〇世杵屋(キネヤ)六左衛門作曲。歌詞内容は秋景色の描写。お座敷長唄の代表曲。
あき-の-うなぎつかみ [1]-[4] 【秋の鰻攫み】🔗⭐🔉
あき-の-うなぎつかみ [1]-[4] 【秋の鰻攫み】
タデ科の一年草。湿地に普通に見られる。茎は枝分かれして1メートルほどになり,茎や葉には逆向きのとげがある。秋に淡紅色の小花をつける。
あき-の-おうぎ ―アフギ [1] 【秋の扇】🔗⭐🔉
あき-の-おうぎ ―アフギ [1] 【秋の扇】
(1)「秋扇(アキオウギ)」に同じ。[季]秋。
(2)〔漢の成帝の宮女班
 (ハンシヨウヨ)が君寵(クンチヨウ)のおとろえた自分の身を秋の扇にたとえて詩に詠んだという故事から〕
相手の男から顧みられなくなった女性の身。団雪(ダンセツ)の扇。
(ハンシヨウヨ)が君寵(クンチヨウ)のおとろえた自分の身を秋の扇にたとえて詩に詠んだという故事から〕
相手の男から顧みられなくなった女性の身。団雪(ダンセツ)の扇。

 (ハンシヨウヨ)が君寵(クンチヨウ)のおとろえた自分の身を秋の扇にたとえて詩に詠んだという故事から〕
相手の男から顧みられなくなった女性の身。団雪(ダンセツ)の扇。
(ハンシヨウヨ)が君寵(クンチヨウ)のおとろえた自分の身を秋の扇にたとえて詩に詠んだという故事から〕
相手の男から顧みられなくなった女性の身。団雪(ダンセツ)の扇。
あき-の-か 【秋の香】🔗⭐🔉
あき-の-か 【秋の香】
(1)秋を感じさせるかおり。また,そのもの。特に,松茸(マツタケ)をさす。「満ち盛りたる―の良さ/万葉 2233」
(2)松茸とハモを使った料理。
あき-の-か [1] 【秋の蚊】🔗⭐🔉
あき-の-か [1] 【秋の蚊】
秋になっても生き残っている蚊。[季]秋。《くはれもす八雲旧居の―に/虚子》
あき-の-かた 【明きの方】🔗⭐🔉
あき-の-かた 【明きの方】
「恵方(エホウ)」に同じ。
あきのきょく 【秋の曲】🔗⭐🔉
あきのきょく 【秋の曲】
箏曲(ソウキヨク)。安政年間(1854-1860)吉沢検校が作曲。松坂春栄が1895年(明治28)手事を補作。前歌・手事・後歌の三段形式の純箏曲。歌詞は古今集から秋の歌六首を選ぶ。
あき-の-きりんそう ―キリンサウ [1]-[0] 【秋の麒麟草】🔗⭐🔉
あき-の-きりんそう ―キリンサウ [1]-[0] 【秋の麒麟草】
キク科の多年草。山野に自生する。高さ60センチメートルに達し,茎は細くてかたく,下部は黒紫色。秋,黄色の頭状花を茎の先に穂状に多数つける。アワダチソウ。金花。
秋の麒麟草
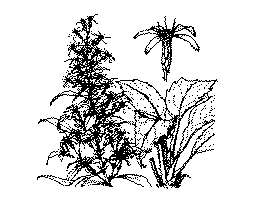 [図]
[図]
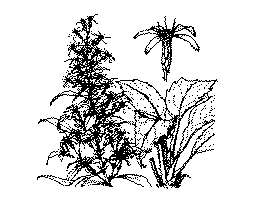 [図]
[図]
大辞林 ページ 137946。