複数辞典一括検索+![]()
![]()
あげ-ばり 【幄・揚げ張り】🔗⭐🔉
あげ-ばり 【幄・揚げ張り】
「幄(アク)の屋(ヤ)」に同じ。「東の方には錦の―を長く起てて/今昔 6」
あけ-ばん [0] 【明け番】🔗⭐🔉
あけ-ばん [0] 【明け番】
(1)宿直や夜通しの勤務が終わること。また,その人。
(2)宿直などの勤務についた翌日の休み。
(3)半夜交替の当直で,明け方の番。
あけび [0] 【木通・通草】🔗⭐🔉
あけび [0] 【木通・通草】
アケビ科のつる性落葉低木。山地に自生。葉は五枚の小葉から成る。四月ごろ,薄紫色の小花が咲く。果実は楕円形で,秋,熟すと縦に裂ける。果肉は甘く食べられる。葉が三小葉から成るものをミツバアケビという。つるを利用して,椅子(イス)や細工物などを作る。木部は利尿・鎮痛剤とする。[季]秋。
〔「あけびの花」は [季]春〕
木通
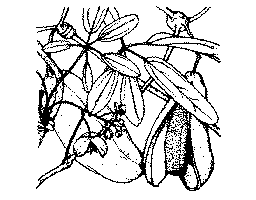 [図]
[図]
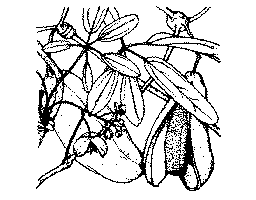 [図]
[図]
あけび-このは [4] 【通草木の葉】🔗⭐🔉
あけび-このは [4] 【通草木の葉】
ヤガ科のガ。体長約3.5センチメートル,開張約10センチメートル。前ばねは褐色,後ろばねは橙黄(トウコウ)色で巴(トモエ)状の黒斑がある。静止した姿は枯れ葉によく似る。幼虫はムベ・アケビなどの葉を食う。成虫は桃などの果汁を吸う害虫。夏,羽化する。日本各地と中国・インドなどに分布。
あげ-びさし [3] 【上げ庇】🔗⭐🔉
あげ-びさし [3] 【上げ庇】
「突き上げ戸」に同じ。
あげ-びたし [3] 【揚(げ)浸し】🔗⭐🔉
あげ-びたし [3] 【揚(げ)浸し】
材料を油で揚げ,熱いまま合わせ酢やだしに浸したもの。味がしみやすい。南蛮漬けなど。
あげ-ひばり [3] 【揚げ雲雀】🔗⭐🔉
あげ-ひばり [3] 【揚げ雲雀】
空高く舞い上がってさえずっているヒバリ。[季]春。
あげ-びょうし ―ビヤウシ [3] 【揚(げ)拍子】🔗⭐🔉
あげ-びょうし ―ビヤウシ [3] 【揚(げ)拍子】
神楽や久米歌(クメウタ)などで,やや拍子を速めて奏すること。また,その部分。舞を伴う。
あけ-ひろ・げる [0][5] 【明け広げる・開け広げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 あけひろ・ぐ🔗⭐🔉
あけ-ひろ・げる [0][5] 【明け広げる・開け広げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 あけひろ・ぐ
戸や窓などをすっかりあける。「仕切りの障子を―・げる」
大辞林 ページ 137993。