複数辞典一括検索+![]()
![]()
いっちょう-いったん イツチヤウ― [0] 【一長一短】🔗⭐🔉
いっちょう-いったん イツチヤウ― [0] 【一長一短】
長所もあり同時に短所もあること。「いずれも―あって,甲乙つけ難い」
いっ-ちょくせん [3][4] 【一直線】🔗⭐🔉
いっ-ちょくせん [3][4] 【一直線】
(1)一本の直線。
(2)まっすぐ。「―に進む」
いっちん-のり [3] 【一陳糊・一珍糊】🔗⭐🔉
いっちん-のり [3] 【一陳糊・一珍糊】
捺染(ナツセン)などの防染に用いる糊。小麦粉の煮たものに,糠(ヌカ)・消石灰・ふのりをまぜて練ったもの。乾くと水に溶けない。
いつ-つ [2] 【五つ】🔗⭐🔉
いつ-つ [2] 【五つ】
(1)ご。五個。物の数を数える時に使う。
(2)五歳。
(3)昔の時刻の名。今の午前と午後の八時頃。五つ時。
いつつ-あこめ [4] 【五つ衵】🔗⭐🔉
いつつ-あこめ [4] 【五つ衵】
女房装束で,あこめを五枚重ねて着るもの。
いつつ-お ―ヲ [3] 【五つ緒】🔗⭐🔉
いつつ-お ―ヲ [3] 【五つ緒】
牛車の簾(スダレ)の一種。左右の縁と中央に垂らした緒の間にそれぞれ一条の緒を垂らしたもの。また,その簾をつけた車。網代(アジロ)車など。
いつつ-お-の-くるま ―ヲ― 【五つ緒の車】🔗⭐🔉
いつつ-お-の-くるま ―ヲ― 【五つ緒の車】
五つ緒の簾(スダレ)をかけた牛車。いつつお。
いつつ-がさね [4] 【五つ重ね・五つ襲】🔗⭐🔉
いつつ-がさね [4] 【五つ重ね・五つ襲】
「いつつぎぬ」に同じ。
いつつ-がしら [4] 【五つ頭】🔗⭐🔉
いつつ-がしら [4] 【五つ頭】
歌舞伎の下座音楽で,荒事の見得に合わせて,太鼓・大太鼓・笛ではやすもの。「頭(カシラ)」という手を五回重ねることからの称。
いつつ-ぎぬ [3] 【五つ衣】🔗⭐🔉
いつつ-ぎぬ [3] 【五つ衣】
女房装束で,五枚重ねた袿(ウチキ)。江戸時代には,女官の正装をいう。いつつがさね。
五つ衣
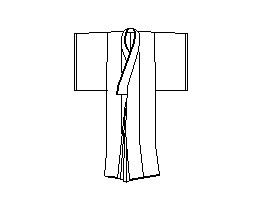 [図]
[図]
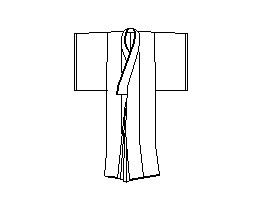 [図]
[図]
いつつ-どうぐ ―ダウ― [4] 【五つ道具】🔗⭐🔉
いつつ-どうぐ ―ダウ― [4] 【五つ道具】
江戸時代,大名行列の持ち道具の五種をいう。槍・打ち物・挟み箱・長柄傘(ナガエガサ)・袋入れ杖(ツエ)など。
いつつ-どき [0] 【五つ時】🔗⭐🔉
いつつ-どき [0] 【五つ時】
⇒いつつ(五つ)(3)
いつつ-の-おしえ ―ヲシヘ 【五つの教え】🔗⭐🔉
いつつ-の-おしえ ―ヲシヘ 【五つの教え】
儒教で説く,人間として守るべき五つの徳。仁・義・礼・智・信のこと。いつつのみち。五常。
大辞林 ページ 138878。