複数辞典一括検索+![]()
![]()
うまし 【美し・甘し】🔗⭐🔉
うまし 【美し・甘し】
(形容詞「うまし」から)
うまし-くに 【美し国】🔗⭐🔉
うまし-くに 【美し国】
よい国。美しい国。「―そ蜻蛉島(アキヅシマ)大和の国は/万葉 2」
うまし-もの 【甘し物】 (枕詞)🔗⭐🔉
うまし-もの 【甘し物】 (枕詞)
美味なるものとして知られていたことから,「阿倍橘(アエタチバナ)」にかかる。「吾妹子(ワギモコ)に逢はず久しも―阿倍橘の苔むすまでに/万葉 2750」
うましあしかびひこじ-の-みこと ウマシアシカビヒコヂ― 【可美葦牙彦舅尊】🔗⭐🔉
うましあしかびひこじ-の-みこと ウマシアシカビヒコヂ― 【可美葦牙彦舅尊】
記紀神話で,太古の混沌(コントン)から葦(アシ)が芽ぶくような物によって化成した男神。生命力の神格化。宇摩志阿斯訶備比古遅神(ウマシアシカビヒコジノカミ)。
うま-じもの 【馬じもの】🔗⭐🔉
うま-じもの 【馬じもの】
〔「じもの」は接尾語〕
馬のようなもの。馬のように。「―縄取りつけ/万葉 1019」
うま-しょうぞく ―シヤウゾク [3] 【馬装束】🔗⭐🔉
うま-しょうぞく ―シヤウゾク [3] 【馬装束】
馬に着ける飾り。
うま-じるし [3] 【馬印・馬標】🔗⭐🔉
うま-じるし [3] 【馬印・馬標】
戦場で,武将が敵味方の識別や自らの存在を誇示するために用いた目印。豊臣秀吉の瓢箪(ヒヨウタン)に金の切裂(キリサキ),徳川家康の七本骨の金の開扇(カイセン)などが有名。馬幟(ウマノボリ)。
→指物(サシモノ)
馬印
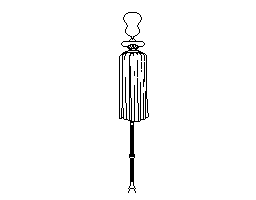 [図]
[図]
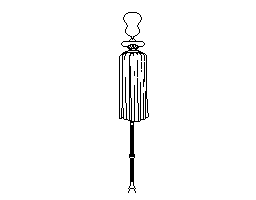 [図]
[図]
うま-ず 【不生】🔗⭐🔉
うま-ず 【不生】
(1)子を生まないこと。「出家させて夫婦―の業をはらし/浄瑠璃・賀古教信」
(2)「うまずめ」に同じ。「前の奥(=先妻)の―殿/浄瑠璃・賀古教信」
うまず-め [0] 【石女・不生女】🔗⭐🔉
うまず-め [0] 【石女・不生女】
子供を生めない女。
うま-すげ [2] 【馬菅】🔗⭐🔉
うま-すげ [2] 【馬菅】
カヤツリグサ科の多年草。小川や池の水辺などに生える。葉は線形で細長い。花茎は高さ50センチメートルぐらいで上方に少数の小穂をつける。
大辞林 ページ 139463。