複数辞典一括検索+![]()
![]()
えん-ねつ [0] 【炎熱】🔗⭐🔉
えん-ねつ [0] 【炎熱】
太陽の照りつける夏のきびしい暑さ。
えんねつ-じごく ―ヂ― [5] 【炎熱地獄】🔗⭐🔉
えんねつ-じごく ―ヂ― [5] 【炎熱地獄】
⇒焦熱地獄(シヨウネツジゴク)
えん-ねん [0] 【延年】🔗⭐🔉
えん-ねん [0] 【延年】
(1)寿命を延ばすこと。長生きすること。「詩歌管絃は,嘉例―の方也/庭訓往来」
(2)「延年舞」に同じ。
(3)寿命が延びるほどに楽しむこと。「夫はなけれども出て共に―す/今昔 3」
えんねん-そう ―サウ [0] 【延年草】🔗⭐🔉
えんねん-そう ―サウ [0] 【延年草】
⇒延齢草(エンレイソウ)
えんねん-まい ―マヒ [0] 【延年舞】🔗⭐🔉
えんねん-まい ―マヒ [0] 【延年舞】
寺院芸能の一。平安中期に興り,鎌倉・室町時代に最も栄えた。延暦寺・興福寺などの寺院で,大法会のあとの大衆(ダイシユ)の猿楽や稚児の舞などによる遊宴歌舞の総称。のちに遊僧と呼ばれる専業者が出現し,中国の故事に題材をとる風流(フリユウ)や連事(レンジ)などは能楽の形式に影響を与えたといわれる。現在も地方の寺院にわずかに残っている。延年。
延年舞
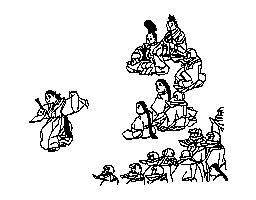 [図]
[図]
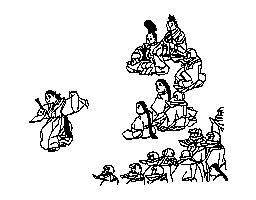 [図]
[図]
えん-のう ―ナフ [0] 【延納】 (名)スル🔗⭐🔉
えん-のう ―ナフ [0] 【延納】 (名)スル
期日に遅れて納めること。納付を延期すること。「授業料を―する」
えん-のう ―ナフ [0] 【捐納】🔗⭐🔉
えん-のう ―ナフ [0] 【捐納】
中国で,政府が財政を補うため人民に金銭・米穀を納めさせて官職を与えたり優遇したりしたこと。北辺防備のため漢代に始まり,以後,乱用されて弊害を生じた。捐官。
えん-のう  ン― [0] 【援農】🔗⭐🔉
ン― [0] 【援農】🔗⭐🔉
えん-のう  ン― [0] 【援農】
農作業労働を手伝い,助けること。また特に,有機農産物の産直などで,消費者による生産状況の理解と農業の体験,労働力不足の補いなどのために,消費者が農作業を手伝うこと。
ン― [0] 【援農】
農作業労働を手伝い,助けること。また特に,有機農産物の産直などで,消費者による生産状況の理解と農業の体験,労働力不足の補いなどのために,消費者が農作業を手伝うこと。
 ン― [0] 【援農】
農作業労働を手伝い,助けること。また特に,有機農産物の産直などで,消費者による生産状況の理解と農業の体験,労働力不足の補いなどのために,消費者が農作業を手伝うこと。
ン― [0] 【援農】
農作業労働を手伝い,助けること。また特に,有機農産物の産直などで,消費者による生産状況の理解と農業の体験,労働力不足の補いなどのために,消費者が農作業を手伝うこと。
えん-のう [0] 【演能】🔗⭐🔉
えん-のう [0] 【演能】
能{(6)}を演ずること。
えん-の-うばそく 【役優婆塞】🔗⭐🔉
えん-の-うばそく 【役優婆塞】
⇒役小角(エンノオヅノ)
大辞林 ページ 139878。