複数辞典一括検索+![]()
![]()
お-ひたき [0] 【御火焚・御火焼】🔗⭐🔉
お-ひたき [0] 【御火焚・御火焼】
江戸時代から京都地方などで行われる神事。陰暦一一月に社前に神楽を奏し供物を供え,火を焚いて祭った。また,鍛冶屋の鞴(フイゴ)祭りなど,民間で行われることもあった。おほたき。[季]冬。
お-ひたし [3] 【御浸し】🔗⭐🔉
お-ひたし [3] 【御浸し】
菜・山菜などをゆでて,合わせ醤油をかけた料理。「ほうれん草の―」
おびただし・い [5] 【夥しい】 (形)[文]シク おびただ・し🔗⭐🔉
おびただし・い [5] 【夥しい】 (形)[文]シク おびただ・し
〔近世中頃までは「おびたたし」と第四音節が清音〕
(1)ものの数や量がはかりしれないくらいたくさんある。非常に多い。「―・い数」「―・い出血」
(2)度合・程度がはなはだしい。「無責任なこと―・い」
(3)おおげさだ。仰々しい。「只同じ詞なれど―・しく聞こゆ/無名抄」
[派生] ――さ(名)
お-ひつ [0] 【御櫃】🔗⭐🔉
お-ひつ [0] 【御櫃】
炊いた飯を釜から移し入れておく木製の器。めしびつ。おはち。
御櫃
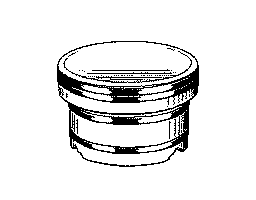 [図]
[図]
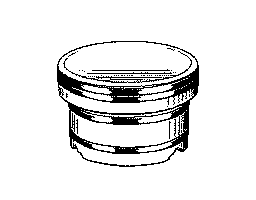 [図]
[図]
おひつじ-ざ ヲヒツジ― [0] 【牡羊座】🔗⭐🔉
おひつじ-ざ ヲヒツジ― [0] 【牡羊座】
〔(ラテン) Aries〕
黄道十二星座の一。一二月下旬の宵に南中する星座。牡牛(オウシ)座の西にある。かつては春分点がこの星座にあった。「白羊宮」に相当する。
おび-てつ [0] 【帯鉄】🔗⭐🔉
おび-てつ [0] 【帯鉄】
(1)帯状に圧延した鉄板。
(2)木箱などの荷造り用のテープ状の鉄。
おびと 【首】🔗⭐🔉
おびと 【首】
(1)首長。統率者。「汝は我が宮の―たれ/古事記(上訓)」
(2)上代の姓(カバネ)の一。地方の土豪や中央の下級官人の姓。八色(ヤクサ)の姓の制により廃止。
おび-ど [0][2] 【帯戸】🔗⭐🔉
おび-ど [0][2] 【帯戸】
帯桟つきの板戸。帯桟戸。
お-ひとかた [3] 【御一方】🔗⭐🔉
お-ひとかた [3] 【御一方】
「おひとり様」を丁寧にいう語。
おび-とき [2][0] 【帯解き】🔗⭐🔉
おび-とき [2][0] 【帯解き】
子供の付け紐(ヒモ)をやめて普通の帯を使い始める祝儀。男は五歳,女は七歳の一一月の吉日に行なったが,次第に一一月一五日に定着した。ひもとき。おびなおし。[季]冬。《―も花橘のむかしかな/其角》
大辞林 ページ 140401。