複数辞典一括検索+![]()
![]()
――に 居(イ)る🔗⭐🔉
居(イ)る🔗⭐🔉
――に 居(イ)る
人の影響下にいる。他人をまねる。
居(イ)る
人の影響下にいる。他人をまねる。
 居(イ)る
人の影響下にいる。他人をまねる。
居(イ)る
人の影響下にいる。他人をまねる。
かざ-しも [0] 【風下】🔗⭐🔉
かざ-しも [0] 【風下】
風の吹いて行く方向。かざした。
⇔風上(カザカミ)
――に立・つ🔗⭐🔉
――に立・つ
他に先んじられて,その影響を受ける。
かざしも-なみ [4] 【風下波】🔗⭐🔉
かざしも-なみ [4] 【風下波】
⇒かざしもは(風下波)
かざしも-は [4] 【風下波】🔗⭐🔉
かざしも-は [4] 【風下波】
気流が山を吹き越すとき,風下側で気流が波を打つ現象。波頭に当たる部分に吊(ツ)るし雲ができる。
かさ-じるし [3] 【笠標】🔗⭐🔉
かさ-じるし [3] 【笠標】
戦場で敵味方の識別のために兜(カブト)に付ける目印。多く布を使う。
笠標
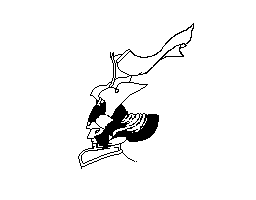 [図]
[図]
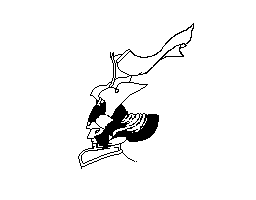 [図]
[図]
かさじるし-つけ-の-かん ―クワン 【笠標付けの鐶】🔗⭐🔉
かさじるし-つけ-の-かん ―クワン 【笠標付けの鐶】
兜の鉢の後部中央にある鐶。笠標を付けるためのものであるが,赤の総角(アゲマキ)も付けた。高勝鐶(コウシヨウカン)。
かざ-じるし [3] 【風標】🔗⭐🔉
かざ-じるし [3] 【風標】
「風見(カザミ){(2)}」に同じ。
かざ・す [0][2] 【翳す】 (動サ五[四])🔗⭐🔉
かざ・す [0][2] 【翳す】 (動サ五[四])
(1)手に持って頭上に高くかかげる。「団旗を―・して進む」
(2)物の上方におおいかけるように手をさしだす。「火鉢に手を―・す」
(3)光などをさえぎるために,手などを額のあたりに持っていっておおう。「小手を―・す」
かざ・す 【挿頭す】 (動サ四)🔗⭐🔉
かざ・す 【挿頭す】 (動サ四)
〔「髪挿す」の転〕
(1)草木の枝や花を髪にさす。中古以降は,冠に挿すこともいい,造花や玉なども用いた。「藤波を―・して行かむ見ぬ人のため/万葉 4200」
(2)ものの上に飾りつける。「造りたる桜をまぜくだものの上に―・して/頼政集」
かさ-すげ [2] 【笠菅】🔗⭐🔉
かさ-すげ [2] 【笠菅】
カヤツリグサ科の多年草。水辺や湿地に群生する。高さ約1メートル。茎は三角柱状。葉は広線形で長く,ざらつく。晩春,雄花穂を頂生し,その下に数本の雌花穂を斜出する。葉で蓑(ミノ)・笠・縄などを作る。スゲ。
かさ-だか [0] 【嵩高】 (形動)[文]ナリ🔗⭐🔉
かさ-だか [0] 【嵩高】 (形動)[文]ナリ
(1)物の体積や容積の大きいさま。かさばっているさま。「―な荷」
(2)人を見下して横柄な態度をとるさま。「―に物を言う」
(3)大仰なさま。「嘉例の祝でも,あんまり騒ぎが―な/浄瑠璃・妹背山」
大辞林 ページ 141044。