複数辞典一括検索+![]()
![]()
こそこそ-ばなし [5] 【こそこそ話】🔗⭐🔉
こそこそ-ばなし [5] 【こそこそ話】
小声で内密に話す話。ひそひそ話。
こそこそ-やど 【こそこそ宿】🔗⭐🔉
こそこそ-やど 【こそこそ宿】
男女が人目を避けて内密に忍びあう宿。あいまい宿。「―の情け事/浄瑠璃・雪女」
ごそ-ごそ [1] (副)スル🔗⭐🔉
ごそ-ごそ [1] (副)スル
あらくこわばった物が触れる音を表す語。また,そういう音を立てて動くさま。「天井裏で何かが―(と)している」「―(と)探しまわる」
ごそしちこく-の-らん 【呉楚七国の乱】🔗⭐🔉
ごそしちこく-の-らん 【呉楚七国の乱】
前漢景帝がとった呉・楚・趙など諸王の勢力を抑圧する政策に対し,紀元前154年呉王 (ビ)を初めとする七王が起こした反乱。三か月で鎮圧され,中央政府の統制力は強化された。
(ビ)を初めとする七王が起こした反乱。三か月で鎮圧され,中央政府の統制力は強化された。
 (ビ)を初めとする七王が起こした反乱。三か月で鎮圧され,中央政府の統制力は強化された。
(ビ)を初めとする七王が起こした反乱。三か月で鎮圧され,中央政府の統制力は強化された。
こ-そだて [2] 【子育て】 (名)スル🔗⭐🔉
こ-そだて [2] 【子育て】 (名)スル
子を育てること。育児。
ごそ-つ・く [0] (動カ五[四])🔗⭐🔉
ごそ-つ・く [0] (動カ五[四])
がさがさ,ごそごそと音を立てる。「立ち枯れの萱を―・かせた後ろ姿の/虞美人草(漱石)」
こぞっ-こ [4] 【小僧っ子】🔗⭐🔉
こぞっ-こ [4] 【小僧っ子】
小僧・丁稚(デツチ)あるいは年少の男子をののしっていう語。青二才。こわっぱ。「この―が」
こぞっ-て [2] 【挙って】 (副)🔗⭐🔉
こぞっ-て [2] 【挙って】 (副)
〔動詞「こぞる」に助詞「て」の付いた「こぞりて」の転〕
ある集団を構成する者全員が同じ行動をするさま。残らず。あげて。「家内一同―お待ちいたしております」「この条例に市民は―反対している」
ごそっ-と [2] (副)🔗⭐🔉
ごそっ-と [2] (副)
一度にたくさん。のこらず。ごっそり。「着物を―盗まれた」「会員が―減った」
こ-そで [0][1] 【小袖】🔗⭐🔉
こ-そで [0][1] 【小袖】
(1)袖口が狭く,垂領(タリクビ)で前を引き違えて着る衣服。現在の長着の原形。平安時代には,貴族の装束の内衣であり,庶民は日常着として用いた。次第に貴族の服装が簡略化されるにつれて上衣(ウワギ)となり,男女ともに広く着用するようになった。室町時代にさらに洗練されて,打掛(ウチカケ)・被衣(カツギ)などの豪華な装飾用の小袖を生んだ。近世になって袂(タモト)が長くなり,身丈も長くなって近世後期にはほぼ現在の長着の形となった。
(2)礼服の大袖の下に重ねた筒袖・盤領(マルエリ)の衣服。
(3)絹の綿入れ。
→布子(ヌノコ)
小袖(1)
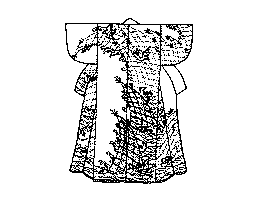 [図]
[図]
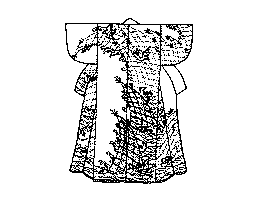 [図]
[図]
大辞林 ページ 144299。