複数辞典一括検索+![]()
![]()
しゃ-きん [0] 【謝金】🔗⭐🔉
しゃ-きん [0] 【謝金】
謝礼のための金銭。礼金。謝礼金。
しゃく [1] 【勺・夕】🔗⭐🔉
しゃく [1] 【勺・夕】
(1)尺貫法の容積の単位。合の一〇分の一。升の一〇〇分の一。約0.018リットル。せき。
(2)尺貫法の面積の単位。坪の一〇〇分の一。約0.033平方メートル。せき。
(3)登山の路程で,合の一〇分の一。
しゃく 【尺】🔗⭐🔉
しゃく 【尺】
■一■ [2] (名)
(1)長さの単位。寸の一〇倍,丈の一〇分の一。一尺の長さは時代などによって様々である。中国から伝来し,大宝令では大尺・小尺を制定,のち唐大尺・唐小尺に変える。やがて唐大尺系統の曲尺(カネジヤク)が現れ主流となった。近世には享保(キヨウホウ)尺・又四郎尺,また用途により鯨尺・呉服尺などが行われたが,明治時代に曲尺と鯨尺以外は禁止され,メートル条約加入後,1891年(明治24)曲尺一尺を三三分の10メートル(約30.3センチメートル)と定義し,尺貫法における長さの基本単位とした。1958年(昭和33)まで,これは公認の単位として用いられた。
(2)ものさし。
(3)長さ。たけ。「―が足りない」
■二■ (接尾)
〔「隻(セキ)」の借字〕
助数詞。魚などを数えるのに用いる。「腰に鮭の一二―なきやうはありなんや/宇治拾遺 1」
――も短き所あり寸も長き所あり🔗⭐🔉
――も短き所あり寸も長き所あり
〔楚辞(卜居)〕
尺は寸より長いが,時には短くて足らないこともあり,寸は尺より短いが,時には長くて余ることがあるという意。賢者も事によっては劣ることがあり,愚者も事によってはまさることがあるというたとえ。
――を打・つ🔗⭐🔉
――を打・つ
「尺を取る」に同じ。
――を取・る🔗⭐🔉
――を取・る
ものさしで長さをはかる。尺を打つ。
――を枉(マ)げて尋(ヒロ)を直(ノ)ぶ🔗⭐🔉
――を枉(マ)げて尋(ヒロ)を直(ノ)ぶ
〔孟子(滕文公下)〕
短いもの(尺)を曲げて縮め,長いもの(尋)を長くのばす意で,小利を捨てて大利をとることのたとえ。
しゃく [1] 【杓】🔗⭐🔉
しゃく [1] 【杓】
柄杓(ヒシヤク)。
しゃく [1][0] 【笏】🔗⭐🔉
しゃく [1][0] 【笏】
〔本来の字音「こつ」が「骨」に通うのをきらって,その長さが一尺ほどあるところから「尺」の音を借りたものという〕
束帯を着るとき,右手に持つ細長い板。初めは式次第などを紙に書き,裏に貼って備忘用としたが,のちには儀礼用となった。材質は木または象牙。手板(シユハン)。さく。
笏
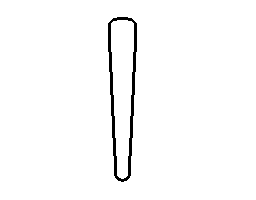 [図]
[図]
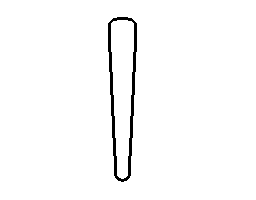 [図]
[図]
大辞林 ページ 146011。