複数辞典一括検索+![]()
![]()
しゃく-の-むし [0] 【癪の虫】🔗⭐🔉
しゃく-の-むし [0] 【癪の虫】
人間の腹中にあって癪を起こすもとになると考えられていた虫。転じて,癪にさわっていらいらする気分。「―が起こる」
しゃく-ば [0] 【釈場】🔗⭐🔉
しゃく-ば [0] 【釈場】
「講釈場」の略。講談専門の寄席。
しゃく-ば [0][1] 【借馬】🔗⭐🔉
しゃく-ば [0][1] 【借馬】
馬を借りること。また,その馬。
じゃく-はい [0] 【若輩・弱輩】🔗⭐🔉
じゃく-はい [0] 【若輩・弱輩】
■一■ (名)
年の若い者。年少者。話し手が自分について用いるときは,へりくだった意味になる。「―の分際で何を言うか」「―ですが,どうぞよろしく」
■二■ (名・形動)[文]ナリ
経験が乏しく未熟であること。また,そのさまや人。「―ナコトヲユウ/日葡」
じゃくはい-もの [0] 【弱輩者】🔗⭐🔉
じゃくはい-もの [0] 【弱輩者】
年が若く未熟な者。
じゃく-はく [0] 【弱拍】🔗⭐🔉
じゃく-はく [0] 【弱拍】
音楽で,拍節の弱い部分。普通二拍子では二拍目,三拍子では二拍目と三拍目,四拍子では二拍目と四拍目。最初の強拍の前の弱拍をアウフタクトという。上拍。アップ-ビート。
⇔強拍
しゃく-はち [0] 【尺八】🔗⭐🔉
しゃく-はち [0] 【尺八】
(1)〔長さ一尺八寸を基準とするのでいう〕
縦笛の一。簧(シタ)(リード)はなく,歌口に直接唇をあてて吹奏する。古代尺八(雅楽尺八)・一節切(ヒトヨギリ)・普化(フケ)尺八(虚無僧(コムソウ)尺八)・多孔尺八(新尺八)などがあるが,今日多く使われているのは普化尺八で,太い竹の根元に近い部分で作る。指孔は五孔。流派としては都山流・琴古(キンコ)流・明暗流がある。竹。
(2)紙・絹などの幅一尺八寸のもの。
(3)男根に対する口淫。フェラチオ。
尺八(1)
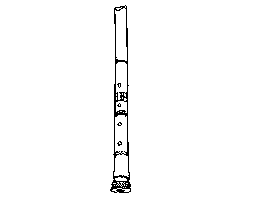 [図]
[図]
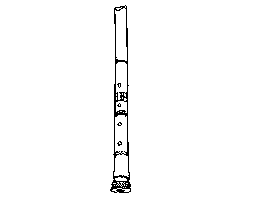 [図]
[図]
じゃく-はん [0] 【雀斑】🔗⭐🔉
じゃく-はん [0] 【雀斑】
そばかす。
しゃ-くび 【しゃ首】🔗⭐🔉
しゃ-くび 【しゃ首】
〔「しゃ」は接頭語〕
首をののしっていう語。「よつぴいて―の骨をひやうふつと射て/平家 11」
しゃく-びょうし ―ビヤウシ [3] 【笏拍子】🔗⭐🔉
しゃく-びょうし ―ビヤウシ [3] 【笏拍子】
神楽(カグラ)・催馬楽(サイバラ)などで拍子をとるための楽器。初め二枚の笏を用いたが,のち笏を縦にまん中で二つに割った形となった。主唱者が両手に持ち,打ち鳴らして用いる。さくほうし。びゃくし。
笏拍子
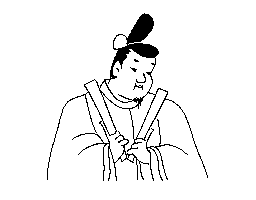 [図]
[図]
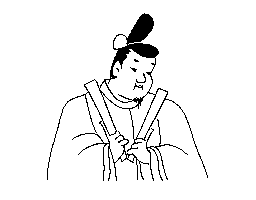 [図]
[図]
大辞林 ページ 146024。