複数辞典一括検索+![]()
![]()
しょう-ぎ セウ― [1] 【小義】🔗⭐🔉
しょう-ぎ セウ― [1] 【小義】
すこしの道義。ちょっとした義理。「―に泥(ナズ)むは愚の極なり/当世書生気質(逍遥)」
しょう-ぎ シヤウ― [0][1] 【床几・牀几・将几】🔗⭐🔉
しょう-ぎ シヤウ― [0][1] 【床几・牀几・将几】
(1)折り畳み式の腰掛け。脚を打ち違えに組み,革・布などを張って尻を乗せるようにしたもの。室内の臨時の座や,野外の腰掛けとして用いる。
(2)細長い板に脚を付けた,簡単な腰掛け。「―で夕涼みする」
床几(1)
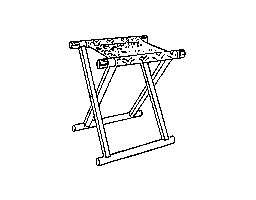 [図]
[図]
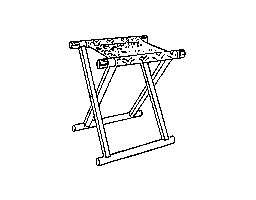 [図]
[図]
しょう-ぎ シヤウ― [1] 【省議】🔗⭐🔉
しょう-ぎ シヤウ― [1] 【省議】
内閣の各省の会議。また,その議決。
しょう-ぎ シヤウ― [0] 【将棋・象棋・象戯】🔗⭐🔉
しょう-ぎ シヤウ― [0] 【将棋・象棋・象戯】
将棋盤を用いて二人で行うゲーム。二〇枚ずつの駒を並べ,交互に動かして,相手の王将を詰めた方を勝ちとする。インドに起こり中国を経て,奈良時代末に日本に伝わったという。古くは大象棋・中象棋・小象棋などの別があり,現在の将棋は室町中期に小象棋をもとに成立したと考えられている。「―をさす」
しょうぎ-さし シヤウ― [3] 【将棋指し】🔗⭐🔉
しょうぎ-さし シヤウ― [3] 【将棋指し】
将棋をさすことを職とする人。棋士(キシ)。
しょうぎ-だおし シヤウ―ダフシ [4] 【将棋倒し】🔗⭐🔉
しょうぎ-だおし シヤウ―ダフシ [4] 【将棋倒し】
(1)将棋の駒を一列に立てて並べ,端の駒を倒して順々に他の端まで倒す遊び。ドミノ倒し。
(2)人込みなどで一人が倒れたことにより,順々に折り重なって倒れること。「乗客が―になる」
しょうぎ-どころ シヤウ― [4] 【将棋所】🔗⭐🔉
しょうぎ-どころ シヤウ― [4] 【将棋所】
近世,将棋の名人の別名。将棋の指南・免状の発行権などの特権をもつ。初代大橋宗桂以下,大橋・大橋分家・伊藤の三家から出た。
しょうぎ-の-こま シヤウ― 【将棋の駒】🔗⭐🔉
しょうぎ-の-こま シヤウ― 【将棋の駒】
将棋に使用する五角形の木片。双方二〇枚ずつ,計四〇枚で一組。各人の二〇枚は,それぞれはたらきの異なる,王将(玉将)一,飛車・角行(カツコウ)各一,金将・銀将・桂馬・香車(キヨウシヤ)各二,歩(フ)九から成る。
大辞林 ページ 146462。