複数辞典一括検索+![]()
![]()
ぞうじんぐうし-ちょう ザウジングウシチヤウ 【造神宮使庁】🔗⭐🔉
ぞうじんぐうし-ちょう ザウジングウシチヤウ 【造神宮使庁】
もと,伊勢神宮の造営および神宝・装束の調進をつかさどった官庁。
そうじん-ふ 【宗人府】🔗⭐🔉
そうじん-ふ 【宗人府】
中国,明・清代に皇族(宗人)に関することをつかさどった官庁。
そうず ソフヅ [0] 【添水】🔗⭐🔉
そうず ソフヅ [0] 【添水】
懸け樋(ヒ)などで水を引いて竹筒に注ぎ入れ,一杯になると重みで反転して水を吐き,元に戻るときに石などを打って音を発するようにした仕掛け。もと農家で猪(イノシシ)や鹿(シカ)をおどすのに用いられた。ししおどし。添水唐臼(ソウズカラウス)。[季]秋。
〔「僧都」とも書く〕
添水
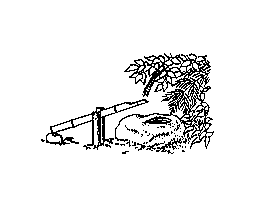 [図]
[図]
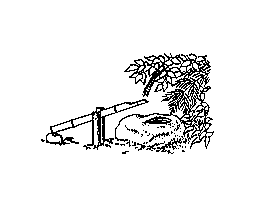 [図]
[図]
そう-ず サフヅ [0] 【挿図】🔗⭐🔉
そう-ず サフヅ [0] 【挿図】
本文の中に入れる図。さしえ。
そう-ず ―ヅ [1] 【僧都】🔗⭐🔉
そう-ず ―ヅ [1] 【僧都】
(1)僧綱(ソウゴウ)の一。僧正の下,律師の上に位し,僧尼を統轄する。初め一人であったが,のちに大・権大・少・権少の四階級に分かれる。
(2)明治以降,各宗派の僧階の一。
(3)添水(ソウズ)。
そう・ず サウ― 【請ず】 (動サ変)🔗⭐🔉
そう・ず サウ― 【請ず】 (動サ変)
〔「しやうず」の直音表記〕
「しょうずる(請)」に同じ。「大方世にしるしありと聞ゆる人の限り,あまた―・じ給ふ/源氏(総角)」
そう ず サウ― 【候ず】 (連語)🔗⭐🔉
ず サウ― 【候ず】 (連語)🔗⭐🔉
そう ず サウ― 【候ず】 (連語)
■一■〔動詞「そう(候)」の未然形「さう」に打ち消しの助動詞「ず」の付いたもの〕
多く補助動詞として用いられ,「(で)ありません」の意を表す。「いやいや,これまでは思ひも寄り―
ず サウ― 【候ず】 (連語)
■一■〔動詞「そう(候)」の未然形「さう」に打ち消しの助動詞「ず」の付いたもの〕
多く補助動詞として用いられ,「(で)ありません」の意を表す。「いやいや,これまでは思ひも寄り― ず/平家 2」
■二■〔動詞「そう(候)」の未然形「さう」に推量の助動詞「うず」が付いた「さううず」の転〕
多く補助動詞として用いられ,「でしょう」「(で)ありましょう」の意を表す。「今年は風雪が好程に麦がよう―
ず/平家 2」
■二■〔動詞「そう(候)」の未然形「さう」に推量の助動詞「うず」が付いた「さううず」の転〕
多く補助動詞として用いられ,「でしょう」「(で)ありましょう」の意を表す。「今年は風雪が好程に麦がよう― ず/四河入海 25」
ず/四河入海 25」
 ず サウ― 【候ず】 (連語)
■一■〔動詞「そう(候)」の未然形「さう」に打ち消しの助動詞「ず」の付いたもの〕
多く補助動詞として用いられ,「(で)ありません」の意を表す。「いやいや,これまでは思ひも寄り―
ず サウ― 【候ず】 (連語)
■一■〔動詞「そう(候)」の未然形「さう」に打ち消しの助動詞「ず」の付いたもの〕
多く補助動詞として用いられ,「(で)ありません」の意を表す。「いやいや,これまでは思ひも寄り― ず/平家 2」
■二■〔動詞「そう(候)」の未然形「さう」に推量の助動詞「うず」が付いた「さううず」の転〕
多く補助動詞として用いられ,「でしょう」「(で)ありましょう」の意を表す。「今年は風雪が好程に麦がよう―
ず/平家 2」
■二■〔動詞「そう(候)」の未然形「さう」に推量の助動詞「うず」が付いた「さううず」の転〕
多く補助動詞として用いられ,「でしょう」「(で)ありましょう」の意を表す。「今年は風雪が好程に麦がよう― ず/四河入海 25」
ず/四河入海 25」
ぞう-す ザウ― [1] 【蔵主】🔗⭐🔉
ぞう-す ザウ― [1] 【蔵主】
禅寺で,経蔵をつかさどる僧の役職名。蔵司。
大辞林 ページ 148108。