複数辞典一括検索+![]()
![]()
だいもく-おどり ―ヲドリ [5] 【題目踊り】🔗⭐🔉
だいもく-おどり ―ヲドリ [5] 【題目踊り】
日蓮宗の行事。太鼓に合わせ,法華経の題目を唱えながら踊る。京都市左京区の湧泉寺で,八月一五,一六日に行われる盆踊りが有名。
だいもく-こう ―カウ [0] 【題目講】🔗⭐🔉
だいもく-こう ―カウ [0] 【題目講】
日蓮宗の信者の講。
だいもく-しゅう [3] 【題目宗】🔗⭐🔉
だいもく-しゅう [3] 【題目宗】
〔題目を唱えることから〕
日蓮宗の俗称。
だいもく-だいこ [5] 【題目太鼓】🔗⭐🔉
だいもく-だいこ [5] 【題目太鼓】
南無妙法蓮華経という題目を唱えながらたたく太鼓。
だい-もつ [0] 【代物】🔗⭐🔉
だい-もつ [0] 【代物】
(1)代金。代価。ぜに。「―はいかほどでござる/狂言・張蛸」
(2)代わりとなる物。[日葡]
だいもつ-の-うら 【大物浦】🔗⭐🔉
だいもつ-の-うら 【大物浦】
摂津国,淀川旧河口にあった船着き場。今の兵庫県尼ヶ崎市大物町。
たい-もん [0] 【体文】🔗⭐🔉
たい-もん [0] 【体文】
悉曇(シツタン)字母の,子音を表す三五字。
→摩多
だい-もん [1] 【大門】🔗⭐🔉
だい-もん [1] 【大門】
大きな門。大内裏や寺などの,外構えの大きな門。正門。総門。おおもん。
→おおもん(大門)
だい-もん [1] 【大紋】🔗⭐🔉
だい-もん [1] 【大紋】
(1)大形の紋様。
(2)大形の家紋を五か所に染めた直垂(ヒタタレ)。袴にも五か所に紋をつける。室町時代に始まり,江戸時代には五位以上の武家の通常の礼服となった。
大紋(2)
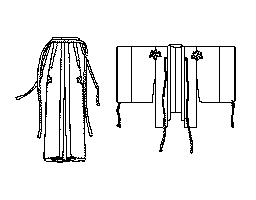 [図]
[図]
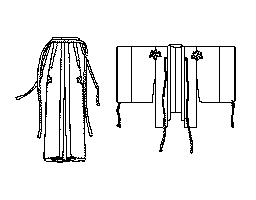 [図]
[図]
だいもん-の-こうらい ―カウライ 【大紋の高麗】🔗⭐🔉
だいもん-の-こうらい ―カウライ 【大紋の高麗】
大形の紋のついている高麗縁(ベリ)。
だい-もん [0] 【大問】🔗⭐🔉
だい-もん [0] 【大問】
試験問題などで,まとまった大きな問い。
⇔小問(シヨウモン)
ダイモン [1]  (ギリシヤ) daim
(ギリシヤ) daim n
n 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ダイモン [1]  (ギリシヤ) daim
(ギリシヤ) daim n
n ギリシャ思想において,神と人との中間者で,個人の運命を導く神霊的な存在。ソクラテスは行為に際して,時折自己の内奥にダイモン的なもの(ダイモニオン)の声を聞いたという。デーモン。
ギリシャ思想において,神と人との中間者で,個人の運命を導く神霊的な存在。ソクラテスは行為に際して,時折自己の内奥にダイモン的なもの(ダイモニオン)の声を聞いたという。デーモン。
 (ギリシヤ) daim
(ギリシヤ) daim n
n ギリシャ思想において,神と人との中間者で,個人の運命を導く神霊的な存在。ソクラテスは行為に際して,時折自己の内奥にダイモン的なもの(ダイモニオン)の声を聞いたという。デーモン。
ギリシャ思想において,神と人との中間者で,個人の運命を導く神霊的な存在。ソクラテスは行為に際して,時折自己の内奥にダイモン的なもの(ダイモニオン)の声を聞いたという。デーモン。
大辞林 ページ 148596。