複数辞典一括検索+![]()
![]()
つり-かご [0] 【釣り籠】🔗⭐🔉
つり-かご [0] 【釣り籠】
釣った魚を入れるかご。びく。
つり-がね [0] 【釣(り)鐘】🔗⭐🔉
つり-がね [0] 【釣(り)鐘】
寺院の鐘楼などに釣ってある大きな鐘。撞木(シユモク)でついて鳴らす。梵鐘(ボンシヨウ)。
つりがね-かずら ―カヅラ [5] 【釣鐘葛】🔗⭐🔉
つりがね-かずら ―カヅラ [5] 【釣鐘葛】
ノウゼンカズラ科の常緑つる性木本。北アメリカ原産。観賞用に栽培。長さ15メートルになる。葉は三出複葉で,中央の小葉は巻きひげに変化。五月,葉腋に橙褐赤色の鐘状花を二〜五個開く。
つりがね-ずみ [4] 【釣(り)鐘墨】🔗⭐🔉
つりがね-ずみ [4] 【釣(り)鐘墨】
松煙に蝋(ロウ)を混ぜて釣り鐘形に作った墨。乾拓に用いる。乾打碑(カンダヒ)。
つりがね-そう ―サウ [0] 【釣鐘草】🔗⭐🔉
つりがね-そう ―サウ [0] 【釣鐘草】
(1)ホタルブクロ・ナルコユリ・ツリガネニンジンなど,釣り鐘状の花をつける草の通称。
(2)ホタルブクロの別称。[季]夏。
つりがね-どう ―ダウ [0] 【釣(り)鐘堂】🔗⭐🔉
つりがね-どう ―ダウ [0] 【釣(り)鐘堂】
寺院で,釣り鐘を釣っておく堂。鐘楼。
つりがね-にんじん [5] 【釣鐘人参】🔗⭐🔉
つりがね-にんじん [5] 【釣鐘人参】
キキョウ科の多年草。山野に自生。高さ約70センチメートル。葉は輪生する。秋,茎頂に円錐花序を出し,青紫色の鐘状の花を花柄の先に下向きに輪生する。若葉はトトキといい食用になる。根茎は太く漢方で鎮咳・去痰などの薬用とする。
釣鐘人参
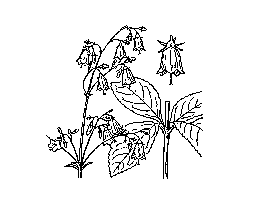 [図]
[図]
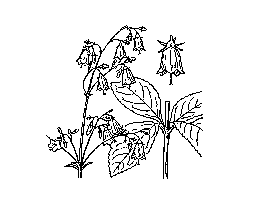 [図]
[図]
つりがね-ぼし [4] 【釣(り)鐘星】🔗⭐🔉
つりがね-ぼし [4] 【釣(り)鐘星】
牡牛座のヒヤデス星団の和名。
つりがね-マント [5] 【釣(り)鐘―】🔗⭐🔉
つりがね-マント [5] 【釣(り)鐘―】
〔着た姿が釣り鐘のようになることから〕
丈の長いマント。以前,軍人や学生などが用いた。
つりがね-むし [4] 【釣鐘虫】🔗⭐🔉
つりがね-むし [4] 【釣鐘虫】
繊毛虫綱ツリガネムシ科の一属の原生動物の総称。形は逆釣り鐘状で,体長40〜200マイクロメートルで,下端から体長の四,五倍の長さの柄を生じて他物に着生する。大部分は淡水産で汚れた沼や溝などにすむが,海産もある。
釣鐘虫
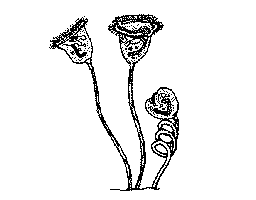 [図]
[図]
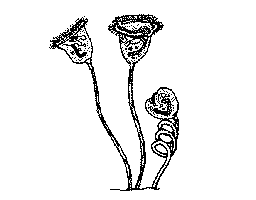 [図]
[図]
つり-かびん ―クワビン [3] 【釣(り)花瓶】🔗⭐🔉
つり-かびん ―クワビン [3] 【釣(り)花瓶】
上からつり下げるように作った花瓶。つりはないけ。
大辞林 ページ 149841。