複数辞典一括検索+![]()
![]()
つり-ばな [0] 【吊花】🔗⭐🔉
つり-ばな [0] 【吊花】
ニシキギ科の落葉低木。山地に自生。葉は楕円形。初夏,葉腋(ヨウエキ)から出た長い花柄の先に緑白色または淡紫色の小五弁花をつけ集散状に垂れ下がる。秋, 果(サクカ)は熟して五裂し,赤色の種子を現す。
果(サクカ)は熟して五裂し,赤色の種子を現す。
 果(サクカ)は熟して五裂し,赤色の種子を現す。
果(サクカ)は熟して五裂し,赤色の種子を現す。
つり-ばな [0] 【釣(り)花・吊り花】🔗⭐🔉
つり-ばな [0] 【釣(り)花・吊り花】
生け花で,花器を天井からつり下げて用いる形式のもの。
つり-はないれ [3] 【釣(り)花入れ】🔗⭐🔉
つり-はないれ [3] 【釣(り)花入れ】
床の間の天井からつり下げて用いる花入れ。唐銅(カラドウ)・砂張(サハリ)・竹・陶磁器などで作り,藤蔓や鎖でつるす。
釣り花入れ
 [図]
[図]
 [図]
[図]
つり-ばり [0] 【釣(り)針・釣り鉤】🔗⭐🔉
つり-ばり [0] 【釣(り)針・釣り鉤】
魚釣りに用いる鉄製の先の曲がった針。型も多様で,擬餌鉤(ギジバリ)など種類が多く,大きさは一般に号数で表す。古くは骨角製のものが用いられた。鉤(ハリ)。
釣り針
 [図]
[図]
 [図]
[図]
つりばり 【釣針】🔗⭐🔉
つりばり 【釣針】
狂言の一。主人と太郎冠者が西宮の夷(エビス)へ詣で,妻を授けてくれるよう祈願し,夢のお告げによって釣り針で釣ると,主人には美女がかかるが,太郎冠者には醜女がかかる。釣女。
つり-ひげ 【釣り鬚】🔗⭐🔉
つり-ひげ 【釣り鬚】
江戸時代,中間・奴などが口ひげの先を上にはね上げたもの。墨で描いたり,作りひげを用いたりもした。
つり-びと [0] 【釣(り)人】🔗⭐🔉
つり-びと [0] 【釣(り)人】
魚を釣る人。
つり-ひも [0][2] 【吊り紐】🔗⭐🔉
つり-ひも [0][2] 【吊り紐】
物をつるすために用いるひも。
つり-ぶね [0] 【釣(り)舟・釣(り)船】🔗⭐🔉
つり-ぶね [0] 【釣(り)舟・釣(り)船】
(1)魚釣りに用いる小舟。また,釣りをしている舟。
(2)舟形の釣り花入れ。
(3)江戸時代から明治初年にかけて行われた婦人の結髪の一種。
釣り舟(3)
 [図]
[図]
 [図]
[図]
つりふね-そう ―サウ [0] 【釣船草】🔗⭐🔉
つりふね-そう ―サウ [0] 【釣船草】
ツリフネソウ科の一年草。山中の水湿地に自生。茎は高さ約50センチメートル,多汁質で紅色を帯びる。葉は広披針形。秋,上方の葉腋から花柄を出し,紅紫色の花を数個つり下げる。花は左右対称で先の巻いた距(キヨ)がある。[季]秋。
釣船草
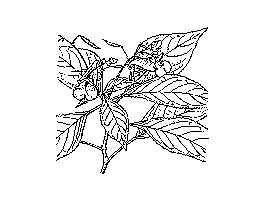 [図]
[図]
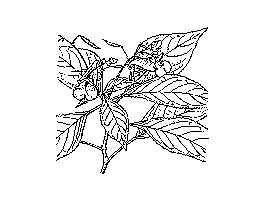 [図]
[図]
大辞林 ページ 149845。