複数辞典一括検索+![]()
![]()
とこなつ-に 【常夏に】 (副)🔗⭐🔉
とこなつ-に 【常夏に】 (副)
いつも変わらず,永遠に。一説に,夏の間を通じてずっと。「新川のその立山に―雪降り敷きて/万葉 4000」
とこ-なつか・し 【常懐し】 (形シク)🔗⭐🔉
とこ-なつか・し 【常懐し】 (形シク)
常に心がひかれる。「なでしこの(ナデシコノ異名「常夏」ニカケテ)―・しき色を見ばもとの垣根を人や尋ねむ/源氏(常夏)」
とこなみ 【床次】🔗⭐🔉
とこなみ 【床次】
姓氏の一。
とこなみ-たけじろう ―タケジラウ 【床次竹二郎】🔗⭐🔉
とこなみ-たけじろう ―タケジラウ 【床次竹二郎】
(1866-1935) 政治家。鹿児島県生まれ。東大卒。原・高橋内閣の内相,犬養内閣の鉄道相,岡田内閣の逓信(テイシン)相を歴任。その間,政権の座を目指して政党遍歴・新党結成を繰り返し,政党政治に混迷をもたらした。
とこ-なめ 【常滑】🔗⭐🔉
とこ-なめ 【常滑】
河床や谷道の岩などに水苔がついていつもなめらかなこと。「妹が門入り泉川の―にみ雪残れり/万葉 1695」
とこなめ 【常滑】🔗⭐🔉
とこなめ 【常滑】
愛知県知多半島の中部西岸にある市。常滑焼で知られ,急須・土管・植木鉢・衛生陶器を多く生産。
とこなめ-やき [0] 【常滑焼】🔗⭐🔉
とこなめ-やき [0] 【常滑焼】
愛知県常滑市に産する陶器。平安・鎌倉頃に始まるといわれ,初め自然釉(シゼンユウ)焼き締めの壺などを焼いたが,のち土管で有名になった。また,朱泥の陶器でも知られる。とこなべやき。
とこぬし-の-かみ [6] 【地主の神】🔗⭐🔉
とこぬし-の-かみ [6] 【地主の神】
その土地を治める神。地主(ジヌシ)の神。
とこ-の-ま [0] 【床の間】🔗⭐🔉
とこ-の-ま [0] 【床の間】
座敷の正面上座に一段高く構え,掛軸・置物・花瓶などを飾る場所。室町時代の押板(オシイタ)と上段を原形として生まれた。ゆかの仕上げにより畳床と板床があり,また形式としては本床・蹴込み床・踏み込み床・洞床(ホラドコ)・袋床・釣り床・織部床・置床などがある。
床の間
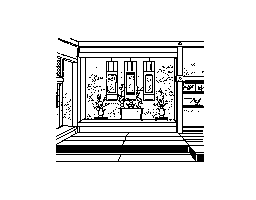 [図]
[図]
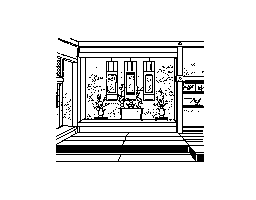 [図]
[図]
大辞林 ページ 150647。