複数辞典一括検索+![]()
![]()
ひしき-もの 【引敷物】🔗⭐🔉
ひしき-もの 【引敷物】
敷物。また,寝具。「思ひあらば葎(ムグラ)の宿に寝もしなむ―には袖をしつつも/伊勢 3」
ひ-しき [3] 【火敷】🔗⭐🔉
ひ-しき [3] 【火敷】
香をたくとき,火を埋めた灰の上におく金属・陶器・玉の薄片。香敷。隔火。
ひ-しき [0] 【非職】🔗⭐🔉
ひ-しき [0] 【非職】
(1)「非蔵人(ヒクロウド)」に同じ。
(2)寺院・神社で,役職にない僧侶や神官。
ひしぎ [0] 【拉ぎ】🔗⭐🔉
ひしぎ [0] 【拉ぎ】
(1)ひしぐこと。「一―に取て伏せ/浄瑠璃・日本振袖始」
(2)(普通「ヒシギ」と書く)能管の最高音域の音。登場の囃子(ハヤシ)の冒頭や全曲の終わりなどに吹かれる鋭くヒィーと鳴る音。
ひじき [1] 【鹿尾菜・羊栖菜】🔗⭐🔉
ひじき [1] 【鹿尾菜・羊栖菜】
褐藻類ヒバマタ目の海藻。北海道南部から九州までの沿岸の潮間帯下部の岩上に生育。主枝は円柱形で,長さ20センチメートル〜1メートル。長さ3〜4センチメートルの小枝を多く出す。根は繊維状根。春から初夏,繁茂し,採集乾燥して食用とする。[季]春。
ひじき-も 【鹿尾菜藻】🔗⭐🔉
ひじき-も 【鹿尾菜藻】
ヒジキの古名。「懸想じける女のもとに,―といふ物をやるとて/伊勢 3」
ひじ-き ヒヂ― [0] 【肘木】🔗⭐🔉
ひじ-き ヒヂ― [0] 【肘木】
(1)社寺建築で,斗(マス)とともに斗 (トキヨウ)を構成する腕木状の水平材。斗,または桁(ケタ)を受ける。位置や施された彫刻によってさまざまな種類がある。
(2)碾(ヒ)き臼(ウス)の取っ手。
肘木(1)
(トキヨウ)を構成する腕木状の水平材。斗,または桁(ケタ)を受ける。位置や施された彫刻によってさまざまな種類がある。
(2)碾(ヒ)き臼(ウス)の取っ手。
肘木(1)
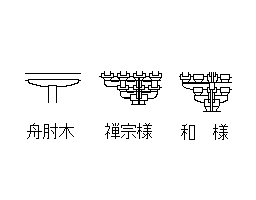 [図]
[図]
 (トキヨウ)を構成する腕木状の水平材。斗,または桁(ケタ)を受ける。位置や施された彫刻によってさまざまな種類がある。
(2)碾(ヒ)き臼(ウス)の取っ手。
肘木(1)
(トキヨウ)を構成する腕木状の水平材。斗,または桁(ケタ)を受ける。位置や施された彫刻によってさまざまな種類がある。
(2)碾(ヒ)き臼(ウス)の取っ手。
肘木(1)
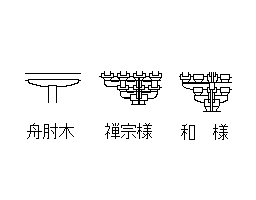 [図]
[図]
ひ-じき 【非色】🔗⭐🔉
ひ-じき 【非色】
禁色(キンジキ)の着用を許されないこと。また,その人。
ひ-じき 【非食】🔗⭐🔉
ひ-じき 【非食】
「非時(ヒジ){(1)}」に同じ。
ひじき-おぼの🔗⭐🔉
ひじき-おぼの
〔「おぼの」は「おもの(御物)」の転〕
殯宮(モガリノミヤ)に供える食事。「此の日―をたてまつる/日本書紀(持統訓)」
びしき-こうぞう ―コウザウ [4] 【 式構造】🔗⭐🔉
式構造】🔗⭐🔉
びしき-こうぞう ―コウザウ [4] 【 式構造】
⇒まぐさしきこうぞう(
式構造】
⇒まぐさしきこうぞう( 式構造)
式構造)
 式構造】
⇒まぐさしきこうぞう(
式構造】
⇒まぐさしきこうぞう( 式構造)
式構造)
大辞林 ページ 152835。