複数辞典一括検索+![]()
![]()
ひなつ-ぼし 【火夏星・ 惑星】🔗⭐🔉
惑星】🔗⭐🔉
ひなつ-ぼし 【火夏星・ 惑星】
火星の異名。けいこく星。なつひぼし。「天の原南にすめる―/夫木 19」
惑星】
火星の異名。けいこく星。なつひぼし。「天の原南にすめる―/夫木 19」
 惑星】
火星の異名。けいこく星。なつひぼし。「天の原南にすめる―/夫木 19」
惑星】
火星の異名。けいこく星。なつひぼし。「天の原南にすめる―/夫木 19」
ひな-どり [2] 【雛鳥】🔗⭐🔉
ひな-どり [2] 【雛鳥】
鳥のひな。特に,ニワトリのひな。
ひな-ながし [3] 【雛流し】🔗⭐🔉
ひな-ながし [3] 【雛流し】
三月三日の雛祭りのあと,雛などを川や海へ流すこと。祓(ハラエ)に使った形代(カタシロ)を流す風習の名残という。流し雛。[季]春。
ひな-にんぎょう ―ニンギヤウ [3] 【雛人形】🔗⭐🔉
ひな-にんぎょう ―ニンギヤウ [3] 【雛人形】
雛祭りに飾る人形。穢(ケガ)れや禍(ワザワイ)を移して流す人形(ヒトガタ)が起源といわれる。平安時代に始まる。江戸時代以降,多く三月三日の桃の節句に飾るようになった。普通,内裏雛・三人官女・五人囃子(バヤシ)・随身(ズイジン)・衛士(エジ)(仕丁(ジチヨウ))などを一組とする。おひなさま。ひな。
雛人形
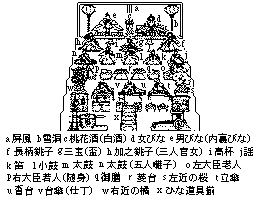 [図]
[図]
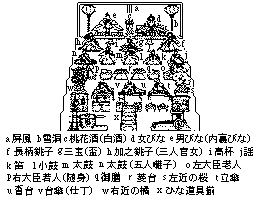 [図]
[図]
ひな-の-うすつぼ [1] 【雛の臼壺】🔗⭐🔉
ひな-の-うすつぼ [1] 【雛の臼壺】
ゴマノハグサ科の多年草。山地に自生。茎は高さ約1メートルで,紫色を帯びる。葉は卵形。八〜一〇月,茎の先に暗紫色で壺形の小花を多数円錐状につける。
ひな-の-しゃくじょう ―シヤクヂヤウ [1]-[0][1]-[2] 【雛の錫杖】🔗⭐🔉
ひな-の-しゃくじょう ―シヤクヂヤウ [1]-[0][1]-[2] 【雛の錫杖】
ヒナノシャクジョウ科の腐生植物。全体が白色の多年草で,暖地の山中の樹下に自生。根茎は塊状。茎は高さ約7センチメートルで,数個の鱗片をまばらに互生。晩夏,茎先に白色の小花を一〇個内外つける。
ひな-の-せっく [1] 【雛の節句】🔗⭐🔉
ひな-の-せっく [1] 【雛の節句】
「雛祭り」に同じ。
ひな-びと [2] 【鄙人】🔗⭐🔉
ひな-びと [2] 【鄙人】
田舎の人。里人。
ひな・びる [3] 【鄙びる】 (動バ上一)[文]バ上二 ひな・ぶ🔗⭐🔉
ひな・びる [3] 【鄙びる】 (動バ上一)[文]バ上二 ひな・ぶ
田舎らしい感じがする。野暮である。いなかびる。「―・びた温泉」「男などの,わざとつくろひ―・びたるは憎し/枕草子 195」
大辞林 ページ 152994。