複数辞典一括検索+![]()
![]()
ひ-の-まる [0] 【日の丸】🔗⭐🔉
ひ-の-まる [0] 【日の丸】
(1)太陽をかたどった丸。古くから,赤色や金色の丸の図様で扇や船印などに用いられた。「―扇」
(2)「日の丸の旗」の略。
ひのまる-ごじょうまい ―ゴジヤウ― 【日の丸御城米】🔗⭐🔉
ひのまる-ごじょうまい ―ゴジヤウ― 【日の丸御城米】
江戸時代,幕府の御城米のこと。廻送に際し必ず船尾に日の丸の幟(ノボリ)を立てて幕府の御用船である表示としたことからの称。
ひのまる-の-はた [7] 【日の丸の旗】🔗⭐🔉
ひのまる-の-はた [7] 【日の丸の旗】
(1)白地に赤い丸を描いた旗。
(2)日章旗のこと。
ひのまる-のぼり [5] 【日の丸幟】🔗⭐🔉
ひのまる-のぼり [5] 【日の丸幟】
白地の布に赤い日の丸を描いた幟。中世から八幡船などに用いられ,1854年(安政1)には江戸幕府が日本の船はこの印の幟とすることを定めた。
ひのまる-べんとう ―タウ [5] 【日の丸弁当】🔗⭐🔉
ひのまる-べんとう ―タウ [5] 【日の丸弁当】
〔外観や配色が日の丸の旗に似るところから〕
御飯のまん中に梅干しを一個だけ入れた弁当。
ひ-の-まわり ―マハリ 【火の回り】🔗⭐🔉
ひ-の-まわり ―マハリ 【火の回り】
火が燃え広がっていくこと。火回り。火足。「―が早い」
ひ-の-み [0][3] 【火の見】🔗⭐🔉
ひ-の-み [0][3] 【火の見】
「火の見櫓(ヤグラ)」の略。
ひのみ-ばしご [4] 【火の見梯子】🔗⭐🔉
ひのみ-ばしご [4] 【火の見梯子】
火事の方向や場所を見定めるために設けた梯子。頂上に半鐘をつるし,番人が打ち鳴らして火事を知らせた。
ひのみ-ばん [3] 【火の見番】🔗⭐🔉
ひのみ-ばん [3] 【火の見番】
火の見櫓で見張りをすること。また,その人。火の見番人。
ひのみ-やぐら [4] 【火の見櫓】🔗⭐🔉
ひのみ-やぐら [4] 【火の見櫓】
火災を早く発見するために,遠方まで見渡せるように高く立てた櫓。望火楼。火の見。
火の見櫓
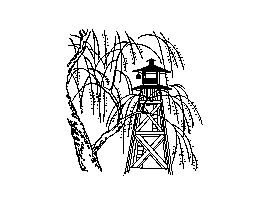 [図]
[図]
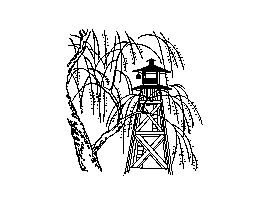 [図]
[図]
ひ-の-みかげ 【日の御蔭】🔗⭐🔉
ひ-の-みかげ 【日の御蔭】
(1)〔日をおおってかげをなす所の意〕
宮殿や殿舎の壮大さをほめたたえていう語。あまのみかげ。「天の御蔭―と隠りまして/祝詞(祈年祭)」
(2)日の神,すなわち天照大神(アマテラスオオミカミ)の威徳。「宮柱したつ磐根(イワネ)にしきたてて露もくもらぬ―かな/新古今(神祇)」
大辞林 ページ 153012。