複数辞典一括検索+![]()
![]()
ふくよう-ご [0] 【副用語】🔗⭐🔉
ふくよう-ご [0] 【副用語】
文の骨子となる体言・用言に依存し,それにさまざまな意味をつけくわえる語。副詞・連体詞・接続詞・感動詞など。語形変化がなく,連用または連体のいずれか一方の機能をもち,実質概念の希薄な語の総称として用いられる。
ふく-よか [2] 【膨よか・脹よか】 (形動)[文]ナリ🔗⭐🔉
ふく-よか [2] 【膨よか・脹よか】 (形動)[文]ナリ
(1)柔らかそうにふっくらとしているさま。ふくやか。ふくらか。「―な顔」「年とともに―になってきた」
(2)豊かな香りを漂わすさま。「―な新茶の香り」
[派生] ――さ(名)
ふくら [0] 【膨ら・脹ら】🔗⭐🔉
ふくら [0] 【膨ら・脹ら】
■一■ (名)
(1)柔らかにふくらんでいること。また,ふくらんでいる物や部分。
(2)物の中心の部分。中央。「物ふかう勢の―を隠し備へし所に/太閤記」
(3)一張りの弓の長さ。一ふくらは七尺五寸(約2.3メートル)。弓場の間(ケン)数を測る時に用いる。
■二■ (形動)[文]ナリ
ふっくらしているさま。ふくよか。ふくらか。「…と云ふ口許こそ―なりけれ/婦系図(鏡花)」
ふくら-しば [3] 【膨ら柴】🔗⭐🔉
ふくら-しば [3] 【膨ら柴】
ソヨゴの別名。
ふくら-すずめ [4] 【脹雀・福良雀】🔗⭐🔉
ふくら-すずめ [4] 【脹雀・福良雀】
(1)肥え太った雀。また,寒気のために羽をふくらましている雀。
(2)家紋・文様の一。{(1)}が羽をのばした姿を図案化したもの。
(3)女性の髪の結い方の一。唐人髷(マゲ)を変形したもので,髷を左右に二つつくる。江戸末期以降,一〇代の少女が結った。{(2)}に似ているところからの名。
(4)女帯の結び方。お太鼓に似て,結びの両端をはねのように出すもの。振袖・訪問着などに用いる。
(5)ヤガの一種。体は太い。はねは褐色で,前ばねには黒斑が,後ろばねには青色の紋がある。日本全土のほかアジアに分布。
(6)日本刀の切っ先の刃がふくらみを帯びているもの。
脹雀(3)
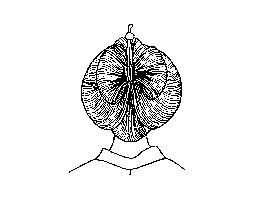 [図]
脹雀(4)
[図]
脹雀(4)
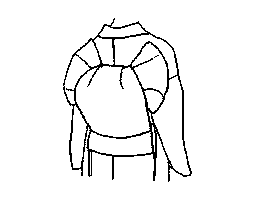 [図]
[図]
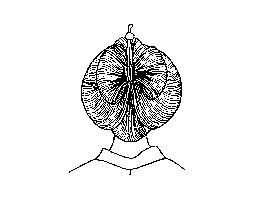 [図]
脹雀(4)
[図]
脹雀(4)
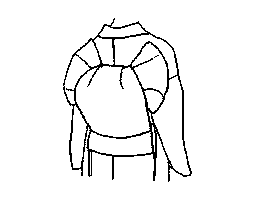 [図]
[図]
大辞林 ページ 153425。