複数辞典一括検索+![]()
![]()
ほろ [1] 【母衣】🔗⭐🔉
ほろ [1] 【母衣】
鎧(ヨロイ)の背につける幅広の布。流れ矢を防ぎ,また,旗指物の一種としても用いられた。平安時代には単に背に垂らし,時に下端を腰に結んだが,のちには竹籠(タケカゴ)を入れた袋状のものとなった。
母衣
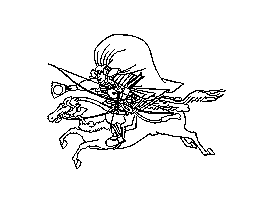 [図]
[図]
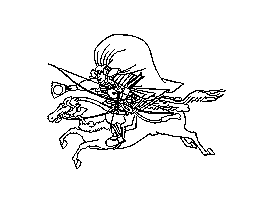 [図]
[図]
ほ-ろ 【保呂】🔗⭐🔉
ほ-ろ 【保呂】
「保呂羽(ホロバ)」の略。「―の風切りはいだる矢負はせて/平家 4」
ほろ (副)🔗⭐🔉
ほろ (副)
(多く「と」を伴って)
(1)涙のほろりと落ちるさま。「―と泣いたる可愛さ/浄瑠璃・平家女護島」
(2)雉(キジ)・山鳥・ほととぎすなどの鳴き声を表す語。「いづれ山ぢのほととぎす,―とないたをいつ
 わすれう/浄瑠璃・吉野忠信」
わすれう/浄瑠璃・吉野忠信」

 わすれう/浄瑠璃・吉野忠信」
わすれう/浄瑠璃・吉野忠信」
ほろ (接頭)🔗⭐🔉
ほろ (接頭)
名詞・形容詞などに付いて,すこし,なんとなくなどの意を表す。「―酔い」「―にがい」
ぼろ [1] 【襤褸】🔗⭐🔉
ぼろ [1] 【襤褸】
■一■ (名)
(1)使い古して役に立たなくなった布。ぼろぎれ。「くず屋に―を出す」
(2)着古して破れた衣服。つぎはぎをしてむさくるしい衣服。「―をまとう」
(3)つたない箇所。欠点。失敗。「余りしゃべると―が出る」「―をかくす」
■二■ (名・形動)
古くなったり,壊れたりして役にたたない・こと(さま)。ぼろぼろ。「―の自転車」「―靴」
ぼろ🔗⭐🔉
ぼろ
〔形容詞「ぼろい」の語幹から〕
動詞の連用形から転じた名詞の上に付いて,程度のはなはだしい意を表す。「―儲(モウ)け」「―勝ち」「―負け」
ぼろ [1] 【梵論・暮露】🔗⭐🔉
ぼろ [1] 【梵論・暮露】
有髪の乞食坊主の一種。中世末期にはその中から尺八を吹く薦僧(コモソウ)(虚無僧(コムソウ)の前身)が現れたので,薦僧・虚無僧の異名としても用いられた。ぼろぼろ。梵論子(ボロンジ)。梵字(ボンジ)。「もしこの御中にいろをし房と申す―やおはします/徒然 115」
ポロ [1]  polo
polo 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ポロ [1]  polo
polo 馬に乗り,マレット(先が T 字型になっている杖)でボールを打って相手のゴールに入れる競技。一チーム四名から成る。
ポロ
馬に乗り,マレット(先が T 字型になっている杖)でボールを打って相手のゴールに入れる競技。一チーム四名から成る。
ポロ
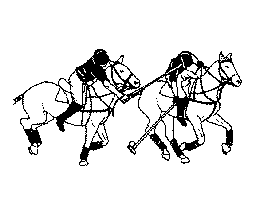 [図]
[図]
 polo
polo 馬に乗り,マレット(先が T 字型になっている杖)でボールを打って相手のゴールに入れる競技。一チーム四名から成る。
ポロ
馬に乗り,マレット(先が T 字型になっている杖)でボールを打って相手のゴールに入れる競技。一チーム四名から成る。
ポロ
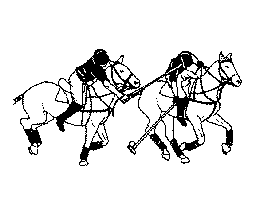 [図]
[図]
大辞林 ページ 154519。