複数辞典一括検索+![]()
![]()
まつまえ マツマヘ 【松前】🔗⭐🔉
まつまえ マツマヘ 【松前】
北海道渡島(オシマ)半島南端にある町。一五世紀半ばに武田信広がこの地を平定,五代慶広が福山城を築き,松前氏を称して城下町とした。江戸時代,蝦夷(エゾ)地経営の中心地。
まつまえ-づけ マツマヘ― [0] 【松前漬(け)】🔗⭐🔉
まつまえ-づけ マツマヘ― [0] 【松前漬(け)】
細切りのするめ・昆布・人参などに数の子を加えて調味し,漬け込んだ食品。
まつまえ-はんとう マツマヘ―タウ 【松前半島】🔗⭐🔉
まつまえ-はんとう マツマヘ―タウ 【松前半島】
北海道南西部,渡島(オシマ)半島南西部,津軽海峡に突出する半島。大千軒岳・前千軒岳があり,南端は白神岬。青函トンネルの北海道側入り口。
まつまえ-ぶぎょう マツマヘ―ギヤウ [5] 【松前奉行】🔗⭐🔉
まつまえ-ぶぎょう マツマヘ―ギヤウ [5] 【松前奉行】
江戸幕府の遠国(オンゴク)奉行の一。老中支配。蝦夷(エゾ)地の行政・海防・開拓などを扱った。1802年蝦夷奉行として箱館に創置,07年松前奉行と改められ,役所も松前に移った。21年松前藩の復封にあたって廃止。
→箱館奉行
まつ-むかえ ―ムカヘ [3] 【松迎え】🔗⭐🔉
まつ-むかえ ―ムカヘ [3] 【松迎え】
門松など正月に飾る松を,年の暮れに山野からとってくること。正月様迎え。
まつ-むし [2] 【松虫】🔗⭐🔉
まつ-むし [2] 【松虫】
(1)コオロギ科の昆虫。体長23ミリメートル内外。頭は小さく,体は舟形で後肢が長く,全体が淡褐色。草原・林にすみ,成虫は八〜一一月に出現する。雄はチンチロリンと美しく鳴く。古来,鳴く虫の代表として親しまれた。本州以南の各地と中国・東南アジアに分布。[季]秋。《人は寝て籠の―鳴き出でぬ/正岡子規》
(2)スズムシの古名。平安時代,マツムシとスズムシの名称は現在と反対であったといわれる。「虫は,鈴虫,ひぐらし,蝶,―,きりぎりす/枕草子 43」
(3)歌舞伎の下座音楽に用いられる楽器。小形の伏せ鉦(ガネ)。六部の出や寂しい寺院などに用いられる。
松虫(1)
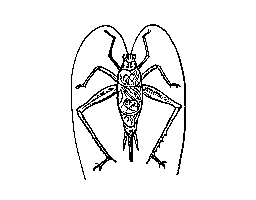 [図]
[図]
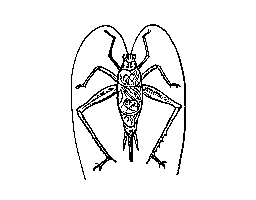 [図]
[図]
まつむし-そう ―サウ [0] 【松虫草】🔗⭐🔉
まつむし-そう ―サウ [0] 【松虫草】
マツムシソウ科の多年草。山中の草地に生える。高さ約50センチメートル。葉は羽状に分裂。秋,径約5センチメートルの青紫色の頭花をつける。花序の中央にある花は小さく,周囲の花は唇形で大きい。リンボウギク。[季]秋。
松虫草
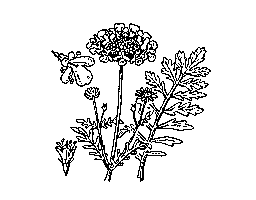 [図]
[図]
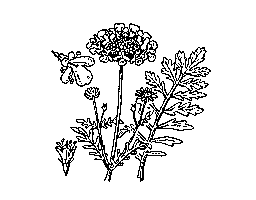 [図]
[図]
大辞林 ページ 154805。