複数辞典一括検索+![]()
![]()
みし-と 【緊と】 (副)🔗⭐🔉
みし-と 【緊と】 (副)
強く力を入れてするさま。しっかと。「立ちながらきぬごしに―いだきて/著聞 8」
み-しね 【御稲】🔗⭐🔉
み-しね 【御稲】
稲の美称。「ささなみや滋賀の辛崎や―搗(ツ)く女の佳ささや/神楽歌」
みしはせ 【粛慎】🔗⭐🔉
みしはせ 【粛慎】
⇒しゅくしん(粛慎)
み-しぶ [0] 【水渋】🔗⭐🔉
み-しぶ [0] 【水渋】
「水銹(ミサビ)」に同じ。
み-しほ 【御修法】🔗⭐🔉
み-しほ 【御修法】
〔「みしゅほう(御修法)」の転〕
「みずほう(御修法)」に同じ。
みしま 【三島】🔗⭐🔉
みしま 【三島】
(1)静岡県東部の市。古代,伊豆国府の地。三島大社の門前町,東海道の宿場町から発展。電気・機械・ゴム工業が盛ん。
(2)大阪府北部の郡。島本町一町が属す。もと摂津国北東部を占め,高槻・茨木・摂津など淀川西岸の各市を含んだ。「三島江」などの形で和歌に詠まれた。((歌枕))「―江の玉江の菰(コモ)を標しめしより/万葉 1348」
みしま-ごよみ [4] 【三島暦】🔗⭐🔉
みしま-ごよみ [4] 【三島暦】
三島大社の下社家である河合家から毎年発行された細字書きの仮名の暦。室町時代に始まり,江戸時代には幕府の許可を得て伊豆・相模の二国に限り頒布された。明治維新まで続いた。
みしま-さいこ [4] 【三島柴胡】🔗⭐🔉
みしま-さいこ [4] 【三島柴胡】
セリ科の多年草。山中の草地に生える。高さ約1メートルで,狭披針形の葉を互生。秋,黄色の小花が花軸の先にむらがってつく。根は解熱・鎮痛薬にされる。和名は静岡県三島がこの取引地であったための名。漢名,柴胡。
みしま-たいしゃ 【三島大社】🔗⭐🔉
みしま-たいしゃ 【三島大社】
静岡県三島市にある神社。祭神は事代主神(コトシロヌシノカミ)・大山祇神(オオヤマツミノカミ)。三島神社。
みしま-で [3] 【三島手】🔗⭐🔉
みしま-で [3] 【三島手】
高麗(コウライ)茶碗の一。三島暦の文字の趣に似た,縄目のような文様があるのでいう。李朝初期から中期にかけて焼かれた。水差し・茶碗などに多い。
三島手
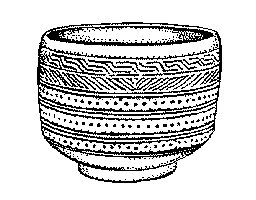 [図]
[図]
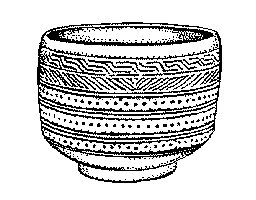 [図]
[図]
みしま 【三島】🔗⭐🔉
みしま 【三島】
姓氏の一。
大辞林 ページ 155017。