複数辞典一括検索+![]()
![]()
むらご-の-おどし ―ヲドシ 【斑濃の縅】🔗⭐🔉
むらご-の-おどし ―ヲドシ 【斑濃の縅】
鎧(ヨロイ)の縅の一。濃淡がまだらになっているもの。また,種々の色の糸で縅したもの。斑濃。色色叢濃。
むらさき [2] 【紫】🔗⭐🔉
むらさき [2] 【紫】
(1)ムラサキ科の多年草。山野に自生する。全体に粗毛があり,根は太く,茎は高さ約50センチメートルで上方で分枝。葉は披針形。夏,上方の葉腋(ヨウエキ)に白花を数個つける。根は乾くと紫色となり,古くから紫色の染料とするほか,漢方で解熱・解毒の薬,皮膚病の薬などに用いる。紫草。
(2){(1)}の根で染め出した色。
(3)「紫色」の略。
(4)醤油のこと。
(5)〔女房詞〕
イワシ。
紫(1)
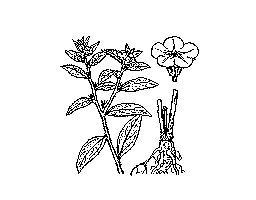 [図]
[図]
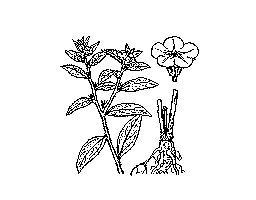 [図]
[図]
――の朱(アケ)を奪う🔗⭐🔉
――の朱(アケ)を奪う
〔「論語(陽貨)」中間色の紫が正色の朱を濁らせる意から〕
佞者(ネイシヤ)の言葉が用いられ,正論が疎んぜられること。また,似てはいるが全く違うこと。
むらさき-いがい ―ガヒ [5] 【紫貽貝】🔗⭐🔉
むらさき-いがい ―ガヒ [5] 【紫貽貝】
海産の二枚貝。貝殻は三角に近い長楕円形で,殻長9センチメートルほど。殻が薄く,光沢のある黒紫色。食用。太平洋・大西洋の北部の浅海に広く分布。
→ムール貝
むらさき-いろ [0] 【紫色】🔗⭐🔉
むらさき-いろ [0] 【紫色】
色名の一。赤と青の中間の色の総称。また,紫草の根で染めた色。パープル。「皮膚が―にはれあがる」
むらさき-うに [5] 【紫海胆】🔗⭐🔉
むらさき-うに [5] 【紫海胆】
ウニの一種。直径5センチメートル内外。体はやや扁平な半球形で,長さ4センチメートルほどのとげが密生する。全体が紫黒色。潮間帯の岩礁などに多い。卵巣は食用。北海道南部から台湾にかけて分布。
むらさき-うまごやし [7] 【紫馬肥】🔗⭐🔉
むらさき-うまごやし [7] 【紫馬肥】
アルファルファの別名。
むらさき-えもん ― ― [5] 【紫衛門】🔗⭐🔉
― [5] 【紫衛門】🔗⭐🔉
むらさき-えもん ― ― [5] 【紫衛門】
〔明治時代,女学生の袴(ハカマ)は紫色が多かったので,平安の歌人赤染衛門(アカゾメエモン)をもじっていう〕
女学生の異名。
― [5] 【紫衛門】
〔明治時代,女学生の袴(ハカマ)は紫色が多かったので,平安の歌人赤染衛門(アカゾメエモン)をもじっていう〕
女学生の異名。
 ― [5] 【紫衛門】
〔明治時代,女学生の袴(ハカマ)は紫色が多かったので,平安の歌人赤染衛門(アカゾメエモン)をもじっていう〕
女学生の異名。
― [5] 【紫衛門】
〔明治時代,女学生の袴(ハカマ)は紫色が多かったので,平安の歌人赤染衛門(アカゾメエモン)をもじっていう〕
女学生の異名。
大辞林 ページ 155400。