複数辞典一括検索+![]()
![]()
もく-う [1] 【沐雨】🔗⭐🔉
もく-う [1] 【沐雨】
雨で身を洗うこと。
→櫛風(シツプウ)沐雨
もく-か ―クワ [0] 【木化】🔗⭐🔉
もく-か ―クワ [0] 【木化】
⇒もっか(木化)
もく-が ―グワ [0] 【木画】🔗⭐🔉
もく-が ―グワ [0] 【木画】
工芸品や家具などの表面装飾法の一。木象眼を用いて絵のように文様を表したもの。もくえ。
もく-かい ―クワイ [0] 【黙会】🔗⭐🔉
もく-かい ―クワイ [0] 【黙会】
⇒もっかい(黙会)
もく-ガス [0][3] 【木―】🔗⭐🔉
もく-ガス [0][3] 【木―】
木材を乾留するとき生ずる可燃性ガス。一酸化炭素・メタンなどを含む。
もく-かん [0] 【木簡】🔗⭐🔉
もく-かん [0] 【木簡】
⇒もっかん(木簡)
もくぎゅう-りゅうば モクギウリウバ [5] 【木牛流馬】🔗⭐🔉
もくぎゅう-りゅうば モクギウリウバ [5] 【木牛流馬】
中国,蜀の諸葛孔明が創案したといわれる兵糧運搬用の車。牛馬にかたどり,機械仕掛けで運行する。ぼくぎゅうりゅうば。
もく-きょ [1] 【黙許】🔗⭐🔉
もく-きょ [1] 【黙許】
⇒もっきょ(黙許)
もく-ぎょ [1] 【木魚】🔗⭐🔉
もく-ぎょ [1] 【木魚】
経を読む時にたたく木製の仏具。ほぼ球形で中空,横に割れ目があり,魚の鱗(ウロコ)が彫りつけられている。禅寺で合図に打ち鳴らす魚板(ギヨバン)から変化したもの。
木魚
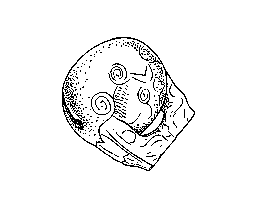 [図]
[図]
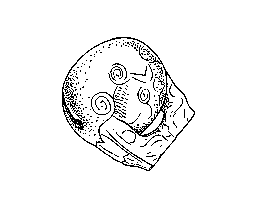 [図]
[図]
もくぎょ-いり-あいかた ―アヒカタ [6] 【木魚入り合方】🔗⭐🔉
もくぎょ-いり-あいかた ―アヒカタ [6] 【木魚入り合方】
下座音楽の一。寺・墓場・寂しい野原の場面などで,人物の出入りに用いる,木魚を加えた合方。
もくぎょ-こう ―カウ [0] 【木魚講】🔗⭐🔉
もくぎょ-こう ―カウ [0] 【木魚講】
江戸後期,葬儀の費用に当てる目的で組織された講。葬儀の際,先達が大きな木魚を首からつるして打ち鳴らし,講中の者が念仏を唱えながら野辺送りをした。
もく-ぐう [0] 【木偶】🔗⭐🔉
もく-ぐう [0] 【木偶】
木でつくった人形。でく。
もくげ [0] 【木槿】🔗⭐🔉
もくげ [0] 【木槿】
⇒むくげ(木槿)
もく-けい [0] 【木契】🔗⭐🔉
もく-けい [0] 【木契】
⇒もっけい(木契)
もく-げい [0] 【目迎】 (名)スル🔗⭐🔉
もく-げい [0] 【目迎】 (名)スル
その人の来る方向に視線を向けて,迎えること。「―目送する」
大辞林 ページ 155616。