複数辞典一括検索+![]()
![]()
よしわら-かぶり ヨシハラ― [5] 【吉原被り】🔗⭐🔉
よしわら-かぶり ヨシハラ― [5] 【吉原被り】
手ぬぐいを二つに折って頭にのせ,その両端を髷(マゲ)の後ろで結んだかぶり方。遊里での芸人や新内流しなどが用いた。
吉原被り
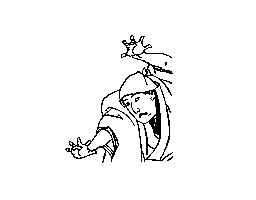 [図]
[図]
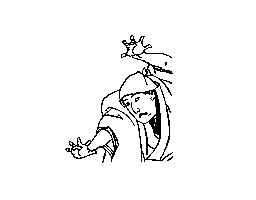 [図]
[図]
よしわら-ことば ヨシハラ― [5] 【吉原言葉】🔗⭐🔉
よしわら-ことば ヨシハラ― [5] 【吉原言葉】
(1)江戸吉原の遊女などが用いた独特の言葉づかい。「あります」を「ありんす」という類。ありんすことば。
(2)知っていることでも知らないふりをして人にたずねるなど,万事あどけなく見せることをいう。「まんざら知りきつてゐる事をも知らぬ風(フリ)で物を尋ねる,諸事あどけなく見せるを俗に―と云ひやす/滑稽本・浮世床 2」
よしわら-さいけん ヨシハラ― [5] 【吉原細見】🔗⭐🔉
よしわら-さいけん ヨシハラ― [5] 【吉原細見】
⇒細見(サイケン)(3)
よしわら-すずめ ヨシハラ― 【吉原雀】🔗⭐🔉
よしわら-すずめ ヨシハラ― 【吉原雀】
(1) [5]
吉原の遊郭に出入りしてその内情にくわしい者のこと。さとすずめ。また,吉原の素見(スケン)客。「―の觜(クチバシ)を閉ぢんと/洒落本・辰巳之園」
(2)歌舞伎舞踊の一。長唄。本名題「教草(オシエグサ)吉原雀」。初世桜田治助作詞。1768年江戸市村座初演。男鳥売,実は八幡太郎義家,女鳥売,実は鷹の精による郭(クルワ)気分の横溢した踊り。清元の改作は「筐花手向橘(カタミノハナムカシノソデノカ)」。
よしわら-にわか ヨシハラニハカ [5] 【吉原俄】🔗⭐🔉
よしわら-にわか ヨシハラニハカ [5] 【吉原俄】
吉原遊郭中の稲荷祭などで郭(クルワ)の芸人・禿(カムロ)・若い衆などが行なった即興寸劇。明和(1764-1772)〜天明(1781-1789)頃盛んで,毎年8月に行なった。
よしわら-の-たいか ヨシハラ―タイクワ 【吉原の大火】🔗⭐🔉
よしわら-の-たいか ヨシハラ―タイクワ 【吉原の大火】
1911年(明治44)4月,浅草吉原の遊廓から出火して山谷堀・千束町・南千住に延焼,二三町約六五〇〇戸を焼いた火事。
よしわら-ようじ ヨシハラヤウ― [5] 【吉原楊枝】🔗⭐🔉
よしわら-ようじ ヨシハラヤウ― [5] 【吉原楊枝】
総(フサ)の長い歯磨き楊枝。吉原の遊郭で用いたのでいう。
よし-わるし [3] 【善し悪し】🔗⭐🔉
よし-わるし [3] 【善し悪し】
「よしあし」に同じ。「世話をやきすぎるのも―だ」
大辞林 ページ 156378。