複数辞典一括検索+![]()
![]()
よめ-とり [4][0] 【嫁取り】🔗⭐🔉
よめ-とり [4][0] 【嫁取り】
嫁を迎えること。また,その儀式。
よめ-な [0] 【嫁菜】🔗⭐🔉
よめ-な [0] 【嫁菜】
キク科の多年草。やや湿った草地に生え,根茎は長い。高さ約50センチメートルで,葉は披針形。秋,枝端に淡青紫色の頭花をつける。春の若葉は食用となり,古くから摘み草の対象として知られる。古名オハギ。[季]春。
〔「嫁菜の花」は [季]秋〕
嫁菜
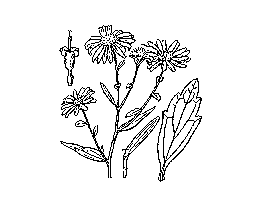 [図]
[図]
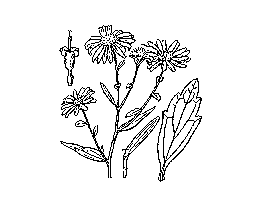 [図]
[図]
よめ-の-ごき [4] 【嫁の合器】🔗⭐🔉
よめ-の-ごき [4] 【嫁の合器】
(1)植物ゴキヅルの異名。
(2)ドングリなどのへたをいう。「頼政は―までひろひこみ/柳多留 24」
よめ-の-さら [0] 【嫁の皿】🔗⭐🔉
よめ-の-さら [0] 【嫁の皿】
ヨメガカサの別名。
よめ-ひろめ [3] 【嫁広め】🔗⭐🔉
よめ-ひろめ [3] 【嫁広め】
嫁を人々に披露すること。
よめ-むかえ ―ムカヘ [3] 【嫁迎え】🔗⭐🔉
よめ-むかえ ―ムカヘ [3] 【嫁迎え】
嫁を迎えること。
よめら・す [3] 【嫁らす】 (動サ五[四])🔗⭐🔉
よめら・す [3] 【嫁らす】 (動サ五[四])
〔「よめいらす」の転〕
嫁入りさせる。「ある知人の娘を同じくある知人の家に―・した/行人(漱石)」
よめ・る 【嫁入る】 (動ラ四)🔗⭐🔉
よめ・る 【嫁入る】 (動ラ四)
「よめいる」の転。「娘おいくを,半四郎かたへ―・らせけるに/浮世草子・娘容気」
よ・める [2] 【読める】 (動マ下一)🔗⭐🔉
よ・める [2] 【読める】 (動マ下一)
〔「読む」の可能動詞形から〕
(1)読む価値がある。「これはちょっと―・める小説だ」
(2)その意味が理解できる。心がわかる。さとる。「君の考えは―・めた」
よ-も [1] 【四方】🔗⭐🔉
よ-も [1] 【四方】
(1)東西南北。前後左右。しほう。「―を見わたす」
(2)あちらこちら。諸方。「―の山々」
よも [1] (副)🔗⭐🔉
よも [1] (副)
(下に打ち消しの語を伴って)まさか。よもや。「手前ばかりでは―あるまい/怪談牡丹灯籠(円朝)」
よもぎ [0] 【蓬・艾】🔗⭐🔉
よもぎ [0] 【蓬・艾】
(1)キク科の多年草。各地の山野に見られ,高さ約1メートル。葉は楕円形で羽状に深裂し,裏に白毛がある。若葉は特に香りがあり,餅に搗(ツ)き込んで草餅とするので餅草ともいう。秋,茎頂に小頭花を円錐状につけ,生長した葉から灸に用いる「もぐさ」を作る。[季]春。
(2)襲(カサネ)の色目の名。表は淡萌黄(モエギ),裏は濃い萌黄,また,表白,裏青とも。夏着用。
蓬(1)
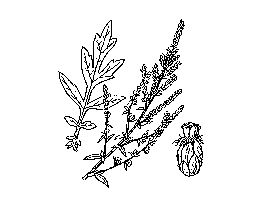 [図]
[図]
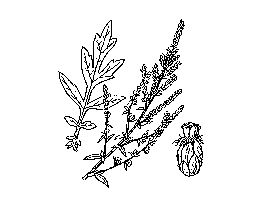 [図]
[図]
大辞林 ページ 156441。