複数辞典一括検索+![]()
![]()
いつ【五】🔗⭐🔉
いつ [1] 【五】
(1)数のいつつ。ご。多く名詞の上に付いて接頭語的に用いられる。「―柱」「―文字」
(2)ご。いつつ。数を数えるときに用いる。「―,む,なな,や」
いつ【厳・稜威】🔗⭐🔉
いつ 【厳・稜威】
(1)神聖であること。斎(イ)み清められていること。「―の真屋に麁草(アラクサ)を―の席(ムシロ)と苅り敷きて/祝詞(出雲国造神賀詞)」
(2)勢いの激しいこと。威力が強いこと。「―の男建(オタケビ)踏み建(タケ)びて/古事記(上)」
いつ【佚】🔗⭐🔉
いつ 【佚】
楽をすること。
いつ【何時】🔗⭐🔉
いつ [1] 【何時】 (代)
(1)不定称の指示代名詞。不定の時を表す。物事の行われたとき,あるいは行われるときがわからなかったり,はっきりしなかったりすることを表す。「―できるか」「今月の―がいいか」「―になったら晴れるのか」
(2)いつものとき。普段。「―の年よりも雨が少ない」「―になく沈んだようす」
い・つ【凍つ・冱つ】🔗⭐🔉
い・つ 【凍つ・冱つ】 (動タ下二)
⇒いてる
いつ-いつ【何時何時】🔗⭐🔉
いつ-いつ [1][0] 【何時何時】 (代)
(1)何月何日,何日の何時などがはっきりしないとき,また,それらをはっきり言わないときに用いる語。「締め切りは―と決める」
(2)いつものとき。普段。「今朝は―より斎(トキ)をとりつくろうて/狂言・若市」
いついつ-までも【何時何時迄も】🔗⭐🔉
いついつ-までも [1][5] 【何時何時迄も】 (副)
「いつまでも」を強めた言い方。永久に。「―お元気で」
い-つう【胃痛】🔗⭐🔉
い-つう  ― [0] 【胃痛】
胃の痛み。
― [0] 【胃痛】
胃の痛み。
 ― [0] 【胃痛】
胃の痛み。
― [0] 【胃痛】
胃の痛み。
いつ-え【五重】🔗⭐🔉
いつ-え ―ヘ [2] 【五重】
(1)五枚重ねること。ごじゅう。
(2)「五重襲(イツエガサネ)」に同じ。
(3)「五重の扇(オウギ)」の略。
いつえ-がさね【五重襲】🔗⭐🔉
いつえ-がさね ―ヘ― [4] 【五重襲】
袿(ウチキ)を五枚重ねて着ること。また,袖口と褄(ツマ)に中陪(ナカベ)を加えて,五枚重ね着したように見せたもの。
いつえ-の-おうぎ【五重の扇】🔗⭐🔉
いつえ-の-おうぎ ―ヘ―アフギ 【五重の扇】
板数七,八枚を一重扇というのに対し,その五倍ほどの板数のある檜扇(ヒオウギ)。
いつえ-の-からぎぬ【五重の唐衣】🔗⭐🔉
いつえ-の-からぎぬ ―ヘ― 【五重の唐衣】
五重襲(イツエガサネ)の唐衣。
いつ-か【五日】🔗⭐🔉
いつ-か [3][0] 【五日】
(1)五つの日数。五日間。
(2)月の第五日目。
(3)五月五日。端午(タンゴ)の節句の日。
〔副詞的用法の場合,アクセントは [0]〕
いつか-がえり【五日帰り】🔗⭐🔉
いつか-がえり ―ガヘリ 【五日帰り】
近世,結婚式後,五日目に里帰りした習俗。「―の花嫁としやなら
 と振りかけて/浄瑠璃・吉野都女楠」
と振りかけて/浄瑠璃・吉野都女楠」

 と振りかけて/浄瑠璃・吉野都女楠」
と振りかけて/浄瑠璃・吉野都女楠」
いつか-の-かぜ【五日の風】🔗⭐🔉
いつか-の-かぜ 【五日の風】
〔論衡(是応)〕
五日に一度風が吹き,十日に一度雨が降ること。気候が順調なさま。「―静かなれば早仕舞の牌(フダ)を出さず。十日の雨穏やかなれば…/滑稽本・浮世風呂(前)」
いつか-の-せちえ【五日の節会】🔗⭐🔉
いつか-の-せちえ ―セチ 【五日の節会】
奈良時代以後,宮中で五月五日に行われた節会。菖蒲(アヤメ)を鬘(カズラ)に挿した臣下が,武徳殿に出御した天皇に菖蒲を献上し,天皇からは薬玉(クスダマ)が下賜される。そののち騎射の御覧があり,宴を行う。平安後期には衰えた。いつかのせち。
【五日の節会】
奈良時代以後,宮中で五月五日に行われた節会。菖蒲(アヤメ)を鬘(カズラ)に挿した臣下が,武徳殿に出御した天皇に菖蒲を献上し,天皇からは薬玉(クスダマ)が下賜される。そののち騎射の御覧があり,宴を行う。平安後期には衰えた。いつかのせち。
 【五日の節会】
奈良時代以後,宮中で五月五日に行われた節会。菖蒲(アヤメ)を鬘(カズラ)に挿した臣下が,武徳殿に出御した天皇に菖蒲を献上し,天皇からは薬玉(クスダマ)が下賜される。そののち騎射の御覧があり,宴を行う。平安後期には衰えた。いつかのせち。
【五日の節会】
奈良時代以後,宮中で五月五日に行われた節会。菖蒲(アヤメ)を鬘(カズラ)に挿した臣下が,武徳殿に出御した天皇に菖蒲を献上し,天皇からは薬玉(クスダマ)が下賜される。そののち騎射の御覧があり,宴を行う。平安後期には衰えた。いつかのせち。
いつ-か【何時か】🔗⭐🔉
いつ-か [1] 【何時か】 (副)
はっきりその時と指定できない不定の時や漠然とした時などを表す。
(1)昔のある時。いつだったか。いつぞや。「―来たことがある」「―読んだはず」
(2)未来のある時。そのうち。いずれ。「―会えるだろう」「―解決する」
(3)いつの間にか。いつしか。「―夜もあけていた」
いつか-しら【何時か知ら】🔗⭐🔉
いつか-しら [0][1] 【何時か知ら】 (副)
〔「いつか知らぬ」の転〕
(1)いつの間にか。知らないうちに。「―雨が降り出していた」
(2)近い将来。そのうちに。いつかは。「―わかってくれる時も来るだろう」
いつか-は【何時かは】🔗⭐🔉
いつか-は [1] 【何時かは】 (副)
(1)不定の時を表す。いつかそのうち。「―帰ってくるに違いない」
(2)疑問の意を表す。いつになったら。「浮世をば出づる日ごとに厭へども―月の入る方を見む/新古今(雑下)」
(3)反語の意を表す。いつ…することがあろうか,決してない。「君をのみ思ひ越路の白山は―雪の消ゆる時ある/古今(雑下)」
いつ-がい【乙亥】🔗⭐🔉
いつ-がい [0] 【乙亥】
干支(エト)の一。きのとい。
いつかいち【五日市】🔗⭐🔉
いつかいち 【五日市】
東京都あきる野市の地名。旧町名。多摩川支流の秋川流域を占める。
いつかいち-けんぽう【五日市憲法】🔗⭐🔉
いつかいち-けんぽう ―パフ 【五日市憲法】
1880,81年頃,千葉卓三郎によって起草された民主的憲法草案。詳細な人権規定をもつもので,五日市の豪農深沢家の援助の下,五日市学芸講談会による共同研究と討論を背景に作られた。
いつかいち-せん【五日市線】🔗⭐🔉
いつかいち-せん 【五日市線】
JR 東日本の鉄道線。東京都拝島と武蔵五日市間,11.1キロメートル。多摩川支流の秋川北岸を走る東京の通勤鉄道。
いつか・し【厳し】🔗⭐🔉
いつか・し 【厳し】 (形シク)
荘重だ。立派だ。いかめしい。「さばかり―・しき御身をと/源氏(御法)」
いつき【斎】🔗⭐🔉
いつき 【斎】
(1)心身をきよめて神に仕えること。また,その人。特に斎宮・斎院。「賀茂の―には,孫王の居給ふ例多くもあらざりけれど/源氏(賢木)」
(2)神をまつる場所。「隼は天に上り飛び翔(カケ)り―が上の鷦鷯(サザキ)取らさね/日本書紀(仁徳)」
いつき-の-いん【斎院】🔗⭐🔉
いつき-の-いん ― ン 【斎院】
⇒さいいん(斎院)
ン 【斎院】
⇒さいいん(斎院)
 ン 【斎院】
⇒さいいん(斎院)
ン 【斎院】
⇒さいいん(斎院)
いつき-の-みこ【斎王】🔗⭐🔉
いつき-の-みこ 【斎王】
⇒さいおう(斎王)
いつき-の-みや【斎宮】🔗⭐🔉
いつき-の-みや 【斎宮】
(1)斎王(イツキノミコ)の居所。また,その忌みこもる御殿。
(2)神をまつる場所。特に伊勢神宮。「度会(ワタライ)の―ゆ神風にい吹き惑はし/万葉 199」
(3)大嘗祭(ダイジヨウサイ)の悠紀(ユキ)殿・主基(スキ)殿。
いつき-め【斎女】🔗⭐🔉
いつき-め [0] 【斎女】
神事に奉仕する少女司祭者。春日神社・大原野神社・松尾神社・住吉神社などに仕えた。斎子(イツキコ)。
い-つき【居着き・居付き】🔗⭐🔉
い-つき  ― [0] 【居着き・居付き】
(1)居つくこと。一定の場所に住みつくこと。
(2)内湾や岩礁など,一定の場所にすみついている魚。
― [0] 【居着き・居付き】
(1)居つくこと。一定の場所に住みつくこと。
(2)内湾や岩礁など,一定の場所にすみついている魚。
 ― [0] 【居着き・居付き】
(1)居つくこと。一定の場所に住みつくこと。
(2)内湾や岩礁など,一定の場所にすみついている魚。
― [0] 【居着き・居付き】
(1)居つくこと。一定の場所に住みつくこと。
(2)内湾や岩礁など,一定の場所にすみついている魚。
いつき-じぬし【居着き地主】🔗⭐🔉
いつき-じぬし  ―ヂ― [4] 【居着き地主】
江戸町内に家屋敷を所有し,そこに住んでいる町人。家持ち。
―ヂ― [4] 【居着き地主】
江戸町内に家屋敷を所有し,そこに住んでいる町人。家持ち。
 ―ヂ― [4] 【居着き地主】
江戸町内に家屋敷を所有し,そこに住んでいる町人。家持ち。
―ヂ― [4] 【居着き地主】
江戸町内に家屋敷を所有し,そこに住んでいる町人。家持ち。
いつき【五木】🔗⭐🔉
いつき 【五木】
熊本県南部,球磨(クマ)郡の村。九州山地中にある。
いつき-の-こもりうた【五木の子守唄】🔗⭐🔉
いつき-の-こもりうた 【五木の子守唄】
五木村の子守り奉公の娘たちが歌った子守唄。もとはこの地方の臼(ウス)唄。
い-つぎ【居接ぎ】🔗⭐🔉
い-つぎ  ― [0] 【居接ぎ】
接ぎ木の方法の一。台木を掘り上げないで,畑に植えたまま接ぎ木をするもの。揚げ接ぎより根付きがいい。
― [0] 【居接ぎ】
接ぎ木の方法の一。台木を掘り上げないで,畑に植えたまま接ぎ木をするもの。揚げ接ぎより根付きがいい。
 ― [0] 【居接ぎ】
接ぎ木の方法の一。台木を掘り上げないで,畑に植えたまま接ぎ木をするもの。揚げ接ぎより根付きがいい。
― [0] 【居接ぎ】
接ぎ木の方法の一。台木を掘り上げないで,畑に植えたまま接ぎ木をするもの。揚げ接ぎより根付きがいい。
いつ-ぎぬ【五衣】🔗⭐🔉
いつ-ぎぬ 【五衣】
平安時代,男子が参内するときの正式の装束。袍(ウエノキヌ)・下襲(シタガサネ)・半臂(ハンピ)・単(ヒトエ)・引倍木(ヒキヘギ)の五種でひとそろい。
い-つ・く【居着く】🔗⭐🔉
い-つ・く  ― [2] 【居着く】 (動カ五[四])
(1)外から来たものがそのままそこに住むようになる。住みつく。「野良猫が―・いてしまった」
(2)落ち着いてそこに居る。「すこしも家に―・かない息子」
[可能] いつける
― [2] 【居着く】 (動カ五[四])
(1)外から来たものがそのままそこに住むようになる。住みつく。「野良猫が―・いてしまった」
(2)落ち着いてそこに居る。「すこしも家に―・かない息子」
[可能] いつける
 ― [2] 【居着く】 (動カ五[四])
(1)外から来たものがそのままそこに住むようになる。住みつく。「野良猫が―・いてしまった」
(2)落ち着いてそこに居る。「すこしも家に―・かない息子」
[可能] いつける
― [2] 【居着く】 (動カ五[四])
(1)外から来たものがそのままそこに住むようになる。住みつく。「野良猫が―・いてしまった」
(2)落ち着いてそこに居る。「すこしも家に―・かない息子」
[可能] いつける
いつ・く【斎く・傅く】🔗⭐🔉
いつ・く 【斎く・傅く】 (動カ四)
(1)心身の汚れを去り神に仕える。《斎》「此の三柱の神は,胸形君等の以ち―・く三前の大神なり/古事記(上)」
(2)神に仕えるような気持ちで大事に世話をする。《傅》「海神(ワタツミ)の神の命のみくしげに貯ひ置きて―・くとふ玉にまさりて/万葉 4220」
いつくさ-の-たなつもの【五種の穀物・五穀】🔗⭐🔉
いつくさ-の-たなつもの 【五種の穀物・五穀】
「五穀(ゴコク)」に同じ。いつつのたなつもの。「臍(ホソ)の中に―生(ナ)れり/日本書紀(神代上訓)」
いつく・し【厳し・美し】🔗⭐🔉
いつく・し 【厳し・美し】 (形シク)
(1)いかめしい。おごそかだ。「皇神(スメカミ)の―・しき国/万葉 894」
(2)尊く立派だ。大切だ。重々しく格式がある。「―・しうもてかしづきたてまつり給ふ/増鏡(おどろの下)」
(3)美しい。「―・しくかたじけなきものに思ひはぐくむ/源氏(若菜下)」
いつくしま【厳島】🔗⭐🔉
いつくしま 【厳島】
広島湾西部の島。最高所は弥山(ミセン)。島をおおう原始林は国の天然記念物。神の島とされ,出産・埋葬を忌んだ。北西岸に厳島神社があり,日本三景の一。宮島。
いつくしま-ぎれ【厳島裂】🔗⭐🔉
いつくしま-ぎれ 【厳島裂】
厳島神社蔵の名物裂。二重の隅入り角文の中に雨竜(アマリヨウ)文のある,花色の緞子(ドンス)。厳島緞子。
いつくしま-じんじゃ【厳島神社】🔗⭐🔉
いつくしま-じんじゃ 【厳島神社】
厳島にある神社。主神,市杵島姫命(イチキシマヒメノミコト)。平氏・鎌倉幕府・毛利氏などの崇敬庇護のもとに栄えた。本社・平家納経・鎧など多くの国宝を蔵する。安芸(アキ)国一の宮。
いつくしま-の-たたかい【厳島の戦い】🔗⭐🔉
いつくしま-の-たたかい ―タタカヒ 【厳島の戦い】
1555年,主君大内義隆を殺して領国を奪った陶晴賢(スエハルカタ)を毛利元就(モトナリ)が厳島に敗死させた戦い。毛利氏発展の基となる。
いつくしみ【慈しみ】🔗⭐🔉
いつくしみ [0] 【慈しみ】
慈愛。恵み。
いつくし・む【慈しむ】🔗⭐🔉
いつくし・む [4] 【慈しむ】 (動マ五[四])
〔「うつくしむ」の転〕
かわいがって,大事にする。「我が子のように―・む」
いつ-ぐん【逸群】🔗⭐🔉
いつ-ぐん [0] 【逸群】
「抜群(バツグン)」に同じ。「―の才」
い-つ・ける【射付ける】🔗⭐🔉
い-つ・ける [3][0] 【射付ける】 (動カ下一)[文]カ下二 いつ・く
(1)矢を射て物に当てる。「疑惑の矢を胸に―・けられたやうな気分/行人(漱石)」
(2)(光などが)強く照らす。「夏の日差しが肌に―・ける」
(3)矢で射通して他の物につける。「大きな野猪(クサイナギ),木に―・けられてぞ死にて有りける/今昔 27」
いつ-げん【逸言】🔗⭐🔉
いつ-げん [0] 【逸言】
言い過ぎ。過言。失言。
いつ-ごろ【何時頃】🔗⭐🔉
いつ-ごろ [0] 【何時頃】
おおよその時を漠然とさす語。いつじぶん。「今度は―上京されますか」
いつ-ざい【逸材】🔗⭐🔉
いつ-ざい [0] 【逸材】
抜きんでてすぐれた才能。また,その才能をもっている人。逸才(イツサイ)。「角界の―」
いつ-じ【逸事・軼事】🔗⭐🔉
いつ-じ [1] 【逸事・軼事】
世に知られない事柄。
いつ-しか【何時しか】🔗⭐🔉
いつ-しか [1] 【何時しか】
■一■ (副)
〔「いつか」を強めていった語。「し」は強めの助詞〕
(1)いつの間にか。「夏も終わり―秋になった」
(2)いつになったら,と待ち望むさま。早く来るとよいなあという気持ちを表す。「けふよりは今こむ年の昨日をぞ―とのみまちわたるべき/古今(秋上)」
■二■ (形動ナリ)
早すぎるさま。「あはれ,―なる譲位かな/平家 4」
いつ-じぶん【何時時分】🔗⭐🔉
いつ-じぶん [0][3] 【何時時分】
いつごろ。いつ。
いつしほご-じょうやく【乙巳保護条約】🔗⭐🔉
いつしほご-じょうやく ―デウヤク 【乙巳保護条約】
日韓協約のうち1905年(明治38)に締結された条約をいう。
いつ-ぞ【何時ぞ】🔗⭐🔉
いつ-ぞ 【何時ぞ】 (副)
〔「ぞ」は係助詞〕
不定の時を表す。過去・未来ともにいうが,現代では主に過去のある時をさす。いつ。いつか。「―のことだったかはっきりしないが…」「五三のあたひをためて,―の時節を待てども/浮世草子・一代男 5」
いつぞ-や【何時ぞや】🔗⭐🔉
いつぞ-や [1] 【何時ぞや】 (副)
日時をはっきり覚えていない時や,はっきり言う必要のない時に用いる。先頃。いつであったか。せんだって。「―どこかでお会いしましたね」「―は結構なものをありがとう」
いつぞんそうしょ【佚存叢書】🔗⭐🔉
いつぞんそうしょ 【佚存叢書】
中国では散逸したが日本に伝存する漢籍一六種を収めて叢書としたもの。三六冊。林述斎編。1799〜1810年刊。
いつ-だつ【逸脱】🔗⭐🔉
いつ-だつ [0] 【逸脱】 (名)スル
本筋や決められた範囲からそれること。「本来の目的から―する」
いつ-つ【五つ】🔗⭐🔉
いつ-つ [2] 【五つ】
(1)ご。五個。物の数を数える時に使う。
(2)五歳。
(3)昔の時刻の名。今の午前と午後の八時頃。五つ時。
いつつ-あこめ【五つ衵】🔗⭐🔉
いつつ-あこめ [4] 【五つ衵】
女房装束で,あこめを五枚重ねて着るもの。
いつつ-お【五つ緒】🔗⭐🔉
いつつ-お ―ヲ [3] 【五つ緒】
牛車の簾(スダレ)の一種。左右の縁と中央に垂らした緒の間にそれぞれ一条の緒を垂らしたもの。また,その簾をつけた車。網代(アジロ)車など。
いつつ-お-の-くるま【五つ緒の車】🔗⭐🔉
いつつ-お-の-くるま ―ヲ― 【五つ緒の車】
五つ緒の簾(スダレ)をかけた牛車。いつつお。
いつつ-がさね【五つ重ね・五つ襲】🔗⭐🔉
いつつ-がさね [4] 【五つ重ね・五つ襲】
「いつつぎぬ」に同じ。
いつつ-がしら【五つ頭】🔗⭐🔉
いつつ-がしら [4] 【五つ頭】
歌舞伎の下座音楽で,荒事の見得に合わせて,太鼓・大太鼓・笛ではやすもの。「頭(カシラ)」という手を五回重ねることからの称。
いつつ-ぎぬ【五つ衣】🔗⭐🔉
いつつ-ぎぬ [3] 【五つ衣】
女房装束で,五枚重ねた袿(ウチキ)。江戸時代には,女官の正装をいう。いつつがさね。
五つ衣
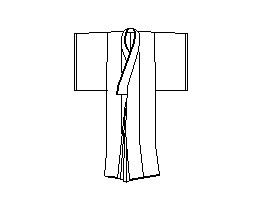 [図]
[図]
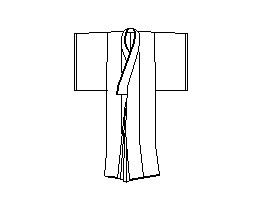 [図]
[図]
いつつ-どうぐ【五つ道具】🔗⭐🔉
いつつ-どうぐ ―ダウ― [4] 【五つ道具】
江戸時代,大名行列の持ち道具の五種をいう。槍・打ち物・挟み箱・長柄傘(ナガエガサ)・袋入れ杖(ツエ)など。
いつつ-どき【五つ時】🔗⭐🔉
いつつ-どき [0] 【五つ時】
⇒いつつ(五つ)(3)
いつつ-の-おしえ【五つの教え】🔗⭐🔉
いつつ-の-おしえ ―ヲシヘ 【五つの教え】
儒教で説く,人間として守るべき五つの徳。仁・義・礼・智・信のこと。いつつのみち。五常。
いつつ-の-かりもの【五つの借り物】🔗⭐🔉
いつつ-の-かりもの 【五つの借り物】
〔仏教の説で,人の肉体は地・水・火・風・空の五大が仮に集まってできたものであり,死ねばこの五つに帰るというところから〕
人の肉体。「世は―,取りに来た時,閻魔大王へ返さうまで/浮世草子・一代男 4」
いつつ-の-くも【五つの雲】🔗⭐🔉
いつつ-の-くも 【五つの雲】
「五障(ゴシヨウ)」に同じ。
いつつ-の-さわり【五つの障り】🔗⭐🔉
いつつ-の-さわり ―サハリ 【五つの障り】
「五障(ゴシヨウ)」を訓読みした語。「名にし負はば―あるものを/和泉式部集」
いつつ-の-たなつもの【五つの穀】🔗⭐🔉
いつつ-の-たなつもの 【五つの穀】
五種類の主要な穀物。すなわち米・麦・粟(アワ)・黍(キビ)・豆のこと。[和名抄]
いつつ-の-つみ【五つの罪】🔗⭐🔉
いつつ-の-つみ 【五つの罪】
「五罪(ゴザイ)」を訓読みした語。「おのが―や消ゆると/林葉集」
いつつ-の-にごり【五つの濁り】🔗⭐🔉
いつつ-の-にごり 【五つの濁り】
「五濁(ゴジヨク)」を訓読みした語。「―深き世に,などて生まれ給ひけん/源氏(蓬生)」
いつつ-ぼし【五つ星】🔗⭐🔉
いつつ-ぼし [3] 【五つ星】
家紋の一。一つの円のまわりに四つの円を並べたもの。五星(ゴセイ)。
いつつ-もん【五つ紋】🔗⭐🔉
いつつ-もん [3] 【五つ紋】
背・両袖・両胸に一つずつ計五つの紋のついた羽織や着物。礼装に用いる最も格式の高いもの。五所紋(イツトコロモン)。
い-つづけ【居続け】🔗⭐🔉
い-つづけ  ― [0] 【居続け】 (名)スル
(1)幾日もの間,家を離れてほかの所にとどまること。
(2)遊里などで,幾日もの間泊まりつづけて遊ぶこと。
⇔一夜切(イチヤギ)り
「―の客」
― [0] 【居続け】 (名)スル
(1)幾日もの間,家を離れてほかの所にとどまること。
(2)遊里などで,幾日もの間泊まりつづけて遊ぶこと。
⇔一夜切(イチヤギ)り
「―の客」
 ― [0] 【居続け】 (名)スル
(1)幾日もの間,家を離れてほかの所にとどまること。
(2)遊里などで,幾日もの間泊まりつづけて遊ぶこと。
⇔一夜切(イチヤギ)り
「―の客」
― [0] 【居続け】 (名)スル
(1)幾日もの間,家を離れてほかの所にとどまること。
(2)遊里などで,幾日もの間泊まりつづけて遊ぶこと。
⇔一夜切(イチヤギ)り
「―の客」
いつ-でも【何時でも】🔗⭐🔉
いつ-でも [1] 【何時でも】 (副)
(1)常に。絶えず。「―肌身離さず身につけている」
(2)任意のあるとき。どのときと限ることなく。「気が向いたら―おいで」
いつところ-どう【五所籐】🔗⭐🔉
いつところ-どう [5] 【五所籐】
五か所に籐(トウ)を巻いた弓。
いつところ-もん【五所紋】🔗⭐🔉
いつところ-もん [5] 【五所紋】
「五(イツ)つ紋(モン)」に同じ。
いつとものお-の-かみ【五伴緒神・五部神】🔗⭐🔉
いつとものお-の-かみ イツトモノヲ― 【五伴緒神・五部神】
記紀神話で,瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)の降臨に従った五神。天児屋命(アマノコヤネノミコト)・太玉命(フトダマノミコト)・天鈿女命(アマノウズメノミコト)・石凝姥命(イシコリドメノミコト)・玉祖命(タマノオヤノミコト)。五伴緒(イツトモノオ)。
いつとも-の-ふみ【五部書】🔗⭐🔉
いつとも-の-ふみ 【五部書】
(1)五種の書を合わせて一組としたもの。
(2)五経(ゴキヨウ)の異名。
いつ-なんどき【何時何時】🔗⭐🔉
いつ-なんどき [1] 【何時何時】 (副)
〔「いつ」を強めたいい方〕
いつ。「―大地震が起こるか分からない」
いつ-に【一に】🔗⭐🔉
いつ-に [1][2] 【一に】 (副)
〔漢文訓読から出た語〕
(1)多くのことが一つのことに集中しているさまを表す語。全く。ひとえに。「―各員の努力にかかっている」
(2)また別に。ひとつには。「法隆寺―斑鳩(イカルガ)寺という」
いつ-にゅう【溢乳】🔗⭐🔉
いつ-にゅう [0] 【溢乳】 (名)スル
授乳直後,乳児が少量の乳を口から出すこと。乳流。乳多。
→吐乳(トニユウ)
いつねん【逸然】🔗⭐🔉
いつねん 【逸然】
(1600頃-1668) 中国明末の黄檗(オウバク)宗の禅僧。1645年来日し,その画風はいわゆる長崎派絵画の主流となった。逸然派の祖。
いつ-ねんごう【逸年号】🔗⭐🔉
いつ-ねんごう ―ネンガウ [3] 【逸年号】
大宝令による公年号制の確立以前に用いられた年号のうち正史に逸せられたもの。法興・白鳳・朱雀など。異年号。
→私年号
いつ【何時】(和英)🔗⭐🔉
いつう【胃痛】(和英)🔗⭐🔉
いつう【胃痛】
a stomachache.→英和
いつか【何時か】(和英)🔗⭐🔉
いつか【何時か】
some time (or other) (未来の);some day;one of these days (近日);once[at one time](過去の);→英和
the other day (先日).
いつく【居着く】(和英)🔗⭐🔉
いつく【居着く】
settle down;stay long.
いつざい【逸材】(和英)🔗⭐🔉
いつざい【逸材】
a man of exceptional talent.
いつぞや【何時ぞや】(和英)🔗⭐🔉
いつぞや【何時ぞや】
once (かつて);→英和
some time ago (過日).
いつだつ【逸脱】(和英)🔗⭐🔉
いつだつ【逸脱】
(a) deviation.〜する deviate.→英和
いつつ【五つ】(和英)🔗⭐🔉
いつつ【五つ】
five.→英和
〜児quintuplets.
いつなんどき【いつ何時】(和英)🔗⭐🔉
いつなんどき【いつ何時】
(at) any moment.
いつに【一に】(和英)🔗⭐🔉
大辞林に「いつ」で始まるの検索結果 1-100。もっと読み込む