複数辞典一括検索+![]()
![]()
しで【四手・垂】🔗⭐🔉
しで [1][2] 【四手・垂】
〔動詞「しづ(垂)」の連用形から〕
(1)玉串や注連縄(シメナワ)などに下げる紙。古くは木綿(ユウ)を用いた。
(2)槍の柄につけ,槍印とするヤクの毛で作った払子(ホツス)のようなもの。
(3)カバノキ科の落葉高木。アカシデ・イヌシデ・クマシデなどの総称。
四手(1)
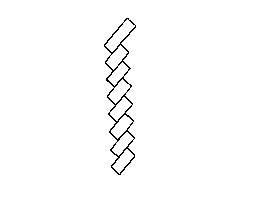 [図]
[図]
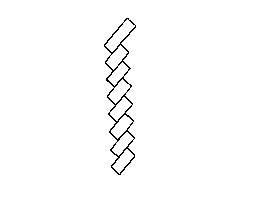 [図]
[図]
し-で【死出】🔗⭐🔉
し-で [1] 【死出】
死んであの世に行くこと。「―の道連れ」
してい-こうけんにん【指定後見人】🔗⭐🔉
してい-こうけんにん [0] 【指定後見人】
管理権を有する最後の親権者が,遺言で指定した未成年者の後見人。
してい-せき【指定席】🔗⭐🔉
してい-せき [2] 【指定席】
(劇場や列車などで)あらかじめすわる人が定められる席。
⇔自由席
してい-つうか【指定通貨】🔗⭐🔉
してい-つうか ―クワ [4] 【指定通貨】
外国との取引に使用することを認められた通貨。日本では1971年(昭和46)に為替貿易自由化の一環として廃止された。
してい-とうけい【指定統計】🔗⭐🔉
してい-とうけい [4] 【指定統計】
国または地方公共団体が実施する統計調査で,行政管理庁統計基準局が指定承認を行なったもの。
してい-とし【指定都市】🔗⭐🔉
してい-とし [4] 【指定都市】
人口五〇万以上の市で,政令によって指定された都市。市民生活と直結した事務や権限が都道府県から委譲され,また,行政区を設けられるなど,普通の都市とは異なった取り扱いが認められる。大阪・名古屋・京都・横浜・神戸・北九州・札幌・川崎・福岡・広島・仙台・千葉の各市。政令指定都市。政令都市。
しで-いし【志手石】🔗⭐🔉
しで-いし 【志手石】
木や木の葉などの化石。「色黒うして縦理(モクメ)あり―と名づく/仮名草子・東海道名所記」
しで-う・つ【しで打つ】🔗⭐🔉
しで-う・つ 【しで打つ】 (動タ四)
砧(キヌタ)を絶えず打つ。「さ夜ふけて衣―・つ声聞けば/後拾遺(秋下)」
〔「しで」は繁しの意という〕
し-でか・す【仕出かす・為出来す】🔗⭐🔉
し-でか・す [3] 【仕出かす・為出来す】 (動サ五[四])
(1)してしまう。やってのける。困ったことを引き起こす場合に使う。「大それたことを―・す」
(2)見事に作り出す。「次第に思ひ入をはづさず,金銀を―・し/浮世草子・新永代蔵」
して-かた【仕手方】🔗⭐🔉
してき-しもんきかん【私的諮問機関】🔗⭐🔉
してき-しもんきかん ―クワン [8][7] 【私的諮問機関】
内閣総理大臣・各省庁大臣・局長などが,非公式に設ける諮問機関。設置には,法令上の根拠は必要ない。
→審議会
してき-せいさい【私的制裁】🔗⭐🔉
してき-せいさい [4] 【私的制裁】
⇒私刑(シケイ)
してき-ねんきん【私的年金】🔗⭐🔉
してき-ねんきん [4] 【私的年金】
民間企業・団体などが行う,企業年金・団体年金の総称。
→公的年金
しで-こぶし【四手辛夷・幣辛夷】🔗⭐🔉
しで-こぶし [3] 【四手辛夷・幣辛夷】
モクレン科の落葉高木。中部地方の山地に自生し,また庭木として栽植。早春,葉に先だち花被片十数個から成る微紅色を帯びた白色で芳香のある花を開く。ヒメコブシ。
しで-ざくら【四手桜】🔗⭐🔉
しで-ざくら [3] 【四手桜】
ザイフリボクの別名。
しで-さんず【死出三途】🔗⭐🔉
しで-さんず ―サンヅ 【死出三途】
〔「死出の山」と「三途の川」の意〕
あの世。また,死んで冥土に行くこと。「―よみぢの箱根大井川/柳多留 104」
して-して🔗⭐🔉
して-して (接続)
〔「して」を重ね意味を強めた語〕
そうして。それから。「―親ぢや人はなんとしてゐらるるぞ/狂言・武悪」
して-せん【仕手戦】🔗⭐🔉
して-せん [0] 【仕手戦】
株式取引で,ある銘柄をめぐって大量の売買が行われ,売り方と買い方が相争うこと。
しで-の-き【四手の木】🔗⭐🔉
しで-の-き [3] 【四手の木】
アカシデの別名。
しで-の-たおさ【死出の田長】🔗⭐🔉
しで-の-たおさ ―タヲサ 【死出の田長】
〔「賤(シズ)の田長」の転という〕
ホトトギスの異名。しでたおさ。「名のみたつ―は今朝ぞなく庵あまたとうとまれぬれば/伊勢 43」
しで-の-たび【死出の旅】🔗⭐🔉
しで-の-たび 【死出の旅】
(1)人が死後,死出の山に行くこと。
(2)死ぬこと。「―に出る」
しで-の-やま【死出の山】🔗⭐🔉
しで-の-やま [1] 【死出の山】
(1)死者が越えていかなければならない険難を山にたとえた語。
(2)死者が冥府において初七日の間に秦広王の庁へ行く途中にある山。
しで-の-やまじ【死出の山路】🔗⭐🔉
しで-の-やまじ ―ヤマヂ [1] 【死出の山路】
死出の山の山道。「夏は郭公を聞く。語らふごとに,―を契る/方丈記」
しではら【幣原】🔗⭐🔉
しではら 【幣原】
姓氏の一。
しではら-きじゅうろう【幣原喜重郎】🔗⭐🔉
しではら-きじゅうろう ―キヂユウラウ 【幣原喜重郎】
(1872-1951) 外交官・政治家。大阪生まれ。東大卒。四度外相となる。その国際協調主義政策は軍部から幣原軟弱外交と非難された。第二次大戦後,東久邇内閣の後継首相として組閣,新憲法制定に着手した。
しではら-やき【志手原焼】🔗⭐🔉
しではら-やき [0] 【志手原焼】
兵庫県三田(サンダ)市志手原で産した陶磁器。宝暦・明和(1751-1772)頃の創業という。盛時には青磁・染め付け・呉須赤絵などを産した。三田焼の先駆。1941年(昭和16)閉窯。
しでます-しんとう【垂加神道】🔗⭐🔉
しでます-しんとう ―シンタウ [5] 【垂加神道】
⇒すいかしんとう(垂加神道)
して-また🔗⭐🔉
して-また (接続)
そしてまた。「―,こなたはどれへ向けてござる/狂言記・薩摩守」
して-みる-と🔗⭐🔉
して-みる-と [3] (接続)
先行の事柄の結果として後続のことが起こることを表す語。それから判断すると。そうしてみると。
しで-むし【埋葬虫】🔗⭐🔉
しで-むし [2] 【埋葬虫】
シデムシ科の甲虫の総称。体長10〜35ミリメートルほど。大部分の種は腐敗した動物の死体に集まり,これを食べる。モンシデムシ・クロシデムシ・ヒラタシデムシなど。全世界に分布。埋葬(マイソウ)虫。
して-も🔗⭐🔉
して-も (連語)
(「…にしても」の形で)
(1)…でも。「それに―困ったことになった」
(2)たとえ…としても。「行くに―午前中は無理だ」
して-や・る【為て遣る】🔗⭐🔉
して-や・る [0] 【為て遣る】 (動ラ五[四])
(1)うまくやって思いどおりの成果を得る。首尾よくしおおせる。「―・ったりという顔でマウンドを下りる」「ここへもちよつと出かけて又六百―・つた/浄瑠璃・丹波与作(中)」
(2)食う。食らう。「奈良茶をあり切りさらさらと―・り/滑稽本・膝栗毛(初)」
してん-にてん【四天二天】🔗⭐🔉
してん-にてん 【四天二天】
互いに優劣のないさまをいう語。「諸々の御敵,信玄公に―の御大将衆とせりあひ/甲陽軍鑑(品五三)」
してん-の-ほし【四天の星】🔗⭐🔉
してん-の-ほし [2] 【四天の星】
⇒四天(シテン)の鋲(ビヨウ)
し-でん【史伝】🔗⭐🔉
し-でん [0] 【史伝】
(1)歴史に伝わった記録。「―小説」
(2)歴史と伝記。
し-でん【市電】🔗⭐🔉
し-でん [0] 【市電】
市営電車。また,市街地を走る路面電車。
し-でん【師伝】🔗⭐🔉
し-でん [0] 【師伝】
師匠から直接教え伝えられること。また,その伝えられたこと。「―を受ける」
し-でん【紫電】🔗⭐🔉
し-でん [0][1] 【紫電】
(1)紫色の電光。
(2)鋭い光。鋭い眼光や,とぎすました刀剣の光などにいう。
(3)旧日本海軍の局地戦闘機。のちに中翼配置が低翼に改められ紫電改となり,本土防空戦に活躍。
し-でん【賜田】🔗⭐🔉
し-でん [0][1] 【賜田】
律令制下,戦功や政治上の功績などに対し,天皇の別勅によって与えられた田。別勅賜田。
しでかす【仕出かす】(和英)🔗⭐🔉
しでかす【仕出かす】
⇒為(す)る.
しでん【市電】(和英)🔗⭐🔉
しでん【市電】
<米>a (municipal) streetcar;<英>a tram(car).→英和
大辞林に「しで」で始まるの検索結果 1-47。
 siderostat
siderostat