複数辞典一括検索+![]()
![]()
たたい-にんしん【多胎妊娠】🔗⭐🔉
たたい-にんしん [4] 【多胎妊娠】
二人以上の胎児を同時に妊娠すること。胎児の数により双胎・品胎・四胎妊娠などと呼ぶ。
だ-たい【だ体】🔗⭐🔉
だ-たい [0] 【だ体】
口語文体の一。文末の指定表現として「だ」を用いることを基調とする常体の文章様式。「である体」に比べ,相手に話しかけるような感じがある。だ調。
だ-たい【堕胎】🔗⭐🔉
だ-たい [0] 【堕胎】 (名)スル
人工妊娠中絶。子おろし。
だたい-ざい【堕胎罪】🔗⭐🔉
だたい-ざい [2] 【堕胎罪】
妊婦自身,またその嘱託を受けた者,および医師・助産婦などが堕胎を実行したことにより成立する罪。優生保護法による人工妊娠中絶の場合はこれに該当しない。
だ-たい【大体】🔗⭐🔉
だ-たい 【大体】 (副)
〔「だいたい(大体)」の転〕
もともと。そもそも。「おいらは―職人だからとんだ雑だによつて/洒落本・南閨雑話」
だたいれい【大戴礼】🔗⭐🔉
だたいれい 【大戴礼】
儒家の礼に関する古い記録を整理し,その理論と解説を記したもの。前漢の戴徳編。八五編中,三九編が現存。「礼記(ライキ)」(小戴礼)はこれをさらに整理したものといわれる。だいたいれい。
たたかい-と・る【闘い取る】🔗⭐🔉
たたかい-と・る タタカヒ― [5] 【闘い取る】 (動ラ五[四])
闘ってかちとる。「―・った自由」
[可能] たたかいとれる
たたき-あみ【叩き網】🔗⭐🔉
たたき-あみ [3] 【叩き網】
刺し網を張りめぐらし,船べりや水面をたたいて魚群を送り込む漁法。
たたき-いし【叩き石】🔗⭐🔉
たたき-いし [3] 【叩き石】
(1)ものをたたいたり,すりつぶすのに用いた,丸いまたは扁平な石器。
(2)藁(ワラ)をたたいて柔らかくするのに用いる台石。
たたき-つち【叩き土】🔗⭐🔉
たたき-つち [3] 【叩き土】
花崗(カコウ)岩・安山岩などの風化した,可溶性ケイ酸に富む土。
→たたき(三和土)
たたき-な【叩き菜】🔗⭐🔉
たたき-な [3] 【叩き菜】
正月六日の夜に七草粥(ナナクサガユ)の菜をまな板の上に載せてたたくこと。また,その行事。
→七草(ナナクサ)を囃(ハヤ)す
たたき-なます【叩き鱠】🔗⭐🔉
たたき-なます [4] 【叩き鱠】
アジなどを細かくたたいて作った料理。
たたき-わけ【叩き分け】🔗⭐🔉
たたき-わけ [0] 【叩き分け】
ものを半分ずつ分けること。山わけ。「利徳(モウケ)は茶屋と―/安愚楽鍋(魯文)」
たたき-あ・う【叩き合う】🔗⭐🔉
たたき-あ・う ―アフ [4] 【叩き合う】 (動ワ五[ハ四])
(1)互いにたたく。
(2)互いに取るに足りないようなことを言い合う。「無駄口を―・う」
たたき-う・る【叩き売る】🔗⭐🔉
たたき-う・る [4][0] 【叩き売る】 (動ラ五[四])
(1)大道商人が台を叩いたりして,威勢よく売る。「バナナを―・る」
(2)安売りする。投げ売りする。「換金のために―・る」
(3)売りとばす。「家屋敷を―・る」
たたき-かえ・す【叩き返す】🔗⭐🔉
たたき-かえ・す ―カヘス [4][2] 【叩き返す】 (動サ五[四])
(1)たたかれた仕返しに相手をたたく。
(2)たたきつけるようにして返す。「こんな金―・してこい」
たたき-のめ・す【叩きのめす】🔗⭐🔉
たたき-のめ・す [5] 【叩きのめす】 (動サ五[四])
(1)激しく殴ったり蹴ったりして,起き上がれないようにする。「ちんぴらを―・す」
(2)きびしい言葉などで攻撃して立ち上がれないようにする。「最後の一言で―・された」
たたき-わ・る【叩き割る】🔗⭐🔉
たたき-わ・る [4][2][0] 【叩き割る】 (動ラ五[四])
たたいて割る。たたいてこわす。うち割る。「スイカを―・る」
たたく・る🔗⭐🔉
たたく・る (動ラ四)
めちゃめちゃにする。しわくちゃにする。「打ち当て袴の裾,踏み―・つて睨み付け/浄瑠璃・反魂香」
たたけ【狸】🔗⭐🔉
たたけ 【狸】
〔「たたげ」とも〕
(1)タヌキの異名。[名義抄]
(2)タヌキの毛。筆の穂に用いる。[日葡]
たた-さ【縦さ】🔗⭐🔉
たた-さ 【縦さ】
〔「さ」は接尾語〕
たての方。たて。たたし。「―にもかにも横さも奴とそ我(アレ)はありける/万葉 4132」
たた-さま【縦方】🔗⭐🔉
たた-さま 【縦方】 (形動ナリ)
(1)立てたさま。たて。「琵琶の御琴を―に持たせ給へり/枕草子 94」
(2)遠く続いているさま。「ながながと―に行けば/枕草子 223」
たたなめ-て【楯並めて】🔗⭐🔉
たたなめ-て 【楯並めて】 (枕詞)
楯(タテ)を並べて射ることから,地名「伊那佐の山」「泉の川」にかかる。「―伊那佐の山の/古事記(中)」「―泉の川の水脈(ミオ)絶えず/万葉 3908」
たたなわ・る【畳なはる】🔗⭐🔉
たたなわ・る タタナハル 【畳なはる】
■一■ (動ラ四)
幾重にも重なる。「登り立ち国見をせせば―・る青垣山/万葉 38」
■二■ (動ラ下二)
{■一■}に同じ。「よれたる下うち―・れたる,いとめでたし/宇津保(蔵開上)」
たたふし-の-まい【楯節舞】🔗⭐🔉
たたふし-の-まい ―マヒ 【楯節舞】
⇒吉志舞(キシマイ)
たたま・る【畳まる】🔗⭐🔉
たたま・る [3] 【畳まる】 (動ラ五[四])
積もり重なる。「悲しき事恐ろしき事胸に―・つて/にごりえ(一葉)」
たたみ-いす【畳み椅子】🔗⭐🔉
たたみ-いす [3] 【畳み椅子】
携帯に便利なように折り畳むことのできるいす。
たたみ-いと【畳糸】🔗⭐🔉
たたみ-いと [4] 【畳糸】
青麻で製し,畳表や縁(ヘリ)などを縫うのに用いる糸。
たたみ-いわし【畳鰯】🔗⭐🔉
たたみ-いわし [4] 【畳鰯】
カタクチイワシの稚魚を竹の簀(ス)などで海苔(ノリ)のように漉(ス)き上げ,天日で干して板状にした食品。
たたみ-おもて【畳表】🔗⭐🔉
たたみ-おもて [4] 【畳表】
藺草(イグサ)の茎を織り合わせて作ったござで,畳の表面に縫いつけるもの。
たたみ-こも【畳薦】🔗⭐🔉
たたみ-こも 【畳薦】 (枕詞)
畳薦は幾重にも重ねて編むところから,「重(ヘ)」と同音の地名「平群(ヘグリ)」や「隔(ヘダ)つ」にかかる。「―平群の山の熊白檮(クマカシ)が葉を/古事記(中)」「―隔て編む数通(カヨ)はさば/万葉 2777」
たたみ-さし【畳刺(し)】🔗⭐🔉
たたみ-さし [3] 【畳刺(し)】
畳を刺して作ること。また,それを業とする人。畳職。
たたみ-すいれん【畳水練】🔗⭐🔉
たたみ-すいれん [4] 【畳水練】
畳の上で水泳の練習をするように,方法や理屈は知っているが,実地の練習をしないため,実際の役に立たないこと。畳の上の水練。畑水練。
たたみ-つき【畳付(き)】🔗⭐🔉
たたみ-つき [3] 【畳付(き)】
(1)畳表で表面をおおってあるもの。下駄などにいう。
(2)茶入れ・水指(ミズサシ)などの底の,畳に当たる部分。盆付き。
→茶入れ
たたみ-め【畳(み)目】🔗⭐🔉
たたみ-め [0] 【畳(み)目】
(1)物を畳んだときにできる折り目。
(2)畳表の編み目。
たたみ-や【畳屋】🔗⭐🔉
たたみ-や [0] 【畳屋】
畳を作るのを業とする人。また,畳を売る家。
たたら【踏鞴】🔗⭐🔉
たたら [0] 【踏鞴】
(1)足で踏んで風を送る,大きなふいご。鋳物に用いる。
(2)「たたらぶき」に同じ。
踏鞴(1)
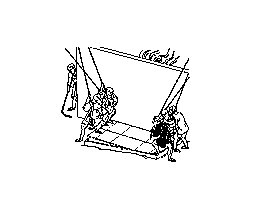 [図]
[図]
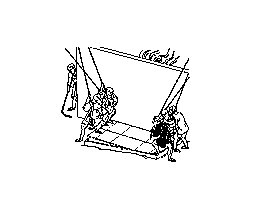 [図]
[図]
たたら-まつり【踏鞴祭(り)】🔗⭐🔉
たたら-まつり [4] 【踏鞴祭(り)】
⇒鞴祭(フイゴマツ)り
たたら-はま【多多良浜】🔗⭐🔉
たたら-はま 【多多良浜】
福岡市北東部,博多湾に面する海岸。元寇(ゲンコウ)の古戦場。また,1336年足利尊氏が菊池武敏を破った地。
たたり-め【祟り目】🔗⭐🔉
たたり-め [0][4] 【祟り目】
たたりに遭うとき。災難に遭うとき。「弱り目に―」
たたわ・し🔗⭐🔉
たたわ・し タタハシ (形シク)
〔「湛(タタ)ふ」の形容詞形〕
(1)満ちたりている。欠けたところがない。完全だ。「春花の貴からむと望月の―・しけむと/万葉 167」
(2)いかめしく,立派だ。「をとこざかりにいたりて容貌(ミカタチ)魁(スグ)れて―・し/日本書紀(綏靖訓)」
だたい【堕胎(する)】(和英)🔗⭐🔉
だたい【堕胎(する)】
(have) an abortion.→英和
たたかいぬく【戦い抜く】(和英)🔗⭐🔉
たたかいぬく【戦い抜く】
fight it out;fight to a[the]finish.→英和
たたきあい【叩き合い】(和英)🔗⭐🔉
たたきあい【叩き合い】
⇒殴(なぐ)り合い.
大辞林に「だた」で始まるの検索結果 1-44。